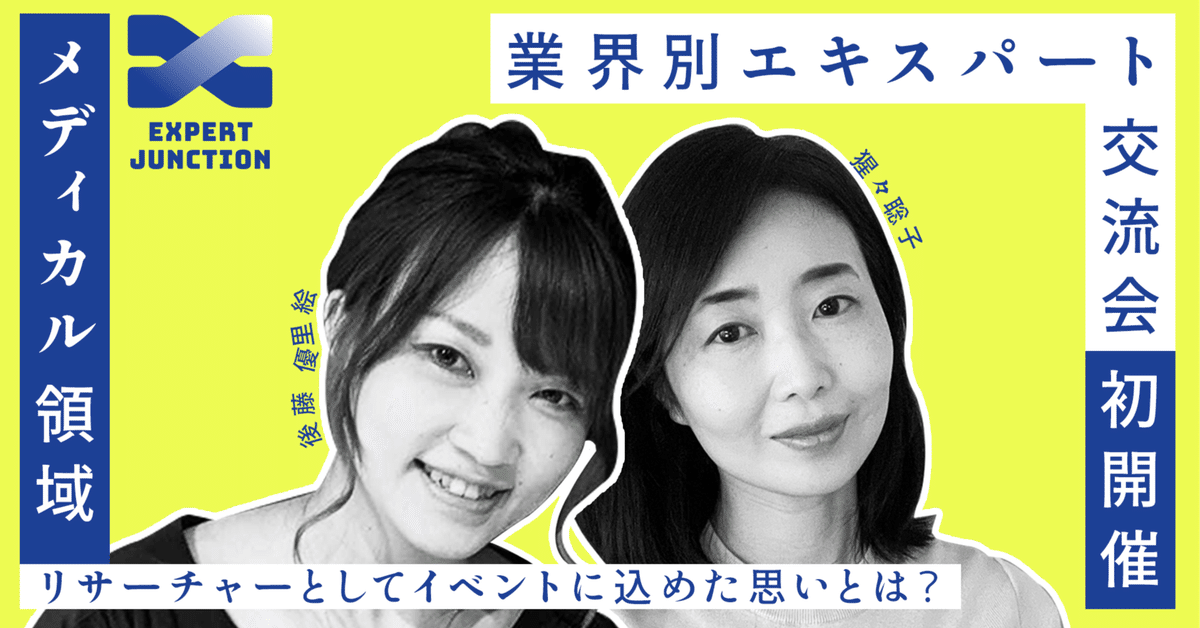
\初開催!/業界別エキスパート交流会の主催者が語る、開催の背景や実際に感じたこと(Research Division 後藤 優里絵 & 猩々 聡子)
6月9日(金)、ミーミルでは初の試みとして、特定の業界・分野における専門性を持つエキスパート向けのイベント、「EXPERT Junction」を開催しました。今回は「メディカル領域」。
普段からエキスパートやクライアントの間に立ちコミュニケーションを行うリサーチ部門のメンバーが、本イベントを主導しました。
これまで部署としてイベント運営を行なった経験がない部門で、なぜオフラインイベントを主催することになったのか。
その背景にあったリサーチャーとしての思いやイベントの裏側について、プロジェクトリーダーを務めた後藤 優里絵(以下、後藤さん)と 猩々 聡子(以下、猩々さん)のお二人に伺いました。

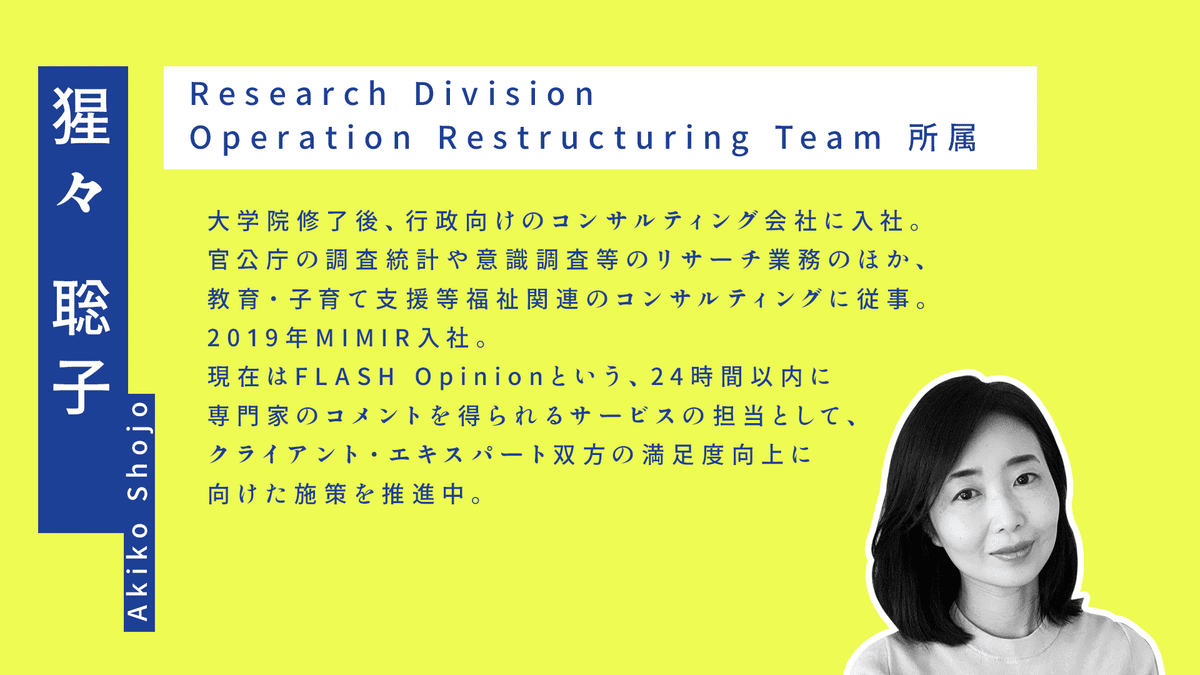
サービスを支えてくれているエキスパートに感謝の思いを込めて、我々ができる特別な機会を提供したかった
交流会の目的について、教えていただけますか?
後藤さん:
大きく分けて2つあります。
1つ目は、「エキスパート同士の交流や繋がりの機会を提供する」ことです。
当社には、年に一度行なっている「EXPERT AWARD」という別のイベントがあります。
このイベントには様々な領域のエキスパートが参加されるのですが、特定の業界に関することや込み入った話はしにくいこともあると思います。
なので、今回の交流会では領域を絞った上で、より深い話や共通知によるエキスパート同士の繋がりの機会を提供したいという気持ちがありました。
イベント名の「EXPERT Junction 」にもまさにそういった思いが込められています。

2つ目は、「専門性やお人柄も含めたエキスパートへの理解を深める」ことです。
今回ご招待したのは医療・製薬・介護といったメディカル領域の方々なのですが、クライアントからご相談いただく案件の中で、比較的ニーズの高い領域の一つとなっています。
日頃から案件に積極的にご対応いただき、専門性の高いご知見を提供いただいているエキスパートを優先的にご招待いたしました。
そこで、私たちリサーチャーとしても、エキスパートの専門性やお人柄をより理解することによって、今後より良いコミュニケーションや適切な案件をお届けできるようにしたいという思いもありました。

猩々さん:
私たち自身は、エキスパートの皆さまのような専門性を持っているわけではないため、クライアントから受けた案件をどのエキスパートに依頼すべきか、判断に迷うこともあります。
エキスパートに本来届けるべき体験を提供するためにも、エキスパートの専門性をより詳細に理解することが大切だと考えました。
案件に活かす目的があったということですね。
普段の業務内容について教えていただけますか?
猩々さん:
私は普段、FLASH Opinionというサービスメニューを担当しています。
クライアントからいただく質問に対して、エキスパートに数百文字程度のテキスト回答の執筆を依頼し、24時間以内に5件以上のご見解をクライアントへお届けする、というサービスです。
まず何よりも、エキスパートあってのサービスであり、このサービスが選ばれるためにもエキスパートのご協力がなくてはなりません。
ニーズが高い領域の案件が続くときや、かなりニッチな分野のご相談があるときは、特定のエキスパートにご負担をかけてしまっていることもあります。
後藤さん:
私は事業会社のクライアントを担当するチームに所属しており、インタビュー・サーベイなどの案件を担っています。
猩々さんと同じで、ニッチなテーマやタイトなスケジュールの際などに、エキスパートに無理なお願いをしてしまっていると感じることがあります。
毎日エキスパートになんらかのご連絡をさせていただいたり、多くのフィードバックもいただいたりする中で、メールや電話だけではなく、対面でお話しする機会が欲しいと、個人的にずっと感じていました。
猩々さん:
本業で忙しい中でいつも、専門性が高く示唆に富んだ素晴らしい回答を寄せてくださるエキスパートの方々には、直接お礼をお伝えしたいと思っていました。
今回のイベントはそういった感謝を伝える場として、我々にとっても非常に大切なものでした。

コンテンツの企画に苦心。それが、知見の循環という感動体験に繋がった
交流会において、こだわった点を聞かせてください。
後藤さん:
「ユーザベース感を出したいよね」という話を猩々さんとしていました。
ユーザベースはパーパスとして「経済情報の力で、誰もがビジネスを楽しめる世界をつくる」と掲げていますが、ミーミルはエキスパートの知見を社会へ還元し、流通していくことで、その実現に向けた役割を果たそうとしているんです。
具体的には、エキスパート向けにはNewsPicksと共同で、NewsPicks Expertというプラットフォームサービスを運営・提供しています。
また、クライアントに対するサービスとしては、SPEEDAと組織融合を進めながら、SPEEDA EXPERT RESEARCHという機能提供を通じて、エキスパート知見の活用を促進しています。
ミーミル単体で事業を営んでいる訳ではないのです。
そういった組織連携の面白さやユーザベースの全体感をお伝えすることも我々だからこそできると考え、具体的なコンテンツへの落とし込みを行いました。
猩々さん:
とはいえ、コンテンツが一番頭を悩ませたところですね。
SPEEDAとNewsPicksそれぞれとコラボレーションするという大枠は決めていました。
NewsPicks for Kidsの5月号がちょうど、メンタルヘルスをテーマに取り上げていたので、こちらとの連携は比較的順調に進めていましたが、SPEEDAに関してはなかなか良い具体案が浮かびませんでした。
そこで、SPEEDA上でトレンドレポートなどを執筆されているアナリストの方に、「イベントに登壇していただけませんか」と相談をしました。
すると「私が登壇するよりも、エキスパートの方々にディスカッションしてもらった方が絶対いいですよ」とご意見をいただいたんです。
それが「リアル公開FLASH Opinion」という、目玉コンテンツ誕生のきっかけでした。
FLASH Opinionは、クライアントがSPEEDAの画面上で、様々な質問に対するエキスパートの見解を見ることができるものですが、通常、回答を寄せてくださるエキスパートは他のエキスパートの回答を見ることはありません。
それをリアルの場で行ない、質問に対してエキスパート同士でディスカッションしていただくというのが「リアル公開FLASH Opinion」です。
新しいFLASH Opinionの体験が生まれることに、企画の段階からワクワクしていました。

リアル公開FLASH Opinionを進める上で工夫した点・難しかった点はありますか?
猩々さん:
テーマを設定するのが難しかったポイントです。アナリストさんに相談を持ちかけながら検討を進めました。
一言でメディカル領域といっても、ご参加いただくエキスパートの専門性は異なります。
医療・製薬・介護分野において、データを主に扱う方もいれば、医療機器を専門とされる方がおられたりと様々なエキスパートが参加される中で、参加者全員が興味を持ち、意見を話していただけるようなテーマにこだわりました。
結果、医療DXの観点で「医療データヘルスケアの未来は?~健康医療情報のデジタル化・データヘルス~」がテーマに決まりました。
事前に参加者にはテーマに関連する質問に回答いただき、その中から複数名にご登壇いただいたのですが、当日のディスカッションの幅が広がりながら示唆に富む時間になるよう、異なる専門性や視点をお持ちの方々にお声がけするなどの工夫もしました。
当日の実際の様子はいかがでしたか?
猩々さん:
会場全体で活発な議論が行われ、まさに「知見の循環」がその場で起こっていることがとても感動的でした。
また、登壇いただいたエキスパートのそれぞれの専門性や、回答の背景にある考えを知ることができて良かったです。
ミーミルのバリューで個人的に一番好きなものが「知的探究心からはじめる」なのですが、エキスパートの知的探究心を喚起する機会になったかな?と嬉しく思いました。

後藤さん:
私はそのとき会場後方にいましたが、エキスパートがものすごく頷いていらっしゃる様子を見て、興味深く聞いてくださっているんだなと感じました。
同じ業界の経験や視点を持つ方たちが集まると、どんどん会話が進んでいくことに驚いたと同時に、次回のイベントのコンテンツへの展開の可能性も感じました。
エキスパートの専門性と熱量があってこそ、我々のサービスが成り立っているという実感が得られた
イベント全体を通した感想を教えてください。
後藤さん:
まずは無事に終えられて、安心しました。
イベント開始時には少し表情の硬かったエキスパートの皆さんも、ご帰宅時には笑顔で柔らかい雰囲気になられているのを拝見し、楽しんでいただけたことを感じました。
そして、交流会でお話しさせていただく中で、改めて、エキスパートの方々の専門性の高さを実感しました。
ご自身が専門とされている領域に対して、これほど熱量高く向き合っておられるのか、と感服すると同時に、エキスパートの皆さまがいてくださってこそミーミルの事業が成り立っていることを強く認識しました。
猩々さん:
イベント後のアンケートでも、交流やディスカッションの時間がもっとあったらよかったというお声をいただきました。
リアル公開FLASH Opinionも交流会も楽しんでいただけたからこそのコメントだと思うので、今後もイベントをよりよいものに進化させていきたいです。
また、今回のイベントは、私たち以外のリサーチメンバーにも手厚くサポートしてもらいました。
「エキスパートあってのわたしたち」という意識が皆のベースにあるので、イベントの主担当であれサポートメンバーであれ、役割やエキスパートのおもてなしに真摯に向き合う姿勢は違いがなかったように感じます。
忙しい中、それぞれが業務を調整してくれたことに、感謝しています。
ご自身の主業務にはどのように活かせそうですか?
後藤さん:
エキスパートの方と直接お話しすることによって得られた様々な気付きや、エキスパートあってこそのサービスであるという実感を、日々のコミュニケーションを通じて自分の言葉で伝えていきたいと思いました。
また、業界の知識やサービス全般に関してのご意見もいただいたので、ミーミル全体として少しずつ形にしていけたらいいなと思っています。
猩々さん:
まずは、エキスパートの専門性への理解が深まったので、案件の依頼精度の向上に努めたいという思いがあります。
FLASH Opinionはまだまだ発展途上で進化し続けているサービスです。
クライアントとの質問内容の調整やエキスパートとクライアントをつなぐ過程において、事務局として果たすべき役割やサービス設計を含めて改善に取り組んでいきたいと考えています。
最後に、今後のイベントの展望について教えてください。
後藤さん:
今回はメディカル領域で実施しましたが、次回以降はまた異なる領域で展開していきたいと考えています。
今年度はあと2回の開催を予定しており、9月に「製造業領域」、12月に「資源・エネルギー領域」での実施を考えています。
3ヶ月ごとのイベント開催なので、イベントを終えてひと息ついたら次のイベント準備に取り掛かるようなスピード感で忙しくなりますが、今回の反省を活かしてさらにクオリティアップを目指したいと考えています。
ぜひ、楽しみにしていてください!

インタビュー後記
筆者も本イベントに一部携わらせていただきました。
今年3月のEXPERT AWARDのプロジェクトリーダーを担当したこともあり、アドバイスを伝えながら、共に新しい座組みのイベントに向き合う経験からは、自分自身も多くを学ばせてもらいました。
リアル公開FLASH Opinionについても、今後の発展の可能性が感じられる良コンテンツだと感じました。
イベントにおける体験も当然ですが、我々がエキスパートに届ける価値の本質は、エキスパートの自己実現や豊かな人生に繋がるための機会提供だと思います。
その機会の具体例が「自らの知見を提供する」ことや「知見が循環したその先に価値を生む」ことであり、まさにこのコンテンツはそれを支える、イベントならではの体験だったように感じます。
次回はまた違う業界にフォーカスしての開催とのことで、さらに違う発見や喜ばしい体験に繋がることを期待しています。
