
[書評]ユダの福音書
『ユダの福音書』を現代によみがえらせた最初の出版物
メアリー・スパロウダンサー著『光のラブソング』が〈教師〉の存在との遭遇体験をすべて描いた本ながら、教わったユダの秘密だけは書いてなかった。同書に収録された「ユダの福音書 バルベーローと長年の秘密」でその一端は示唆されるが、さらに深く知りたい読者は、そこで言及されていた本書『原典 ユダの福音書』を読むのが筋だろう。
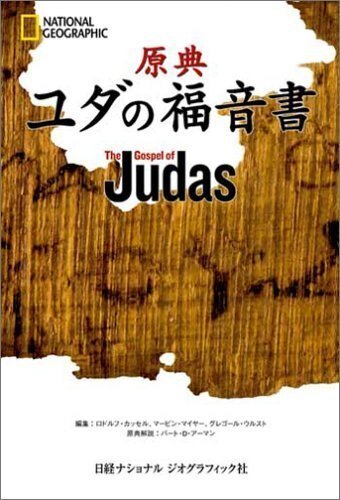
ただし、本書はそこで言及された米国版 The Gospel of Judas の英語訳を日本語に訳したものである。つまり、ユダの福音書(それ自体がギリシア語原本からコプト語への翻訳)の重訳にあたる。日本語訳を担当したのは、藤井留美、田辺喜久子、村田綾子、花田知恵、金子周介、関利枝子。
ギリシア語原本から数えてみると、ギリシア語→コプト語→英語→日本語の4重訳となるわけだ。だから、本文そのものにもっと迫りたい場合は、同じナショナル・ジオグラフィック社から出ている批判版や、その他の専門書に当たる必要がある。
とまれ、本書でまず有難いのは、編者マイヤーによる「はじめに」の文章だ。これを読むと、前掲の「ユダの福音書 バルベーローと長年の秘密」の背景がよく分る。秀逸な入り口といえる。
マイヤーは手際よく、ユダという人物のこと、ユダとイエスの関係、『ユダの福音書』の根底をなすグノーシス思想の特徴などを説明する。本書が世に出るまでの歴史的経緯と思想的神学的文脈の両方がすっと頭に入る。
ところで、この「はじめに」には驚く箇所がある。ボブ・ディランの歌が引用されているのだ。
きみはやがて悟るだろう
イスカリオテのユダには
神が味方していたのだと(〈神が味方〉)
この歌が発表された1964年頃は、『ユダの福音書』のコプト語訳が収められたチャコス写本は存在も知られていなかったから、ディランは詩人の直観でうたったのかもしれない。
この箇所の〈イスカリオテのユダに/神が味方していたのかどうか〉(Whether Judas Iscariot / Had God on his side)は、後に1970年のロック・オペラの歌 Jesus Christ Superstar(詩:Tim Rice)のユダの視点に影響を与えたと言われている。
*
1970年代に発見されたチャコス写本は全部で66ページからなり、収められた四つの書のうち三番目の『ユダの福音書』は33-58ページにあたる。
以下、各ページのうち、気がついた点を記す。写本原本のページ数は本書にならい、【】で示す。
*
しばしばイエスはそのままの姿で弟子たちの前には現れず、一人の子供として弟子たちの中にいた。【33】
(大人の)イエスが子供の姿で現れたとの記述は、ふつうの新約聖書には出てこない。ふつうの新約聖書が用いられるキリスト教会(「新興正統教会」と本書は記す)には知られていないが、ナグ・ハマディ文書などには出てくる(例えば、同文書にはイエスが姿を変える話が The Second Discourse of Great Seth[大いなるセツの第二の教え]にある)。
この〈正統〉をめぐる争いはローマがアレクサンドリアに勝ったわけだが、勝敗が違えばそれ以降の歴史も変わったかもしれない。ボルヘスはグノーシス主義についてこう述べる。
もしローマでなくアレクサンドリアが覇権を握っていたならば、ここで概略を紹介した突拍子もない話の数々も、一貫性があって威厳にあふれた正統な逸話ということになるだろう。(10-11頁)
よくあることだが、歴史は勝者の歴史であって、それ以上でもそれ以下でもない。何が〈正統〉かということも、勢力争いの帰趨が変われば変わるだろう。その程度のものだ。その程度のものだが、それが二千年続いて、やっといま変わり始めているのかもしれない。
*
(パンに感謝の祈りを唱えている弟子たちに近づいて笑ったイエスに対し、弟子たちが理由を尋ねると、イエスが答える。)
「私はあなたがたを笑っているのではない。〈あなたがたは〉自分たちの意志でそうしているのではなく、そうすることによって、あなたがたの神が賛美される[だろう]からそうしているのだ」【34】
ここでは、イエスが明確に「あなたがたの神」と自分の神とを区別する。本書は〈ここで「弟子たちの神」と表現されている神は、至高神ではなく、この世の支配者である〉と注釈する(26頁)。
この「弟子たちの神」と「イエスの神」の区別は、スパロウダンサーが「ユダの福音書 バルベーローと長年の秘密」で強調する点の一つである。
*
ユダはイエスに[言った]。「あなたが誰か、どこから来たのか私は知っています。あなたは不死の王国バルベーローからやって来ました。私にはあなたを遣わした方の名前を口に出すだけの価値がありません」【34】
本書は〈イエスがバルベーローの「不死の王国(あるいはアイオーン)」から来た神の子であることを告白することは、セツ派(グノーシス主義の一派)の用語によれば、イエスが天上の神の王国から来た神の子であることを公言することである。セツ派の文書では、バルベーローは万物の神なる母体で、「無限のもの」と呼ばれる父のプロノイア(先見、摂理)である〉と注釈する(29頁)。
本書の注釈は、続けてバルベーローの名について考察している。評者には、スパロウダンサーの「ユダの福音書 バルベーローと長年の秘密」における考察のほうが興味深く思える。
なお、本書の内容をドラマ化したDVD「ユダの福音書 イエスと”裏切り者”の密約」(日経ナショナル・ジオグラフィック社、2006)は興味深い映像を含むが、このユダとイエスの会話部分のうち〈あなたは不死の王国バルベーローからやって来ました〉は省いている。
同DVDに収められた特典映像で、マービン・マイヤーがこのくだりに触れる時に、わざわざ〈不滅の王国から来られたのですね〉(You are from the immortal realm of the divine)と語り、やはり〈バルベーロー〉への言及は注意深く避けている。ただし、マイヤーは本書に収められた小論では〈バルベーロー〉を詳しく論じている。
*
(イエスはユダに言った)
「だがお前は真の私を包むこの肉体を犠牲とし、すべての弟子たちを超える存在になるだろう。」【56】
議論を呼ぶ箇所だが、本書は〈ユダはイエスから、イエスの真実の霊的自己に衣を着せている、あるいはそれを身にまとっている肉なる体(人間)を犠牲にささげて、自分を助けるよう命じられる。イエスの死は、ユダの働きにより、内なる霊的人間の解放へと変えられる〉と注釈する(70-71頁)。この解釈は、すぐ後の【57】とよく符合するように思われる。
*
(イエスはユダに言った)
「これでお前にはすべてを語ったことになる。目を上げ、雲とその中の光、それを囲む星々を見なさい。皆を導くあの星が、お前の星だ」
ユダは目を上げると明るく輝く雲を見つめ、その中へと入っていった。地上に立っていた人々に、雲の中から声が聞こえた。【57】
本書は〈この箇所は「ユダの変容」とも呼べるだろう〉と注釈する(71頁)。確かに、キリストの変容を思わせるような、何らかの変容、ないし昇天を示唆する箇所だ。
*
本書の翻訳について。「十三番目の精霊であるお前が、なぜそんなに躍起になるのか。」(44頁)は「十三番目の霊」の誤植。原文は 'You thirteenth spirit, why do you try so hard?' で、spirit は原文の注に 'demon' (daemon) とある。本書では本文を「精霊」とし、注で「霊」とするが、それぞれ「霊」と「ダイモン」などとすべし。「精霊」はこの文脈に全く合わない。110頁、および186頁(2箇所)の「精霊」も誤植。キリスト教関連の翻訳書で「精霊」と出てきたら、まず誤植。
創意あふれる「先在の知識」の訳はすばらしい(167頁)。これは別のグノーシス文書の翻訳で、原文は 'Forethought' ('Barbelo Conceives' in 'The Secret Book of John')。日本では「摂理」とされる語だが、ここは文脈的に無理がある。
*
本書に収められた4つの小論のうち、バート・D・アーマンの「よみがえった異端の書 『ユダの福音書』の驚くべき教え」には、慄然とさせられる。あまりにも鋭い分析が展開されているのだ。
グノーシス主義と伝統的なキリスト教との違いを説明する中で、アーマンは、〈この世界は、唯一絶対の神が創造したのではないということだ。この世界を創造した神は、旧約聖書の神であり、それは神の領域から派生した、劣位の神なのだ〉とさらっと述べる(109頁)。
グノーシス専門家にとっては常識に属することでも、本書を読む一般読者には驚天動地の文章ではないか。
この延長線上に、〈(グノーシス派の教義ではイエス・キリストは)旧約聖書の神、創造神の息子でもない〉と述べるのは、アーマンからすれば理の当然である(110頁)。
このような背景知識があれば、本書のユダの言葉も、少しは理解しやすくなる。
もっとも、このこと(イエスが旧約聖書の神の息子でないこと)は、スパロウダンサーが指摘するとおり、新約聖書ヨハネ8章(44節)にはっきり書いてある(Mary Sparrowdancer, 'Declaration of Independence
against a War God', 2006)。
