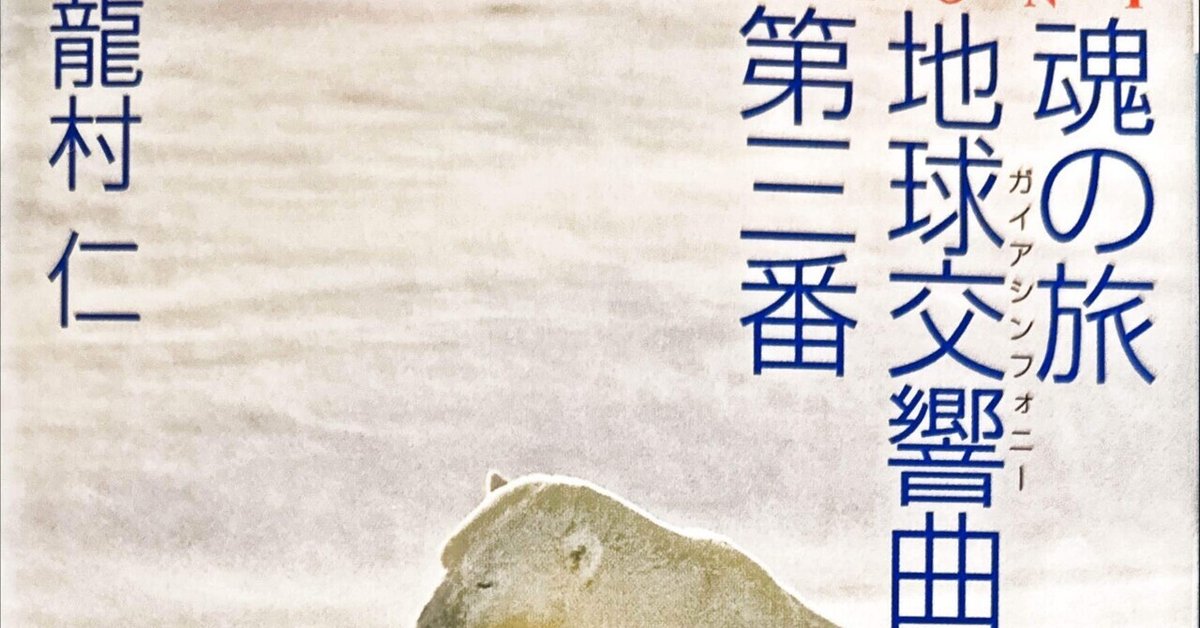
『魂の旅 地球交響曲第三番』ノート
龍村 仁 著
角川ソフィア文庫
著者の龍村仁は、NHK出身の映画監督である。独立後、ドキュメンタリー映画『地球交響曲(ガイアシンフォニー)』のシリーズを第一番から第六番まで制作している。このシリーズは、全国で220万人の観客を動員したそうだが、筆者は寡聞にしてこの映画のことは知らなかった。
この本は、筆者が星野道夫ファンだということを知っている友人が紹介してくれた。友人も星野道夫ファンで、いわば読書においての同好の士だ。
筆者の本棚を調べてみたら星野の本がほかに5冊ある。このnoteでも『旅をする木』と『約束の川』を取り上げたことがある。友人は、この本と、『悠久の時を旅する』という写真エッセイ集(2020年初版)を紹介してくれた。
星野道夫という存在に魅了された龍村が、『地球協奏曲』の第三番で星野を取り上げようとしていたが、撮り始める前に星野道夫はカムチャツカ半島で取材中に不慮の事故で亡くなってしまう。しかし、龍村はなんとか映画を完成させたいとアラスカに渡る。
そして星野のアラスカに対する思いに感銘して交流を始めたエスキモーやインディアンの人たちをはじめ、星野と会ったこともないのに、彼の行動力と思索、自然や生きものへの憧憬、人間の原初的な感覚を大事にしてきた彼の生き方に魅了された多くの友人たちの星野への思いと、なんとか『第三番』を完成させたいという著者の大いなる熱意が見事にシンクロする。その環がどう繋がって『第三番』の完成に至ったのかが、この本に事細かに描写されている。
龍村は、あるときは星野道夫の著書をもとにその足跡を辿り、あるときは彼から聞いた話の断片を頼りに、星野道夫のことを知らない人物も訪ね、シナリオもなくほとんどぶっつけ本番で取材を進めてきた。
南東アラスカの先住民クリンギット族の「ワタリガラス神話」の語り部であるボブ・サムは、星野が青森県の三内丸山遺跡(縄文時代)と一緒に訪れてみたいと思っていた人物だ。
この頃、星野は、アラスカ各地に残る「ワタリガラス神話」を持つ先住民を訪ねる旅をはじめていた。
その旅をはじめるにあたって、星野は敬愛する作家のリチャード・ネルソンに会うために南東アラスカの港町シトカを訪れたのだが、リチャードの車が町にさしかかった時に偶然見かけたボブを星野に紹介した。星野とは初対面のボブの挨拶抜きの「昨日、墓場でワタリガラスの巣を見つけたよ……」という言葉に星野は驚く。町ではほとんど見かけることのないボブをたまたま見かけ、声を掛けたところ、その男の口からワタリガラスという言葉が出るとは……。この日は星野が神話の旅を始めた初日だったのだ。
そのほか、「私の知る全ての科学的知識に照らしてみて、宇宙には意志がある」という天才宇宙物理学者のフリーマン・ダイソンにも取材をしている。
フリーマンは、〝生命の多様性〟について次のように語る。
35億年前にこの地球に初めての原初生命体が誕生した頃、〝死〟は生命システムの中には組み込まれておらず、分裂と増殖を繰り返すだけで、必ず死ぬとは定められてはいなかった。
生まれた生命が必ず死を迎えるという仕組みが生命システムにプログラムされたのは〝性〟が誕生した時からだとフリーマンはいう。二つの遺伝子の組合せの繰り返しで生命が多様化し、未曾有の危機が訪れても、その多様性の中から、危機を乗り越えられる新種の生命を生み出すチャンスが生まれる。それはすなわち生命全体を永続させるために種や個体を多様化し、複雑化させていこうとする、何かの大いなる〝意志〟の現れで、その代償として個体の〝死〟があるという。
リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』に通じる考え方であり、示唆に富む。
マイナス40度にもなるフェアバンクスに住む老人ビル・フラー――彼はきわめて個人的な、社会の尺度からは最も離れたところにある人生の成否の存在を星野に教えてくれた人物だ。アラスカを終生の地と定めた星野にとって、ビルの生き方こそ、自分の人生の理想の姿だと思っていた。
また南東アラスカにある巨木を削って作った古代カヌーでハワイとタヒチの間の5000キロの海を、近代航海器具を一切使わずに成し遂げたナイノア・トンプソン――彼は星野とは一面識もなかったが、〈旅をする木〉という一点で星野と繋がる。
ブッシュ・パイロットで星野の戦友ともいえる存在のドン・ロス。ブッシュ・パイロットとは、個人所有の小型機で、客からの要請で、一歩間違えば〝死〟につながるアラスカの大自然の滑走路もないところで離着陸をする仕事を請け負うパイロットだ。
北海道余市にあるフゴッペの洞窟と、青森県の三内丸山遺跡のことも書かれている。
星野の言葉を覚えていた著者はボブ・サムをこの洞窟に連れて行った。するとその洞窟の壁面に彫られている絵を見た途端、ボブの様子がおかしくなったのだ。あとで聞いたところによると、それらの絵は、自分たちの祖先が刻んだシトカの洞窟に刻まれた〈舳先にワタリガラスのシンボルをつけたカヌーの絵〉とほとんど変わらないものだったというのである。
また三内丸山遺跡の訪れたときは、ボブは自分の祖先と共通のシンボルを見つけて驚く。星野道夫が直感したように、そしてボブ・サムをこの遺跡に連れて行きたいと考えていた動機――クリンギット族の神話が語る数千年前の南東アラスカの先住民と、東北地方や北海道に住んでいた縄文人との間に繋がりがあったということの証明のように龍村には思え、縄文人は〝海の民〟であったのではないかと彼は推測する。
全編が、星野道夫の最期のエッセイ集『旅をする木』の足跡を辿る旅、それも数々の〝シンクロニシティ〟に導かれ、星野道夫に魅入られ触発された数々の出会いに満ちている。
著者は前書きに、映画監督が自分の作品の〝裏話〟を書くということはあまり潔いことではないと書いているが、この本は決して取材の裏話だけで終わってはいない。映画監督という視点を超えて書いたこの『魂の旅 地球交響曲第三番』は、単なる取材記にとどまらず、自然と人間の織りなす時空を超えた〝魂〟の物語だ。
この本を読んで、筆者にとってますます星野道夫が大きな存在になった。
いま筆者は『旅をする木』をまた読み始めた。これで読み返すのは5回目である。ドッグイア(Dog ears、Dog-ear)と付箋やマーカーだらけだが、読むたびに思わぬ発見がある。
