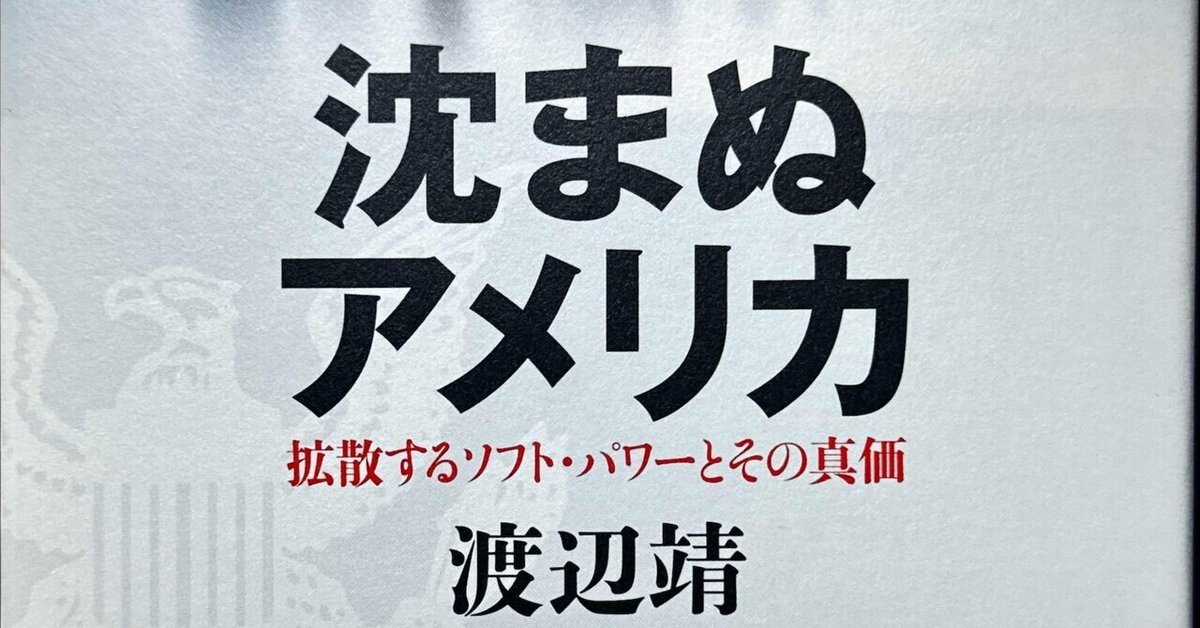
『沈まぬアメリカ』ノート
渡辺 靖 著
新潮社刊
著者はアメリカ研究が専門の文化人類学者である。筆者は2015年にこの本を購入して読んだ。当時の印象として、アメリカの今後の行く末を暗示するようなことが書かれていたと記憶しており、再読してあらためてその感を深くした。
副題に「拡散するソフト・パワーとその進化」とある。
アメリカのソフト・パワー(文化・価値〈観〉)の源泉となっている「ハーバード大学」、「リベラル・アーツ」、スーパーマッケットの「ウォルマート」、キリスト教保守主義の「メガチャーチ」、「セサミストリート」、「政治コンサルタント」、「ロータリークラブ」、「ヒップホップ」を切り口に、何度も衰退論が囁かれつつも世界中に拡散している〝アメリカン・レガシー〟のパワーを分析した現代アメリカの文化論となっている。
もちろんアメリカは現在でも、その経済力と軍事力において圧倒的な優位を保っているハード・パワー国家であることは間違いない。
いまから11年前の2013年9月に、オバマ大統領はシリア政府による化学兵器使用問題をめぐる演説の中で、「アメリカはもはや世界の警察官ではない」と述べる一方で、「アメリカは世界における指導的立場を担っていかなければならない。今でも例外的で特別な国だ」(本書P13)と述べている。前者はハード・パワーの国としてのアメリカの役割について、後者は民主主義の理念を基としたソフト・パワーについて言及している。
しかし、いまのアメリカ社会は二極化・分断のため、国内のソフト・パワーさえも存亡の危機に立たされているように思われる。
「はじめに」で著者が引用しているが、アメリカの国家情報会議(National Intelligence Council)は2012年の報告書(Global Trends 2030)で、2030年の世界情勢を展望しており、その分析がまさにいまの世界情勢を予見していた。
曰く、「アメリカは世界のリーダーであり続けるものの一極体制は終わり、世界は多極化していくだろう」と予測し、アメリカの相対的衰退論を展開している。
さらにアメリカ国内の状況として、「格差拡大に伴うミドルクラスの縮小」、「党派対立」、「硬直した利害関係」などにより、「リベラルデモクラシーの盟主」を自負するアメリカの国内ガバナンスの弱体化で末期症状的な機能不全に陥っているという「本質的衰退論」も叫ばれるようになった。
本質的かどうかは別として、大統領選を年内に控えたいまのアメリカの現状と先行きの不透明さをよく言い表している。
アメリカは、ヨーロッパの旧世界を支配していた特権階級の世襲化に反旗を翻して、市民=デモス主体の社会建設を目指した実験国家である。そんな自由主義観に基づいて建国されたアメリカは移民国家でもあり、その民族の多様性は新たな文化を生み出した。
この本に直接的に触れられてはいないが、音楽分野におけるブルースやジャズやロックミュージックもその多様性と混淆から生まれたものであろう。
その意味で、アメリカから生まれたソフト・パワーはいまだに世界を席巻しているといえる。
取り上げられたテーマに戻るが、批判的思考の鍛錬の場としての人文科学、社会科学、自然科学の三分野にまたがる「リベラル・アーツ教育」――これはもともと「人間を解放する自由学芸」という意味で、ヨーロッパの大学制度の伝統を引き継いではいるが、その要諦は宗教的権威や国家的権力、伝統や因習や偏見から「精神と知性」を解放することにある(本書P28)。それは健全な民主主義に必要な異なる視点や立場を互いに尊重・尊敬し合う市民を育てるのに最低限必要なものであろう。
近年、このリベラル・アーツ教育の是非について論議があるが、それが国際標準としてアメリカのソフト・パワーを下支えしていることは間違いない。いまやこの教育はアラブ諸国や東南アジアにも〝輸出〟されている。
スーパーマーケットのウォルマートは、1902年、ワイオミング州で第一号店がオープンした。その店頭には、「我々はより安く売る」と「満足を保証する」という2つのモットーを掲げ、特売やセールを行わず、年間を通じて「毎日低価格」の販売方法をとった。
創業者のウォルトン氏は、企業の社会的責任(CSR)が問われる以前から、災害の被災者への物資支援や義捐金の提供などをしており、環境問題や社会的差別などの問題にも取り組んで、アメリカの世論形成に少なからぬ影響を与えている存在であった。
ウォルトン氏は、「ウォルマートとは文化であり、それは世界の他の地域でも通用する文化である」と公言し、2015年の時点でも世界27か国、1万1千以上の店舗を展開し、220万人の従業員を抱え、毎週2億人以上の顧客が店を訪れている。
著者は、もしウォルマートが国家なら、国内総生産で世界28位にランクインし、その順位はオーストリアの一つ上、ノルウェーの一つ下に匹敵し、雇用者数では世界でもアメリカ国防総省と中国の人民解放軍の次に大きいという(いずれも執筆当時の数字・本書P66)。
ただ影の面としては、出店地域からの批判がある。元々からある地元の商店にとっては勝ち目のない価格競争を強いられているからだ。
このウォルマートの二面性を、「田舎の人びとにとっての救世主か、それともスモールタウンの殺害者か」と、ザ・ニューヨーカー誌のスーザン・オルレアン記者が的確に表現している。
あと一つ「セサミストリート」をとりあげる。
カラフルなキャラクターのエルモやクッキーモンスターやビッグバードが有名だ。それに多くの俳優がゲスト出演していた記憶がある。
筆者が子どもと一緒にみていた頃は、NHK教育テレビで放映していたが、子ども向けの教育番組と銘打ちながらもなかなか面白い内容であった。
この番組ができたきっかけは、1966年、ニューヨークで開かれたあるパーティの席で、カーネギー財団のロイド・モリセット副理事長と放送ジャーナリストのジョーン・ガンツ・クーニー氏が、新しいタイプの幼児教育番組の必要性について意気投合したところから始まる。
そしてその構想に、カーネギー財団のアラン・パイファー理事長とフォード財団のマクジョージ・バンディ理事長が合わせて600万ドルの支援を約束し、他の財団やアメリカ教育省などからの助成金200万ドルを加えた総額800万ドルをもとに「セサミ工房」の前身となる非営利団体「子どもテレビ工房」が創設された。ちなみにマクジョージ・バンディ理事長の前職は、ケネディー・ジョンソン両政権の時の国家安全保障担当大統領補佐官(1961年~1966年)であり、〝ベスト・アンド・ブライテスト〟の一人である。
モリセット氏とクーニー氏が共有していたのは、アメリカの未来に対する危機感であった。1960年代半ばから、アメリカではベトナム戦争の泥沼化、インフレの発生、人種問題や青少年の非行、薬物依存者の増大、ケネディ大統領の暗殺(1963年)、公民権運動を推進したキング牧師の暗殺(1968年)など社会不安が高まっている中で、次世代教育の重要性が叫ばれ、幼児期のうちに人種や身分にまつわる偏見をなくし、社会の融和を目指すべきだと二人は考えていたのだ。
制作手法として斬新だったのは、教育の専門家と調査研究の専門家、テレビの制作プロデューサーの三者が対等の関係だったこと、そしてビッグデータの活用がこの番組の成功の原因となった。
一例を挙げると、それまでの幼児番組の常識を打ち破った1時間番組であったが、1時間あれば母親がテレビを子守代わりにして家事に専念できるというデータをもとにしたからだという。
また、幼児の集中力は2、3分が限度で、総じて軽快なテンポを好むというデータを踏まえ、1時間を30~40のセグメント(部分・節)に分けて、それぞれのセグメントのテンポや場面、キャラクターをすべて変えて幼児の関心がテレビから離れないように工夫をしていた。
そして新進の人形師が日本の浄瑠璃からヒントを得て考え出したマペット(マリオネット〈操り人形〉とパペット〈指人形〉合成語)を採用し、多様なキャラクターと生身の俳優の共演も特徴的で、人選も人種のバランスを考えて制作されていた。舞台は言語や宗教が異なる人種・民族が共存共栄するニューヨーク市の下町をモデルにした架空の「セサミストリート123番地」であった。
セサミストリートが目指した社会融和の理念はアメリカにおけるリベラリズムが目指した理想と重なる。差別や偏見、無知は知性や理性の力によって克服しうる、克服しなければならないというものだ。
このセサミストリートはこれまで約30の言語、150か国で放映されてきており、それぞれの地域の文化や事情を反映して綿密にローカライズされてきており、アメリカのポップカルチャーの象徴として世界に広がり、1983年には中国でも番組が制作され、1993年~2001年まで北京語による中国版セサミストリート(芝麻街)の放映が続いた。
2010年には、セサミ工房は中国の有力メディアとの共同制作で、中国版「ビッグバードが世界を見る」の放映が始まった。ちょうど中国のGDPがわが国のそれを抜いて世界第2位になった時期だ。タイトルからして、中華思想的だと思うのは筆者だけだろうか。
理想主義を標榜してスタートしたセサミストリートが、その普遍性ゆえにローカライズされ中国で制作されているという事に歴史の皮肉を感じるのである。
ほかのテーマに触れる余裕はないが、いまに続くアメリカ社会の光と影をよく切り取った内容となっている。
