
知ってるようで知らない「投資助言」とは?
FX界隈ではよく目にする「インフルエンサーによる先出し予想」や
「FX業者の斡旋(IB・アフィリエイト)」による収益化。
これらは昔から
”違法行為なのではないか?”
と言われてきましたが、
実際のところ詳しい弁護士を通さない個人にとっては
「どこまでが違法でどこまでがセーフなのか」が未知数のゾーンです。

昨年末には、【私人逮捕系Youtuber】として注目を集めている
”新宿109 KENZO”氏がこの話題にメスを入れることとなり、
一時世間を賑わせました。
私自身も実際にアフィリエイト広告を打ったりしているので
この際、徹底的に曖昧な情報をまとめてみようと思い執筆に至っています。
この著書が、これから投資系ジャンルで稼ごうと思っている方にとって
お役に立てれば幸いです。
では早速本題に入りましょう。
①投資助言業務とは何なのか?
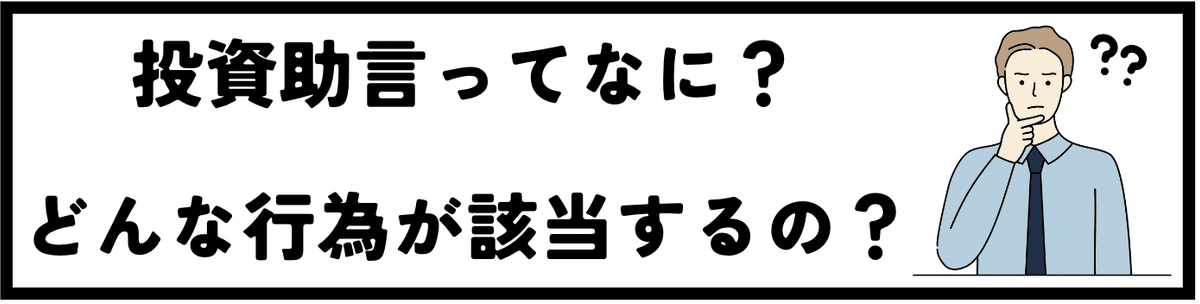
投資助言の資格とは、顧客に投資に関する助言を
行う際に必要となる資格や認可を指します。
代表的なもので言うと、「未来の価格予想」がこれに該当します。
日本では、主に以下の資格や登録制度が関係します。
1. 投資助言・代理業登録
日本で投資に関する助言を業として行うには、金融商品取引法に基づいて「投資助言・代理業」の登録を行う必要があります。

投資助言・代理業とは
顧客に対し、有価証券や金融商品(株式、債券、投資信託など)に関する投資の助言を行うことや、金融商品取引業者の代理・媒介をする業務。
「投資助言・代理業」の登録は、その責任制から
誰でも取得可能なわけではなく一定の条件が加味されます。
<登録要件>
知識や経験
業務を適切に遂行できる投資の専門知識や経験が求められます。
内部管理体制
コンプライアンスや内部監査などの適切な体制が整備されていること。
純資産要件
財務的な安定性があること(純資産が一定額以上など)。
登録審査
金融庁や各財務局への申請・審査が必要。
これらを全てクリアした屋号に対してのみ
「有償での投資助言業」が可能となるのです。
(*無償の範囲での投資助言に関しては、
現在のところ金商法違反に問われる可能性は極めて低いと言えます。)
2. 関連資格
「投資助言・代理業」の登録は、審査制となっていることから
以下の資格を取得しておくと、投資助言業務のスキルや信頼性を
高く評価され審査に通りやすくなるとされています。
(1) 日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)

投資分析や運用に関する高度な知識を持つことを証明する資格。
資産運用業務や投資助言に関する専門性が高い。
(2) ファイナンシャル・プランナー(FP)

個人の資産形成やライフプラン設計におけるアドバイスを提供。
直接的に投資助言を行う資格ではないが、資産形成の相談に役立つ。
(3) 証券外務員資格

証券会社や銀行、金融商品仲介業者で、金融商品を販売・勧誘するための必須資格。
「一種外務員資格」が特に投資助言業務で役立つ。
(4) CFA(Chartered Financial Analyst)

国際的な投資分析の資格で、投資助言業務におけるグローバルな信頼性を向上させる。
3. 投資助言の規制と注意点
投資助言を業務として行う場合、以下の点に注意が必要です。
無登録での助言は違法
投資助言・代理業の登録なしで、有償の助言を行うと法律違反になります。
助言内容の責任
助言が投資家の損失につながった場合でも、助言者には説明責任が求められます。
広告や勧誘の規制
不当表示や過剰な勧誘は禁止されています。
まとめ
投資助言を行うためには、金融商品取引法に基づく登録が必須であり、資格としてはCMAやFPなどが役立ちます。
また、無登録の助言は違法となるため、法律や規制をしっかりと理解し、適切な資格や登録を得たうえで業務を行うことが重要です。
②投資助言の資格を取得するメリット、デメリット、取得手順

有償の先出し予想をするならば、
「投資助言・代理業の登録」が必要なことがわかりました。
ですが、SNSを見渡しても実際に登録している人はほぼいません。
”それはなぜか?”
本章では、この点について「メリット・デメリット」と「取得の手順」についてもまとめていきます。
<メリット>
法的に投資助言を行える
投資助言・代理業登録を行えば、合法的に投資助言業務を展開できます。
これにより、有償での助言やサービス提供が可能になります。
信頼性の向上
投資助言の資格や登録があることで、クライアントからの信頼が高まり、専門家としての地位が確立されます。
ビジネス機会の拡大
投資アドバイザリー業務に参入できるため、企業や個人向けのコンサルティング、セミナー運営、SNSでの有料サービスなどの新しい収益源を得るチャンスが広がります。
専門性の向上
資格取得の過程で投資分析、法律、金融商品の知識が深まり、自身のスキル向上にもつながります。
収入面での期待
投資助言業務の報酬は高い場合が多く、特に成功報酬型のビジネスモデルでは高収益が期待できます。
<デメリット>
取得と登録のコスト
資格取得のための講座費用や受験料、投資助言・代理業登録に必要な申請料(約15万円)や維持費用(顧問弁護士費用、内部管理コスト)がかかります。
法的・倫理的責任
投資助言の内容には法律上の責任が伴います。不適切な助言や説明不足は、顧客からのクレームや損害賠償請求につながるリスクがあります。
継続的な学習が必要
法規制や市場環境の変化に対応するため、定期的な勉強や資格更新が必要です。
内部体制の整備が必要
金融庁や財務局に認可されるためには、適切な管理体制(内部監査、コンプライアンス部門の設置など)が求められるため、個人で運営する場合の負担が大きいです。
競争環境の厳しさ
多くの企業や個人が投資助言業に参入しており、差別化が必要となります。
<取得手順>
1. 必要な資格を取得
投資助言・代理業登録そのものには特定の資格は必要ありませんが、以下の資格を持っていると登録審査で有利です。
日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)
試験合格後、実務経験(3年以上)が必要。
FP(ファイナンシャル・プランナー)資格
日本FP協会やきんざいで受験。
証券外務員資格
金融商品仲介業者で働く場合は必須。
2. 会社設立または個人事業主として登録
法人か個人事業主としての登録が必要です。
法人の場合、純資産が1,000万円以上の要件があります。
3. 内部管理体制を整備
法律に基づくコンプライアンス体制を整えます。
マニュアルの整備
コンプライアンス規程、リスク管理規程などの作成。内部管理部門の設置
法律違反を防ぐ監視体制の構築。
4. 投資助言・代理業登録の申請
申請先:金融庁または管轄の財務局。
必要書類:
登録申請書
事業計画書
業務運営体制図
純資産の証明資料(法人の場合)
5. 登録審査
金融庁または財務局による審査が行われ、登録の可否が決定します。
審査期間は約3か月~半年程度。
6. 登録完了後の業務開始
登録後は、金融庁の監督下で投資助言業務を行います。
毎年の報告義務や監査に対応する必要があります。
まとめ
投資助言の資格や登録は、信頼性の担保や業務範囲を合法的に広げれるという大きなメリットがありますが、取得や運営にはコストや時間が伴います。
特に、法規制への対応と内部管理体制の構築が面倒になっており、
個人でビジネス構築できていないうちにはなかなか手が出せない内容になっています。
そのため、投資界隈では「グレーゾーン」と言う扱いで投資助言・代理登録を行わないまま有償の価格予想やアドバイスを行っていると言うのが現状です。
③登録と維持費用について

投資助言・代理業の登録には、以下のような費用がかかります。
1. 登録申請費用
申請手数料: 約15万円(非課税)
登録申請時に、金融庁または財務局に支払う必要があります。
2. 運営に必要なコスト
登録後の運営には継続的に費用がかかります。主なものを以下に挙げます。
(1) 純資産要件の確保(法人の場合)
法人として登録する場合、最低1,000万円以上の純資産が必要です。
設立時にこれを確保するための資本金が必要。
(2) 内部管理体制の構築
内部監査・コンプライアンス体制の整備:
マニュアル作成、監査体制の整備などにコストが発生。
人件費:
内部管理責任者やコンプライアンス担当者の雇用が求められる場合、追加の人件費が必要。
(3) 継続的な顧問契約費用
法的アドバイスを受けるために、弁護士や専門コンサルタントとの顧問契約を結ぶ場合があります。
顧問弁護士費用: 月額数万円~10万円程度が相場。
(4) 事務所費用
オフィススペースを借りる費用やインフラ整備(PC、セキュリティソフトなど)が必要。
(5) 保険加入費用
投資助言業者は、万が一に備えて業務上の損害賠償保険(PL保険)への加入を推奨されます。
保険料: 年間数万円~数十万円。
(6) 年次報告や監査対応
毎年の監査や、金融庁への報告業務に伴うコストが発生。
3. 資格取得にかかる費用(任意)
資格そのものは登録に必須ではありませんが、取得することで登録時の信頼性が高まります。
以下は代表的な資格とその取得費用の例です。
証券外務員資格: 2~3万円(受講料+試験料)
FP(ファイナンシャルプランナー)資格: 約2~5万円(受験料+教材費)
CMA(証券アナリスト): 30~50万円(受講費用+試験料)
<総合的なコスト例>
初期費用(申請+体制整備): 50万~300万円程度
規模や体制による差が大きい。
年間運営費: 50万~200万円以上
人件費、保険料、監査対応などが含まれる。
まとめ
登録費用そのものは15万円と手頃ですが、運営に必要な体制を整えるためのコストが大きくなります。
特に法人として登録する場合、最低1,000万円以上の純資産が必要というハードルが大きくこの点が取得難易度を高めていると言えるでしょう。
