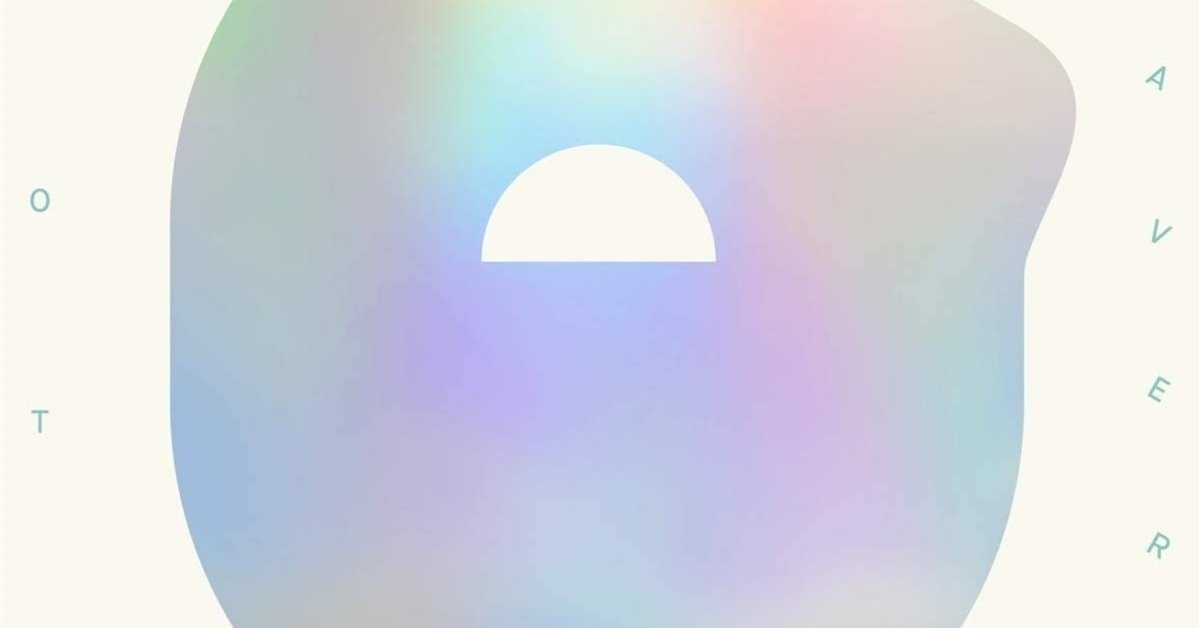
家で聴くための音楽、その7:Geotic『Traversa』
“パッシブ”なダンス・ミュージック
家にいることが増えてきた人に、家で聴くとよい感じではないかしら、と感じる音楽を紹介していく連載。
第7回はGeoticの『Traversa』(2018)。
この連載で紹介している音楽は、積極的にこちらからなにかに働きかけるためのものではなく、むしろ、受動的に聴くこと、それによって、リラックスしたり、気を紛らわせたりするものであることが多い、と思う。
「と思う」としたのは、音楽の聴き方というのは本質的には自由だと感じる一方で、キュレーションする際には、やはり、ある観点でもって、このようなシチュエーションに似合うものである……という意図を持たないと、なんとも茫洋とした選択になってしまうのではないかと感じるからだ。
とはいえ、この考えをだらだらと話していても、話は進まない。これはあくまで書き手の話。
受動的に聴く、パッシブに楽しむ音楽といえば、静的で、落ち着いた内容のものになるのではないかと予想されるかもしれない。では、ダンス・ミュージックはどうだろう?
GeoticことWill Wiesenfieldは、ロサンゼルスのビートメイカー。彼の名を高めたのは、バス(Baths)名義での活躍。「Cerulean」(2010年)は、当時流行していたチルウェイブとヒップホップを縦横無尽に組み合わせたようなデビュー・アルバム。続く「Obsidian」(2013年)では、よりダークな重厚なサウンドを生み出し、インディー・ロックの愛好家などにも高く評価された。
ビートメイカーといっても、ストリートの雰囲気というよりは、ファンタジックでエモーショナルな世界観を作っている。内省的、ともいえるかもしれない。
彼は、Web上でGeotic名義でも多数の作品をリリースしていた。ギターだけ、あるいは声だけを使った、ビートのない幻想的な作風だった。実験的な音作りの名義かと思いきや、データだけではなくフィジカルでもリリースされている『Abysma』(2017)では、しっかりとしたビートがあり、その上でドリーミーなシンセやメロディアスなピアノなどが漂うという、アンビエントな雰囲気をたたえたダンス・ミュージックになっている。
『Abysma』に続く『Traversa』では、世界観は変わらないものの、より丸みを帯びた音像になった印象を受ける。ほどよい疾走感があるけれど、聴き手を置いていくほどにアップテンポではない。これがGeoticの身上だ。
リバーブのかかったシンセ、ピアノやヴァイオリンの音色に感じるほのかな美しさは、どちらかといえば静的なもの。(よい意味で)ゲームのサウンドトラックに組み込まれていてもおかしくない。Baths名義でもボーカルを取る彼だけあって、自然に歌声を入れてくるのも、お手の物といった感じ。
聴きやすい、と評しても、間違いではないだろう。ツルッとしたシンセサイザーの音色、重すぎないビートの質感も、耳障りになる要素を排除しているかのようだ。
音楽を「部屋か車で、1人で聴くもの」と語る彼らしく、フロアで盛り上がるような作風とはちょっと違う。落ち着いてリラックスできる世界観にまとめているのが好印象。
全編を通じて、基本は四つ打ちのリズムではあるものの、Kompactレーベルの作品を思い切りエモーショナルに解釈したような「Aerostat」、細かいプチプチしたリズムをアクセントにする「Town Square」などには、2000年代のエレクトロニカのようなムードも感じる。
Will WiesenfieldはBathの音楽を「アクティブ」なもの、一方でGeoticの音楽を「パッシブ」なものと位置づけているとのこと。
積極的に踊らせる、ぐっと引きずり込んで聴かせるというわけではない、押し付けがましくない仕上がり。ダンス・ミュージックとはいっても、リスナーの身体を強制的に揺らすようなヒプノティックなものではない。“パッシブ”で繊細なダンス・ミュージックで、多くの人の耳に馴染みそうな作品だ。
ビートの立った音楽といえども、何を持って、フロア向きとするのか、あるいはベッドルーム向きとするのかは、個々人の価値判断にもよるところで、断言はしづらいけれど……。
すくなくとも、Geoticはベッドルームで聴いても違和感のない音楽、外に出づらい環境の中で、どこか遠くの世界を想起させてくれる音楽である、ということは確かではないかしら。
