
勉強すればするほど、自分は何もわかってないことに気づく矛盾〜知ってるつもり 無知の科学〜
学びの第一歩は「何も知らないこと」に気づくこと

読書をしていて一番感じることは、
「自分は何も知らないんだなぁ」
ということ。
矛盾しているかのように聞こえますが、知れば知るほど自分が何も知らないことに気づくんですよね。
それは何故だろうか?と思ったため著書『知ってるつもり 無知の科学』を読みました。
本書は2人の専門が違う認知科学者が
なぜ人間はほれぼれするような知性と、がっかりするような無知を併せ持っているのか?
あるいはなぜ個人としては限られた理解しか持ちあわせていないのに、種としてこれほどの偉業を成し遂げてこられたのか?
本書はこうした疑問に答えていきます。
自分の無知を自覚する簡単な実験として
トイレやファスナーの仕組みを語りなさい
というものがございます。
日常で使っているモノについてどれだけ深く語るかを質問しているのですが、この時点での回答は「理解している」というものが多いモノ。
しかし、「具体的にどのような仕組みで動くのか?」と質問すると、たいていの人はほとんど何も語れない。
知っていると思っているのに、実はそれほど知らないものです。
なんでこういった「実はそれほど知らない現象」に陥るのでしょうか?
人間の能力は本当に限られているのだ!

とはいえ、「実はそれほど知らない現象」は人間の脳の情報処理の観点からすると当然と言えます。
というのも、
1.人間の脳の記憶量はパソコンの1/500ほどしか保存できない
2.それでいて、世界の構造は複雑であるため記憶しきれない
3.だから、「だいたいこう動くんだろう」と仕組化する脳処理を覚えた
という思考様式で生きてきたのです。
先ほどのトイレや、ファスナーも「だいたいの使い方」で流れたり、閉めたりといったことができます。
個人としては、人間の処理能力なんてそんなものです。
では、何故こんなにも人間は種としてこれほど君臨できるのか?

となると、個の能力が高いとはいえないのに、何故ここまで人は繁栄したのでしょうか?
結論から言うと、『コミュニティ化』にあります。
人間は「言語」を覚えたことによって、
知識を遺すこと
に成功し、共有しました(過去に『オリジン・ストーリー』と言う本の中で紹介しております)。
私たちは言わば、「知識のコミュニティ」の中に生きています。
加えて、人間の脳は中と外を区別できず、コミュニティの中の知識を全て自分のモノだと勘違いしています。
コミュニティの知識を自分のものにしている錯覚から、「実はそれほど知らない現象」が起こっているのです。
本当に賢い人とは、コミュニティにより貢献している人
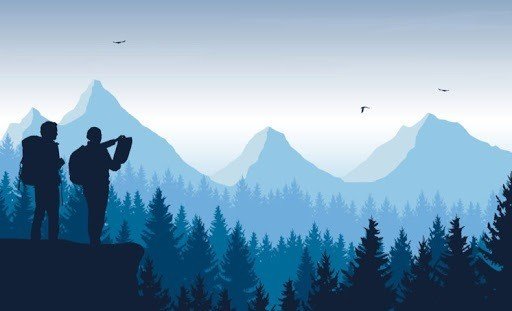
人間は、一人では問題解決できないことがほとんどです。
赤ん坊の時からずっとコミュニティの中で親や知人からモノ(知識)を教わり、自分のモノにして成長してきました。
社会に出たらよりそういったコミュニティに属する機会を自分から増やせます。
そして、コミュニティに貢献することこそが人間としての役割ともいえます。
会社→新規顧客の確保による利益の増大
家族→子供にいろいろな世界(学校など)を経験させる
趣味→コツを教え、より願った結果に近づかせる
という風に様々なコミュニティの中で貢献していくことが人間としての本質とも言えるかもしれません。
であれば、知性が高い人、賢い人とは「コミュニティ」により貢献できる人
という結論が本書には書かれておりました。
「無知の科学」を追ったつもりが人間の本質に繋がるとは・・・(笑)
久しぶりに超名作に出会いました!
