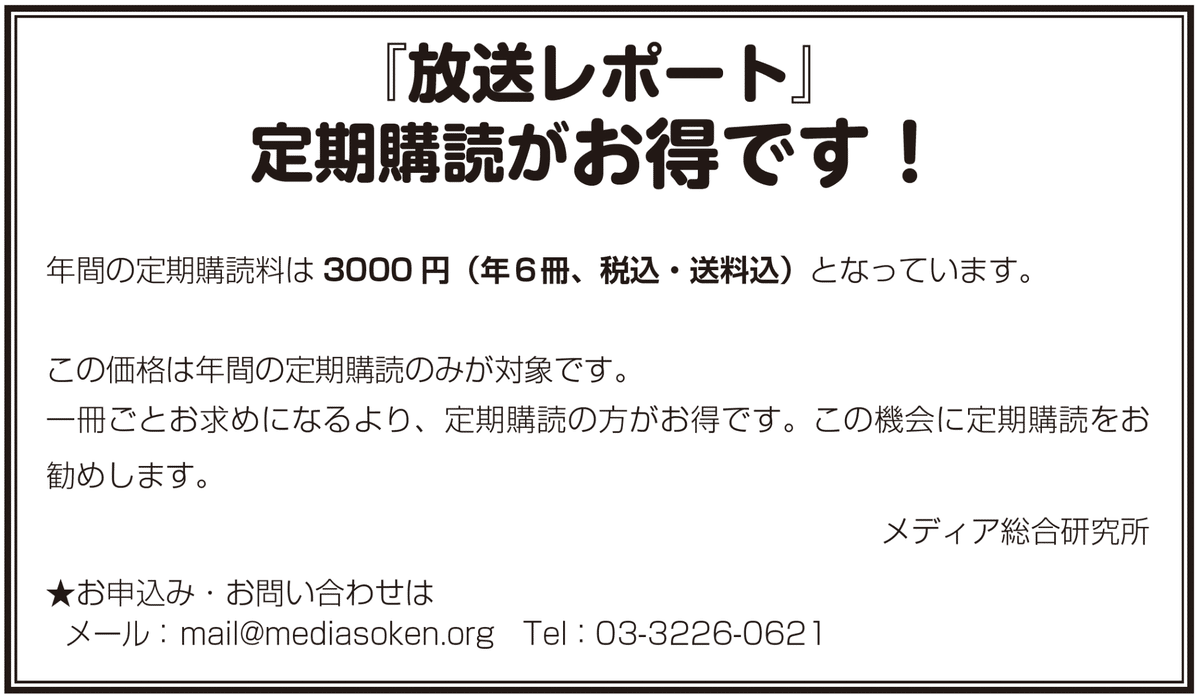ラジオの現場から
放送レポート297号(2022年7月)
石井 彰 放送作家
開局特番は未来につながる挑戦を
昨年から今年、そして来年にかけて民放AMラジオ各局では、70週年開局特別番組が続きます。
日本の民間放送、それはもちろんラジオから始まりました。それまでNHK一局だった放送に、1951年9月名古屋の中部日本放送(CBC)と大阪の新日本放送(のちの毎日放送)が始まりました。また同年12月、東京にラジオ東京(現在のTBS)が開局します。
そして52年から53年に、全国の主要都市に、民放ラジオ局が次々と開局されていきました。今年は北海道のHBC、STV、宮城のTBC、新潟のBSN、長野のSBC、静岡のSBS、富山のKNB、石川のMRO、福井のFBC、兵庫のCRK、広島のRCC、徳島のJRT、そして東京の文化放送が開局70周年を迎え、それぞれ開局記念特別番組の放送を予定、また既に放送しました。
私自身も、いくつかの局で開局記念特別番組を担当したことがあります。あまり代わり映えのしない日常の番組とは違って、ある種のお祭り気分のようなものが放送局全体にあふれていたことを、今も鮮明に思い出します。営業は特別CMを企画セールスしますし、事業はイベントを実施して、そうした熱気が番組制作にも、じわじわ伝わってきます。
つい惰性に流されがちな番組制作に、新たな刺激がもたらされることはいいことだと思います。
とはいえ、その編成がどこも似たようなものになるのは残念です。まず開局記念日前後に70時間生放送という外枠が決まってしまいます。
1日だけの大騒ぎではなく、この1年に継続的な企画は考えられないでしょうか? こう提案すると即座に「ただでさえ業務が忙しいから、1日だけの打ち上げ花火にしましょう」という声が各部門から出ました。
番組企画では必ず出されるのが、終了した人気番組やコーナーの1日限定復活プログラムです。ラジオの歴史と聴取者の思い出が重なる企画として悪くはないのですが、どうしても懐古趣味になりがちです。そもそも終了したのには、それなりの理由があったことに知らんぷりして、ただ復活するのはどうでしょうか?
また、たまたま保存されていた人気番組の再放送にも疑問があります。ただ再放送するのではなく、その番組や内容が現在にとって、どんな意味を持つのかを、きちんと伝えてほしいものです。
往年の人気パーソナリティーやアナウンサー大集合も、昔話だけの同窓会談義に終始しがちです。過去のパーソナリティーではなく、未来のパーソナリティーこそ見つけてほしいものです。中学生や高校生に思い切って、番組のある部分を任せてみては、いかがでしょうか?
つまり過去を振り返るより未来を見通す企画を考えてほしいのです。過去の栄光にすがるのではなく、未来の10年を迎えられるには、というテーマで貫いてほしいのです。
予算もつけやすく、スポンサーからもご祝儀CMが集まりやすい機会を活かして、ふだんできないことをやってみませんか?
そこでぜひ挑戦してほしいのが、ラジオドラマです。これからの地域に活力となるような物語を公募して作ってみませんか。
昨年70周年を迎えた局の中ではTBSラジオが出版してベストセラーになった『TBSラジオ公式読本』(リトルモア)が秀逸でした。
来年開局70周年を迎える青森、岩手、秋田、山形、福島、愛媛、高知、長崎、熊本、大分、鹿児島の放送局、そして60周年の茨城の局は、他局の開局特番企画を積極的に参考に、未来につながる果敢な挑戦を考えてほしいと期待しています。