
【感想】『実力も運のうち』と能力主義|これを支える機能主義
こんにちは、白山鳩です! クルッポゥ!
マガジン『本を読んだら鳩も立つ』での本のご紹介です。
前回の記事はこちらです。↓↓↓
さて今回は、ハーバード大学の有名教授、マイケル・サンデルの著書『実力も運のうち 能力主義は正義か?』から、
能力主義の問題点を探るとともに、
この能力主義の根幹にあるのではと思われる機能心理学について見ていきます。
1つの記事あたり、だいたい5分で読めますので、お気軽にスクロールしてみてください!
能力主義の威信
さて、マイケル・サンデルといえば、
『これからの正義の話をしよう』
で2010年代前半に一世を風靡したのを覚えていらっしゃる方も多いと思います。
「制御不能のトロッコがこのままでは5人の作業員に突っ込みそうだが、あなたは目の前のレバーを引いて、1人の作業員が立つ別路線に引き込むべきか?」
という思考実験「トロッコ問題」を有名にしてくれた、ハーバード大学の倫理学の教授です。
さて、今回サンデルが問題にしたかった内容は、タイトルにもあるとおり、
「能力主義は正義か?」
というテーマです。
アメリカ社会において、子どもを裏口入学させるセレブが後を絶たないことを取り上げ、サンデルはこんな指摘をしました。
不平等な社会で頂点に立つ人びとは、自分の成功は道徳的に正当なものだと思い込みたがる。
能力主義の社会において、これは次のことを意味する。
つまり、勝者は自らの才能と努力によって成功を勝ち取ったと信じなければならないということだ。
逆説的だが、これこそ不正に手を染める親が子供に与えたかった贈り物だ。
彼等の本当の気がかりが、子供を裕福に暮らせるようにしてやることに尽きるとすれば、子供に信託ファンドを与えておけばよかったはずだ。
だが、彼らはほかの何かを望んでいた。
それは、名門大学への入学が与えてくれる能力主義の威信である。
遊んで暮らすだけの金を子どもに与えたいなら、信託ファンドを買い与えておけばよい。
なのに、不正をしてでもセレブたちは自分の子どもたちに「学歴」という箔を与えようとする。
それだけ、「能力は絶対だ」という能力主義がアメリカ社会を支配しているとサンデルは指摘するのです。
能力主義による「機会の平等」は本当か?
サンデルが指摘する能力主義とは次のような考えです。
「人種や民族、性別や階級にかかわらず、
あらゆる市民が同じ条件で競い合い、
努力と才能の許すかぎり出世できるようにするものである」
「能力のある人間は、機会の平等を与えられている」というわけですね。
これは一見平等な考えのように見えるからこそ、その奥にある不平等さが無視される恐ろしさが潜んでいます。
たとえば、学歴。
「東大生の親の過半数は高所得者である」というのはしばしば指摘されるところです。
(2021年4月22日閲覧)
生まれる以前の時点で既に自分の能力を育てるための環境に差があるのに、
「機会の平等」を声高に叫ぶのには虚しさがあります。
「いまから一時間後にスペイン語のテストを受けてください。
試験問題、試験時間など、試験の条件は平等にしておきますから」
と言われて、スペイン語のネイティブと同じテストを受けさせられたら、
「機会は平等だった」
と言われても納得は行かないはずです。

しかし、競争の激しい能力主義社会は、
勝利者には「自分一人の力で成功した」というおごりを、
敗者には屈辱と怒りを生みだす、
とサンデルは指摘します。
公正な能力主義(社会的地位は努力と才能の反映であるとするもの)の創造を執拗に強調することは、われわれの成功(あるいは不成功)の解釈の仕方に腐食作用を及ぼす。
そのシステムが才能と勤勉に報いをもたらすという考え方は、勝者をこうそそのかす。
つまり、彼らの成功は彼ら自身の手柄であり、彼等の美徳の尺度だと考えるように
ーーそして、彼らよりも運に恵まれていない人びとを見下すように、と。
(中略)
運命の偶然性を実感することは、一定の謙虚さをもたらす。
「神の恩寵がなければ、つまり幸運な偶然がなければ、私もああなっていただろう」と感じられるのだ。
ところが、完全な能力主義は恵みとか恩寵といった感覚をすべて追い払ってしまう。
共通の運命を分かち合っていることを理解する能力を損ねてしまうのだ。
自分の才能や幸運の偶然性に思いを巡らすことで生じうる連帯の余地は、ほとんど残らない。
こうして、能力は一種の専制、すなわち不当な支配になってしまうのである。
能力主義社会VS貴族社会
さて、サンデルは能力主義の社会と、
生まれた時点で既に身分が固定されているかつての封建的な貴族社会とを比較します。
そしてこのとき、
「能力主義社会において貧しいことは自信喪失につながる」
ということを指摘するのです。

封建社会で農奴の身分に生まれれば、生活は厳しいだろう。
(※かつては「農奴」に生まれると一生「地主」に従う生活を強いられ、別の身分、職業を選択することはできなかった)
だが、従属的地位にあるのは自分の責任だと考えて苦しむこともないはずだ。
また、自分が苦役に耐えながら仕えている地主は、自分より有能で才覚があるおかげでその地位を手に入れたなどと思い込んで悩む必要もない。
地主は自分よりもその地位にふさわしいわけではなく、運がいいにすぎないことがわかっているはずだからだ。
対照的に、能力主義社会の最下層に落ち込めば、どうしてもこうした考えにとらわれてしまう。
すなわち、自分の恵まれない状況は、少なくとも部分的には自ら招いたものであり、出世するための才能とやる気を十分に発揮できなかった結果なのだ、と。
人々の出世を可能にし、賞賛する世界では、出世できない者は厳しい判決を宣告されるのである。
論点① 正義は守られているか
以上の議論から、サンデルは2つの論点を指摘しています。
1つ目は、
「能力主義社会を実現するにあたって、正義が守られず、不平等や不正がまかり通っている」
という論点です。

人びとが能力主義について不満を訴える場合、
理念についてではなく、理念が守られないことについての不満であるのが普通だ。
すなわち、裕福で権力を持つ人びとは、自分たちの特権を永続させるために制度を不正に操作してきたとか、
知的職業階級の人びとは自分たちの優位性を子供に引き継ぐ方法を考え出し、能力主義社会を世襲の貴族社会へ変えてしまったとか、
大学は能力に基づいて学生を選抜すると主張しながら、裕福でコネのある人びとの子弟に下駄をはかせている、
などといった具合だ。
こうした不満によれば、能力主義は神話であり、いまだ果たされていない遠い約束なのだ。
この論点は、政治や社会への女性参画のためのクオータ制のようなアファーマティブ・アクションの主張へとつながっていくわけですね。
論点② 能力主義社会はそもそも善い社会か
先ほどの論点①は、能力主義という理念そのものに賛同しつつ、その理念が不正によって曲げられている現状をどうにかすべきでは、という発想でした。
一方、論点②は、能力主義社会そのものに問いを投げます。
一つ目の異論は正義に関するものであり、哲学の世界ではよりおなじみのものだ。
いっぽう、二つ目の異論はおごりと屈辱に関わっており、現在の政治情勢を理解するにはこちらのほうが重要かもしれない。
能力主義的エリートに対するポピュリストの抗議は、公正さだけでなく社会的評価にも関係する。
こうした抗議を理解するには、それを駆り立てる不満や怒りを見極め、評価しなければならない。
そうした不満や怒りは正当だろうか、それとも見当違いだろうか?
それらが正当なものだとすれば、対処するにはどうすればいいだろうか?
能力主義は必ず激しい競争社会を生み出し、
その結果、おごる勝者と屈辱にまみれる敗者もまた必ず生まれます。
そのような社会は善い社会か、という問いをサンデルは投げかけているわけです。
適格者のくじ引き
この2つ目の論点に関して、能力主義による大学入試を改革するための方法として、
「くじ引きで入学者を決める」
という驚くべき方法をサンデルは提案しました。

有名大学への出願者のうち、一定の人数は「足切り」とした上で、残り3万人の受験生からくじ引きで決めてしまえばいいとサンデルは言います。
しかし、適格者のくじ引きを支持する最も説得力ある根拠は、能力の専制に対抗できることだ。
適格性の基準を設けて、あとは偶然に任せれば、高校生活は健全さをいくらか取り戻すだろう。
心を押し殺し、履歴を詰め込み、完璧性を追求することがすべてとなってしまった高校生活が、少なくともある程度は楽になるだろう。
能力主義によって膨らんだ慢心をしぼませる効果もある。
頂点に立つ者は自力で登り詰めたのではなく、家庭環境や生来の素質などに恵まれたおかげであり、それは道徳的に見れば、くじ運がよかったに等しいという普遍的真実がはっきりと示されるからだ。
機能主義を理解する
さて、『実力も運のうち』について見てきました。
ここまで読むと、この逆説的なタイトルに込められた意味もなんとなくわかってくるような気がしてきますね。

さて、サンデルの指摘するような「能力主義」が誕生しているそのきっかけを探るための補助線として、
今回は「機能主義」という考えを取り上げます。
「機能主義」については、哲学者である芦田宏直さんのツイートをまつめたtogetterが詳しいですが……
togetterに書いてあるような「自由な魂の主体」がどうのこうこと突然言われても、忙しいビジネスパーソンであるみなさまは困るかと思いますので……

鳩なりに、以下、まとめてみます。
少し遠回りになりますがお付き合いください。
機能主義とは、
「インプットとアウトプットの間に規則があるとする考え」
です。
例として「パブロフの犬」が挙げられています。
いわゆる「条件反射」ですね。
「ベルが鳴る」というインプットに対し「唾液が出る」というアウトプットが、結果として必ず現れるようになる。
このとき、「ベルが鳴る」というインプットと「唾液が出る」というアウトプットの間に規則があると見なせます。
この機能主義の考えは、行動経済学や認知心理学に影響を与えました。
行動経済学とは、人間の中に共通して見られる特性を理論化したものです。
行動経済学では、「代表性バイアス」「アンカリング」といった人間の持つ性向が一般化され解き明かされています。
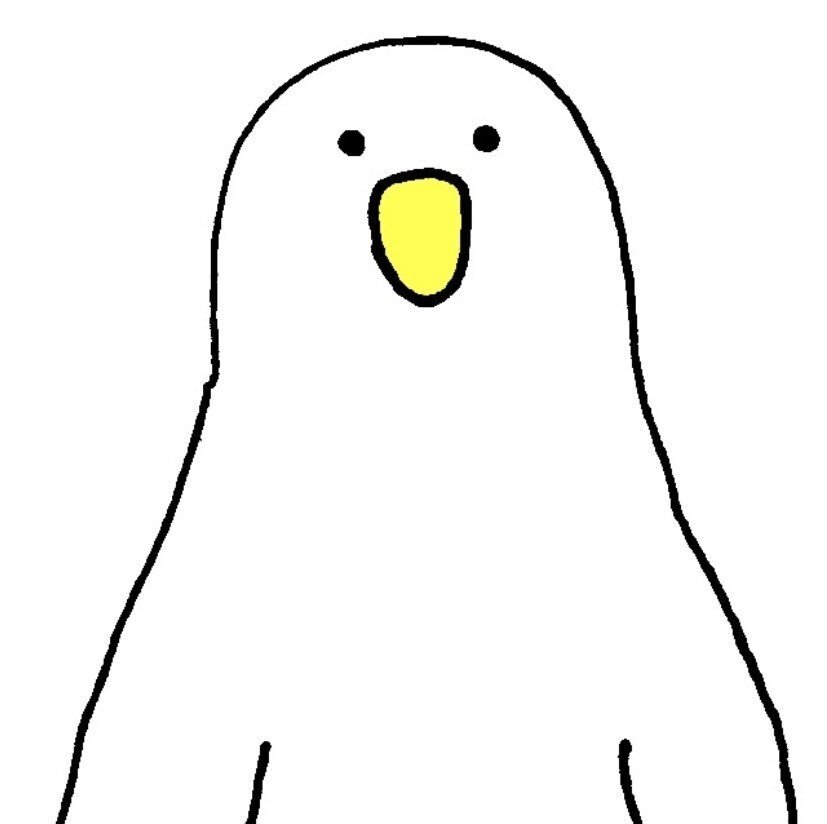
さてこのとき、行動経済学、すなわち機能主義では、
「インプットとアウトプットの関係性の集合」を「実体」と見なします。
これはどういうことか。
例えば、いくつかの質問に答えた結果で、相手がどんなタイプの人間かを指摘する心理テストがありますよね。
「『率先垂範』『努力家』『気が利く』といった性格が当てはまるあなたは『リーダー』タイプ!」
というアレです。
このときの「率先垂範」「努力家」「気が利く」といった質問の答えの集まりは、「インプットとアウトプットの関係性の集合」です。
そして、それらの要素が集まった結果、「リーダータイプ」という「実体」が生まれるわけです。
つまり、「実体」とは、
インプットとアウトプットを繰り返した「結果」であり、
出発点ではありません。
機能主義は、「人間は複雑でも実体的でもないという確信に基づいている」と芦田さんは指摘しています。
そして近代以降では、これがある「差別」につながると続けます。

ここまで見てきたとおり、機能主義では「事象の結果」だけを対象とします。
「頭がいい」人間は、どんな人間だろうと評価されます。
このとき、
「頭がいい(から大卒だ)と思っていたら……なんだ、実際は中卒か」
(なんだ、大したことないヤツか)
と指摘すると、これは「学歴差別だ!」と非難されるわけです。
「頭がいい」という事実だけを見よ! というわけですね。
このように、「でも実際は〇〇だよね」という内容を指摘すると、機能主義に基づく近代では「差別」と見なされるわけです。
機能主義では、「頭がいい」という結果だけを見ます。
そのとき、「でも実際は〇〇だよね」という「相関関係以外の要素」を指摘することは許されないわけです。
機能主義に支えられる能力主義
さて、随分と遠回りをしました。
サンデルの指摘した「能力主義」と、「機能主義」の関係を見ていきましょう。
「頭がいい(から大卒だ)と思っていたら……なんだ、実際は中卒か」
(なんだ、大したことないヤツか)
と指摘すると、これは「学歴差別だ!」と非難されます。
また、機能主義では結果に対して因果関係が用意されます。
「彼が頭がいいのには理由がある
← それは、彼が努力したからである」
と、物事を因果で結びつけるわけです。
そして、「頭がいい」という事実だけを見る……これは「能力主義」です。
つまり、能力主義とは機能主義に支えられているとも言えそうです。

能力主義社会において、サンデルは、
『能力主義社会において正義は守られているか』
ということはよく論点に上がるが、
そもそもの問題として
『能力主義社会というのは善い社会なのか』
もまた考えるべきだ。
と指摘しました。
このように、「能力主義社会自体がそもそもおかしいのでは?」という自問自答ができなかったというのは、
機能主義が前提となっている社会では、
能力主義もまた社会の前提となっていたからでは、
と鳩は思うわけです。

機能主義は能力主義を生み、
そして能力主義は「成功している者は、何かしらの裏付けがある」という考えを生み、
結果、勝者にはおごりを、敗者には屈辱を生むこととなってしまいました。
だからこそ、「自分の人生の偶然性に思いをいたす」ためのサンデルの「くじ引き」のようなアイデアは、絶対的な関係性が支配する機能主義から抜け出すための深い示唆があるなあと思った鳩でした。

次回「本を読んだら鳩も立つ」では、森博嗣の『科学的とはどういう意味か』から、「サイエンス」の意義について書いていきます。
お楽しみに。
to be continued...
参考資料
・マイケル・サンデル、鬼澤忍訳(2021)『実力も運のうち 能力主義は正義か?(早川書房)
