
非和声音を含むメロディーのハモり方
筆者 三島ゆかり
今回のテーマは、音階を一音ずつ上がるメロディを例に、メロディの一音ずつにコードを宛がってハーモニーを生みだす方法論について、です。
(筆者代理補足)
モチーフ

モチーフに対する考え方
非和声音とは、そのコードのキャラクターではない音のことです。
モチーフでは小節にDmのコードが振ってあり、レミファソ、とメロディの音があるので、レがルート、ミは9th、ファが3thで、ソは11thと考えてしまう向きもいるでしょうが、この場合のミ、ソは、テンションではなく非和声音の音として考えます。
非和声音として別のコードを一時的にあてた方が面白い効果が得られる場合があり、今回はその解説をしてゆきます。
(筆者代理補足)
1.ダイアトニック+ブロック・コード

ブロック・コードは、トップとボトムでオクターブ離れたメロディを鳴らし、そのオクターブの間にコードのすべての音を詰め込みます。
独特の響きを持ち、ときに効果的ですがときに聴き苦しさを伴います。
(こういう効果を求めるときは、トップ・ノートの下は長2度でも短2度でもお構いなしなのです。)
2.ダイアトニック+ドロップ2

ドロップ2は上から二つ目の音をオクターブ下げることにより、ひとつひとつの音がブロックコードよりも聴きやすくなります。
また上から2つめを下げたことにより、トップと元3番目が空きすぎるときは元3番目をテンションノートとします。
トップとボトムが10度で流れるとき、もっとも美しく響きますが、この例ではうまくいっていないところがあります。
3.クロマティック+ブロック・コード

メロディーの2音目「ミ」と3音目「ファ」が半音で動いているので、その部分に当てたコードの音すべてを半音で動かした例です。
そこだけ調にない音が増えるので刺激的です。
このようにコードの音をすべて半音で動かすことをクロマティック・アプローチと言います。
4.クロマティック+ドロップ2

クロマティックに動かすことにより、2つめの和音の10度問題は
解決しましたが、いささか刺激的に過ぎるかもしれません。
5.ドミナント+ブロック・コード

クロマチックに動かすよりは部分転調と考えドミナント・モーションにした方が刺激が和らぐという考えです。
ただし、内声のなめらかな流れは損なわれます。
6.ドミナント+ドロップ2
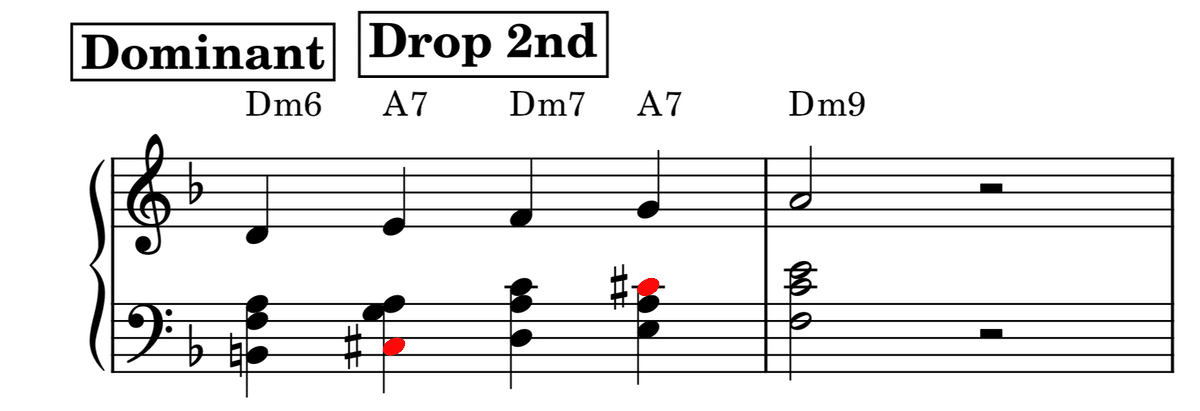
機械的にドロップ2としたところです。
ブロック・コードよりも内声の動きが目立つだけに同音の連続が気になります。
7.ディミニッシュ+ブロック・コード
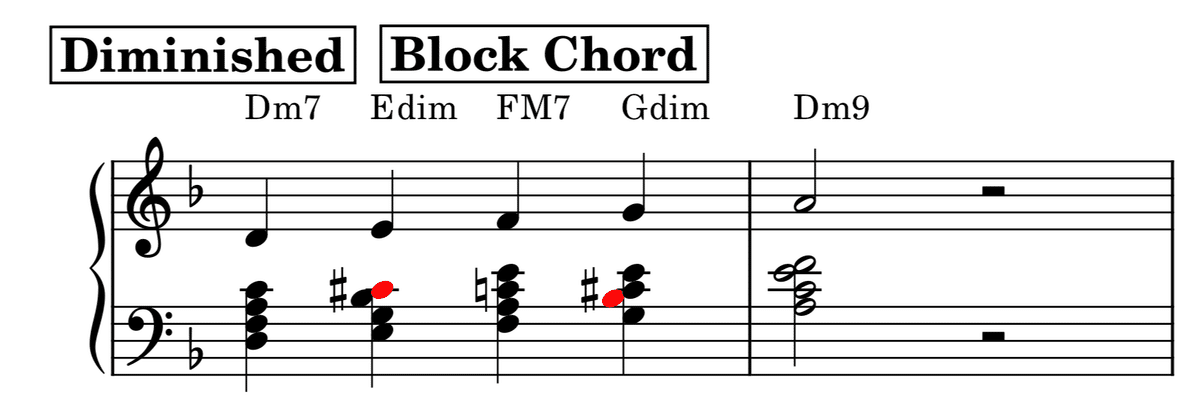
内声の流れがなめらかになりました。
ただし、いかにも予定調和で教則本的な響きなので、違うことをやりたくなるかもしれません。
8.ディミニッシュ+ドロップ2

ドロップ2とすることで内声のなめらかさが際立つと思います。
なおC#dim、Edim、GdimはすべてA7に♭9thを加えたものなので、機能的にはドミナント・モーションと同義です。
ご案内
今回の記事の筆者である三島ゆかりさんが音楽ソフト「Musescore」の使い方について入門書を書かれています。
PCに不慣れな初心者のための手引きとなっております。
「クラシック・ギタリストのためのMusescore入門」は以下のサイトから購入してダウンロードできます。
推薦図書(2025/01/17追記)
(以下筆者:抹茶金魚)
この記事の内容にご興味のある方にお薦めの本です。
お役に立てば幸いです。
初心者向けにはこちら。
「ジャズピアノバイブル バラードアレンジ編 」 安田 芙充央
ピアノの演奏を目的とした内容ですが、コードやテンションについても学ぶことが出来ます。
中級・上級者向けにはこちら。
「リードシート奏法4」 稲森康利
易しく分かりやすく、を求める方にはちょっと早い内容ですが、シンプルでいて深く学べ、自分で考えることを楽しめる一冊だと思います。
