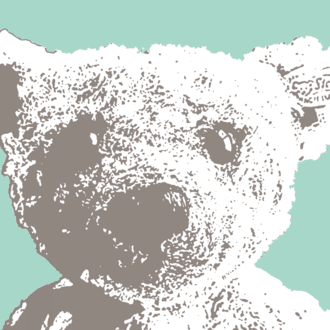エンベロープとは? 〜ADSRとAHDSFRの違い〜 [音楽用語 vol.002]
エンベロープ(envelope)
音が出ている時に、変化を時間軸で見た線のことをいいます。
「エンベロープ」=「包み込む」や「包絡線(ほうらくせん)」という言葉の意味があります。
シンセサイザーには音作りに重要な役割を果たすモジュール、EG(エンベロープジェネレータ)があります。
「ADSR」
EG(エンベロープジェネレータ)のなかには「ADSR」という音を作るのに大変重要なパラメーターがあります。
シンセサイザーはこのパラメーターを操作して音作りをします。
「A」・・・「Attack」アタック(音の立ち上がり)
「D」・・・「Decay」ディケイ(アタックからの減衰)
「S」・・・「Sustain」サスティン(持続音量)
「R」・・・「Release」リリース(信号がなくなってからの減衰)
音作りに関しては、特性を確認しながら実際にシンセを触りながら音を出して確認するのが分かりやすいです。
「ADSR」はいたるところに出てくるので、仕組みを把握(はあく)しておくと必ずDTMに役に立ちます。
例えばドラムのキック、スネア、ハイハット、タムなど、ソフト音源だとエディットでエンベロープを調整できるものが多いので、理解していると理想の音に近づけることができます。
EQやコンプよりもイメージに近づけられることが多いです。
使うソフトによってエンベロープの見方が異なるかもしれませんが、エンベロープを理解すると以下のような解決もできます。
「キックが固い」・・・アタックを少し遅らせる。
「スネアの厚みがない」・・・ディケイを少し長く取る。
「タムの響きが欲しい」・・・リリースを伸ばす。
ピッチ(音高)と時間軸の関係も調整できると、ドラムのリアルなところを引き出せるようになります。
この辺りも実際に音を出しながら確認すると分かりやすいです。
「AHDSFR」
一般的に「ADSR」を扱いますが、さらに「AHDSFR」と細かく分けられることがあります。
「H」・・・「Hold」ホールド(アタックから最大音量の維持)
「F」・・・「Fade」フェード(サスティンからの減衰)
「エンベロープ・フィルター」とは
ベース・ギターでよく使われるエフェクターで、ピッチのエンベロープを調整して、オートワウと同じ効果を作るものです。これもエンベロープを理解していると、イメージの音に近づけることができます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『エンベロープ』をもっと詳しく知りたい方はこちら
いいなと思ったら応援しよう!