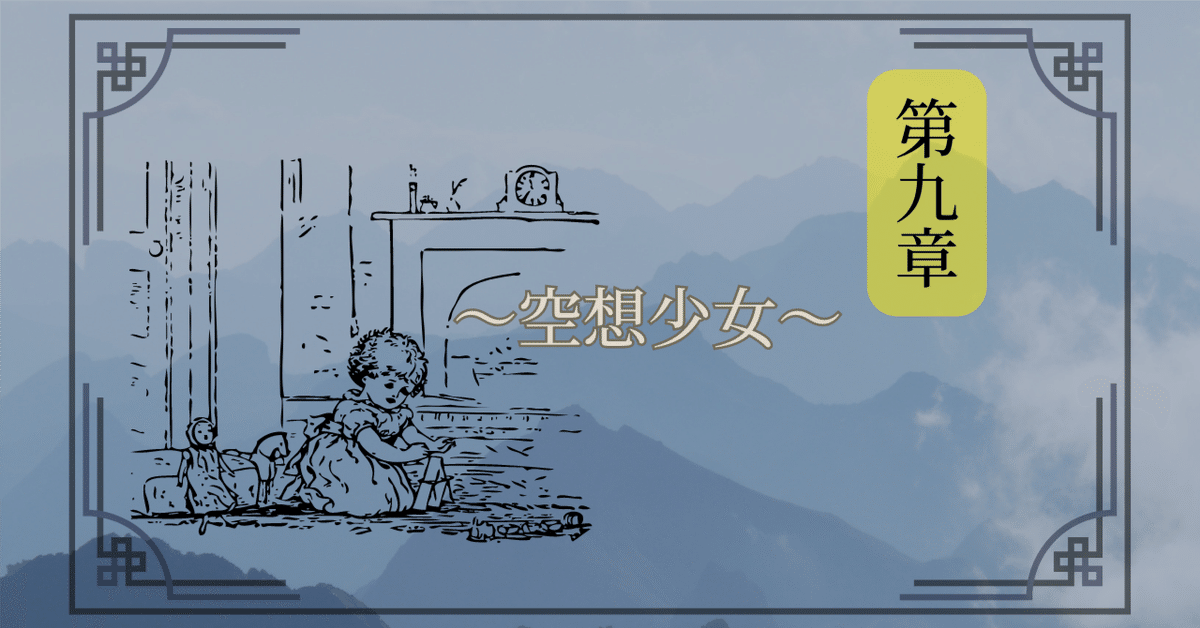
月の妹たち 第九章 ~空想少女~
沈黙が、老婆と女の間で風にたなびく木立の影のように細かく揺れていた。老婆の痩せて骨張った手は、女の白い両の手の中にあって、お互いにひんやりと夜の息遣いを感じ取っている。
姉さんの手は、乾いて美しく冷たいまま。わたしだけ日に焼けて、醜く年老いたのね。
老婆は泣きたい思いに駆られるが、涙となるはずの水分が身体から湧いてこない。
老婆が姉と別れたのは、二十八の年だった。あのとき姉に関しては、一生分泣きつくしたのだ。
自殺だった。
嫁いだ先で子供に恵まれず、思い詰めて、柿の木に首を括ったのだと言われているが、本当はもっと別の理由で死んだのだと双子の妹はわかっている。姉に密かな想い人がいたことを、双子の妹は知っていた。
それは都会からの若い移住者で、まだ姉も若者も未婚だった頃の話。夏の間、束の間関係を持った二人は、両者に良い縁談が持ち上がったことで、別れる運びとなった。
しかし、結婚後も、若者は夫の留守を見計らって訪ねてきた。
困り果てた姉は、決して二人きりにならぬよう、いつも若者が来るときには、近所に住む妹を呼び寄せて、あくまで友情の関係の外へは出なかった。
しかし、本当のところ、その三人での逢瀬が忘れがたいほど楽しかったのではないだろうか。
のちに姉の遺品には、三人で食べた菓子の包み紙が三枚ずつ、綺麗に折られて見つかった。丁寧に日付が書いてあった。
夫がいて、近しい肉親に守られながら、愛人と偽りの友情を演じる生活は、一見綱渡りのようで、
実はひだまりの中の揺籠みたいに、彼女を幸福の中に閉じ込めていたのかもしれない。
愛人とはあくまでプラトニックだったがゆえに、次に起こる当然の成り行きを姉は見誤った。
若者の家庭に、子供が出来たのだ。
若者は昼間の潔癖な愛とは別に、夜は夫としての義務を果たしていた。
そのことが、姉を手酷く傷つけたことは間違いない。最後の日、妹の家を訪ねてきた姉は言った。
「皆、平気なの?わたし、月の光にさえ、焦がされる思いなのに。」
あの言葉の意味を妹だけが知っている。
姉はそう言うと、すたすたと立ち去り、その足で納屋の奥へ隠れると、手際よく使い古したロープを持ち出して、まっすぐに家の裏手の柿の木へ向かったのだ、と、妹は想像してみる。
ぞっとするほど、手慣れたものをそこに感じずにはいられなかった。姉は果報者に見えて、ある意味ずっと絞首台への道をなぞり、確認し、見定めていたのではないだろうか。
その後、若者は家庭に六人の子を成し、一人を亡くし、一人を養子に出した。
三女が亡くなったのを機に、なぜか一番上の女の子が、養子に出たいと言い出して聞かず、しぶしぶ親戚筋へ任せたとのことだった。
怨念とは、本人の預かり知らぬところで成就するものなのかもしれない。
妹は、ときおり、家を出た少女のことを思い描いて、酷い仕打ちを押しつけてみたり、はたまた思わぬ幸運を授けてみたり、第二の物語の主人公として、好き勝手に動かしてみる。
その想像が尽きない限り、姉の死は生きていて、手で触れられるところまで降りてくるのだ。
老婆は月に焦がされる若い女の青い影を、優しい瞳で見守った。
