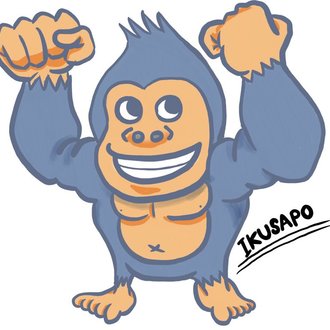もしトレーナーが膝関節のトレーニングを機能解剖から考えてみたら
こんにちは!!
イクサポです!!!
タイトルはちょっと遊びました笑笑
今高校野球でちょっとした問題が話題を呼んでいます。
この記事を呼んでみなさんはどう思われますか?
もし選手に一番近いトレーナーという立場のあなたが助言を求められたらなんと答えますか??
賛否両論あると思いますが、自分としてはこの監督の判断は懸命だったと思います。
なぜなら右肘の違和感に気づいていたから。つまり選手と監督の間には信頼関係があり、違和感を伝えることができる関係であったのではないかと推測します。
このような違和感の訴えに対して、監督が考え抜いた末に出した答えだと思うので、指導者の方でこの判断ができるのは素直に凄いなと思いました。
みなさんも選手の立場、指導者の立場になって一度考えてみてはいかがでしょうか?
さて、本題に移ります!!
今回は、機能解剖の観点から膝関節のトレーニングについてみていきます!!
トレーニングを考える上で、必ず必要な解剖の知識とそこからどのようにトレーニングに展開をするかを書いていきます!!
それではいきましょう( ´ ▽ ` )
膝関節は内旋・外旋を考える
膝関節は大腿脛骨関節と膝蓋大腿関節から成り立ちます。
大腿脛骨関節では、屈曲・伸展の運動方向に加えて、内旋・外旋も生じます。
これらの運動は膝関節では、
膝関節伸展に伴い、脛骨外旋
膝関節屈曲に伴い、脛骨内旋
と連動して動きます。
膝関節のトレーニング作っていく上ではこの膝関節の内旋・外旋に着目します。
理由としては単純で、
膝関節の屈伸よりも内外旋の方が問題になりやすいからです。
そして、膝関節内外旋を見ていく中では、解剖学的な以下の3つの特徴を理解することが重要です。
・関節面の構造
・骨の大きさ
・半月板
1つずつ見ていきましょう!!
ここから先は

Physio365〜365日理学療法学べるマガジン〜
365毎日お届けするマガジン!現在1000コンテンツ読み放題、毎日日替わりの現役理学療法士による最新情報をお届け!コラム・動画・ライブ配信…
育成年代のフィジカルサポートの環境改善に使わせて頂きます!🙇 皆さんの力で日本サッカーを発展させて行きましょう🔥