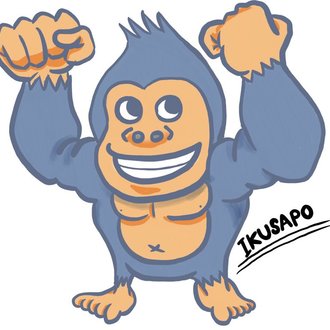【徹底解説!】 フィットネス-疲労理論の全て 〜トレーニング負荷管理テンプレ付き〜
ためためこんにちは!
イクサポです!!
また日本中でコロナウイルスが広がりを見せています。部活動やチーム活動も中止になっているところが多いと思います。
まん防が出ている都道府県もあり、不要不急の自粛が余儀なくされています。しんどいと思いますが、日本全体で乗り越えていかないといけないと思うので、是非協力してがんばりましょう!
ということで、今回のテーマは前回に引き続いて書いていきます!
前回、超回復理論の脆弱性について書きました!
今回は、その超回復理論にとって代わることが期待されているフィットネス疲労理論について、超回復理論と比較しながら説明していこうと思います!!
このフィットネス疲労理論は、スポーツ現場のトレーニング負荷管理にも大いに使える理論なので是非参考にしてください!!
それではいきましょう!
前回のおさらい
超回復理論について、ざっくりとおさらいしてみましょう!!

・トレーニングをすると、筋線維が破壊され一時的にパフォーマンスが落ちる。
・トレーニング後48〜72時間ほどで筋肉は修復されていく。
・回復が終わると以前より少しパフォーマンスが上がる。この状態を「超回復」と呼ぶ。
・この段階でトレーニングをすると、次の超回復でさらにパフォーマンスは上がる。
・48時間〜72時間の間隔でこのサイクルを繰り返すとパフォーマンスを効率にあげていくことができる。
また、同時にこの理論には脆弱性があると説明しました!
❶時間経過に伴うパフォーマンスの変化を正確に表すことができない
❷アスリートやトレーニング熟練者のように毎日トレーニングを繰り返し実施していく場合に、適切にパフォーマンスの変化を表すことが難しい
❸試合までに疲労を抜くためにトレーニングをあまりしない期間を設けなければならず、現場でのコンディション調整を上手く説明できない。
つまり、アスリートにおいてはこの理論を用いてトレーニング負荷管理やコンディショニングを行うには限界があるということがわかります!
それでは、現場でのトレーニングやコンディショニングを説明できる超回復理論に代わるような理論はあるのでしょうか?
フィットネス疲労理論とは?
超回復理論に代わるような理論とされているのが、フィットネスー疲労理論です。
このフィットネスー疲労理論は、two-factor theory : 二要因論とも呼ばれています。ここで出てくる2つの要因が、フィットネスと疲労です。

基本的な考え方として、
トレーニングをすると、フィットネスが向上する一方で疲労は蓄積する。
フィットネスは身体にプラスの効果, 疲労は身体にマイナスの効果があり、プラスマイナスの合計がパフォーマンスとして現れる
という考え方です!
これだけ聞いても意味がわからないと思うので、この理論を理解するために、プラスの出力やマイナスの出力とは?そもそもフィットネスと疲労は何を用いて表すのか?という部分を説明していこうと思います!!
トレーニングの入力と出力
育成年代のフィジカルサポートの環境改善に使わせて頂きます!🙇 皆さんの力で日本サッカーを発展させて行きましょう🔥