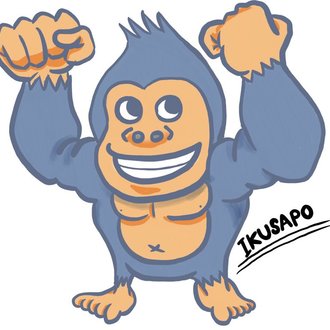最低限知っておくべき足関節の治療戦略
お疲れ様です!
イクサポです!!
先日新しくサポートをさせていただく場が増えました!
そして、育成年代の子供たちの成長の速さにびっくりしています!!
正直、言葉一つで動きもパフォーマンスも変わる。
反対に言えば、それだけ『言葉』には気をつけないといけないと感じています。
伝え方、伝える順番、声の強弱などを工夫して子供たちにスッと入ってくる『言葉』を選択しています。
さて、今回は前回の続きです!
前回は足関節のシンプルな評価についてお伝えしました!
今回は最低限知っておきたい治療戦略についてお伝えします!
シンプルな評価から治療に繋げるには??
前回は背屈と底屈を評価する方法を紹介した。
これらの『シンプル』な評価から治療に繋げて見ていく。
治療の流れとして
⑴可動域制限の改善
⑵OKCでのアプローチ
⑶CKCでのアプローチ
で進めていく。今回は⑴を中心に説明する。
(⑵、⑶はトレーニングになるため)
まず、治療アプローチ移る前に背屈や底屈時に骨の動きを確認する。
<骨の動き>
背屈:腓骨外旋・挙上→遠位脛腓関節が開く
底屈:腓骨内旋・下制→遠位脛腓関節が閉じる
両方→ 内側楔状骨に対する舟状骨の回内
立方骨の挙上
<背屈>
背屈時は距骨が脛腓間に入り込むため、安定した状態となる。
それ故、足部の内外転は制限されるため正常な完全背屈をした状態では、後ろからみた時に下腿軸と足部軸が一直線になる。(距腿関節のシワが地面と平行にできる)
しかし、背屈制限がある人では、特に足部の運動軸が偏移しており、内転制限により、背屈していくと足部が外転する人が多くみられる。
<底屈>
底屈時は反対に足部は不安定な状態である。
そのため自由に動かせる状態かつ、正常な関節運動を行うことができる状態であることが重要である。
正常な関節運動が獲得できていないと、距骨が内側偏移し、内反を伴った底屈となる。
つまり、この背屈と底屈の可動域制限が出ているということは、正常な骨の運動(関節運動)が生じていないと考えることができる。
それではこのような関節運動を獲得するためには、どのような治療が必要なのだろうか?
とっくの昔にもう答えは出ている。
骨の動きを制限するであろう部位にアプローチしていくのだ。
足の形状など他にも細かくみていけば、アプローチする部分は多くあるが、今回はシンプルな評価から必要最低限の治療に繋げることを念頭に説明する。
それでは具体的なアプローチ部位についてみていこう!!
*動画と画像で6箇所のアプローチについてまとめています!
1. 屈筋支帯
屈筋支帯とは、後脛骨筋、長母趾屈筋、長趾屈筋の屈筋群が通る部位を覆っている場所である。
ここにある、後脛骨筋、長母趾屈筋、長趾屈筋は距骨の後方を通るため、硬くなることで底背屈時の距骨の後方滑り、前方への転がりを制限する。
リリースの方法としては、以下のように内果と踵を結んだラインに対して、垂直に母指をあて、下から押し上げるようにリリースしていく。
この時、底背屈の自動運動を行ってもらうとより効果的である。

2. Kager's Fat Pad
これはアキレス腱と長母趾屈筋の間に存在している脂肪体である。

この脂肪体は周囲の組織と癒着しやすいため、これも距骨の動きを制限する原因となりやすい。
リリース方法としては簡単で、アキレス腱の下に手を当てつまむような形で固定する。その後、足関節の底背屈を繰り返す。
セルフケアでも行えるため、選手たちにも伝えやすい方法である。
3. 長腓骨筋、長母趾屈筋
この2つは腓骨の骨運動に大きく関わってくる。
通常足関節の運動には、腓骨の動きが大きく関わる。しかし、癒着や短縮が生じていると、腓骨の正常な動きを制限してしまう。特に外側での制限はこの2つが主な原因になることが多い。
リリースの方法は以下の画像のように腓骨頭をポイントに、腓骨から筋を引き剥がすように上から下まで丁寧にリリースを行う。特に腓骨頭付近と、外果近くは硬くなっている場合が多いため、より時間をかけて行うことをおすすめする。


外果の後方深くまで指を入れていくと、長母趾屈筋を触診できるので、指を当てたまま、自動運動で足関節の底背屈や足趾の屈伸をしてもらいます。
だいぶ奥になるので爪のケアをしてから行いましょう!
4. 長趾伸筋・長趾伸筋
ここは前面の筋になる。
前面の筋は、遠位遠位脛腓関節の開閉を制限する。そのため結果的に距骨の後方滑りや前方への転がりの制限に繋がる。
この部位のリリース方法もシンプルである。
以下の画像のように、内果と外果を結んだ線の中央付近に指を当て、足関節底屈、足趾屈曲を行っていきます。
このあたりにはちょうど伸筋支帯があり、また距骨内側頭が触診できる場所なので癒着があればリリースできるポイントでもあります。

5. 小趾外転筋
立方骨は外側縦アーチの要の骨となるため、その偏位はアーチの支持性に大きな影響を及ぼす。外側縦アーチは立方骨を頂点としたアーチを形成する。立方骨が下制すると、外側縦アーチは低下してしまい、外側荷重や底屈運動時の内反を生じやすくなる。
長腓骨筋・小趾外転筋にアプローチを行うことで、立方骨を挙上し、正常な外側縦アーチの形成に繋がる。
リリース方法は、第5中足骨頭を見つけて、そこよりも踵よりの部分に手をあて、足趾を内外転させる。第5中足骨頭から踵骨まで指の当てる位置を変えながらリリースしていく。
6. 後脛骨筋・母趾外転筋
内側縦アーチを形成する上で重要なのが、舟状骨と内側楔状骨の位置関係であり、舟状骨がトップにあり、内側楔状骨が下にきていることが基本である。
舟状骨を引き上げる役割をしているのが後脛骨筋であり、ここの制限は内側縦アーチの低下に繋がる。
また底屈・背屈を行う場合、内側楔状骨が舟状骨に対して回内をしていくことで正常な関節運動が生じる。ここを制限するのが母趾外転筋であり、この筋は後脛骨筋とも連結があるため、リリースしていく必要がある。
リリース方法は、
舟状骨を触診し、骨を下に辿り、母趾外転筋との境目に指をあてる。指を当てた状態で、背屈+内反運動をくり返し行う。
今回は、可動域制限改善に最低限必要なアプローチ部位について書いた。
可動域制限が改善されたら、OKCのトレーニングを行い、CKCのトレーニングへと移行していく。
可動域制限が改善されていない状態でトレーニングへ移行しても、正常な関節運動を行えず、再発のリスクが高まってしまう。
まずは、今回の最低限のアプローチから足関節の正常な可動域、関節運動を獲得した上で、トレーニングに移行していくことで、より良いトレーニングの効果が期待される。
それでは!!
お知らせ
※ 僕の共同マガジンPITTOCKROOMで初のセミナーが開催されます!
選手、サッカー指導者、トレーナーの全ての方々が学べる内容となっております。
ぜひ興味のある方はきてください!オンライン受講も行っています!!

<料金体系>
・当日参加者:3000円(学生2000円)
・オンライン受講:2000円
・当日参加(マガジン購読者):1500円
・オンライン受講(マガジン購読者):500円
〜ライタープロフィール〜

イクサポ
理学療法士・アスレティックトレーナー学生!!
日本一に輝いた大学サッカーチームの専属トレーナーとして、日本トップレベルの選手のトレーニングや治療を担当。その他、育成年代のトレーニングサポートを行うべく "イクサポ "を立ち上げ、情報発信中!!
公式Twitter : イクサポ
ここから先は

Physio365〜365日理学療法学べるマガジン〜
365毎日お届けするマガジン!現在1000コンテンツ読み放題、毎日日替わりの現役理学療法士による最新情報をお届け!コラム・動画・ライブ配信…
育成年代のフィジカルサポートの環境改善に使わせて頂きます!🙇 皆さんの力で日本サッカーを発展させて行きましょう🔥