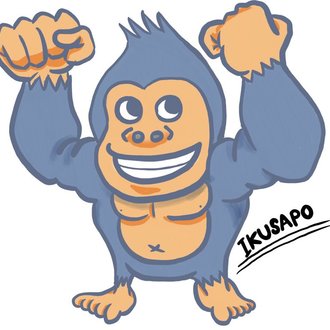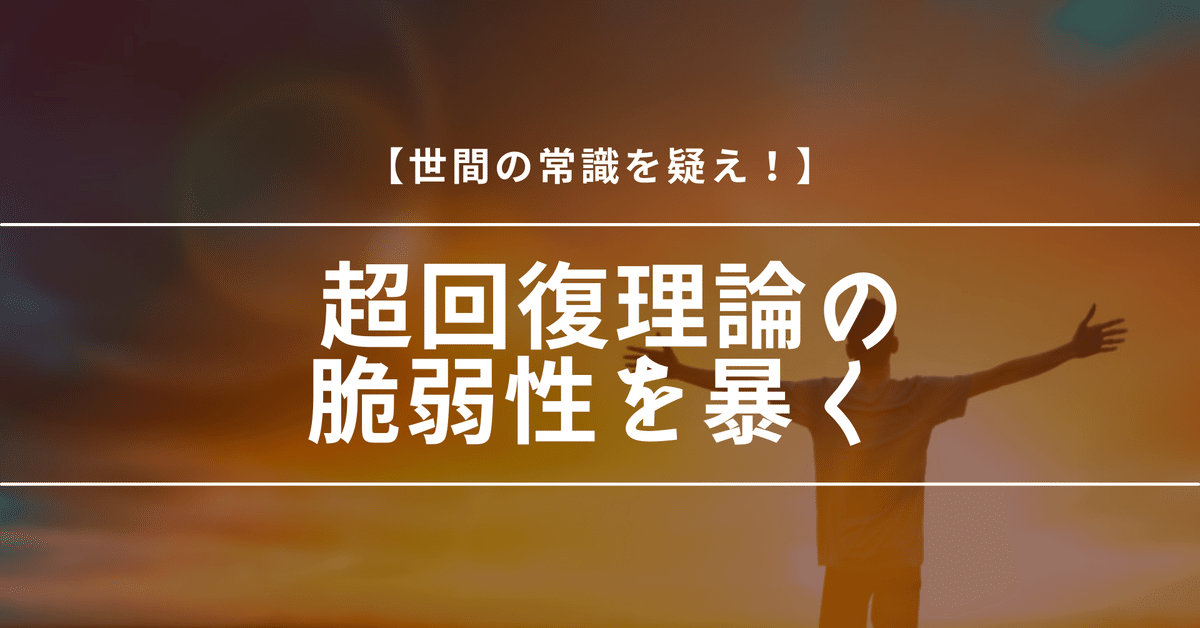
【世間の常識を疑え!】 超回復理論の脆弱性を暴く!!
こんにちは!!
イクサポです!
昨日、僕のTwitter1万人突破記念の無料セミナーを行いました!
今回のテーマは
『フィットネスと疲労をデータで可視化する』
でした。

1時間のコンパクトの時間設定でしたが、約30名の方が参加してくださり、現場でデータをどのように活用していくのかについてお伝えしました!
参加してくださった方々には、トレーニング負荷管理ができる開発中のアプリのβ版を配布しました!!
個人的にも非常に楽しかったですし、参加者の皆さんも満足してくださった方々が多かったので、今後も定期的にやっていこうと思います!!
イクサポさん@ikusapo_pt と河合学さん@KawaiManabu の「フィットネスと疲労をデータで可視化する」というセミナーを受けました!久しぶりのスポーツ科学な講義はやはり楽しかったです🎉ありがとうございました!!
— そうしゅん|サッカー×プログラミング 名古屋 (@shumpei_s) April 10, 2021
データ活用して選手のパフォーマンス向上させます!!
イクサポ(@ikusapo_pt)さん×河合(@KawaiManabu)さんのセミナー面白かった😄
— AKIRA@Pride of 17 (@akiraC9) April 10, 2021
疲労を可視化。これ一般診療でもよくぶつかる壁。
自分は、日々の患者様から地域高齢者やジュニアアスリートへ利用して行けたらなぁと漠然と考えてみて…発展させていければなぁ😄
イクサポ @ikusapo_pt さんのフォロワー1万人達成記念セミナーでの河合 @KawaiManabu さんとの話は改めてモニタリングの重要性を感じた。
— 中村 龍🐉ラグビーSCコーチ🏉 (@nsc_ryu) April 10, 2021
そしてモニタリングができるアプリが使えるのはとても楽しみ。
指導チームで活用するしかない!
※写真は過去にエクセルでモニタリングしたものです https://t.co/whk5q1HmiN pic.twitter.com/OJch2vqBuK
それでは、本題に移ります!!
今日はなかなか挑戦的なタイトルになってます。笑
今回は、上記のセミナーに付随して、世間で非常に多く使われている
『超回復理論』
について深掘りしていこうと思います。
わかりやすい理論であるため、今や専門職である僕たちだけでなく、一般の方々にも浸透してきており、メディアにおいても頻繁に使われていますよね。
ただ、実はなかなかツッコミ所がある理論なんです。これ。
なので、2週間連続で超回復理論はどんな理論なのかという部分から、理論の弱点や、より洗練された理論についても説明していこうと思います!

それでは行きましょう!!
超回復理論とは??
一般的に広がっている概念として以下のようなものがあります。

・トレーニングをすると、筋線維が破壊され一時的にパフォーマンスが落ちる。
・トレーニング後48〜72時間ほどで筋肉は修復されていく。
・回復が終わると以前より少しパフォーマンスが上がる。この状態を「超回復」と呼ぶ。
・この段階でトレーニングをすると、次の超回復でさらにパフォーマンスは上がる。
・48時間〜72時間の間隔でこのサイクルを繰り返すとパフォーマンスを効率にあげていくことができる。
最初に行っておくと、超回復理論も理論としては成り立っている理論です。しかし、少し単純すぎるというだけです。
そのため実は、トレーニング初心者には非常に使いやすい理論なんです。
なぜなら、
『トレーニング後にしっかり休んで、しっかり栄養をとればパフォーマンスは上がりますよ』
ということを理解してもらうのには非常にわかりやすいからです。
しかし、この理論を使ってトレーニング熟練者やアスリートがコンディションやパフォーマンスをあげていこうとすると失敗します。
超回復の元になった汎適応症候群
そもそも、超回復理論の土台になった概念があったことはご存知でしょうか??
育成年代のフィジカルサポートの環境改善に使わせて頂きます!🙇 皆さんの力で日本サッカーを発展させて行きましょう🔥