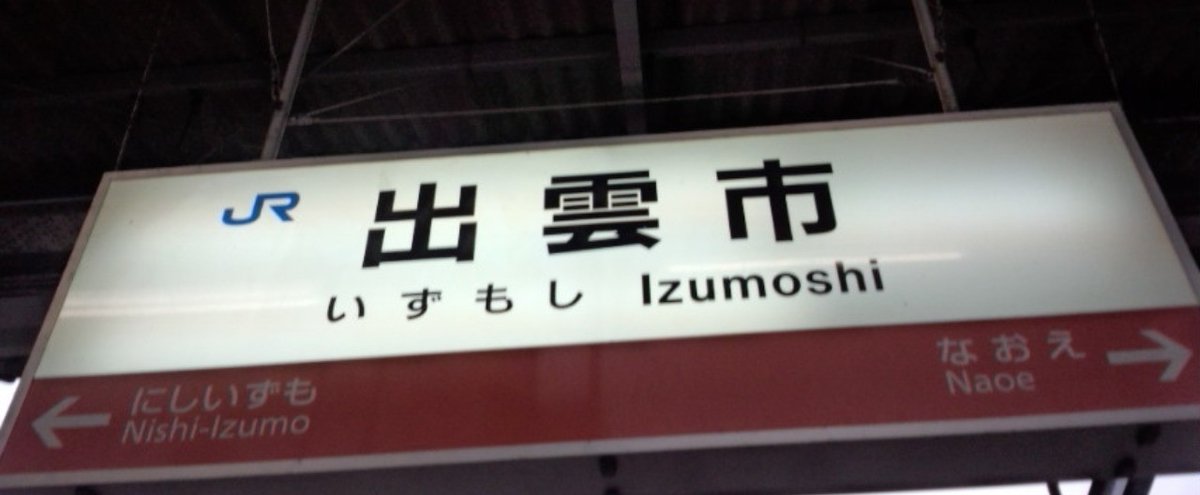
出雲大社のこと
出雲大社の関係者の方から出雲市駅の近くで晩御飯をご一緒しながらお話を伺ってきました。残念ながら出雲大社に伺う時間はありませんでしたので駅の写真だけです。
お恥ずかしながら、大国主命が医療看護の神様でもあるとは知りませんでした。言われてみれば、赤剥けになった因幡の白兎に真水で洗って蒲の穂を当てておきなさいとアドバイスをしていましたね。薬草の知識も豊富で現在にも漢方で使用されている植物の名前が大国主命からの伝承として、たくさん記録に残っているそうです。
末っ子の大国主命がヤガミヒメを娶ったことに怒ったお兄さん達に殺されかけたところを、治療看護したのが、キサガイヒメノミコトとウムギヒメノミコトと言われており、いわば集中治療を受けたのが大国主命が初めてだということです。
”殺されかけた”と表現しましたが、その当時の表現では、その時大国主命は死んでいたので、多分、黄泉の国をさまよっている所を連れ戻されたというかんじなのではないでしょうか。黄泉の国の話は、イザナキとイザナミの話にも出てきます。黄泉の国で朽ち果てようとしているイザナミを見てしまったことで、イザナキは怒りをかいます。そこで興味深いのが、イザナミはイザナキに死んでいると宣言されて死んだということです。当たり前ですが、自分が死んでいると宣言する人は誰もいないわけです。死というものは、個人に帰属するものではなく、社会が決めるということが、神話の時代からも当たり前のことであったということです。その時代の死はどこらへんだったのかという話に及び、多分白骨化が重要なポイントであったのではないかということでした。
近代だけを見ても、死の三大兆候 心拍停止、呼吸停止、瞳孔散大 を持ってのみ死が宣言されていた時代から脳死という概念も出てきています。死という概念を社会が変えていっているわけです。死というものが、絶対的に定義されることは現在もこれから先もないのでしょう。死というものが、ある意味、曖昧であるにもかかわらず、非常に重要であるということが、多くの人を悩ませ考えさせられる。そこが重要なんだともおっしゃっていました。正解がないから考えなくてはならないことだと理解しています。
神話の神様たちは非常に人間的で感情豊かです。何かを決めるときにも集まって相談します。10月に出雲大社に集まるのがそれを象徴しています。人間というものが有限である、完璧ではないから、集まって補完し合いながら無限なものを求めていく、それが神道の本質なのかもしれません。
ちなみに、平成の大遷宮では、屋根を葺いていた檜皮を炭として寄贈され、島根大学病院の新病棟の各室の天井裏に設置されたそうです。島根県ならではの試みです。持続可能性とくくってしまうとスケール感が小さくなってしまう気がします。神社は目に見えないものを感じる場所だそうで、病院も患者さんの検査結果などに現れないものも感じ取らないと良い医療が提供できない、そんな考えの伝承と捉えていくとしっくりくるような気がしています。。
