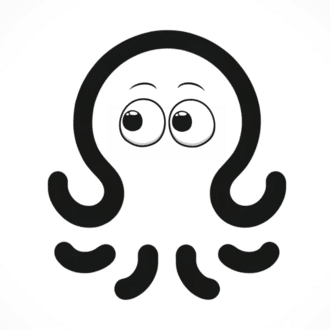【コミュニケーションスキル】会話の本質を理解できれば勝手に話し上手になる
会話が上手な人と下手な人って違いって何でしょう。
皆さんも「この人はよく話を理解してくれるな」「会話のテンポが良くて話しやすいな」と感じることもあれば、「すごく話しにくい」「話がうまく噛み合わないな」などと思った経験もあると思います。
この違いが起きることには明確な理由がありますし、その理由がわかれば対処することも可能です。
人とうまくコミュニケーションを取るために何が必要なのか。
今日はそんな話をしていきます。
そもそも会話を上手とは何かを認識しているか?
会話を上達させる前に、会話が上手とはどういったものか定義していく必要があります。
よくビジネススキルなどが詳しく記載されている本がたくさんありますが、意外とそもそものゴールの定義を明確にしていないものが多い気がします。
野球で例えるなら、バッティングのコツや球速の上げ方はものすごく説明するのに、そもそも野球の勝利条件を説明していないといったイメージでしょうか。
確かにバッティングが良くなり、球速も上がれば野球において有利ですが、そもそも野球は27個のアウトの間に相手より1点でも多く取ることを目指すスポーツです。
ホームランを打つことも、150km/h投げることもできればいいというだけで、必要不可欠ではないのです。
それよりもいかにアウトを取るか、いかに点を取るかを考えるべきで、その手段としてバッティングやピッチングといった具体的な手段を探していく流れが自然なのです。
では、話を戻します。
前述の流れに沿えば、まずは会話が上手になるためには“会話が上手”とはどのような状態かを明確にします。
そもそも、人はなぜ会話をするのでしょうか。
簡単に言ってしまえば
相手に情報を伝達するため
ということになるでしょう。
仕事の大事な業務連絡であっても、日常の些細な会話であっても、相手に何らかの情報を伝えるために会話をすると思います。
ただ、これだけでは大きなゴールではないと思います。
なぜならば会話はコミュニケーションの一手段でしかないためです。
ではコミュニケーションの目的は何でしょうか。
それは
自分と相手の脳内イメージを一致させる
ということだと僕は考えています。
もう一度言います。
自分と相手の脳内イメージを一致させる
ことです。
そのために人は会話をしますし、ラインをしますし、手紙を書きます。
耳が不自由な方は手話を使います。
つまり、「会話が上手」ということのもっとも本質部分は
言葉のやり取りを通して相手と脳内イメージを一致させることが上手
ということになります。
ということは、極論テレパシーができるようになれば会話なんて必要ありませんし、相手の考えることがわかるテクノロジーが生み出されれば会話は必要なくなります。
脳内イメージが一致すればそれで目的は達成されているからです。
会話が上手な人の思考
では実際にどうすれば脳内イメージは一致させることができるのでしょうか。
そもそもイメージを一致させる前に、言葉では伝わらないほど前提常識に差があるのであれば、どう頑張っても会話は成立しませんのでその場合は省きます。
詳細はこちらの記事で書きました。
今回は、会話をより円滑に、上達させる方法を考えていきます。
言葉で情報を伝えることのできる人なんてほぼいない
最初にして最重要となる要点は
言葉は脳内の1/10の情報も伝えていない
ということです。
これは具体的に考えた方が早いです。
例えば友達が近くのレストランを紹介するとしましょう。
「隣町の新しいレストラン、内装小洒落た感じで雰囲気いいし、特にオムライスはフワトロ&デミグラスソース付きで美味しい!ぜひ行ってみて!」
と言った具合でしょうか。
まずはこの文から相手の状況を想像してみてください。
想像しましたか?
では次に参ります。
先ほど書いた通り“会話が上手な人”は“脳内イメージを一致させることが上手な人”です。
ということで説明してくれた友達の脳内をできるだけ描いてみましょう。
「(あれは久しぶりにカフェでゆっくり読書してちょうどお腹が空いてた日だったかな。そのタイミングで見つけた)隣町の新しいレストラン、(入った瞬間the・洋食屋のいい匂いしたな)内装(は西洋チックなんだけどどこか温かみがある懐かしい感じのする)小洒落た感じで雰囲気いいし、(あ!案内してくれた人も紳士的ですごく心地よいサービスだったな。それでもって)特にオムライスは(綺麗な黄色かつ絶妙な火加減が見た瞬間わかるような)フワトロ&(食べる前から香ばしい良い匂いがして、一口食べたらわかる深みがあって旨味が凝縮された)デミグラスソース付きで(ああ、幸せだったなー)美味しい!(他にもセットのスープもめちゃくちゃ美味しかったしデザートもいっぱいあったなー。)ぜひ行ってみて!」
どうでしょうか。(長いですが、、)
読みにくい文章極まりないので控えめに書きましたが、おそらく友達の脳内イメージをより鮮明に文字にするとこのような感じになるのではないでしょうか。
みなさんのイメージと近かったでしょうか。
おそらくここまで細かく想像することはできなかったと思います。
ですが、説明した本人はおそらくこのイメージが8.9割ほど相手に伝わっていると思っているはずです。
つまり何が言いたいかというと、
言葉で表している情報は自分の脳内のごく一部である
ということです。
そもそも普通に考えればわかります。
自分の脳内イメージは、五感を使って実際に経験したものから作り出されています。
対して相手の脳内イメージは、あなたの極度に限定的な文字情報を聴覚で聞き取ってイメージしているに過ぎません。
この情報が一致するわけありません。
もし一致できるのであれば、グルメリポートなんて映像を使う必要はありません。
少しでも五感を使って相手の脳内イメージを作るために、映像や音、はたまた食べている人のリアクションなどを伝えることが、広告の手段となるのです。
こう考えてみれば、自然と会話が上達する方法が見えてこないでしょうか。
一聞いて一理解するだけで満足しない
さて、脳内イメージを一致させるために私たちは何をすれば良いのでしょうか。
僕が思うにそれは、
相手の話に対して様々な可能性を予測する
ということです。
これは相手の話を単に予測するのではありません。
そして深く予想するのでもありません。
様々なシチュエーションの可能性を予測しながら話を聞くということです。
例えば先ほどの例で「オムライス」という単語を聞いたときに、ただ単に「オムライスか、、」と考えるのではなく、「オムライスか。フワトロ?家庭的?ケチャップ?ホワイトソース?チキンライス?それとも新しいタイプ?」というように色々な可能性を予測するということです。
そして話を進めて聞いていくうちに、「あっ、フワトロ&デミグラスのやつね」となるわけです。
さらには、「ご飯はチキンライス?」と聞き「いや和風の出汁きいた混ぜご飯みたいだった」と返ってくれば、より相手と脳内を一致させることができます。
ここで注意したいことは選択肢を広く予測することです。
“深く”ではなく、“広く”です。
例えば上の例で言えば「オムライスか。フワトロかん。フワトロの中でも目の前で割ってくれるタイプかな。最初からフワトロで出てくるタイプかな」というように、一つに絞って考えないということです。
こうやって広く予想することで瞬時に相手との脳内イメージを合わせつつ、より細かな部分まで想像・質問できるようになります。
自分の脳内を相手に伝えることが難しいのならば、まずは自分から相手の脳内を知るように行動してみるのです。
そして予測と答え合わせを重ねていくと、その人の言葉から作り出すイメージがより正確になっていきます。
つまり、”一聞いて一理解する”のではまるでお話になりません。
一聞いて十理解しようとして初めて会話が成り立つのです。
まとめ
さて、今回もまとめていきます。
① 会話のゴールは脳内イメージを一致させること
② 言葉だけではイメージの1/10の情報も伝わらない
③ イメージを一致させるためにも”一聞いて十理解しようとする”
これは学力関係なくできることであり、誰でもやろうと思えば身につけることができます。
しかし一方で、学力がある人ほどこの能力が身についているように思うのも事実です。
それはおそらく、普段から知識を豊富に持っているが故に、一つの物事に対して、様々な思考を巡らせているからだと思います。
例えば散歩している犬を見て、毛並みが整っているから愛されているな、あの犬種はお金持ちの家だな、この時間を歩くのは飼い主は主婦だなとか、一つの事象からいろいろなことを想像しているのです。
なので、相手の思考を予測するのはもちろん、日々目に見える情報からその背後に広がる可能性について考えてみるのもアリだと思います。
いいなと思ったら応援しよう!