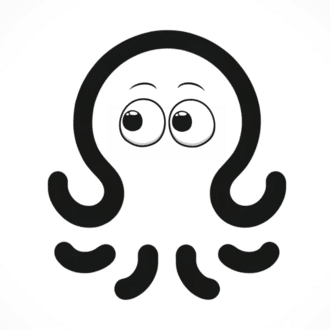【誰でもできる】リーダーの視点を持つために僕が意識していること
よくビジネス書などを読んでいると、「経営者の視点を持つべきだ」なんて言葉をよく目にしますが、どのような視点か理解している人は少ないと思います。
僕自身もまだまだ学生という身分であるため、経営者視点がどのようなものかはわかりません。
しかし、経営者視点でなくとも、野球部には様々な視点を持った選手もいます。
キャプテンのように常に視座を高くしてチーム全体を見る人もいれば、自分のことで精一杯の人もいます。
その多くの部員を観察する中で、視点を変える方法を見つけることができました。
これを知れば、どんな視点も身につけることができると思います。
例えばあなたが社会人だとしたら経営者の視点を持つことができますし、部活をしているのであればキャプテンや監督の視点を持つこともできるようになります。
注目すべきは主語
さて、今回は早速結論から伝えます。
視点を変える方法。
それは、、、
なりたい視点を持っている人と主語を合わせる
というものです。
自分が必要とする視点を持っている人を観察し、その人が使う主語を自分でも使うことができるようになれば視点は劇的に変わります。
一体なぜでしょうか。
僕たちが見ている世界を考える
視点の話をするにあたり、まず人が見えている世界を理解しなければなりません。
なぜなら、視点を考える以前にどうやって視点が作られているかがわからなければ真の意味で改善することはできません。
例えば昔のブラウン管テレビの調子が悪い時は叩いて直したりしていませんでしたか?叩けば一時的に直りますが、根本が直ったわけではないのですぐ調子が悪くなります。
もし本当に直したいのであれば、テレビの仕組みに詳しい電気屋さんなどに持ち込むのが適切な方法でしょう。
つまり、いくらテレビの状態を一時的に直す方法は知っていても、仕組みを知っていなければ結局元に戻ってしまうということです。
これを視点の話で置き換えれば、自分たちが見えている世界の仕組みを知らずに視点を変えても、すぐに元の視点に戻ってしまうというわけです。
僕たちは同じ世界を見ているようで全く違う世界を見ている
では僕たちは世界をどのように見ているのでしょうか。
おそらくこの答えは一つではないと思います。
ですが僕は、
人は自らの頭で言語化できた世界しか見ることができない
と考えています。
もう少しわかりやすく言えば、“同じものを見ていても言語化できる量が違えば見えている世界も違う”ということです。
例えば小さい子供は「ブーブー」と言って車を認識しています。
そして車は移動する手段であり、両親が運転して自分は後部座席に乗るものです。
一方で大人になった私たちは、高級車と普通の車の違いを認識することができます。乗るにしても、仕事で車を運転する人もいれば、気になっている女性を乗せて運転する人もいたりと、それぞれの車にそれぞれの状況が存在することも知っています。
国産車であれば右ハンドルで、外車であれば左ハンドルだったりもします。
つまり、子供にとって車は「ブーブー」でしかないのに対し、大人は「高級車orファミリーカー、タクシーor乗用車、国産車or外車」と言った様々な言語化をすることができます。
こうなるともう見える景色は全く違ってきます。
おそらく子供が銀座の車道を見ても車がたくさん走っているだけに見えるでしょう。
しかし車に対して多く言語化できる大人からは、そのきらびやかさや凄さ、そこに住む人々の価値観を感じる=認識することができます。
この例のように、僕たちは言葉によってそれぞれ見えている世界が違います。
ということは
視点を変えるためには、“使う言葉”を変えるしかない
という結論に至ります。
”使う言葉”を変える超簡単な方法
では“使う言葉”を変えるにはどうしたら良いでしょうか。
言葉遣いを変えればいいのか、
それとも難しい言葉を覚えればいいのか、
はたまた口癖を変えればいいのか、
僕自身色々と悩みました。
そこでたどり着いた結論が
主語を変える
というものです。
人は言語化できる範囲で世界を認識すると書きましたが、ここでもう一つ注目すべきポイントがあります。
それは、“できる”と“する”の違いです。
いくら語彙が豊富で、色々なことを言語化“できる”能力があったとしても、それを言語化“しよう”としなければ情報量のある認識はできません。
例えばオリンピックなどの解説や実況がとても面白いと感じたことはないでしょうか。しかし、その話をしている人は普段からもそのスポーツの実況や解説をしているはずです。
それにも関わらずこのような違いが生まれるのは、普段は仕事として中立的立場で言語化“している”のに対し、世界の舞台では日本を応援する主体的に“できる”限り言語化して国民に伝えようとしているからです。
人は往々にして100%世界を言語化して認識しているわけではないのです。
その時の気分や環境によっても認識する世界は異なります。
言い換えれば、皆さんはリーダーに必要な世界を認識“できる”能力はあるのに、それを“しない”がためにリーダーの世界を認識していない視点になってしまっているということです。
そのみなさんの言語化“できる”能力を最大限に発揮するための方法が“主語を変える”ということなのです。
ではなぜ主語を変えるべきなのでしょうか。
それは
主語によって見る世界の範囲が決まる
からです。
経営者やキャプテンといったリーダーが持つ視点の特徴として、組織やその業界を広く見渡すことが挙げられます。
なぜそれができるかと言えば、それは単に主語を「会社は〜、チームは〜、私たちは〜」といった規模で考えているからです。
人の集合を一つの主語として捉えると、影響力やパワーも増して、選択肢も大きく広がります。そうなってくると、自ずととの規模にあった視野を持つ必要があります。
野球で“自分”がレギュラーを取ることを考えたらチーム内に目を向けますが、“チーム”で優勝することを考えたらチーム外に目を向けます。
この時点でどちらがキャプテンの広い視点でどちらが個人的な狭い視点かがわかると思います。
つまり、主語が変われば勝手に自分の考える世界が変わっていくということです。
特に“勝手に”というところがポイントです。
人は何かを変えるときは常にそれを意識しなければなりません。
一方で、同時に複数のことを意識し続けられる器用な人はそう多くありません。
しかしこの方法ならば、意識して変化させるのは“主語”のみです。
その他は“勝手に”変化していくのです。
僕のチームでも学生のトップに立つ人間は「俺たちはどうすべきか、俺たちがどうなりたいのか」を常に話し合っています。
そこには個人的な要望はありません。
常にチームのために考え続けています。
ゆえに、彼らの主語は基本的に「チーム」「俺たち」もしくは「監督」になります。「監督」はチームのトップですから社長のようなものです。
彼らは自然に監督の考えを汲み取ることが、チーム全体を俯瞰する上で必要だと感じ取っています。チームのトップである監督の視点をなんとか身につけようとしているのです。
だからこそ、もし視点を変えたければ、その視点を持っている人の主語を真似することから始めてみることです。
まとめ
それでは今回もまとめていきます。
① 人が見ている世界はその人が言語化できる世界である
② 言語化できる能力はあってもそれを常に100%発揮しているわけではない
③ リーダーの視点で言語化するためにも“主語”を変える
みなさんも周りを見れば納得するのではないでしょうか。
自己中心的な人は「僕、私、俺」を多用しますし、人の目を気にする人は「他の人、世間、会社の人」みたいな言葉を使うでしょう。
スケールの大きい人は「世界、海外、未来」といった主語でしょうし、周りを気遣える人は「あなた、彼、あの人」になるでしょう。
意識して観察すればその人の人間性と主語の関係が見えてきます。
視点を変えるために色々な人の主語を観察するのも実は面白いかもしれません。
いいなと思ったら応援しよう!