
Case 9-2024: An 84-Year-Old Man with a Fall
Zaven Sargsyan, M.D., Sunita D. Srivastava, M.D., Virginia A. Triant, M.D., M.P.H., and Brian B. Ghoshhajra, M.D.
患者情報の要約
84歳男性 転倒を主訴に病院受診.
3週間前に別の病院を肉眼的血尿で受診.
微量の尿潜血が陽性となり、赤血球沈渣は4-5個/HPFだった.
血液検査で凝固機能は正常、CBCでは貧血を認めたが以前から指摘があり悪化もなかった.
腹部造影CT検査では、膀胱内に直径10mmの線状の領域が認められた.
血尿の原因として腎結石が膀胱内に通過したことが考えられる.
患者は帰宅となり、他の病院に併設された泌尿器科クリニックで経過を見られることになった.
心房細動に伴う脳卒中予防のために長年服用していたリバーロキサバンは継続するように指示された.
受診の1週間前、男性は右顔面と右腕の痺れ、運動性失語症(expressive aphasia)を訴え他院を受診(症状はERを受診する前に消失).
彼はこの症状が出る2週間前からリバロキサバンを何回も内服していなかった.
CTAでは脳梗塞や、前方循環・後方循環に臨床的に意義のある動脈硬化は検出されなかった.
CBCで貧血は残存していたが、電解質、AST/ALT、ALP、腎機能、凝固機能は正常だった(Table 1).
尿検査では潜血1+、沈渣では赤血球 6-10/HPF、白血球 6-10/HPFだった.
患者は他の病院に入院した.
入院2日目、造影頭部MRIでは全体的な中等度の萎縮と軽度の虚血性変化を認めた.
経胸壁心エコーではLVEFは60%、推定右室圧の上昇、mild-moderateのMR、mild ARを認めた.心室中隔、心房中隔は異常がなかった.

患者はTIAによる症状だったと告げられ退院した.リバーロキサバンの内服を継続するように指示されるとともに、他院の脳神経内科でフォローアップを受ける予定になった.
今回の受診日、患者は自宅の風呂で転倒した.
救急隊(Emergency medical services)が要請され、血糖値は130mg/dLだった.
患者は転倒前の状況を思い出すことはできなかった.
彼はERで、他院を退院後に調子が良くないこと(全身脱力とめまい)を報告した.
腹痛、胸痛、尿路の症状はなかった.
妻は患者について、入院前は完全に自立しており、運転や食糧の買い物が可能だったが退院後、衰弱が進行し歩行や着替えにも助けを要するようになったと話した.
妻は、前回入院中に点滴が留置されていた左腕に発赤があると証言した.
既往歴は、Af、HFpEF、COPD、うつ病、高血圧、前立腺癌(放射線治療を受けた)だった.
内服は、アムロジピン、フィナステリド(前立腺癌治療薬)、フロセミド、ロサルタン、リバロキサバン、ロスバスタチン、ベンラファキシン(イフェクサー).
アレルギーはなし.アルコールや違法薬剤の使用はなし.
1日1箱のタバコを吸い、退職後は妻とマサチューセッツに住んでいた.
体温は36.1℃、血圧 145/68、PR 61、呼吸数 18回、SpO2 93%(室内気).
BMIは24.4、患者は明らかに活気が無く、粘膜は乾燥していた.心音は不整、左肘前窩に紅斑があり軽度の硬結があったが、波動はふれなかった.
左膝には擦り傷(abration)があった.
彼は協力的(cooperatively)であったが、混乱が見られ、時々質問に対する答えが適切でなかった.
残りの身体診察では異常がなかった.
血液検査では電解質、AST/ALT、ALP、乳酸値、凝固機能は正常だった.
尿検査では潜血3+、白血球3+、尿沈渣で、赤血球 5-10/HPF、白血球 >100/HPF、細菌1+だった.
Creは2.01mg/dL、高感度トロポニンTは68ng/L(基準値 0-14)、他の検査結果はTable 1に示す.
呼吸器感染症のウイルス(SARS、コロナウイルス2を含む)は陰性だった.
心電図は心房細動であり、虚血性変化はなかった.
次に画像検査が行われた.
Dr. Brian B. Ghoshhajra: 頭部CTAと頚椎CTでは急性脳出血や頚椎骨折はなかった.
胸部〜骨盤部CTAでは、少量の胸水が左肺に認められた(Fig1A).
中等度〜重度の冠動脈石灰化と心肥大を認め、石灰化は動脈瘤性拡張を示す胸部大動脈全体に散在していた(Fig.1D).
直径15mmの不定形の左副腎結節を認め、膀胱は円周状に壁が肥厚していた
膀胱内には5mmの結石を2つ認め、前回の小線源治療からの播種を認めた(Fig. 1C).
第8胸椎と第9胸椎の高さで脊柱管の後面に沿って認められた、それぞれ最長直径6mmの2つの局所的な高密度領域は、髄膜腫の可能性が高い (Fig. 1A, 1B)
腹腔動脈起始部の上方で大動脈の局所的な開大と、大動脈裂孔の高さで大動脈の壁肥厚を認めた(Fig.1D).
Dr. McFadden:ERで測定されたトロポニンTは71ng/L(1時間)、70ng/L(3時間)だった.


生理食塩水を500mlボーラス投与した.
尿路感染症が推定され、尿培養を提出の上セフトリアキソンが開始となり入院となった.
フロセミドとロサルタンは中止となり、他の薬剤は継続した.
入院1日目、尿培養でS. aureusが検出された.
頭部単純MRIでは急性の脳梗塞の所見はなかった.
TTEではLVEFは60%で、収縮能は正常で右室の拡大が認められた、軽度〜中等度AR、軽度MR、重度のTRがあり、推定右室圧は上昇していた.
血液培養を採取し、セフトリアキソンは継続となった.
入院2日目、解熱した.肘前窩のエコーでは、部分的に閉塞した表在静脈に1.7cm×0.5cm×1.3cmの無血行性の低エコー性領域を認めた.整形外科コンサルトされたが、手術治療は推奨されなかった.
感受性検査では尿検査で検出されたS. aureusはMSSAだった.
セフトリアキソンは中止となり、経静脈的にバンコマイシンとセファゾリンが開始された.
入院1日目に採取した血液培養からは集塊状の黄色ブドウ球菌が発育したため、血液培養が再度採取された.
入院3日目、患者は安静時に突然の胸痛を訴えた.
痛みの部位は第3肋間にあり放散はなかった.痛みのスケールは5/10だった(10が最強).
痛みは5分間続き、介入なしで改善した.
痛みの改善直後に行われた診察では、血圧193/80で、ECGではAfだったが、虚血性の変化はなかった.
胸部X線では、左少量胸水があったが、以前にCTで認めたものと似た程度だった.また左下葉の心臓裏に浸潤影を認めた.
血中トロポニンTは46ng/Lだった.
ロサルタンが再開され、12時間後には血圧167/81であった.
入院4日目、患者は前日とは違う性質の胸痛を訴えた.
痛みの程度は10/10で、腹部に放散する痛みだった.
患者は苦しんでおり、血圧は173/85だった.
胸部、腹部の触診では痛みの変化はなかった.
低用量のヒドロモルフォン(ナルベイン)が開始され、痛みは5/10に軽減した.
この時点の検査結果をTable 1に示す.診断のための検査が行われた.

Differential Diagnosis
Dr. Zaven Sargsyan: 鑑別診断を考えるとき、我々は典型的には全ての患者の所見を一度で説明できる状況を考える.
このケースでは、一連のイベントとして所見を説明できるような(ナラティブ)物語を考慮することが有用である.
この考え方は、単一の疾患概念に固有のものではない(典型的ではない)合併症が常に存在し、(その合併症が)臨床推論で使用される疾患スクリプトに含まれない可能性があることを認識するものである.
例えば、肺炎が膝の腫脹を引き起こすのは、肺炎に伴った脳症が転倒を引き起こすからである.
閉塞性肺疾患は、吸入の抗コリン薬が十分使用されるまでは、尿閉を引き起こさない.
この考えに沿って、私は今回の患者のプレゼンテーションを以下のようにサマライズする.
※疾患スクリプト:症例の置かれた状況(コンテクストcontext)、疾患の特徴、経過などが包括的に構造化された知識の枠組み
高血圧、心不全、心房細動を有する健康な高齢男性が、膀胱結石による急性の一過性血尿を起こしたため、リバーロキサバンの服用を中止した.
その後、左中大脳動脈の閉塞に合致する一過性の神経症状がみられたため、短期間入院した.
退院後1週間以内に、彼は徐々に状態が悪化し、脳症を呈した.その際最近の末梢点滴の挿入部位の発赤を認めた.
彼は蜂窩織炎、膿瘍と共に血栓性静脈炎に罹患しており、血液培養でS. aureusが陽性になった.
CT検査では大動脈の肥厚と嚢の突出(outpouching)を含む複数の異常を認めた.
彼はその後腹部に放散する突然の胸痛を呈した.
未知の要素が多いケースを分析する場合、ひとつのアプローチとして、相対的に確実なものから始めて、わかっていることがわからないことを説明するのに役立つかどうかを確認するという方法がある.
Phlebitis, Cellulitis, and Abscess
患者は末梢点滴カテーテルに関連する静脈炎、軟部組織感染症、細菌性膿瘍を呈している.
静脈炎は末梢点滴カテーテルのよくある合併症で、4日間の留置により50%で合併する.
感染は、カテーテルが緊急の状況(例えばERで脳梗塞の疑いで受診)で留置された場合により起こりやすい.
さらに皮膚膿瘍の大部分はS. aureusにより起こる.これは今回の患者の尿培養の結果を考慮しても重要なことである.
S. aureusによる細菌尿
入院1日目、尿培養でS. aureusが生育したが、これはあまりないことである.
尿道または恥骨上カテーテルがない患者では、S aureusは上行性ではなく血流感染の播種により尿路に感染する.
血液培養でグラム陽性球菌が陽性
入院2日目、血液培養ボトルでグラム陽性球菌が陽性になった.
この結果は暫定的なものではあるが、S. aureus性細菌尿を背景としたブドウ球菌性菌血症の推定を支持するものである.
これらの所見を総合すると、腕の感染を感染源とするS. aureus菌血症の診断に説得力のある事例となる.
Explaining Additional Findings
転移性のS. aureus感染症という用語は、この菌の挙動を癌の挙動になぞらえたもので適切な表現である.
S. aureusは遠隔部位に播種し、拡大する傾向にあり、今回の症例の異常を考える上で重要である.
この患者はAKI、脳症、副腎結節、脊柱管(apinal canal)に沿った腫瘤、進行する心筋症、大動脈の嚢の形成を認めた.
これらの説明のつかない所見は、報告されたS. aureusによる菌血症と関係があるのか、偶然なのか、全く別の病態の物語を示す手がかりとなるのか、いずれであろうか?
特定の診断の有病率は、しばしば臨床医の確率的な推論に影響を与える.
異常の有病率も同様に重要である.
例えば、慢性の性器潰瘍は稀な所見であるが、疲労のような一般的で非特異的な症状がみられる場合、そのような所見は偶然のノイズではなく何らかのシグナルと捉えるべきである.
2つの臨床上の状態(entities)の間の関係性の程度も解釈の参考になる.
例えば、急性呼吸不全と急性の咳はほとんど全て同様のプロセスで起こる.
それに対し、慢性の呼吸不全と慢性膝痛は、(いくつかの一元的なunifying=原因はあるものの)多くは異なるプロセスである.
この推論をベン図で表すと、円の大きさ(有病率を表す)と重なり具合が異なる.
Figure2に、この患者の説明ができない所見とS. aureusの関連の分析を示す.

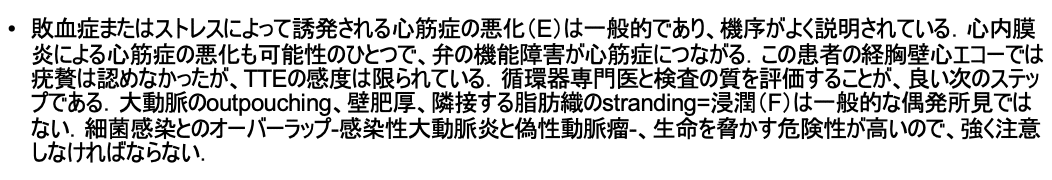
Explaining Additional Findings(続き)
全体として、大動脈病変についてさらに検証することが重要である.
それらは十分原因が判明しておらず、偶然として見逃すことはできない(命を脅かす可能性があるから).
動脈壁の肥厚、周囲の脂肪組織の増生は炎症プロセスを示唆し、合併症として大動脈が拡張している可能性を考える.
大動脈炎は無菌性の炎症(GCA、ベーチェット病など)や感染によって起こりうる.
S. aureusは感染性大動脈炎や偽性動脈瘤の原因として頻度が多い.
大動脈の追加の画像検査が必要である.
しかし、おそらくこの患者は黄色ブドウ球菌に感染しているいう新たに得られた情報を考慮しながら、放射線科の同僚と最初の画像所見を検討することも、並行して行うべきステップである.
ベッドサイドの臨床医にとって診断は反復プロセスであり、これは放射線科医にとって同様である.
最初のCT検査の際の臨床的背景は転倒である(S. aureus感染症ではない)
菌血症という新しい背景は、全く異なる解釈を導くかもしれない.
放射線科医が画像を見直すことは、より詳細な情報やより詳しい説明を得られることのみではなく、臨床経過をアップデートし、同じ画像が現在では異なる意味を持つかどうかを確認する意味がある.
Development of Sudden Chest Pain
今回の患者では、S.aureusの臨床背景を踏まえ、胸痛の鑑別診断を考えなければならない.
可能性のある診断の優先順位をつける際に、疾患の重症度や潜在的な治療法に基づいて、有病率、臨床的適合性、適時診断の重要性を考慮しなければならない.
Stress-Induced Cardiomyopathy
患者のエコー所見でLVEFが低下していることから、ストレス誘発性の心筋症を第一に考える.
この病態はよくあることで、集中治療室に入院した心疾患の既往のない患者92人を対象としたあるシリーズでは、ルーチンの心エコー検査で26%の患者に心尖部の拡大を伴う左室機能不全が認められた.
心尖部の拡張のある患者は、そうでない患者に比べてトロポニン値が高く、心電図異常が多かった.
今回の患者ではこのような異常所見(エコー、心電図)がなかったので、ストレス誘発性心筋症の可能性は低いと考えられた.
Coronary Occlusion
患者の画像検査では動脈硬化所見が認められる.
ACSの発症率は菌血症患者の7-8%だった.
心内膜炎は可能性のある診断として考慮すべきである.繰り返しECGとトロポニンの測定が必要である.
Pulmonary Embolism
入院中の患者が胸痛を訴えたら、PEについて常に考える必要がある.
胸痛の性質は実に多彩であり、PEを心配する際のきっかけとなるバイタルサインの異常がないことは、それがないからと言って疑いが晴れるほど感度が高くない.
肺塞栓症のWells危険度予測スコアのどの要素が最も重視されるかを思い出すことは有益であり、「3点」は肺塞栓症よりも他の診断の可能性が低いことを示す.
この患者における肺塞栓症の疑いの程度は、他の可能性のある診断の確率によって左右される.
Thoracic Radiculopathy
115名のグラム陽性菌菌血症の前向き研究で、ルーチンにPET-CTを行った場合、脊椎椎間板炎は10%の患者で認められた.
胸椎の傍脊柱感染症は、神経根を圧迫し胸部痛を誘発する.
患者の痛みが間欠的で、神経分節をまたがって放散することは胸部の神経根症としては非典型的である.
Pneumonia
グラム陽性菌菌血症に罹患した患者の研究(前述の研究)では、肺膿瘍は14%の患者で認められた.
胸部痛は患者の最後のCT撮影後、数日して出現しており、その間に肺炎が起こったかもしれない.
しかし肺炎の場合の重度な胸痛は、たいてい胸膜痛であり、この患者には当てはまらない.
Parasternal Septic Arthritis
胸鎖関節は、S. aureus菌血症患者の化膿性関節炎でよく罹患する部位である.しかし、この患者の痛みは胸部の触診で悪化しなかった.
Aortitis with Acute Aortic Syndrome
ERで撮影されたCT所見では大動脈の異常が懸念され、胸痛があることから急性大動脈症候群が鑑別の上位に挙がる.
急性大動脈症候群には、大動脈解離、(大動脈)壁内血腫、貫通性潰瘍(血管壁に潰瘍を伴う動脈硬化性病変において,その潰瘍が内膜・中膜へと進展し,内弾性板を穿破するもの)、大動脈瘤破裂が挙げられる.
この患者は急性大動脈症候群のリスクファクター(コントロールできていないHT)、動脈硬化、大動脈障害を有する.
Dr. Zaven Sargsyan’s Diagnosis
Staphylococcus aureus bacteremia leading to infectious aortitis or pseudoaneurysm and an acute aortic syndrome
感染性大動脈炎、偽性大動脈瘤及び急性大動脈症候群を引き起こした黄色ブドウ球菌菌血症


Diagnostic Imaging
Dr. Ghoshhajra: 腹部骨盤部のCTAでは、急速に拡大する感染性の偽性大動脈瘤を認め、歪な外形を呈していた(Fig3).
それは切迫破裂を示唆するものだった.偽性大動脈瘤は、19mm13mmから30mm20mmまで5日間で拡大していた.
Radiologic Diagnosis
急速に拡大する感染性偽性大動脈瘤
Discussion of Management
Dr. Virginia A. Triant: グラム陽性球菌が4本のうち1本の血液培養で検出され、入院1日目にMSSAと判明した.
バンコマイシンの点滴を終了し、セファゾリン点滴が継続された.
感染性大動脈瘤の治療は、原因微生物に基づいた抗菌薬治療と、外科的治療または血管内治療である.
Dr. Sunita D. Srivastava:彼と彼の家族の議論の後に、血管内ステントグラフトを除去することが決定された.患者は2期的な治療を受けた.
正中開腹術により、8mm径の環状ポリテトラフルオロエチレン製コンジットを用いた右総腸骨動脈-上腸間膜動脈バイパス術が施行された.
大動脈の感染部位を除外するため、下行胸部大動脈から上腸間膜動脈下まで胸部血管内ステントグラフトを送達・展開しやすくするために、左大腿動脈を切断した.
上腕動脈への経皮的アクセスも画像診断のために行われた.
血管内ステントグラフトを留置前に、上腕動脈を介した腹腔動脈へのアクセスを得る試みは、拡大した大動脈瘤の影響で不成功に終わった.
それゆえ、開腹切開により適切な肝動脈へのアクセスを確保し、腹腔動脈起始部にアンプラッツァー血管栓閉塞装置を留置した.
大動脈の感染部位を除外するため、下行胸部大動脈から上腸間膜動脈下まで胸部血管内ステントグラフトを送達・展開しやすくするために、左大腿動脈を切断した.
上腕動脈への経皮的アクセスも画像診断のために行われた.
血管内ステントグラフトを留置前に、上腕動脈を介した腹腔動脈へのアクセスを得る試みは、拡大した大動脈瘤の影響で不成功に終わった.
それゆえ、開腹切開により適切な肝動脈へのアクセスを確保し、腹腔動脈起始部にアンプラッツァー血管栓閉塞装置を留置した.
術中に行われた画像検査では、感染した(mycotic)下行大動脈と内臓血管の血管内の遮断はうまくいったと考えられた (Fig 4).
完成時の画像を撮影し、切開を閉鎖し、患者はICUへと移送された.
Dr. Triant: 感染性動脈瘤の治療期間は6週から6ヶ月が推奨される.
患者個別の状況により終生の抑制的な抗菌薬投与が検討され、ある種の耐性菌の場合は術後に好んで用いられる.
今回の患者では、(ステントグラフトが留置されたため)6週間のセファゾリンでの治療の後に、修正の内服抑制治療が計画された.
術後4日目にTTEで大動脈弁に疣贅が見つかったため、抗菌薬がナフシリンに変更になった.
術後14日目、患者はリハビリ施設に退院した.
彼は、MSSAに関連した感染性大動脈瘤と固有弁IEに対して6週間の点滴抗菌薬治療を終了し、セファレキシンによる長期経口抑制抗生物質療法に移行した.

