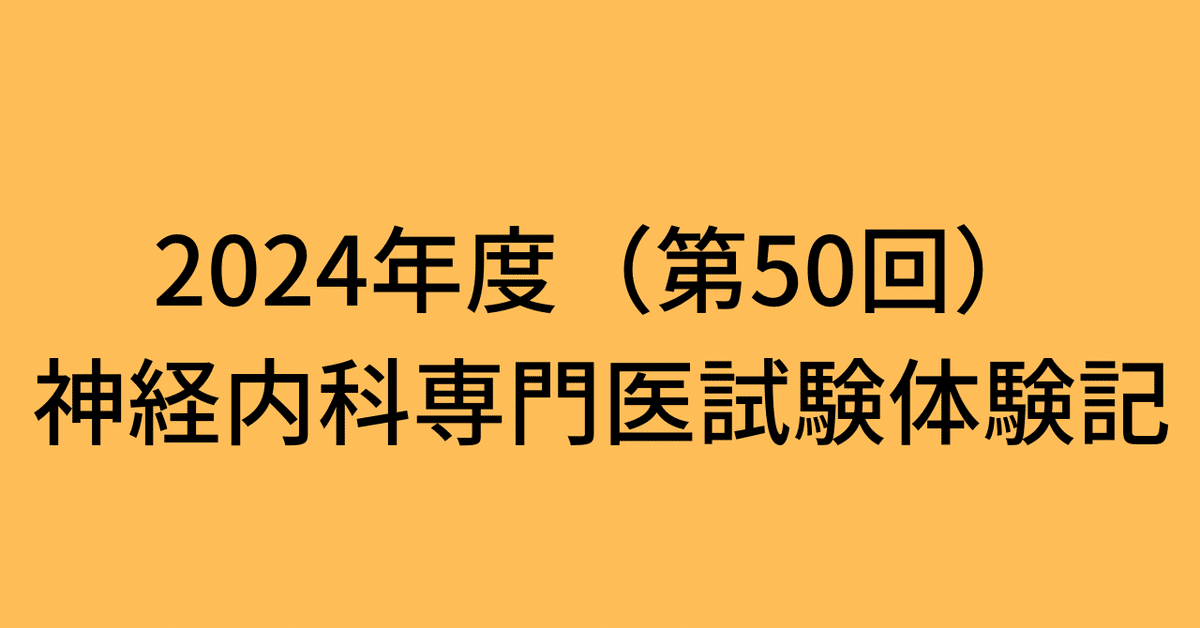
2024年度(第50回)神経内科専門医試験体験記
はじめに
こんにちは、ばくふうんです。
この記事を開いた方は、おそらくこれから専門医試験を受験予定の脳神経内科の先生方かと思います。
国試や内科専門医試験などと異なり、専門性が高まっていくほど受験者数が減っていき、自然と情報が少なくなっていきますよね。私自身も、神経内科専門医試験(特に2次試験)については情報を集めるのに苦労しました。
一部の先生方が試験の概要や勉強の仕方など公開されておられますが、情報は新しいものの方が良いのは間違いないと思うので、今後試験を受けられる先生の参考になればと思い、2024年12月現在で最新の試験の裏側をお見せできればと思います。
なお1万字を超えています。お覚悟ください。
過去問の入手
やみくもに教科書やガイドラインを読んでも、もちろん自分のための勉強にはなるのですが、試験勉強としては効率が良くありません。結局のところ、どの分野が、どの症候が、どの疾患が、どの検査所見が頻出なのかというのは、過去問で実際に問われた内容を見なければ判断できません。
まずは、ご自身の勤務先にいる先輩や出身大学の医局に属する先生などを通じて過去問を入手しましょう。日本神経学会が公表を禁じていますので、さすがにここで過去問を公表することはできませんが、必ず過去問の再現が存在しますので、あらゆるツテを辿って過去問を入手してください。
私が過去問を入手したのは2023年11月、その年の専門医試験が終わった直後でした。当時は2022年までの問題までしかありませんでしたが、その後2023年の再現問題も手に入れました。
実際に目を通す過去問は過去4〜5年分もあれば十分です。一部の噂では4年毎にプール問題が変わるとのことですので、少なくとも4年分は解いておくと安心かと思います。あまりそれ以上昔の過去問を解いても、傾向が変わっていてメリットが少ないかもしれません。
実際に解いてみるとわかりますが、脳卒中やパーキンソン病、認知症など脳神経内科医が避けて通れない疾患が頻出なのは当然として、顔面肩甲上腕筋型ジストロフィーや脳腱黄色腫症などめったに出会わないのにしょっちゅう出題されるもの、CANVASや自己免疫性GFAPアストロサイトパチーなど比較的新しい概念の疾患、電気生理検査(NCS、針筋電図)、脳病理、末梢神経病理、筋病理など、勉強して慣れておかないと太刀打ちできない検査など、要点がなんとなく見えてきます。
なお、日本神経学会から公式に出版されている過去問として、「神経内科専門医試験問題 解答と解説」「神経内科専門医試験問題 解答と解説 第2集」があります。過去問の中から良問を抜粋した問題集で、解説も非常に詳しく記載されているため、純粋に勉強にはなるのですが、第1集は2017年に発行され、2013年〜2015年の過去問から掲載されており、情報が古いです。第2集は2024年に発行され、2017年〜2021年の過去問から掲載されており、買うのであれば第2集だけで十分かと思われます。
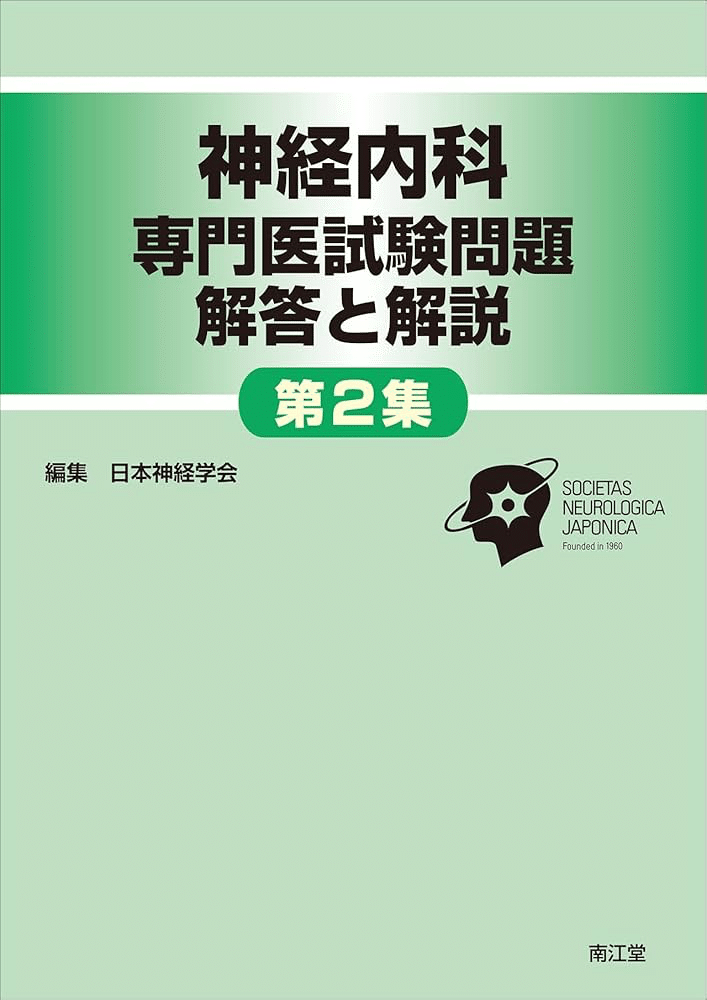
私は専攻医時代に興味本位で第1集を購入し、それとなく勉強しておりましたが、最近の試験の傾向とはかけ離れた問題も多かったため、やはりお勧めはしません(解剖学や病理など、変わらず問われ続けている分野については役に立ちましたが)。
教科書・参考書
ここからは、私が実際に使用していた教科書・参考書を紹介していきます。
試験勉強用に新たに買った本は上記の過去問集くらいで、元々持っていた本を活用して勉強していました。
他の先生方と重なる部分もあるとは思いますが、ご了承ください。
①神経全般:神経内科ハンドブック(医学書院)
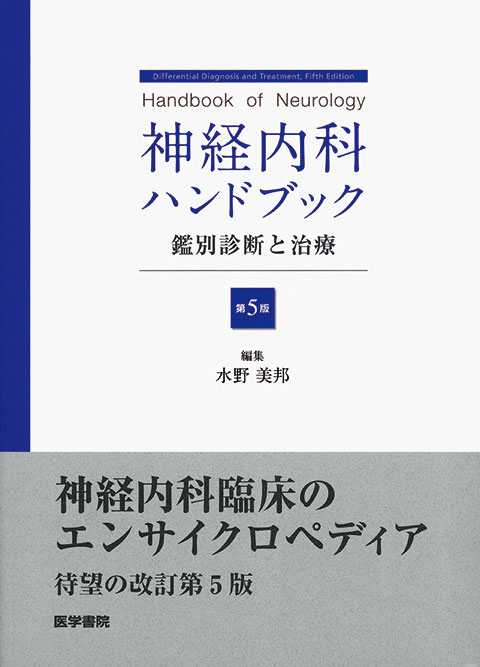
脳神経内科定番の教科書のひとつ。
「ハンドブック」という名前とは裏腹に、1000ページを超える重厚感のある教科書です。各疾患がコンパクトにまとまってはいるのですが、発行が2016年で最新の治療には追いついていないため、そのあたりは各種ガイドラインなどで補う必要があります。通読には不向きなので、各疾患の概要を掴むために辞書的に用いる使い方をしておりました。
②解剖学:臨床のための神経機能解剖学(中外医学社)

神経走行や症候との対応を参照するのに使用していました。
三叉神経主知覚核や三叉神経脊髄路核の違いなど、ややこしい部分を問われることもあるため、解剖学は試験までに何度も確認する機会があると思います。
③症候学:ベッドサイドの神経の診かた(南山堂)
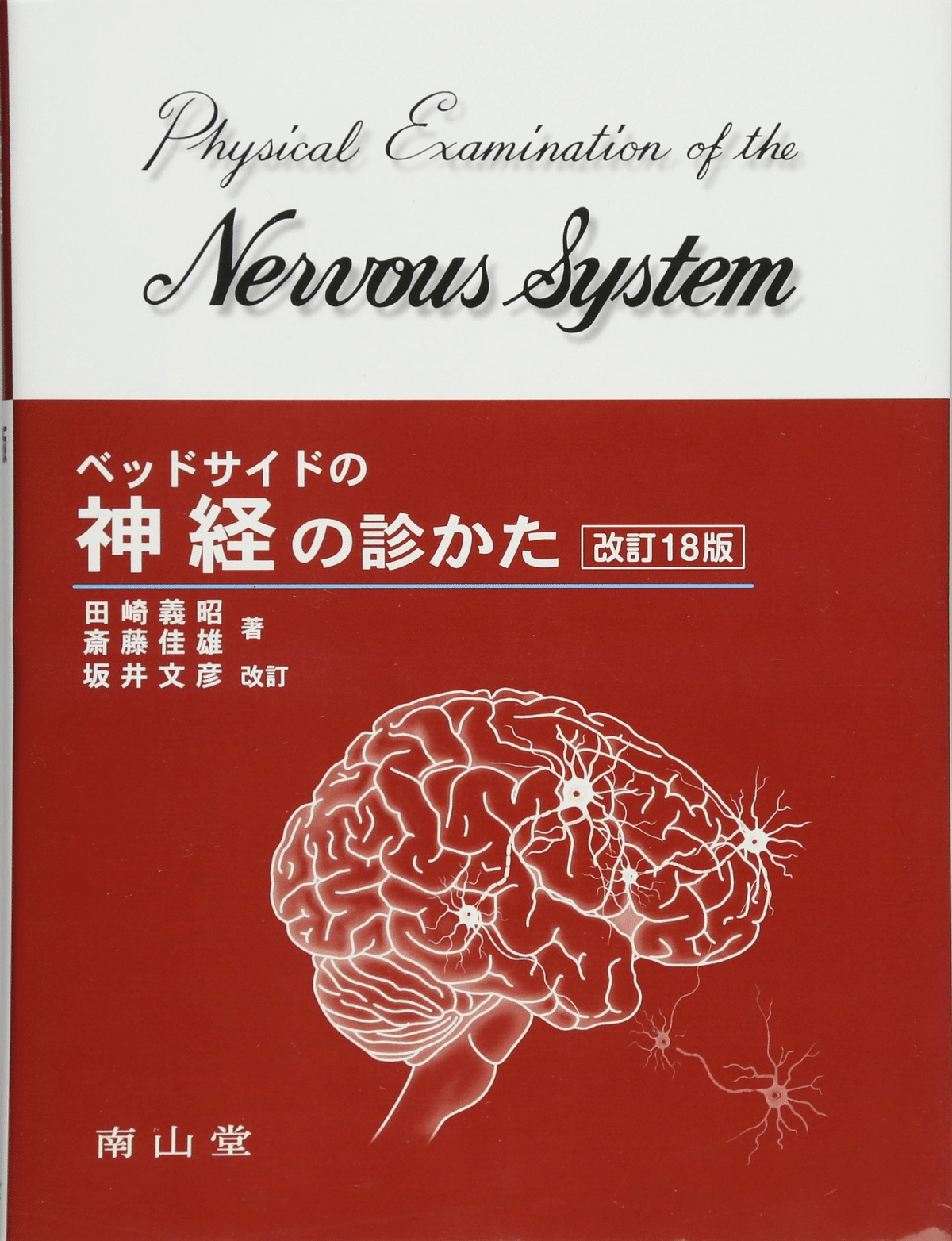
試験勉強というよりは、駆け出しの頃に診察手技を確認するために購入したもの。一応二次試験の準備にも使っていました。こちらも脳神経内科医にとっては定番の教科書ですね。
④高次脳機能:高次脳機能障害の理解と診察(中外医学社)

高次脳機能障害と対応する脳の部位を、MRIでの同定の仕方とともに掲載されており、実臨床でも非常に役に立つ一冊。
⑤末梢神経支配:末梢神経と筋のみかたビジュアルガイド(診断と治療社)

専攻医の頃に研修していた施設では電気生理検査の件数が非常に多く、NCSや針筋電図を行う上で欠かせない、神経根や末梢神経の支配を確認するために購入した本です。末梢神経がどのあたりで分岐して各支配筋へ向かうのかや、「手根管症候群で感覚障害を呈する領域」が図示されているなど、薄い割には何度も開くことになった一冊でした。手根管症候群、橈骨神経麻痺などで、どこに症状が生じるか確認するなどの使い方をしました。
⑥電気生理検査:神経伝導検査と筋電図を学ぶ人のために(医学書院)
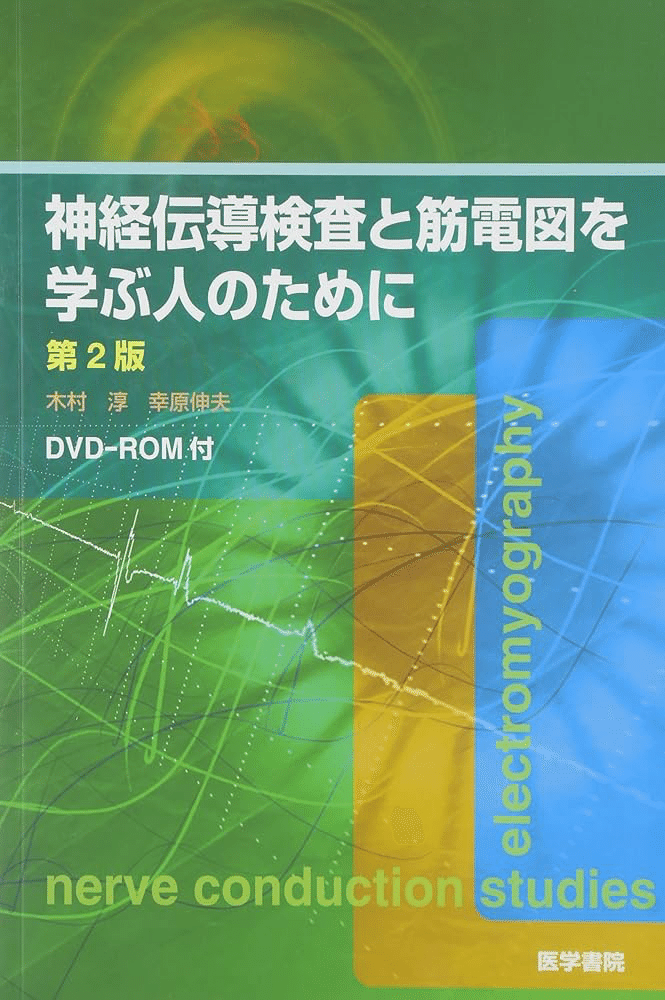
専門医試験に出題される電気生理検査はほとんどがNCSと針筋電図であり、時々反復刺激試験が出る程度です。VEPやSEPの出題は近年はありません。
そんな電気生理検査を学ぶ定番の一冊です。細部まで読み込むと途方もないですので、試験勉強としては辞書的な使い方で十分だと思います。
⑦末梢神経病理:カラーアトラス末梢神経の病理(中外医学社)
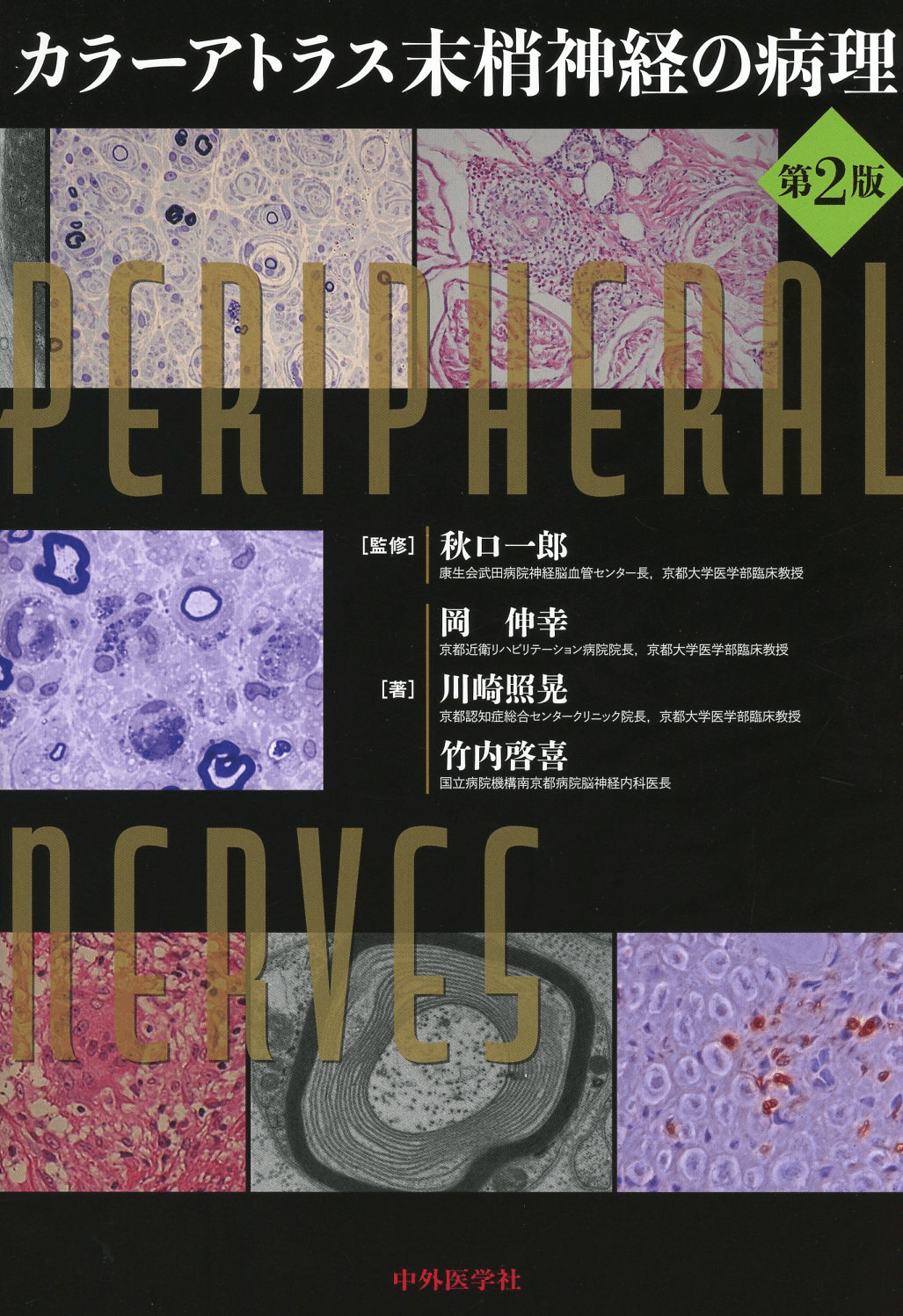
末梢神経病理はこれに尽きます。おそらくどのサイトを見てもこの本が紹介されているのではないでしょうか。
血管炎、CIDP、CMT、MAG抗体関連ニューロパチーなどが頻出です。
⑧筋病理:臨床のための筋病理(日本医事新報社)

こちらも、筋病理といえばの一冊。こちらも皆持ってます。
内容は非常に盛りだくさんなのですが、試験勉強に絞ると、皮膚筋炎、封入体筋炎、ネマリンミオパチー、ミトコンドリア病などを中心に押さえておくと良いと思います。
⑨脳病理:東京都医学研・脳神経病理データベース
どうやっても勉強不足になる脳病理。
私も主要なポイントだけ抑え(たつもりになっ)て、残りはほとんど捨ての精神で挑みました。
その主要なポイントを抑えるのに、東京都医学研・脳神経病理データベースというサイトを利用させていただきました。こちらもいろんな先生方が紹介されていると思います。
パーキンソン症候群(MSA、PSP、CBD)のミクロ病理や、PMLのマクロ・ミクロ病理などが頻出ですが、時々小脳のミクロ病理や脳腫瘍が問われることがあり、過去問再現を見ても誰も正解が分かっていないなどということもザラにあります。
⑩疾患各論:各種ガイドライン
近年は神経分野のガイドラインも充実しており、ガイドラインの内容から逸脱した問題は少なくなりました。
脳卒中ガイドラインは有料ですが、頭痛、パーキンソン病、重症筋無力症などほとんどのガイドラインは日本神経学会のホームページから無料で参照することができます(PDF形式でダウンロードも可能です)。
特にMG、MS/NMOSD、片頭痛などは新たな治療選択肢が増えてきているホットトピックスなので、現在のガイドラインの立ち位置を確認しておくことは重要です。
その他、ギラン・バレー症候群、CIDP、ALSなどもガイドラインの改訂が相次いでおり、要チェックです。
⑪診察手技:日本神経学会e-learning
二次試験で問われる診察手技についてですが、学会から「標準的な神経診察法」としてe-learningが視聴可能です。一度は目を通しておくことをお勧めします。
⑫専門医育成教育セミナー
毎年5月頃に開催される日本神経学会学術集会で専門医育成教育セミナーが開催されています。例えば2024年度は「脳病理」「膠原病による神経障害」「脳波判読」「自律神経障害」の4トピックが扱われました。セミナーで強調された部分が実際に試験で問われることもあるようですので、その年の専門医試験を受験予定の方は是非受講しておくべきです。過去のセミナーも学会のe-learningで視聴できますので、ご活用ください。
というわけで、過去問+背景知識の補足を繰り返し、試験に向けて準備していきました。
ここからは、実際に受験に際しての準備・申請から試験本番の様子や、情報の少ない二次試験の体験記を記していこうと思います。
専門医試験体験記①<症例登録〜受験申請編>
ここから先は
¥ 980
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
