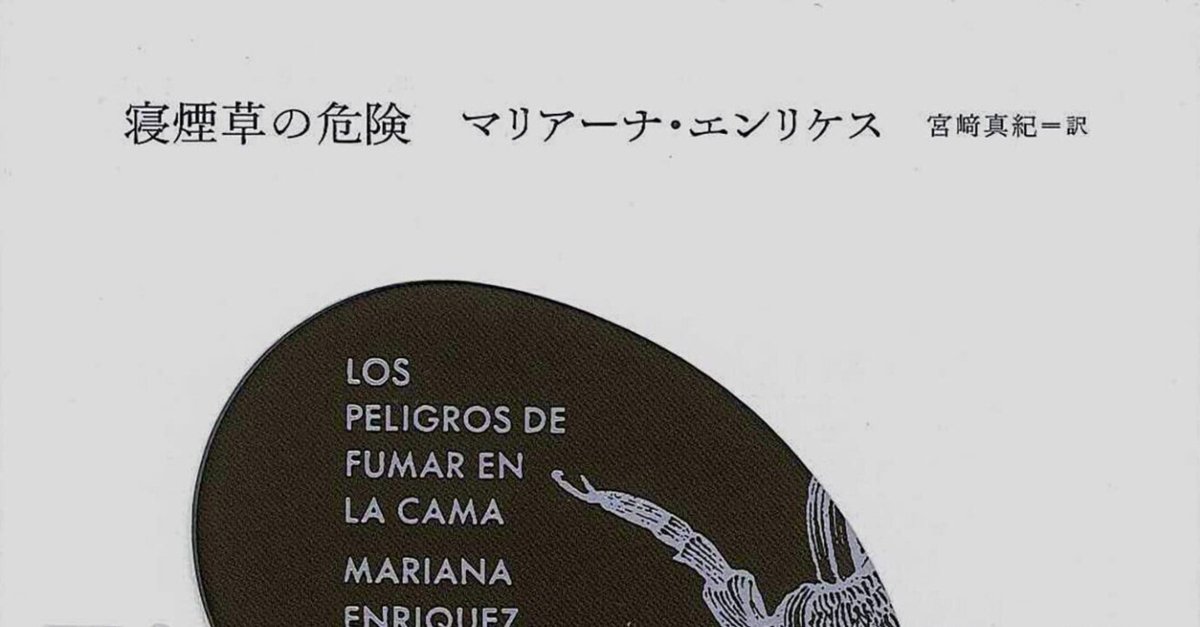
日記:20230630〜マリアーナ・エンリケス「寝煙草の危険」〜
仕事開始しようと思ったらVPNがつながらない。というかWi-Fiがつながっていない。
慌ててルーターのケーブルを全部抜いて再接続したりして、それでも解決せず必死になっていたら、なんとなく復帰した。何だったんだ。
朝の貴重な20分を無駄に費やした。
マリアーナ・エンリケス「寝煙草の危険」読了。素晴らしく面白かった。先に翻訳された『わたしたちが火の中で失くしたもの』の前に出版されていた著者初の短編集。
『わたしたちが火の中で失くしたもの』と比べるとずっと読みやすく、ホラー小説としてわかりやすく結構を保っている。それが良くも悪くもという印象で、中盤以降のグロテスクで扇情的な短編群は、すこし人物造形が薄く作り物めいて感じた部分もあった。
でもそれはそれで、初期衝動的な熱っぽさも感じられる。イアン・マキューアンも初期は露悪的な作風だったし、その後の変遷も含めて見守りたい小説家。
■■■ここからネタバレを含みます■■■
「ちっちゃな天使を掘り返す」
ぼろぼろに腐った体で主人公の後を追いかけてくる赤ちゃんの幽霊がグロかわいい。マンガっぽさもある。
「湧水地の聖母」
いちばんオーソドックスなホラー短編で、「奇妙な味」のお手本のような作品。エンリケスには思春期の少女同士の友情のような脆い関係を題材にした小説がいくつかあるけど、これが最も正面から描いている。
「ショッピングカート」
皮肉めいたパニック・ホラー。街や社会全体が、疑心暗鬼のような状態に陥る作品が見られるのは、エンリケスが育ってきた不安定で弾圧的な時代背景の影響も大きいのかもしれない。
「コカ夫人は猫を食べたあと自殺した。」という突き放すような表現がハードボイルド的でさえある。
この結末はカニバリズムなんだろうか。
「井戸」
前半の作品群ではこれがいちばん好き。病的に神経質で臆病な女家族に囲まれてきた少女・ホセフィーナが、ある日を境に恐怖に囚われ社会から逸脱していく。あらゆるものに怯えるホセフィーナの姿に、強迫神経症だった頃の自分を重ね合わせてしまう。
冷たい手が触れてきそうな気がして、絶対にシーツから脚を出さない。母が出かけるときには、リタおばあちゃんがホセフィーナに付き添うが、帰りが三十分以上遅れると、ホセフィーナは嘔吐する
救いのない結末は残酷なほどに皮肉が効いているし、メタ・ホラー的でもある。
作中で引用される、先住民の少女アナイーが火刑に処せられたあとに、アルゼンチンの国花の赤いセイボの花が咲いたという伝説は、エンリケスの作品全般に通底している気がする。
「悲しみの大通り」
幽霊譚と精神を病んだ友人の妄想のどちらにも取れるような曖昧な話。鼻にこびりつく悪臭が、妄想と現実を橋渡しする。とにかく悪臭に関する描写の生々しさが印象に残る。エンリケスだけでなく、「兎の島」のエンリケ・ナバロもそうだった。
「展望塔」
前半と後半の分岐点に位置する作品。エンリケスは『わたしたちが火の中で失くしたもの』所収の「緑 赤 オレンジ」で、日本の幽霊や妖怪について言及していたけど、この作品の構成は「七人みさき」じゃないか?
ホラーストーリーとして巧みな結末を迎える綺麗な構成の作品。ただ、あまりに上手にまとまっているので、主人公の一人である女性・エリナの描き方に疑問を感じてしまう。特に性的被害を受けたトラウマを抱えているくだりが、ストーリーを盛り上げるためにとってつけられたような印象も受ける。
とはいえ、決して嫌いな作品ではないし、むしろホラー小説として巻中でもかなり好きな部類ではある。
「どこにあるの、心臓」
ここから一気にグロテスクで猟奇的な作品が並ぶ。扇情的な内容ではありながら、描写自体は客観的で素っ気ないところがかえって怖い。
名古屋大学の女子大生が起こした快楽殺人の事件などを思い出して、すこし嫌な気分になった。エンリケス作品には現実の悲惨さや恐怖がバックボーンにあり、それを異形化していくのが魅力だと思うのだけど、この短編に関しては現実に起こる事件の恐ろしさを超えるところまではいっていない気がする。
「肉」
エンリケスのロック趣味が表れている作品。土葬という文化の違いこそあれ、ロックスターの死をきっかけに逸脱してしまう二人の少女と、彼女たちに向けられる他の少女たちからの羨望は、すこし共感できる。
マリエラとフリエタを取り巻く世間の反応や、エル・エスピナの死骸を食べた後、嘔吐していたといった描写に、突飛なダークファンタジーに終わらないリアリティがある。
「誕生会でも洗礼式でもなく」
セックスに関する描写より、自慰行為についてここまで執拗に描く小説家は他にあまり知らない。キリスト教的な道徳教育の影響も感じるのだけど、どうなんだろう。
「戻ってくる子供たち」
これはすごい。これまで読んだ小説の中でもトップクラスに怖い。
子供たちがただそこにいるだけで、得体の知れない恐ろしさを感じるのは半村良「箪笥」のような不気味さを感じる。これだけのボリューム感のある作品で、あの怪談小説が持つ一瞬の切れ味を薄れることなく保っているのは見事。さらに、パニックホラー的な要素も併せ持っている。
いちばん怖かったのは、廃屋に籠った子供たちに主人公・メチが問いかけると、窓から顔を見せる子供たちが一斉に声を揃えて答える場面。子供たちがすでに個々の存在ではなく、人知を超えたひとつの塊のような存在であることが示される。
美少女バナディスの造形も魅力的だし、一部で話題になった日本人の死後の世界観や、十八世紀末パリで満員になったカタコンベに埋葬された死体を掘り返して別の場所に移動した、というエピソードも幻惑的。
バナディスのフェイバリットのひとつとして、マリリン・マンソンやスリップノット、ホラー映画と並んで「日本映画」が挙げられているのも注目。
エンリケスが日本のホラーや怪談にどの程度精通しているのかはわからないけど、行方不明の少年少女が消えた時のままの姿で戻ってくるというテーマは、「耳嚢」などに書き留められた江戸時代の神隠しの逸話を想起させる。
「寝煙草の危険」
収録作中では最もストーリー性が希薄で、散文詩のような作品。小品ではあるものの、炎に焼け焦げる蝶、自慰行為、悪臭など、エンリケスらしいモチーフが詰まっていて、本書の表題作になっているのも頷ける。
「わたしたちが死者と話していたとき」
巻末を飾る作品は、前半の作品群に回帰するような思春期の少女たちのあやふやさを描いたホラー。少女たちの青春とウィジャ盤というモチーフは古典的でさえあるけど、終盤に起こる怪異はホラーというより怪談実話的な不気味さがある。

