
ていねいな保育【支える活動編】
▼前回のコラムもぜひお読みください。
「ていねいな保育」の基礎知識も6回目。今回で一区切りです。
まとめとなるテーマは「支える活動」。文字通りていねいな保育を支えているのは、保育者または保護者たちのどのような活動なのでしょうか?
保育の現場にも「PDCA」導入?
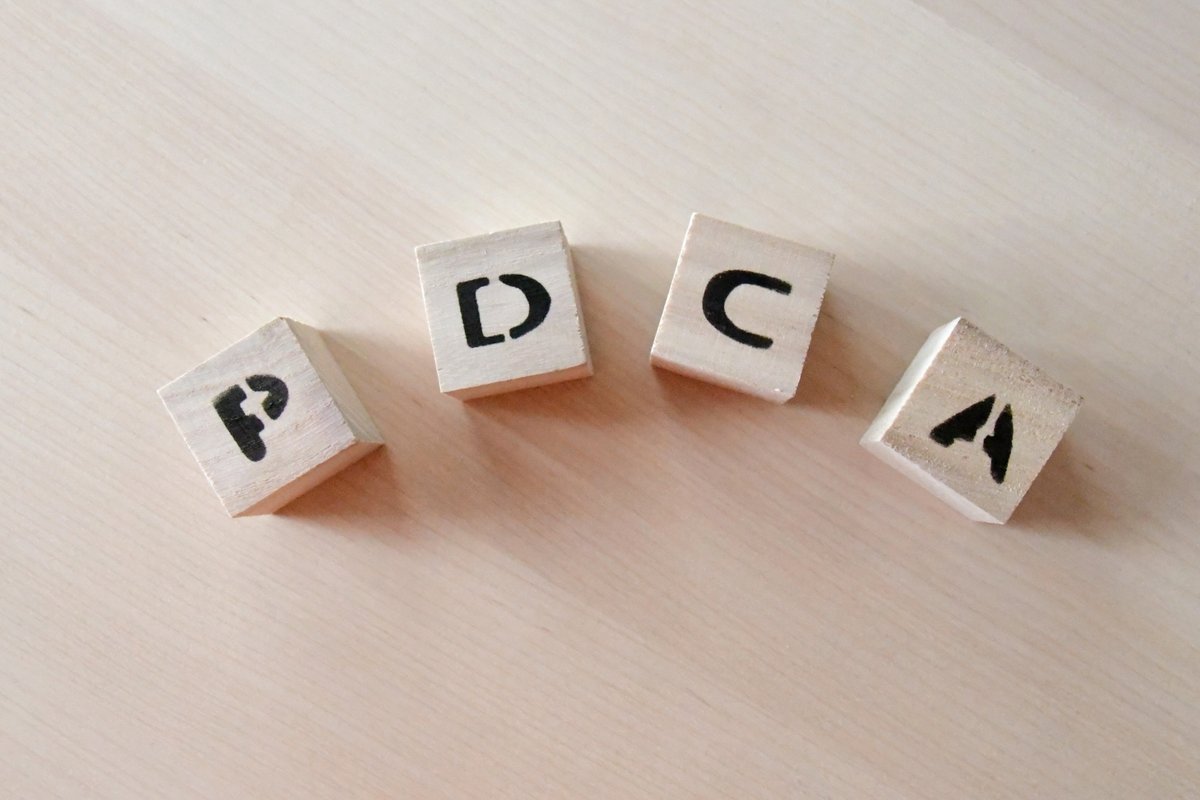
ていねいな保育の根幹でもある「子ども主体の保育」は実は大正時代からあった考え方なのですが、高度経済成長期には、保育所は働く保護者のための預かり施設として見なされ、「子ども主体の保育」を行うには困難な状況でした。しかしその後、小学校以上の学校教育でも学業よりも「生きる力」を重要視する「ゆとり教育」が出てきたことで、保育所の方針も変わってきました。2008年(H20)に改訂された保育所保育指針では、保育の質の向上を目指し、保育の計画や、保育士・保育所の自己評価が重視されるようになりました。
この計画・評価の手法として取られたのがビジネスの世界で多用されていた「PDCA(Plan計画・Do実行・Check評価・Action改善)」サイクルです。
計画をたて、子どもたちの様子を記録し、振り返りを経て、次の計画を立てるというものですが、特に子ども主体の保育を実践していると、まず計画通りに子どもたちは行動しません。
計画が無駄とは言いませんが、実態にともなっていない感じがあり、より良い方法があるのでは?と思っていました。
「PDCA」よりマフィスらしい
「SOAP」サイクルで実態に即した環境づくり

そのようにPDCAサイクルを回しながら模索する中で辿り着いたのが「SOAP」というものです。もともとは医療看護の現場で対象者(患者)の経過をカルテに記録する際の方法だそうで、Sbujective(主観的)Objective(客観的)Assesement(評価)Plan(計画)の順で考えていきます。医療で言うところの患者は保育では子ども、看護者は保育者です。
1.子ども(Aくん・2歳児)から出た(言った)情報=主観的情報(S)
【例】「この前、公園にダンゴムシいたね!、今日もいるかな?」
2.保育者が観察した情報=客観的情報(O)
【例】今度はダンゴムシに興味が出てきたのかな?この前まではアリに興味を持っていたなぁ。最近は昆虫図鑑もよく見ているし・・・。
3.1(S)と2(O)を合わせてアセスメント・評価
【例】生き物にも命があることを伝えたいので、園でダンゴムシのお世話をすることを提案
4.3の分析・評価から保育計画を立てる
【例】何に入れて何を食べて、どのように育てるのか話し合い、必要な道具を用意する。事前に昆虫図鑑やインターネットで調べてみる。
といったように、子どもが発した情報=主観的情報と、保育者が観察して得た情報=客観的情報を合わせて総合的に評価し、その後の計画(環境改善)を立てていくのです。
この流れは子どもの主観的情報から始まり、実態に沿った形で実行されていくので、「計画はしたけれど…」といったことが起こりにくく、使われない書類を作成する時間の削減にも・保育者の業務負担軽減にも繋がり、子どもを主体とした保育の考え方・方法にも則しています。
ただ、PDCAの手法を否定するわけではなく、マフィスではSOAPがフィットしたので採用しています。他にも最近ではOODA(ウーダ)といってObserve(観察)、Orient(状況判断)、Decide(意思決定)、Act(行動)の4つのフェーズから構成される意思決定の理論を採用しているところもあります。
どんな方法であれ、その園の子どもに対して保育者が「子ども主体のていねいな保育」を行うには何が最善なのかの探求の結果なのだと思いますし、それは変化しても良いものだとも思います。
絶対に欠かせない保護者との関わり

言うまでもなく、ていねいな保育は、保育者と保護者の双方が支えています。両者の協力・関わりがなくては成り立ちません。
日々の連絡アプリでのやり取りをはじめ、専門的な視点からの情報発信(このnoteも)、「ラーニングストーリー」など子どもの成長を記録したものを保護者と共有することで、相互の理解を得て、ていねいな保育は実践されていくのです。
「ラーニングストーリー」ってどんなもの?

保護者との連携のため大きな役割を担っているのが、毎月作成している「ラーニングストーリー」です。これは「子どもの成長を保護者・保育者共にポジティブに楽しむ」をコンセプトに作られています。
先にご紹介した「SOAP」にそって、その月に子どもが発信したこと、保育者が観察したこと、それらを元にした保育者の見解、翌月に予想される子どもの姿をA4サイズに写真付きでまとめ、保護者へ渡します。
1枚にまとまるくらいのボリュームで「共に今の姿を楽しむ」ことがメインの目的ではありますが、もう一つの大きな役割として、今後の方向性について両者ですり合わせることを行っています。
Planの部分の「ご家庭と保育園の思い・願い」の横に、保護者からのメッセージを書いていただきます。

時には、保育者から「来月こういうことをしてみようと思いますがどうですか?」と意見・同意を求めたり、保護者から「家庭では最近こうなんですが、園でもそこを伸ばしてみてもらえますか?」とお願いしたり、それぞれの観察・分析に基づき相互にリクエストを出し合うこともあります。
毎月方向性のすり合わせを行うことで、よりていねいな保育の実践に役立てられるのです。
マフィスが実践する「ていねいな保育」とは
今回までで全6回「ていねいな保育」についてご紹介してきました。マフィスが思い、実践している「ていねいな保育」についてなんとなくでもお分かりいただけたでしょうか?
「ていねいな保育」を通じて保護者・保育者、みんなに問うているのは「子育てを楽しんでいますか?」ということ。
子どもはどうしても“大人がやってほしくない事”をします。
そんな時に、子どもがやったことに対して評価をするのではなく、寄り添ってほしい。
子ども、ひいては人間は、自分たちなりに成長するすべを生まれた時から持っています。
どの段階でどのような力や知恵が必要か? 生きる上でのルールをどう知っていくか?
これらは、子どもたち自身が自らの成長によって知り(感じ)、得ていくものです。感情的なことであっても、彼らは自らの気持ちの収め方をすでに知っているのです。
周囲の大人は、子どもたちを観察して、何を思い、どう行動し、いかに自己をコントロールしているのか? どの成長段階にいるのか?を把握し、子どもが本当に必要としている時に手を差し伸べてあげるだけでいい。
成長を一緒に楽しみ、喜んであげるだけでいいのです。それが「ていねいな保育」だとマフィスは考えています。
ここまでお読みいただきありがとうございました。




