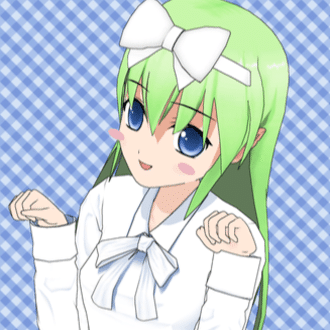そもそも品質工学f 誤差因子を甘く見るな!(69)
本当に、誤差因子を甘く見た実験の多いこと、多いこと。
それに注意喚起をするマンガです、はい。







実際に走らせてみると…



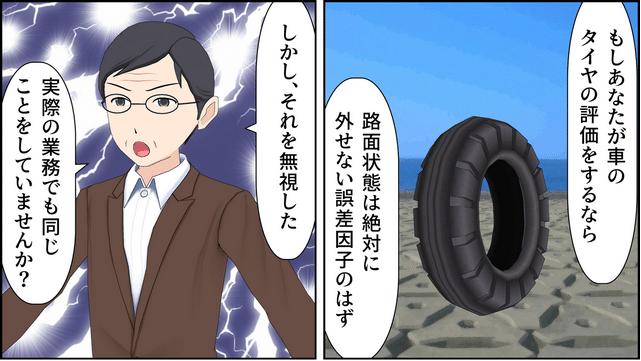




ちなみに、機能が基本機能で、エネルギーの関係で、誰が見ても納得するような素晴らしい入出力だったら、誤差因子はその入出力を乱す、エネルギーの流れを阻害する何か1つでOKです。
だから、品質工学の大先生方は、あまり誤差因子の研究には力が入っていませんでした。当然ですよね?すばらしい機能を思いつくんですから。
では、我々凡人はどうでしょうか?
そんな素晴らしい機能を思いつきますか?
無理でしょ?w
だから、誤差因子に力を入れます。
どんな環境でも強くする。
その「どんな環境」を作るしかないのです。
もちろん、機能をより良いものにする努力は必要です。
その良いものになる前の、ヘボイ機能をカバーするのは誤差因子の多さなのです。
ただ、多ければいいってもんじゃない。
各カテゴリーの主要な誤差があればいい。
それが、環境と劣化、もののばらつき。
温度湿度の環境、劣化と言っても化学的劣化、物理的劣化、ばらつきも製造ばらつきと、使用後のばらつき。
そういった主要なものを抑えているか。
それが重要になってきます!
誤差因子がしっかりしていれば、機能はなんでもいいのか?
そういわけでもありません!
続きが気になる人はこちら!
↓ ↓
いいなと思ったら応援しよう!