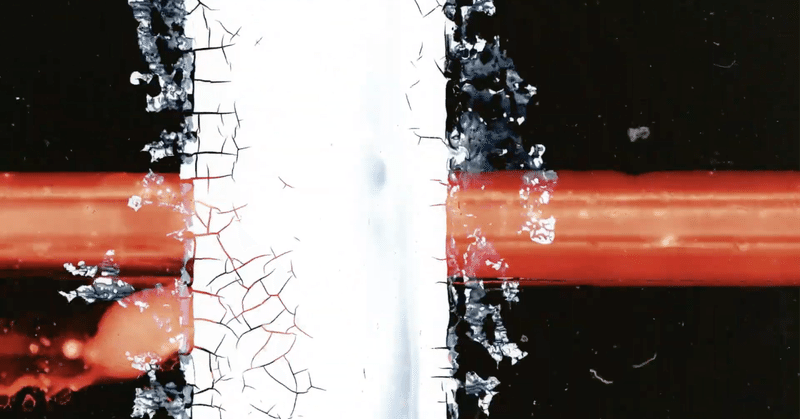#実験映画

【映画評】 イメージフォーラム・フェスティバル2013 萩原朔美『秋丸・春丸―目の中の水』、中野智代『Lily』、黒川芳朱『都市と知覚のフィールドノート1』、宮川真一『みずうみは人を呑み込む』 〝セルフ〟とは
2013年に開催されたイメージフォーラム・フェスティバル2013《創造するドキュメンタリー、無限の映画眼》 開催当時のわたしのメモを読み返していたら、〝セルフ〟についての脳内を螺旋運動するかのような迷宮思考を見つけた。 同フェスティバルはテーマ別に分類されたプログラム群で構成されているのだが、『ジャパン・トゥモロウ』部門の中のEプログラム《対象である自分 セルフドキュメンタリーの現在》。 わたしはEプログラムに触発され、鑑賞後、〝セルフ〟とは何かと問うてみた。 セルフとは何