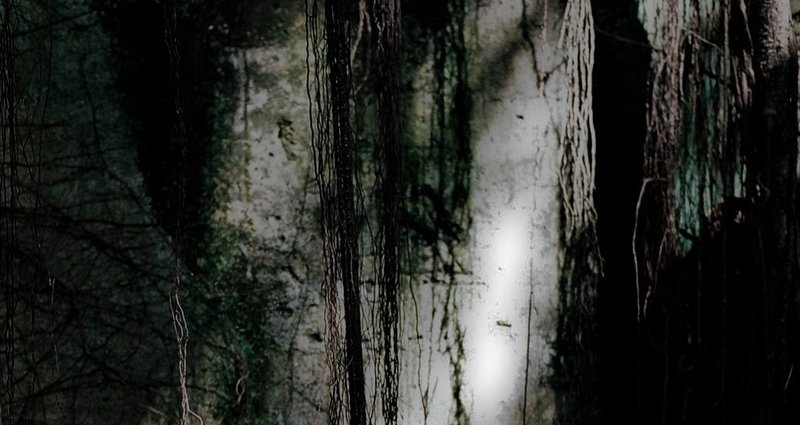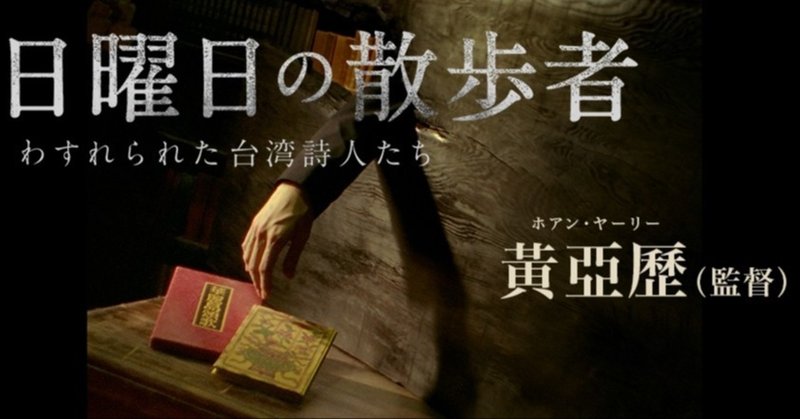2020年12月の記事一覧

【映画評】 レナーテ・ザミ『チェザレ・パヴェーゼ、トリノ - サント・ステファノ・ベルボ』『ブロードウェイ 95年5月』。声となり眼となり
ドイツの映画監督レナーテ・ザミ(Renate Sami 1835〜)の2作品『チェザレ・パヴェーゼ、トリノ — サント・ステファノ・ベルボ』『ブロードウェイ 95年5月』のメモを整理しながら、もし再見できればレビューとしてまとめたいと思っていた。しかし、ドイツでもマイナーな監督であり、まして、日本の地方に住んでいる者に再見の機会はそう簡単には訪れない。このままでは忘却の一途をたどること間違いないだろうから、筋道が見えないながらもメモを再構成し、記事として掲載することにしました