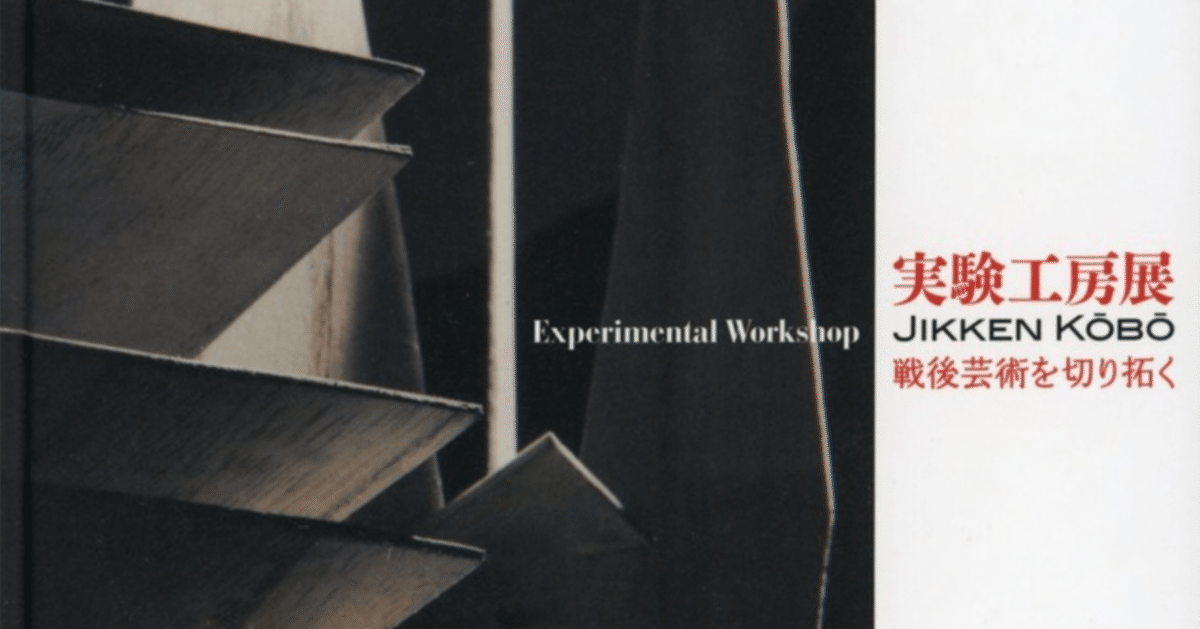
「現代への扉 実験工房展 戦後芸術を切り拓く」
メディア芸術カレントコンテンツ 2013年03月29日更新
実験工房は、終戦後1940年代後半からそれぞれに交流のあった、造形作家の北代省三、福島秀子、山口勝弘、作曲家の鈴木博義、武満徹、音楽批評家、詩人の秋山邦晴、エンジニアの山崎英夫らが集まり始まった。当初は、北代によってグループとしての活動を視野に入れ、「アトム」と命名されていたという。そして、1951年に最初のグループとしての活動である、日比谷公会堂で行なわれた「ピカソ祭」におけるバレエ《生きる悦び》の上演の際に、詩人、美術批評家の瀧口修造によって実験工房と命名されている。そこで照明家の今井直次が加わり、また、実験工房としての活動開始以降には、ピアニストの園田高弘、作曲家の湯浅譲二、福島和夫、版画家の駒井哲郎、写真家の大辻清司、作曲家の佐藤慶次郎が参加し、グループとしての活動は1957年まで続いた。
神奈川県立近代美術館館長水沢勉によれば、実験工房の活動は、一時は「関係者を除いてほとんど忘れかけられていたといってもよい存在であった」(展覧会カタログより)という。しかし、現在では日本におけるテクノロジー・アート、メディア・アートの前史として、あらためてその美術、音楽、舞台芸術を総合した領域横断的な作品制作およびグループとして活動形態など、その先駆的な試みへの関心が高まっている。それは、実験工房が60年代という70年の大阪万博へと向かう、日本のテクノロジー・アートの隆盛期において、その機運の高まりを待たずしてグループとしての活動を終えてしまったということもあるだろう。60年代のアメリカで、アーティストとエンジニアの恊働によるグループ、「E.A.T.(Experiments in Art and Technology)」が、テクノロジーを介したさまざまな芸術領域の総合をめざした「インターメディア」を標榜した活動を行なったことを考えれば、それはまさしく「早やすぎた」活動と言えるものだった。とはいえ、60年代にはメンバー各人の活動によって、実験工房をへたさまざまな試みが、同時代の新しい動向へと継続され、また大阪万博へも結実していった。展覧会では、(実験工房)「前夜」、「「実験工房」の時代 1951-1957」、「1960年代へ」という三部構成となっており、実験工房以後でありながら、その延長線上に位置づけられる活動までを網羅するものだった。
今回のような、実験工房のグループとしての活動を単独でとりあげた大規模な展覧会は初めてのことになる。また、2000年以降、個別のメンバーの実験工房に関係したものには、「風の模型 北代省三と実験工房」展(川崎市岡本太郎美術館、2003年)、「メディア・アートの先駆者 山口勝弘展 「実験工房」からテアトリーヌまで」(神奈川県立近代美術館鎌倉、2006年)、「大辻清司の写真 出会いとコラボレーション」(渋谷区立松涛美術館、2007年)、「Yuasa Joji による湯浅譲二」展(郡山市立美術館、2007年)、「実験工房の作家たち」(千葉市美術館、2011年)、「MOTコレクション 特集展示:福島秀子」(東京都現代美術館、2012年)、「モノミナヒカル-佐藤慶次郎の振動するオブジェ」展(多摩美術大学美術館、2012年)などの展覧会が開催されている。そこにも、近年の実験工房への再評価の過程を見ることができるだろう。
実験工房の総体としての活動がこれまでなかなか振り返られてこなかったことの理由には、活動、作品の性質上、当の作品を観ることができないこと、また、その保存が非常にむずかしいものであること、それぞれの作家が異なる表現をもちいていたこと、などの理由があるだろう。しかし、北代省三の図形の空間における運動を視覚化したような抽象絵画作品や動く彫刻であるモビール作品、山口勝弘のモールガラスを通して観ることで、観客の動きによって見え方を変化させる作品《ヴィトリーヌ》、福島秀子のスタンプによる絵画、大辻清司による公演の記録写真など、個別の作家による多くの作品は、現在でも意義深いものであり、美術館による収集も行なわれている。一方、今回の展覧会では、公演のポスターや舞台装置や衣装のスケッチ、および記録写真など、多くの資料展示が含まれ、今後の研究資料として、作品の再現や発見など、今後さまざまに分析されることになるだろう。
その意味では、『アサヒグラフ』(朝日新聞社発行)に1953年から毎週コラム欄のタイトル・カットとして掲載された、APN(Asahi Picture Newsの略、「あぷん」と読む)の展示は興味を惹かれた。実験工房の北代省三、山口勝弘、駒井哲郎の3人と斎藤義重がオブジェ制作および構成を担当し、それを大辻清司が撮影した写真を掲載したもので、展示では、実際の誌面、それに掲載された同じプリント、さらに同一のオブジェによる掲載されたものとは別のカットによる写真も展示されていることで、それが実際にどのようなオブジェだったのか、どのようにイメージが定着されていったのか、ということが窺えるものとなっていた。また、それらは立体構成によるオブジェであり、また光と影、あるいは動きを写し取ることによって写真としての構成も含めたものである。それは、ミニチュアの模型であり、どこか異星の風景か、あるいは舞台装置か、というものもあり、それは、カタログで大日方欣一も指摘しているように、オートスライド作品のイメージとも通じるものとなっている。
オートスライド作品は、当時の東京通信工業(現ソニー株式会社)が製造した、テープレコーダーの音声とスライドの映像を同期する装置を使用したもので、まだ販売前だった装置を提供されて制作された、スライドによる抽象的な写真とミュージック・コンクレートやテープ操作によってつくられた音響による映像作品である。特筆すべきは、1953年に開催された実験工房第五回発表会で上演されたオートスライドによる4作品のうち、フィルムとテープの消失のためこれまで再現されていなかった駒井哲郎と湯浅譲二による《レスピューグ》が、2009年に再演された音楽と残された原画をもとに有馬純寿によって再制作されたことだろう。
実験工房の活動は、たしかに、前述したE.A.T.の活動に先がけたものであり、60年代以降にはそれぞれのメンバーもインターメディアを指向する動きに同調していった。それは、音楽、美術、詩、映画など、それら複数のメディアの中間領域における新しい表現を模索する動向であり、1966年の「空間から環境へ」展、1969年の「クロストーク/インターメディア」といったイヴェント、そして、70年の大阪万博へと、実験工房を継承した活動が展開されることになる。60年代以降の活動を紹介する最後のセクションは、実験工房としての活動以降、国内外の動向や作家とも交流しながら、各々にとって当時の「実験」が未来へと接続されながら大きく展開し、ある成果となる過程でもあっただろう。
先にあげた実験工房関連の展覧会においても顕著なことは、実験工房以後も作風は変われども、それらの作家にとって実験工房での活動が、それぞれの原点として位置づけられているということではないだろうか。出発点としての実験工房の先鋭性は参照されるべき、非常に示唆に富むものであったことをあらためて思わされた。
「現代への扉 実験工房展 戦後芸術を切り拓く」
2013年1月12日(土)—3月24日(日)
神奈川県立近代美術館鎌倉および鎌倉別館
