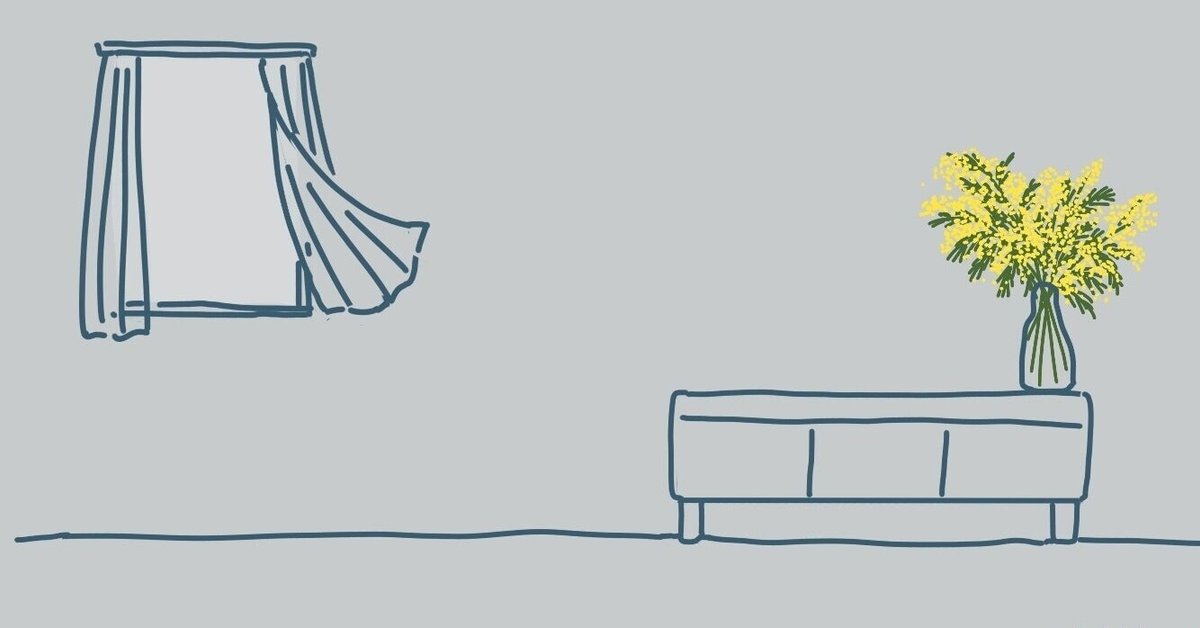
知っていた、信じてた。 #月刊撚り糸
海を眺めて生物の歴史を知る、空を仰いで世界の小ささを知る、そんな高尚な人間にはなれなくても、ケイは充分幸せなのだと自認していた。
ケイは、特別頭のよい人間でもなく、特別見目の整った人間でもない。特別友人が多いわけでもなければ、資産家の家庭に育ったわけでもない。
それでも、幸せなのだと思う。そう信じて生きてきた。
信じることと知っていることは似ているけれど反対だ。
ケイの友人に、リョウという人物がいる。小さく可愛らしく、くりくりとした目がまるで小動物のような、ほんわかとした存在だ。リョウはケイにとって、最も長い時間をともに過ごしてきた友人である。けれど、リョウにとってはその限りでない。また、リョウはケイにとって、なんでも初めにものごとを共有したい相手である。けれど、リョウにとってはその限りでない。
それでもケイは、そう信じていた。
ケイのSNSに、ひとつ投稿があがってきた。リョウの投稿である。
その薬指にあって輝きを放つ指輪。
ケイはなにも、聞いていなかった。
本当はずっと前から知っていた。リョウにとってケイはいちばんではないこと。その他大勢の中の、一角に過ぎないのだということ。
けれど信じていた。ケイにとってリョウはいちばんであると。ずっと、はじめにいるべき人物だと。
信じることと知っていることは似ている。
けれど向かう刃先は反対だ。
ケイの糸が、ぷつんと切れた。
信じる現実を得られないのであれば、海を眺めて生物の歴史を知る、空を仰いで世界の小ささを知る、そんな高尚な人間になれた方がよほどよかった。ひとりで完結して、それでも世界と繋がって、そんな人間であった方が。
本当はずっと前から知っていた。
そうはなれない自分であると。
ケイは皮肉な笑みを微かに浮かべて、リョウの投稿にコメントを残した。目尻をついと拭い、窓の外を眺める。
空は青く広かった。けれど世界が小さいとは、どうしても思えなかった。
【完】
いいなと思ったら応援しよう!

