
『つどい歌えよ、星々よ!』シナリオ分析
全体的な印象
良くも悪くもRTTTの補完という側面が強かった。
RTTT組の空気感を楽しませることに振り切っており、そのぶん多少プロット的な面白さは損なわれていた。なのでRTTTファン向けの作品であり、RTTTの余韻に浸れるか浸れないかがそのまま面白いと感じるか否かの決め手となっただろう。
あらすじ


好きだった点
多彩で味わい深い文章

今回は冒頭部分の疾走感ある文章、アヤベのモノローグの詩的な文章、あるいはデジたんやオペラオーの癖のあるセリフ、あるいはアヤベとオペラオーの屋上でのエモい会話だったりトプロとアヤベの仲睦まじい会話だったりとその時々の雰囲気に適した文体がチョイスされていたような気がした。このような書き分けは余程文章力がないとできないだろう。すごい。フレーバーテキストとか書くの上手そう(小並感)。



オペラオーの想い
なぜ思い出作りなんてことをしようと思ったのかが最後で語られる。勝ち星を上げ続けていたオペラオーはその裏で孤独さを感じており、そんななかで同じ世代の仲間の存在がどれほど大きかったのか、というのがこのセリフだけでなく思い出作りをしたいと思ったことからも伝わってくる。

トプロの打ち明け方と劇
トプロはいわゆる素直な優等生キャラであり、オペラオーやアヤベのように性格面で分かりやすい特徴がないだけに書き手は内に秘めた想いを劇的に表現するのが難しい。だが今回は劇という特殊な舞台を用いて<日常>と<劇中>の対比構造を生み出しており、そこで変化をつけることで素直なトプロが秘めた思いの丈を鮮やかに表現することに成功している。キャラが素直だからこそ周囲の状況で破天荒さを補っているといえ、適切な舞台設定だったといえるだろう。
アヤベさんが良い
一番不愛想なはずのアヤベさんが一番感情豊かだった。特に中盤でトプロに対して心を砕いていた姿はもはや語る必要がないほど彼女の魅力を示していた。またオペラオ―には若干塩対応、トプロには柔らかい表情を見せるなどちょっとしたセリフから関係性の違いが見えてくるのも面白い。


気になった点
テーマパークの部分が省略可能
序盤のテーマパークのシーンは展開的には丸々カットしても問題ない。「テーマパークに行こう!」でその話を終えて、次の話ですぐ写真を見ながらテーマパークでの思い出を振り返る、という流れでもシナリオの本筋に全く影響は出ない。というのもキャラの変化がほぼ描かれていないからだ。
今回の物語における中心的な話題は「トプロが劇での自分の役について考えることを通して99世代での彼女自身の役割に気づく」というものである。なので基本的にはこの主題、あるいはそれに派生する副題を表現するために物語が進行していくことになる。だがテーマパークにおける描写はほとんどが彼女たちの日常風景を描写することに留まっており、その後の展開への寄与もあまり見られなかった。それに貴重な尺を3/8話分も使っているのはかなり勿体ない。ここの尺をトプロの葛藤描写や後半の合宿描写などに回す、あるいはこのシーンにキャラの心理描写を盛り込むなどしていたらよりキャラの内面に迫ったシナリオになっていたかもしれない。
ただ完全に何もなかった訳ではなく、いくつか変化は描かれている。なのでそのままカットするだけでは当然多少問題が残るのだが、それらは多少手を加えれば解決できる程度だ。まずひとつめは「トプロが周囲に気を遣いすぎて自分を疎かにしている」という部分。これは後のアヤベとの会話に掛かってくるのだが、この程度であれば別に後日写真を見ながら振り返っている際に語らせればよい。そしてふたつめが「デジたんが一行に加わったこと」について。この要素を回想だけで盛り込もうとすると若干無理があるように思えるが、これに関してはその要素自体を落としてしまって問題ないだろう。パーク内で一度合流したという事実自体をなくして第四話で脚本がオペラオーに見つかった瞬間で初めて合流したことに改変しても本筋への影響はほぼ誤差の範囲で収まると思われる。今回の物語でデジたんはあくまでも脇役であり、前述の通りこのシーンで大きな変化(たとえばここで劇をすることをオペラオーが思いつくなど)がなかったからだ。

あくまでも個人的な好みだが、葛藤なり何なりは描写ではなく展開で表現してほしい気もする
なのでテーマパークでのシーンはほとんどキャラの日常描写のみに留まっており、シーンとしての価値が低かった。王道であれば主目的である劇の話が冒頭の2話くらいで始まっているべきなのだが、今回はテーマパークのシーンがあったために中盤である4話になるまで出てこなかった。この間「この物語はどういう物語か」というのを提示できていないことになるため、そのぶん読み手に若干の負担をかけることになってしまう。

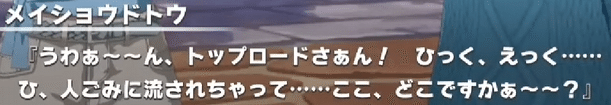

たとえばこのポップコーンのくだりだけで5タップ+暗転(シーン間の⏰のやつ)2回を費やしている。そしてこのシーンは完全に浮いており、他のシーンに関与していない
こういうネタはアニメのように(そのシーンを入れることで)普段は見られないキャラの動きや表情を盛り込める媒体で用いるべきであり、いくら3Dモデルを利用しているとはいえ動きや表情の幅に限度のあるソシャゲではあまり映えない表現だと感じた
また本編ではアヤベのトプロに対する悩みの発端から解決までが第5話、第6話の2話の間に納められてしまっている(物語世界内では前述の通りテーマパークの際に気づいたことになっているが、そこではアヤベが思い悩む様子は見せていない。なので読み手は第5話で初めてアヤベの悩みに気づくことになる)。基本的に人間は間を勝手に補完してくれる生き物なので、できればアヤベの悩みの発端はできるだけ序盤に配置した方が彼女の葛藤を想像しやすくて面白くなりやすい。なのでもしテーマパークのシーンをカットしないのであればパーク内でアヤベがトプロの利他的すぎる振る舞いに指摘するもちゃんと伝わらずモヤモヤ、という流れを入れた方がシーンの要素を増やしつつ展開を面白くできただろう。
シーンの要素については以前別の記事でも紹介したが『WHITE ALBUM2』の丸戸史明先生の言葉を引用したい。この要素が増えれば増えるほどシーンが物語において必要不可欠なものになっていくと考えていいだろう。そして個人的には必要不可欠なシーンの方が読んでいて面白いと感じている。
“丸戸 漫画やアニメ脚本っていうのは、かなり尺が制限されます。小説って書きたいだけ書けるところもあるんですけれど、漫画原作や脚本になると、どうしても短くしなきゃいけないんで、そうすると無駄なことは何一つできない。やったらもったいない。 とすると、脚本を進めるには3つの要素があって。「物語や設定を進める」「キャラクターを描写する」、それから「おもしろい、たとえばネタ的な言動をする」──この3つがあるんですけども、1つのセリフの中に3つの要素のうち1つだけ入ってるのは、すごいもったいないです。だからこの3つのうち最低2つ、できれば3つを入れたい。”
先の展開への期待感が薄い
たとえばテーマパークのシーンも単に親睦を深める目的で行われており、それを通して何か着想を得る必要があった訳ではない。また劇についても何かしら具体的な到達目標があるわけでもない。作中でも言われていた通りこの物語は「思い出作り」がメインであり、それゆえ最初から結果ではなく「RTTT組の楽しそうな一幕」という過程が重視されているシナリオとなっていた。つまり多くのシーンが「今読んでいるこのシーンを味わって読んでほしい」というシナリオだった。換言すると次の展開に対する期待が薄いシナリオだったと言える。要は読者を惹きつける謎が設定されてなかった。
謎の重要性については漫画原作者・小説家である小池一夫が以下のように説明している。
「この後、一体どうなるンだろう」
「どうやってこの問題をクリアするンだろう」
「どうやって勝つンだろう」
という《謎》が、常に読者の心に「ひっかかって」いること。
その「ひっかかり」が、読者にページをめくらせるのです。
創り手は、読者に《謎》を提供していくこと、それをコントロールできているかということを意識することが必要です。
主人公たちが幾多の謎を突破し、目的の達成を阻む敵役と対決してゆく中で、しだいに物語の最大の「謎」に近づき、緊張感を高まっていきます。
そして、キャラクターは物語の核心である《謎》に直面し、最大の難関、最後の対決に望むことになります。
そうクライマックスです。
「第3回 「起承転結」は「主謎技感(シュ・メイ・ギ・カン)」だ!(前編)」 より引用
(記事URL:https://xn--nckg3oobb0816d2bri62bhg0c.com/koike_3/ )
今回のイベストはその瞬間瞬間を鮮やかに彩る描写が多く、《謎》についてはほとんど登場しなかった。唯一あった「アヤベ、どうやってトプロに想いを伝えるンだろう」という部分も前述の通り2話という短い間に解決してしまっていた。そのため物語全体の吸引力が弱く、頁を捲る手が止まらないという印象はなかった(なぜオペラオーが思い出作りをしたいと思ったのかというのもあるが作中で明確な疑問として提示されていないので《謎》として機能していない)。
ただ今回のようにシーンをじっくり味わわせるという目的であれば前方に否応なく意識が向けられてしまう《謎》を設置しない方がいいのかもしれない……しれないのだが、個人的な意見としてはそもそもじっくりと味わわせるシーン、いわば物語のサビはひとつのシナリオにそんなに入れなくていいのではないかと思っている(特にイベストみたいに尺が短い場合は尚更)。なので《謎》とじっくり味わわせるシーンは両方入れてもいい気がする。
クライマックスの量や統一感について(別作品ネタバレ含)
※本項では『宇宙よりも遠い場所』のラストについて軽く言及しています。該当部分にはこんな感じで取り消し線を引いてますので気になる方は読み飛ばしてください。
まず「量」について、今回はクライマックス(サビ)っぽいシーンがやや多いと感じた。断っておくがエモいシーンが多いことに関しては一概に問題だとは言えない。何度も感動的なシーンを畳みかけるタイプの作品が好きだという人も大勢いると思われるし筆者も嫌いではない。だが今回の物語の印象がぼやけやすい理由の一端にはなっていると感じる。
現在アニメ化して人気沸騰中の『ダンダダン』の作者である龍幸伸は物語において「サビは必ず2回」だと言っている。詳しく説明されていないのでこの言葉の正確な意味は分からないが、恐らく映画やアニメなどでよくある「クライマックス(一個目)の後で一旦落ち着いたシーンが入り、その後にもう一度感動的なシーン(二個目)を差し込んでその余韻に浸らせたまま物語が終わる」という流れのことを言っているのだと思う。
『宇宙よりも遠い場所』なら一個目は基地を去る際の報瀬のスピーチ、二個目が帰りしなにオーロラを眺めるシーンだと言える。
またRTTTでは一個目が菊花賞での勝利、二個目が直後に置かれたライブシーンだと捉えることができそうだ。

特別コメンタリーより
……という前提の下、今回筆者が個人的に感情の高まりを感じたシーン、いわゆるサビに相当すると思ったシーンは、
「屋上でのアヤベ-オペラオーの会話」
「廊下でのアヤベ-トプロの会話」
「劇でのトプロ-オペラオーの会話」
「最後の舞台前」
の四つだった。一個目に関してはサビと言えるか正直怪しいところもあるが、逆に本当ならサビには当たらない部分をやや感動的な雰囲気に演出しすぎてサビっぽくなっているという印象を持っている。そしてこれをサビ換算しようがしまいが前述の2回のルールからは逸脱する。
……とはいえこれだけでは到底納得できないだろう。なにせ筆者が勝手にそれぞれのシーンをサビだと誤認しているだけかもしれないからだ。なので続けて「統一感」について言及したい。
先ほどあげた四つのサビ(一個目を削除するなら三つのサビ)で、二個目と三個目では主題が異なってしまっている。二個目で中心に揚げられているのは「他人思いなトプロへの心配」であり、三個目では「友と想ってくれることの喜び」だと言える。そして筆者にはこの二つのサビから統一感を微妙に感じづらかった。
もちろん落ち着いて読めば両者に繋がりがあることは理解できる。アヤベはトプロの他人想いさを心配していたが、そんな彼女だからこそ皆を纏めることができ、それによって孤独だったオペラオーが繋がれた、という風に意味自体は繋がっている。だがこの「二度のサビ」というのはそもそも繋がっているとかじゃなくてほぼ同一であるべきな気がする。もしも二個目にサビが置かれる理由が(筆者の仮説通り)余韻であるならば、そこで余韻に浸るためには読み手にあまり思考の負荷をかけてはいけない。余韻とは考えて生み出すものではなくて自然と感じられるものだからだ。だからこそ一個目のサビで理解させたテーマと同じテーマを二個目でも用いることで二個目のサビに内容的な重みを与えつつ思考せずとも感じられるという最高の状態を生み出せるのではないか。
その観点で見ると二個目と三個目の間には連続するサビとしての繋がりはなく、シーンとして分離してしまっている。であれば三つ目と四つ目をサビと見なして(一つ目、)二つ目をサビから除外すればいいのか?だがそれにしてはアヤベのモノローグが多い。彼女の内面は明らかに(恐らく主人公だった)トプロよりも多く描写されている。なので二つ目をサビから外すのは難しいように感じる(主人公云々については後述の「主人公が誰なのか明確じゃない」でも触れる)。


つまるところ、先ほど提示した四つのサビについて、「サビは必ず2回」のルールに従ってグルーピングすると、
「屋上でのアヤベ-オペラオーの会話」→「廊下でのアヤベ-トプロの会話」
「劇でのトプロ-オペラオーの会話」→「最後の舞台前」
という感じで分類できる。ここから分かるように、このイベストでは物語内で二つのオチがついてしまっていると言える。換言すればオムニバス形式のように話ごとに主人公が変化している。そしてそのアヤベ→トプロへの転換点が見えづらく連続的に推移しているのでサビがやたら多いように感じてしまう原因となっている。
そもそも短いイベストで話を分割するべきか否かについて筆者は統合した方が物語に厚みを与えやすいが分割する話があってもいいというスタンスだが、分割しているならはっきりそう認識させた方がメリハリがついて面白くなりやすいのではないかと思った。
観測者デジたんのセリフが多すぎる(主観)
序盤のデジたんのセリフが多すぎるように感じた(以下は一例)。

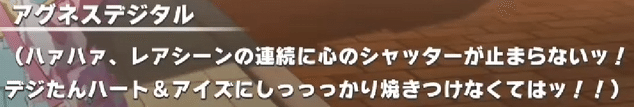


物語世界においてデジたんは実際にこのくらい頻繁に尊死しているというのは分かるが、こういう癖の強いセリフは偶に差し込まれるからこそ面白いのであって、ここまで連打されると途中で飽きてしまう。しかもこれらのシーンにおいてデジたんはトプロたちの輪には入っておらず外側にいるデジたんのセリフが都度差し込まれていることになる。つまりトプロたちの会話だけを進めるだけならデジたんのセリフは不要であり、なんなら差し込まれる度にメインの流れが途切れてしまうので邪魔ですらある。作中で「霊圧も消して」というセリフがあったが、読み手に対してはむしろ彼女の存在が主張されすぎていた。もっと見えないフィルター越しで息を押し殺しつつ発狂しているような表現の方が個人的には好みだった。
恐らくこれはこの物語自体がRTTT組の空気感をじっくり味わわせる目的で作られており、彼女たちのエモさを(それを観測している)作中人物のセリフでも印象づけたいという理由でデジたんが起用されたのだと思う。つまりこの尾行中のデジたんはある意味ユーザーの代わりに発狂しており、彼女が発狂することでユーザーも自然と「このシーンはエモいシーンなんだな」と思うことができるみたいな。にしても流石に多すぎて受け取り方を強めに推奨されてる感じがした(主観)。

主人公が誰なのか明確じゃない
今回のイベストの主人公は誰だったか……という質問に即答できる人は恐らく少ないだろう。RTTTを踏まえたり最後のオペラオーとの対面などを見たらトプロのように思える。だが葛藤とその解決の過程を見ると中盤のアヤベのトプロを想って揺れ動く様はまさしく主人公らしい振る舞いだった。だが前述のようにデジたんはある種ユーザーと非常に近い視点でこの物語を見つめており、共感性という点ではデジたんに軍配があがる。また主人公は物語を大きく動かす役割であると定義するなら「思い出作り」を提案したオペラオーが最も適しているし、ドトウもドジっ子でかわいい。
つまり主人公が定まっていない。これは前述の「クライマックスの量や統一感について」という部分とも関連しているし、この物語の冒頭がデジたんを抜いた4人の語りから始まっていることも影響している(基本的に最初に纏まった量のセリフを喋るキャラが主人公になっていることが多いため)。とにかくこれは誰の物語だったのか、どういう物語だったのかが曖昧になっている。
そして主人公が1人に定まっていないと面白くなりにくい、という考え方の根拠として脚本術の本を多数出版しているフィルムアート社の講座における一文を紹介したい。
読者は主人公の「欲求・目標、動機、リスク、変化」に共感あるいは感情移入しながらページをめくります(前回「キャラクター造型に必要な5つの質問」を参照のこと)。主人公が誰であるのかがはっきりと示されていないと、読者を感情的に惹きつけることはできなくなるのです。
そう考えるとやはり主人公はひとり、がベター(というかベストな)選択肢といえます。物語創作に関する本の多くは、よほどの理由がない限り単独主人公のほうが望ましいと書かれています。
「主人公は2人いてもいい?」より引用
正直言うとトプロがいくら冒頭が並列的だったからといってトプロが口火を切ったのだからトプロが主人公だと言える。だがそれにしては最後のオペラオーとのやり取りに入るまで彼女の内面が見えにくくなっていた。というかこの印象は彼女が元々素直な性格なのも災いしていたと思う。気難しいキャラがポロっと素直な素振りを見せるとそれは内面の提示だと思われやすいが、素直なキャラが素直な素振りを見せてもそれがいつも通りなのか違うのかが分かりづらい。なので素直なキャラを主人公にする場合はある程度しっかり内面を描く必要がある気がする。

結局のところ主人公が明確じゃないというよりは全体の主人公はトプロだったのだから(たとえオムニバス風に視点を移動させる物語だったとしても)序盤にトプロの内面描写を置いて最初と最後を彼女が締める形にした方が全体を通しての纏まりの良さを強調できたのではないかという感じ。
劇中劇がそんなに面白くない
これ自体も別に欠点ではないのだが今回の劇中劇に物足りなさを感じた。
そもそも個人的には物語世界内の独自競技(鬼ドッヂとかチャンバラ陣取り合戦とか)のルールの詳細な説明は基本いらないと思っている。これがたとえば『遊戯王』だったり『蒼の彼方のフォーリズム』の「フライングサーカス」だったりそれなりにボリュームがある作品でそのオリジナルスポーツなりゲームなりをしっかり中心に据えて物語を展開していくなら話は別だが、そういう訳でもない単なる季節イベストのネタとして消化する使い捨ての設定であるならその競技に対する詳細な説明は必要ないし単純に文字数を逼迫するだけになりかねない。
劇とスポーツやゲームは(それ自体が物語を含んでいるか否かという点で)若干条件が違うとはいえそれと同じ理論で劇中劇に関しても今回のように書きたいシーンを書くための都合のいい小道具として使うという方法でも多少いいとは思う。だがもしそうするなら劇中劇に関する描写は最低限に収めるべきだが、今回割とその内容に触れられていた割には劇中劇のストーリーラインが見えてこず単純に雰囲気を提示するだけに留まっていた点が引っ掛かった。有り体に言えばこの劇を観客の前で披露してちゃんと成功するのか、劇として面白いのかに疑問を抱いた。主目的が思い出作りだから別に劇自体の完成度は問われないにしても、そこに疑念が生まれるだけでも全体の読み味には影響が出てしまう。
まあこの印象は前に劇中劇を用いていた『フェアウェルを継ぎ接いで』というイベストでは劇中劇自体もめちゃめちゃ面白かったから生じた感想だと思う。あれは単に面白いだけでなく内容がそのまま各キャラの人生ともリンクしていたため意味が二重に掛かっており非常に完成度が高かった。それと比べてしまうとやはりどうしても落ちてしまう。とはいえ重箱の隅。
その他:解釈違い?(オペラオー、デジたん)
オペラオーとデジたんの両名に若干(ここ重要)の解釈違いを感じた。
特に前半部でそれが見られた。逆に後半ではほぼ感じなかった。
解釈違いなんてものは基本的に身勝手なものなので肩の力を抜いて読んでほしい。
オペラオー:若干ギムレットっぽい?
装飾華美なセリフが多いように感じた。別にオペラオーがそういった言葉遣いをしないという訳ではないが今までよりも肩肘張ったワードチョイスであり、どちらかというとタニノギムレットっぽく感じた。
個人的にはオペラオーには大げさで自信家、かつエンターテイナーな雰囲気を感じている。なので難解で厨二心くすぐるセリフよりは観客が理解できるような誇張気味で分かりやすい言葉選びを好む(が突飛すぎて言ってる意味は分からない)という印象だったのでそことの食い違いがあった。

初出場の2人の活躍をまぐれだと評する声に対する返答。目を覚ましてあげよう的な台詞が続く
こんな感じで平易だが洒落ているセリフもよく使う印象だったが今回はそれがなかった


二段落目が気になった。役者というより詩人っぽい印象?
ちなみに筆者は劇について詳しい訳じゃないので注意

「くべたまえ!」だと多少違和感は和らぐかも

とはいえ、いきなりこういう役柄を演じ始めたことについては一考の余地があるだろう
この違いをRTTTを経て大人になったと捉えることもできる。たとえば↑の画像で悪役を演じ始めたことについては、”世紀末覇王”と呼ばれるほど勝ち続けたために学内でもヒール役っぽく見られており、無意識にそういう役柄を選んだ……みたいな背景があり、その影響でワードチョイスに若干の変化が出てきた……的な。でも個人的には前者はありそうだが後者はややこじつけにも感じる。もしそれを意図しているならアヤベなりデジたんなりにどこかでボソッと「言葉選び変わったよね」みたいなセリフを言わせてほしい。

今回は何度かあった
もしかしたら意図した変化かもしれない
だが、映画『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』の入場者特典である小冊子「また星は巡る」だと(セリフ数が少ないので断定はできないが)今回のような仰々しい喋り方になっているようにも見える。映画本編ではどうだったかは筆者は残念ながら覚えていないのだが、RTTT時点ではまだアプリ版っぽい柔らかい喋り方のままだった。
RTTT時空の時系列は恐らく「RTTT→また星は巡る→(つどい歌えよ、星々よ!)→新時代の扉」となっており、オペラオーの覚醒はRTTTと"また星"の間で発生している。なのでもしも新時代の扉でのオペラオーの口調が今回や"また星"のような口調であるなら覚醒前後で意識的に口調を変えていると言える。だがもし新時代の扉でもRTTTのような語り口だったなら"また星"での語りの違いは単に(アプリ、映画・アニメ=映像付き)⇔(小説=文字のみ)という媒体の違いによる差異(キャラの身振りを伴わない小説では文字でそれを補うことでオペラオーらしい印象に近づくのかもしれない)であり、今回のイベストが小冊子から過学習してしまったと言える。
……というかこの時点で筆者が小説版「新時代の扉」を読んでないことが透けてしまった。もしかしたら今回のイベストはそっちの影響を強く受けているのかもしれない。小冊子と小説で多分書いてる人一緒だし。今度暇なときに買って読んでみます。

序盤はテンションが上がりすぎていただけかもしれない
それはそれでよき
デジたん:やや自分勝手?
今までのデジたんと比べると行動がやや自分勝手に見えてしまった(これも序盤だけであり、後半ではむしろバ車ウマの如く働いていたが)。

こんな感じでデジたんは周囲に気を遣いすぎている印象があった
そのせいで無意識に周囲と距離を置いてしまっており、その欠点を克服することが『デイズ・イン・ア・フラッシュ』における彼女の成長だった(今回のトプロと立ち位置が若干似てる)

このセリフの後「でも見たい」となり、絶対迷惑かけないから……と遠くから観察することになる
この「本当は駄目だけど……」感が身勝手に映り、気配り屋のデジたんらしくないように感じた
そもそも彼女は今まで何度も尾行してきただろうに今更それで思い悩むのは違和感
素直に「観察はする、けど絶対迷惑をかけない」と割り切っていた方が彼女っぽい(主観)
……まあストーカー行為を安易に肯定してはいけないというコンプラ的な問題かもしれない





トプロの好意に対する感謝が一言くらいは欲しかった
まとめ
今回のシナリオを一言で評すなら「写真集めいた物語」と言うところか。楽しげな日常風景、詩的な言い回し、ドラマティックはシーンなど単体で見た時の面白さや感動はひとしおだったが、逆に視点を離してシーン間の連結に目を向けると動的な結びつきが欠けていたようにも思える。ひとつひとつの鮮やかな光景に没入できる人は常に最上の幸福を得られるが、入り切れなかった場合はどこか上滑りしたまま物語が終わってしまう。
そして今回のイベストをRTTTの後日譚、ファンディスク的なものとして位置づけるなら、シーンを楽しませる物語という意図は見事に嵌まっていた。後日譚に必要なのは練り込まれたストーリーラインではなく雰囲気や余韻を感じさせる描写とそれをじっくり味わえる十分なゆとりであり、本作はそのどちらも十分に兼ね備えていた。上で挙げ連ねた数々の”気になった点”とやらもこの目的であるという前提で相対すればたちまち風の前の塵のように吹き飛んでしまう程度でしかない。テーマパークのシーンが日常描写しかないと言っていたがその日常描写を堪能してもらうために余計な雑味を省いただけかもしれない。もしそうであるなら今まで長々と書いてきた駄文はライターからすれば和食を作ったのにステーキもワインもないじゃないかと的外れないちゃもんをつけられているようなものだろう。まあ本記事は対象作品の良しあしを定めたいのではなく筆者が感じた印象が具体的にどういった部分から立ち昇ってきたのかを分析したいだけなのでこれで良しとする。
またこのイベストは来年頭から順次発売されるRTTTや新時代の扉のブルーレイに向けてもう一度99世代の熱を高めようという意味で実装されたのだろうが、今回の視聴にあたってRTTTの再履修を怠った筆者は随所に面白さを感じたものの若干流れに乗り切れなかった感があった。不覚。これが新時代の扉のちょい後くらいの実装ならまた記事内容は変わっていたかもしれない。

まだ見てない人……は流石にここに辿り着かないと思うのでもう一度観たいと思っていた人は是非
