
アイデアは生み出すものではない。探し、拾い、磨くもの。-「発想道場」第1回レポート-
「『楽しく生きていく』『お金を稼ぐ』『社会を動かす』……アイデアはどこでも重要なのに、学校で学ぶ機会がないんですよね。たとえば習字や車の運転は一度身につければその後の人生でずっと使えますが、実はアイデアも同じなんです」
講師の佐藤夏生さんはそう切り出し、「発想道場」初回の授業がスタートしました。
「発想道場」は、クリエイティブの手前にある「発想」を探し、拾い、磨いていくことを目的とした、Loohcs高等学院(以下ルークス)で月に一度実施される連続授業のことです。
参加者は学校外からも募集しています。募集対象は、「アイデア」や「クリエイティブ」に興味があったり、普段の学校では受けられないような授業に興味のある高校生・大学生です。
はたしてアイデアとはどういうもので、わたしたちはそれをどう捉え、学び、身につけていくべきなのでしょうか。
今回は初回ということで、ゲスト講師は置かず、主宰の佐藤さん・金山さんのお2人から、イントロダクションを兼ねてアイデアそのものについて学んでいきました。
今回の授業では、アイデアとはどのようなものかインプットがあった後で、アイデアをより深く理解するためのワークを行いました。そしてさらに具体的なアイデアの構造と学び方のスタンスを知った上で、最後に今後にもつながっていくワークを実施しました。
アイデアは降ってくるものではない、落ちているもの
唐突にスクリーンに映し出されたのは、一枚の夜空の写真。

「星空は、きっと大昔からほとんど変わらずにそこにありますよね。ここにある大きな星を結んで、誰かが『白鳥』だと言い出した。これが『ハクチョウ座』として、時代を超えた世界のスタンダードになったわけです」
講師の金山淳吾さんはこう続けます。
「これは、何かを新しく生み出したわけではなく、元々あったものを見つけたわけです。こんな風に、アイデアは降ってくるものではありません。落ちているものなのです」
アイデア、そしてクリエイティブと言われると、普通の高校生にとっては選ばれしプロフェッショナルのみが生み出せる魔法のようなものに感じられるかもしれません。
しかし、アイデアが「落ちている」のであれば、それは誰でにでも拾い上げることができます。
「アイデアは一部の天才のものではなく、技術なんです。技術が積まれると、『体質』になっていくんですね」
佐藤さんはこう言い切りました。
『体質』になるとは具体的にどういうことなのでしょうか? それは次のワークを通して体感することとなります。
アイデアを体質化するためには?
まず初めのグループワークは、4グループに分かれ、それぞれ「100年後」「50年後」「10年後」「1年後」の未来について5分間で考え、それを1分間プレゼンするというものです。
5分間という短い時間、また「未来」という漠然とした問いであることから、参加者の高校生たちは頭を悩ませつつも、「電脳化」「戦争が起こる」「シンギュラリティ」「昆虫食などの食の変化」「マスクが不要になる」などそれぞれに回答を提出しました。
これに対する金山さんの返答は、非常に興味深いものでした。
「このワークを企業向けに行うと、実はもっとはっきり分かれるんです。100年後は社会のこと、50年後は環境やセカンドキャリアのこと、10年後はキャリアのこと、1年後は今の自分の学びだったり、携帯のキャリアのことだったり。たとえば『明日』って聞かれたら、もっと具体的なことを考えると思うんです。でも、戦争だって食事のトレンドだって明日変わるかもしれませんよね。これって固定観念なんです。それからたとえば、金閣寺のことを考えてみると、100年以上残っているわけじゃないですか。未来って変わるものと変わらないものの集積であるはずなのに、変わるものばかり考えてしまう。これも一つの固定観念です」

未来とは「ないもの」であるにも関わらず、わたしたちは常識的に、情報に基づくような回答をつい出してしまいがちです。もちろんそれが良い悪いという話ではなく、わたしたちはそういう固定観念、思考のフレームワークに知らず知らず囚われてしまっているのです。
「アイデアに正解も間違いもないけれど、囚われている『こういう問いならこういう風に答えるよね』を削除することが、『体質化する』ということであると思うんです」
体質化するためには2つのことが大事だと佐藤さんは述べました。
1つめは、忖度しないこと。周りの笑いなど気にせず無視してしまうこと。
2つめは、思いを入れてみること。客観的な見解だけでなく、「わたしはこうなってほしい」「こうしたい」という自分の思いを加えてみること。
参加した高校生たちは、無意識下の思考の枠組みに気付き、ハッとさせられた様子でした。
目指すべき「アイデア体質」の形を、肌で感じるワークとなりました。
アイデアの土台となるものは?
アイデアが実現に至るまでは四層構造で成り立っている、と金山さんは述べます。

「アイデアの土台には、ひらめきや好奇心があります。感覚的な話ですが、これって『わくわく』するんです。それがアイデアに昇華されると、『ドキドキ』になる。『見つけちゃった!』って感じですね」
土台となる二層は、アタマを動かすフェーズ。インプットをし、記憶を掘り起こします。
アイデアを実践に移すとなると、「プロジェクト」そして「事業」になります。これはカラダを動かすフェーズで、チームづくりと企画づくりを行います。
この「発想道場」で大事にしたいのはアイデアであり、またその土台となるひらめきや好奇心です。
では、ひらめきや好奇心はどのように養えるのでしょうか?
「ひらめく力」と「好奇心」を養うには、【Book Smart × Street Smart(知識×知恵)】の考え方が必要であると金山さんは述べました。
本からの知識を得るとともに、街の変化・季節の変化・心の変化などを感じられるだけの知恵があれば、アイデアのための土台ができあがるというわけです。
アイデアが「探すもの、拾うもの」であるならば、たしかにわたしたちは街に出るべきです。
しかしこれは「書を捨て町へ出よ」ということではなく、あくまで掛け算なのです。知識のまったくない状態では、変化を感じるための視野は狭まってしまうことでしょう。
だからこそ、これからの授業ではゲストスピーカーからのインプットを得ながら、街へ出て感じたことをアイデアへと錬成していきます。
アイデアに正解はないけれど、磨くことはできる
最後のワークは、「ドラえもんの新しいひみつ道具を考える」というものです。ネーミングと機能、デザイン(簡単な絵)をアウトプットとして求められました。
参加者の高校生からは、「ありえた未来を選択して見ることができる『パラレルワールドアイグラス』」や、「四次元ポケットの容量オーバーに対応する『四次元ポケット五次元拡張バッジ.exe』」などのアイデアが出されました。
先ほどのワークよりも自由な発想のあり方に開かれた高校生たちは、笑いを交えながら、楽しげに議論・発表をしてくれました。
この「ドラえもんフレーム」は、あれば幸せになれるものを自由に考えることができ、またシンプルなネーミングやデザインが求められることから、アイデアを考えるにあたって便利なフレームであると紹介されました。
参加者たちの試行錯誤のメモを見ながら、佐藤さんはこう締め括りました。
「アイデアに正解はないけれど、磨くことはできます。思いつきからのバリエーションはたくさんあるわけです。もっとわかりやすく、もっとたのしくを追求していくこと。今後の授業では、その磨き方について学んでいきます」

授業の最後に、次回までの宿題が発表されました。6月の宿題テーマは「From street」。
校舎のある渋谷の街で、アイデアを拾うことが宿題です。街で見つけた「おもしろい、気になる」をスマホで写真に撮り、文章にしたためます。いくつ拾ってきてもいいですが、発表できるのは1つだけです。次回の授業では、それを各々にプレゼンをした上で、アイデアへの昇華の仕方を学んでいきます。
以上のように、初回授業では、アイデアはすべての人に開かれ、「体質」にすることができるものであることを学びました。これからの連続講義でどのようなアイデアが見つけられ、磨かれていくのか、まだ見ぬ「わくわく」や「ドキドキ」に触れられた2時間でした。
(執筆:Loohcs高等学院教員 内野)
-----------------------------------------------------------------------------
「発想道場」は一般参加者を募集しています!
次回の「発想道場」は6月24日(木)14:40〜16:20です。
募集対象は、「アイデア」や「クリエイティブ」に興味があったり、普段の学校では受けられないような授業に興味のある高校生・大学生です。
次回は、発想道場初のゲスト講師に、KDDI∞Labo長の中馬和彦さんを迎えます。中馬さんからアイデアに関わるインプットを得た上で、前回出された宿題である、1人1人が街で見つけてきた「おもしろい、気になる」について、プレゼンをし、アイデアとして磨き上げていくワークを実施します。
参加ご希望の方は、以下のURLからお申し込みください。ご応募お待ちしております!(コロナ感染対策の観点から、定員に達し次第募集を締め切らせていただきます。何卒ご了承ください。)
特設ページはこちら↓
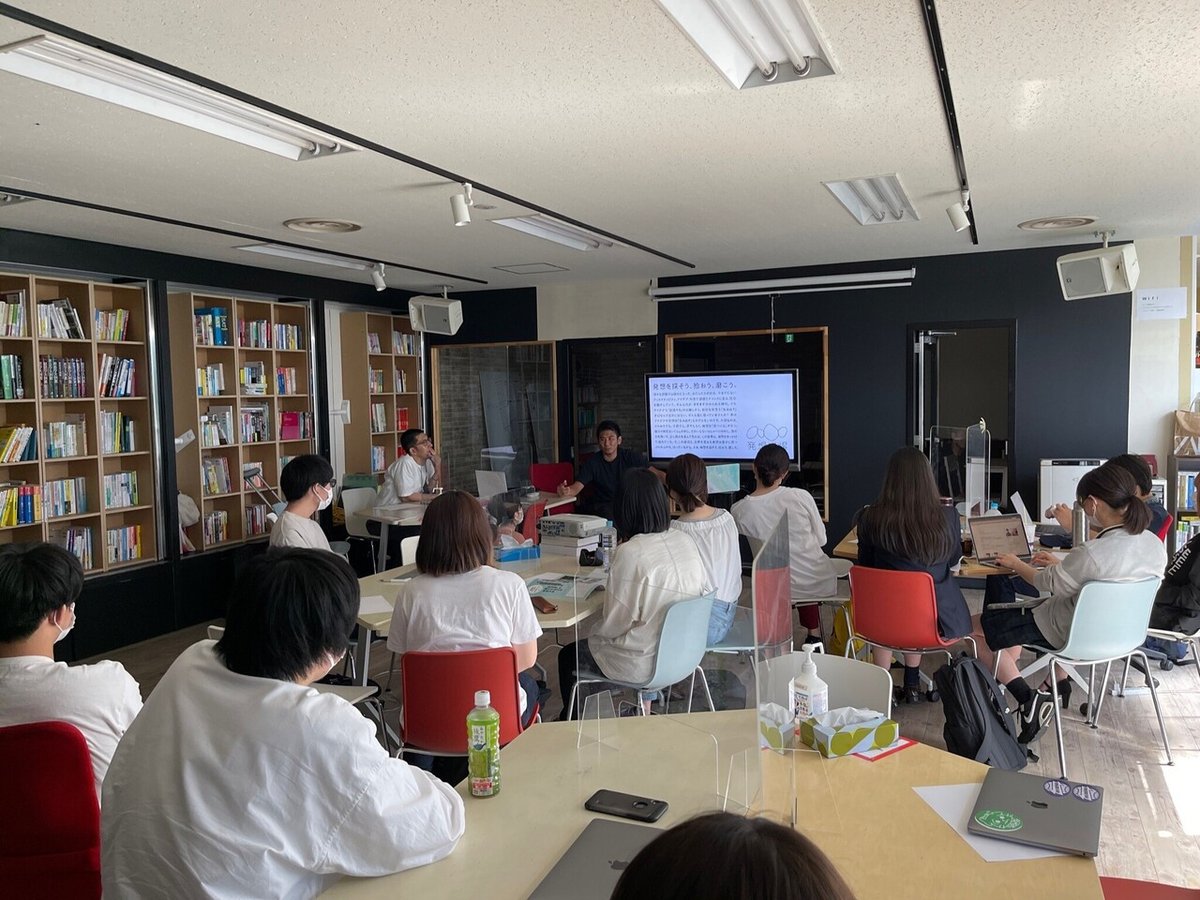
みなさま、そしてアイデアと、お会いできることを楽しみにしています!
発想道場レポートまとめはこちら
\次回発想道場は2021/07/12(月)です!/
詳細はこちら↓
