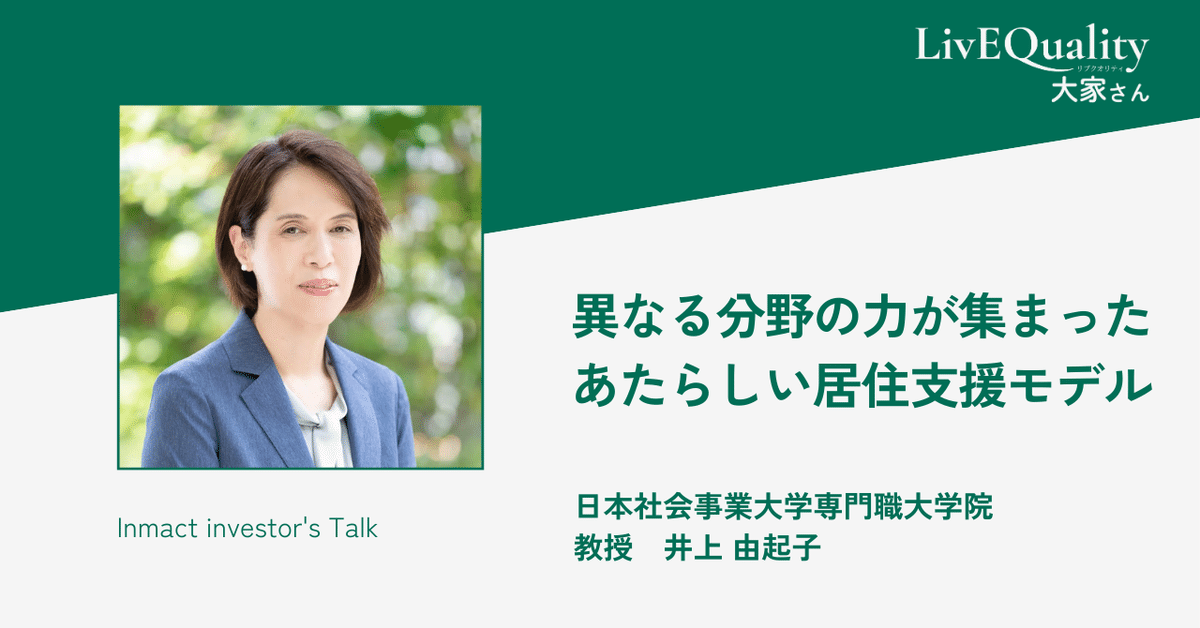
福祉とファイナンスと不動産がつながることで、新しい居住支援のモデルがうまれる
株式会社LivEQuality大家さんです。住まいをかりづらい困窮世帯のシングルマザーを対象に、安心安全で快適な物件を市場より低い価格で貸す、大家さん事業を展開しています。
わたしたちは「インパクトボンド」という新しいファイナンスの仕組みを開発し、資金調達を行うことでこの事業を運営しています。
インパクトボンドは金利のリターンを低めに抑え、ソーシャルリターンという社会的インパクトを最大化するように設計した投資の仕組みです。
わたしたちの取り組みに共感してくださった方々がインパクトボンドを引き受け、インパクト投資家として参画してくださっています。
そんなインパクト投資家の一人、日本社会事業大学専門職大学院 教授の井上由起子さんに、参画を決めた理由や期待についてお話を伺いました。

────井上先生はこれまでに、厚生労働省介護報酬改定検証・研究委員会委員や、国土交通省住宅政策審議会臨時委員など、国や自治体が主催する審議会等の委員を歴任されてます。
本日は社会福祉や居住支援の専門家である井上先生からみて、インパクトボンドやLivEQualityの取り組みをどのように感じているのか、伺えればと思います。
まずはインパクト投資家として参加された経緯や理由について教えてください。
最初のきっかけは、厚生労働省関連の居住支援に関する委員会で岡本さん(LivEQuality代表)と出会い、取り組みを知ったことでした。
建設会社でありながら、シングルマザーの住宅確保と生活支援に取り組んでいることに興味を持って、名古屋まで視察に伺ったんです。
そこでインパクトボンドの仕組みについても詳しく教えて頂き、社会的意義のある取り組みだと感じました。
居住支援は、住宅を確保したうえで、転居先で安心して暮らし続けるための一貫した支援のことを指すのですが、そのためには質の良い住宅を手頃な家賃で確保することが欠かせません。
しかしながら、そういった住宅は大都市の交通至便な場所ではなかなか見つからないのです。
そんな中でLivEQualityは、インパクトボンドという仕組みを開発して投資家が低い利回りを受け入れることで、その分を入居者の家賃低減に回しています。
そうすることで、質の高い住宅を手頃な家賃で名古屋のまちなかに提供できるモデルをつくっている。
この発想は非常に可能性があると感じました。金融と福祉を組み合わせた新しいアプローチだと思いました。
また物件を安価に提供できても、入居後のサポート体制がなければ本当の意味での居住支援とは言えません。
就労に向けたお手伝い、福祉サービスの調整、メンタルを崩された時にその状況に気づき適切なサポートにつなげる存在が必要です。
LivEQualityはNPOを運営していて、そちらでその役割もしっかりと担っていらっしゃる。
ハードとソフトの両面から支援できている点は非常に重要だと感じています。

──── インパクト投資について、従来の寄付や投資と比較したときにどのような違いがあると感じましたか。
私は金融の専門家ではないので、インパクト投資に参加した率直な感想をお話しさせていただきます。
これまでも福祉分野のさまざまな取り組みに寄付は行ってきました。ただ寄付は、どうしても一回限りになってしまいます。
一方でインパクト投資は長期的な関わりになりますので、取り組みへの関心が続き、その点で優れていると感じました。
加えて、低利回りとはいえ資金が戻ってくるので、決断がすんなりできました。もっとも、冷静に考えると、自分の決断は行動経済学のプロスペクト理論に近いんですよね。そこも仕組みとして上手だなぁと。
また、LivEQualityは投資家が集まる「ギャザリング」という場を設けてくれています。そこで生まれるコミュニティも魅力的です。
日々の仕事では福祉関係者の方々とご一緒することが多いのですが、ギャザリングではこれまで接点のなかった業界や職種の方々と出会う機会になりました。
彼らはソーシャルという言葉を好んで使っていて、新鮮でした。

LivEQualityの取り組みは、ファイナンスの要素が加わることで広がりが生まれているように思います。
ファイナンスと福祉という異なる分野の方たちが同じ志でつながることで居住支援の担い手を広げている。
分野が違うからこそ、結びつくと新しい強みが生まれるという感覚を持ちました。
LivEQuality代表の岡本さんは公認会計士、ソーシャルセクターや建設会社での経営経験をお持ちです。
ご自身の専門性を活かして、ファイナンス・不動産・福祉を業界を超えてつなげ、居住支援を展開していると感じています。
──── より多くの人がインパクト投資に参加するためには、どのような取り組みが必要だと思いますか?
まずは、入居されているシングルマザーと子どもたちの生活がどれほど豊かになったのか、具体的には、自立に向けたステップを踏めているか、いわゆるインパクトを数値や物語でわかりやすく社会に伝えていくことです。
また、イギリスやアメリカにはこういった投資に対して税制優遇措置があるようで、日本でもそういった制度が整備されれば、広がっていくのではないでしょうか。
裾野を大きく広げるためには、投資の単位を下げ、沢山の方に投資してもらう方法もあるかもしれません。
少し話が広がってしまいますが、居住支援を必要とする人は多岐にわたります。単身高齢者の方、心の病いを抱えている方、生活保護を受給している方、刑務所出所者の方など、それぞれに生きづらさを抱えています。
その中でも、シングルマザーの方々はサポートを通じて自立につながる可能性が高いと感じます。
実際の事例を見ても、住まいを確保し、保育園を見つけ、仕事を始め、やがて自立していく。その過程で、NPOのスタッフがナチュラルにかかわって、支援を展開しています。
支援というよりも応援、という言葉のほうがフィットする。
子どもについては無条件に応援したくなります。うまくいえませんけれど、福祉に関心を持ち始めた人達にとって、最初に支援したいと思うのがシングルマザーや子どもであるのは感覚的にもよくわかります。共感しやすいのでしょう。

──── ダイナミックな仕組みも必要ですが、具体的なストーリーの発信を通じて、共感を広げることもまた重要ということですね。
最後に井上先生が感じているLivEQualityに対する期待をお聞かせください。
個人として生きていくことが尊重される世の中になり、家族との関係性や人との関わり方は多様になりました。お一人さまを謳歌している人がいる一方で、身寄りがいない人も増えています。
選択肢が増えるのはとてもいいことですが、人は一人では生きていけないのも事実です。
孤立や孤独とどうつきあっていくかを考えたとき、手頃な費用で住宅を確保できるだけではなく、そこから地域とつながり、コミュニティの中で生きていける。そんな風にこの取り組みが発展していってほしいと思います。
「住宅」ではなく「居住」を保障していく。住宅というハードと生活支援というソフトに加えて、居場所づくりや交流の場の提供など、様々な要素を組み合わせていく。
そういった複合的なアプローチが、これからの社会には必要なのではないでしょうか。
2024年秋から国の住宅政策審議会で住生活基本計画の見直しに向けた議論が始まり、居住支援は大きなテーマとなっています。厚労省でも住まいは大きな関心事になっています。
このように政策や制度の面でも注目が集まっている中で、LivEQualityの取り組みには大きな可能性を感じています。
インパクトボンドという新しい仕組みと、現場に寄り添った支援の両立。これからの居住支援のモデルになっていくのではないでしょうか。
株式会社LivEQuality大家さんの取り組みに関心をもっていただけた方は、ぜひこちらのページもご覧ください。
