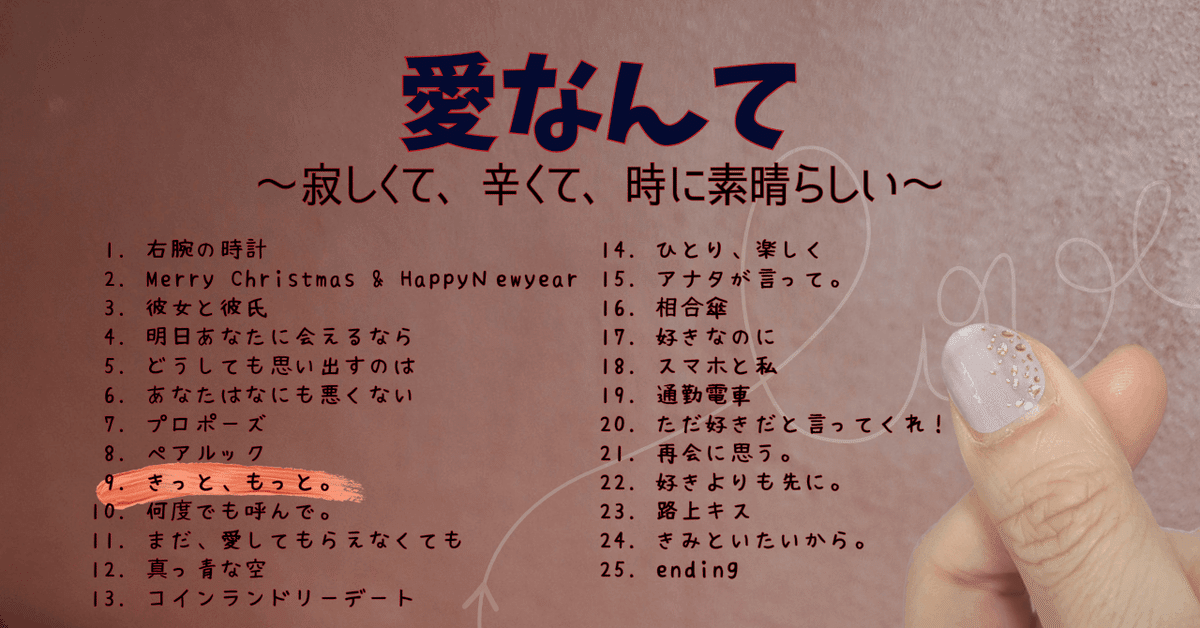きっと、もっと。
私は、とてもだらしない。そして、とてもワガママで、根性がない。
「ただいまー」
同棲が始まったのは、私が仕事を辞めたくて辞めたくて仕方がないときだった。
彼の稼ぎに頼る気は毛頭なかったが、少しでも私の生活が楽になるならと彼が申し出てくれた。
「おかえり。初仕事どうだった?」
「うーん、イマイチ。もう辞めたいよ」
カウンターのあるキッチン。フリーターの私が過ごしてた所とは、ランクが違う。彼は正社員で、私とは懐事情に大きな差があった。それは分かりやすいかたちで現れる。棲む場所、棲む部屋、テレビ、ベッドのマット。大学時代から極貧で、ずっと同じ場所に暮らしている私には考えられない生活だった。
「大丈夫?」
「大丈夫じゃない」
2人だからと新しく買った食卓に、私は項垂れた。
そんな私に、彼はそっとコーヒーを置いてくれた。
「辞める?」
「良いの?」
顔をあげて彼を見つめる。羨望の眼差し。それくらい、初仕事はしんどかった。それが、慣れていくことでなくなっていく緊張感なのかは分からないが、今の私は、もう耐えられないという気持ちでいっぱいだった。
「生活は少し苦しくなるけど、贅沢しなければ俺の稼ぎでどうにかなるよ」
彼は優しく微笑んで、そう言ってくれた。
「だよね」
優しい言葉の中の現実に、私は再び顔を埋めた。
贅沢をしたいわけではないけれど、生活が苦しくなるのは彼に失礼だし、私はもうあの生活を続けたくなかった。
働かなくては仕方ない。
現実は、彼ほど甘く優しくはない。
「俺はね」
途切れた言葉に、私は顔だけを彼に向ける。
彼はまだ、優しく微笑んでいた。
「何もせずにただ辞めるより、転職活動を続けて、良い職場が見つかったら辞めるっていう方法をオススメするよ」
それで良いんだか悪いんだか、分からない答えだ。
きっと、みんな同じことを考えて、同じように行動するんだろうな。なんて、思ってしまった。
でも、今の私にはない考えだった。始めたばかりの転職活動に終止符が打てないなんて。
でもにわかに、心が楽になった気がした。心臓を掴み縛っていたなにかが、緩んだ気がした。
「それなら、出来そうじゃない?まあ、勤め先にとってはよくないかもだけど。俺は、無理してまで続けてほしいなんて思わないよ」
私は黙って、じっと彼の顔を見つめた。彼は変わらず、嫌な顔をせずに微笑んでくれていた。いや、この微笑みこそが彼の日常なのだ。彼は怒ったり、嫌みをいったりしない。むしろ、こうやって許して励ましてくれる。ありがとうすら言えない私に、こうやって優しく諭してくれる。
そんなあなたが、とても愛しい。
「なにかお菓子、持ってこようか」
立ち上がろうと、彼はテーブルに手をついた。その手を、私はぎゅっと掴む。
あなたには私なんかより、見合った人がいるはずなのに。きっとずっと、素敵な人がいるはずなのに。
そう思うのに、どうしてもこの手が放せない。