
テスト実施だけじゃない データドリブンでプロダクトの品質向上を目指すTQM部
プロダクトの品質向上のために、テストフェーズの業務だけでなく、要件や仕様のレビュー、更には開発プロセスの改善にも関わっているTQM(Total Quality Management)部。
今回は、Webシステム開発からプロジェクトマネジメントなど、幅広い業務経験を持つTQM部 部長の岡本さんに、お話を伺いました。
――まずは、岡本さんの現在の業務内容を教えてください。
TQM部で部長をしながら、プロダクトの工程管理を行っています。具体的には、要件や仕様の確認、レビューや工程管理など、プロジェクトが円滑に回るためのサポートを行っています。
また、外部テスターの管理や運用ルールの策定など、テスト進行のディレクションも行っています。
――L is Bに入社する前は、どのようなお仕事をされていたのでしょうか?
大学ではシステム制御工学を学び、そこから小さなソフトウェア開発会社に入社しました。汎用機の開発を行っており、主に、SES企業で銀行システムなどの開発を行っていました。その後、Webシステム開発の会社に転職しましたが、徐々にPMのようなディレクション業務の比重が大きくなり、要件定義から設計、ベンダーコントロールなどを行ってきました。
途中、印刷会社でオンデマンド印刷のディレクションを行ったり、コーヒーが好きなので、カフェを経営していた時期もありました。
――ところで、L is Bにはどのようなきっかけで入社されたのでしょうか?
代表の横井さんから声をかけていただきました。前職で受託開発の仕事をしていたのですが、L is Bもちょうど受託開発をしていた時期で、同じ会社から受託案件をいただいており、それがきっかけで横井さんと繋がりました。
当時、L is Bの会社規模が大きくなっていくタイミングで、営業とエンジニアを繋ぐ役割の人がおらず、開発やプロジェクトマネジメントをして欲しいと声をかけてもらったため、L is Bに入社しました。
プロダクト品質向上のために、商品企画や開発段階から積極的に関わる
――TQM部の部署発足の背景やミッションを教えてください。
もともと、開発の2つの部署内にそれぞれ品質管理チームがありました。ある時、別々で品質管理をしなくてもいいよねという話が社内で出て、TQM部という部署ができました。私は、ソリューション開発の品質管理チームを見ていたので、そのままTQM部の部長として、部署の立ち上げを担当しました。
TQM部発足前の品質管理チームのミッションは、テストフェーズでテストをしっかり実施することでした。
一方で、プロダクトの品質向上のために、テストフェーズのみならず、商品企画や開発フェーズにも関わっていく必要性を、開発本部長の武内さんと話をしていました。
私のプロジェクトマネジメント経験を活かして、プロジェクトマネージャーのサポートという形で、開発プロセスの改善から品質を高めていくことを現在のTQM部のミッションとしています。
――TQM部の業務で大変なことは何ですか?
デリバリー(納期)とクオリティー(品質)のバランスをとることが難しいと感じています。自社プロダクトとはいえ、お客さまからのご要望を反映する期限が決まっていたり、機能追加がお客さまとの契約の条件だったりします。他のご要望との兼ね合いや技術的負債の対応など、さまざまな要因があるため、品質を担保しながら、リリースすることが求められています。
テストは最後の工程なので、開発に遅れが発生してしまうと、テスト期間を十分に確保できないという事態も発生します。開発の遅延を防ぐためにも、工程管理の業務を通して、積極的にテスト前のフェーズにも関わり、プロジェクトの進捗が遅れないようにしています。
――プロダクト品質向上のために、何か取り組まれていることはありますか?
データドリブンで業務を進めていきたいと考えています。
プロダクトの品質を定量的に把握するために、カテゴリごとの不具合の発見率やテスト密度などのデータを取っています。
品質管理をする私たちの立場からすると、テストケースを増やしたいと感じる場合もあります。しかし、収集したデータから客観的に分析してみると、今やらなければならないことは、テストケースを増やすことではなく、初期品質を上げることだったりします。
では、どうやって初期品質を上げようかと検討するわけです。例えば、あるプロジェクトではユニットテストでロジック部分のテストが不十分であることが分かりました。ロジックのテストを十分可能にするために、まずは開発にリファクタリングを進めてもらい、同時にユニットテストが改善できるまではTQM部側のテストでカバーしよう、となりました。
経験に基づいた感覚も大切にしますが、このように定量的なデータから客観的にアプローチすることで、より効果的な取り組みができるようになってきています。

テスト業務を効率的に進めるため、技術力向上のための取り組みも欠かさない
――ところで、TQM部は東京と徳島にメンバーが在籍しており、リモートワークメインの働き方ですが、何か意識していることはありますか?
毎朝、スタンドアップミーティングを実施し、業務の進捗確認をしています。
また、週1回TQM部の定例MTGを実施しています。定例MTGの際に、フリートークの時間を設けていて、業務以外の好きなことを話しています。
ちなみに、私は前回、電視観望(望遠鏡で星を撮影すること)について話しました。星を撮影する時、地球が自転しているので、星を追尾しなければならないのですが、自動追尾させるためには、基準となる星を望遠鏡の真ん中に入れて、現在の望遠鏡の向きを認識させる必要があり、これがとても大変です。そこで、プレートソルビングというものを使うと、データベース上の画像データをもとに、望遠鏡の向きを自動的に調整してくれるのです。この機能に感動したという話をしました。
好きなことを共有してもらうことで、普段の業務だけではわからないメンバーの人となりや興味のあることを知ることができるので、面白いなと思っています。
また、東京勤務のメンバーは、月1回オフィスに集まって、雑談しながら同じ空間で業務を行っています。
あとは、小さなことですが、チャットのテキストだけだと冷たい印象を与えてしまうので、directのスタンプをうまく活用しています。
――TQM部メンバーの技術力向上のための取り組みを教えてください。
JSTQB Foundation Levelを取得したメンバーがいるので、どのように勉強をして資格を取得したのか、部内メンバーにシェアしてもらっています。
また、TQM部メンバーも「価値ある一週間」を取得できるので、業務に必要なツールの情報収集などを行っています。例えば、テストケースはGoogleスプレッドシートで作成しているので、関数について調べたり、テストケースからデータ集計ができるように、GASについて調べているメンバーもいます。また、生成AIなどの最新技術をどう業務に取り入れられるか、調査をしたメンバーもいます。
テスト設計においても、顧客の課題解決の実現を意識する
――岡本さんが業務を進めるうえで意識していることはありますか?
L is Bのサービスはdirectを筆頭に、分かりやすくて使いやすいものが多いと思っています。そのメリットが損なわれてしまわないように、業務を進めることを意識しています。
要件整理や仕様レビューにおいては、極力シンプルで分かりやすくということを心がけているため、ユーザーが解決したいことは何なのか確認し、こういう実装でもよいのでは、と提案することもあります。
ユーザビリティが担保されているのか、顧客の課題が本当に解決されるのかという点は品質管理においても、意識しなければならないと思っています。
――岡本さんが一緒に働きたいと思う人はどのような人でしょうか?
テストは一見地味な作業の繰り返しで、成果の見えづらい、攻めか守りかでいえば明らかに守りの業務になります。そんななかでも責任感とプライドを持って取り組める人でしょうか。
実際にはテスト分析や設計はクリエイティブなもので、分析や設計なりの面白さがあります。テスト実施においても、ソフトウェアテスト7原則※にもあるように全件テストは不可能なため、テストケースにない箇所でバグやユーザビリティの課題を見つけることもあり、決して単純作業だけではないです。また品質管理はテスト業務だけでは不可能なので、企画や開発と一緒に課題を分析して開発プロセスから改善する必要があります。
こういった業務を面白そうと思えるのであれば、向いていると思います。
※ソフトウェアテスト7原則
ソフトウェアテストにおいて、理解しておく必要があるガイドラインのことです。
JSTQBテスト技術者資格制度 Foundation Level シラバスに記載されています。
https://jstqb.jp/dl/JSTQB-SyllabusFoundation_VersionV40.J02.pdf
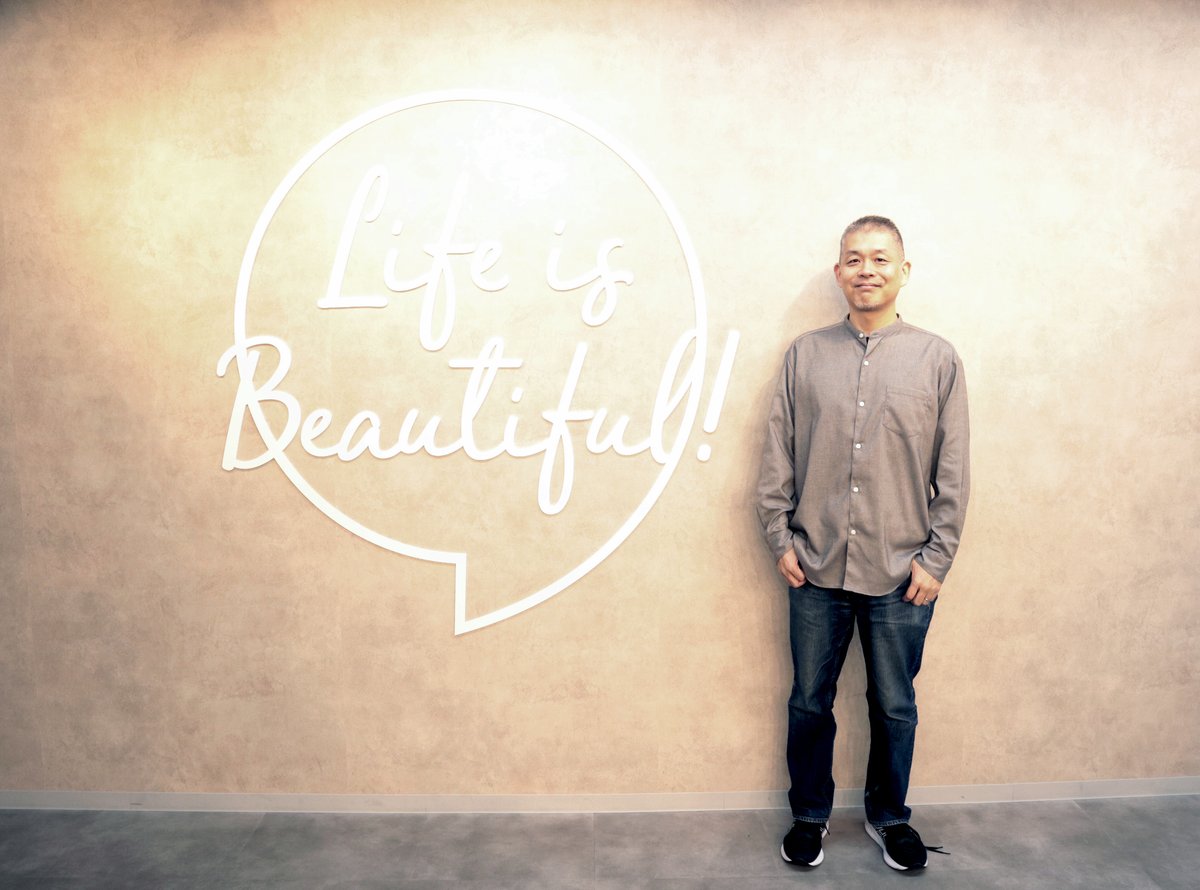
――最後に、応募を検討している候補者へメッセージをお願いします。
私も生成AIなど新しい技術には興味があるので、個人的にいろいろと調べているんですが、有効活用できたらいいなと思っています。
それらを取り入れることで、品質を落とすことなく、より早くお客様にサービスを届けることができると考えています。こういったチャレンジに一緒に楽しみながら取り組んでもらえる人が来てくれたら嬉しいです。
みなさまからのご応募、お待ちしています。
L is Bでは一緒に働く仲間を募集しています!
L is Bについてもっと知りたいという方は採用情報サイトをご覧ください。
またL is Bについて話を聞いてみたいという方を対象に、カジュアル面談を実施しております。
ホームページやnoteは見たけど、 もう少し詳しく話を聞いてみたい
L is Bで働く社員と実際に話をして会社の雰囲気を知りたい
自分がどのポジションに合うのかわからない
上記にあてはまる方は、カジュアル面談ページ内にある「応募する」ボタンからぜひエントリーください!
