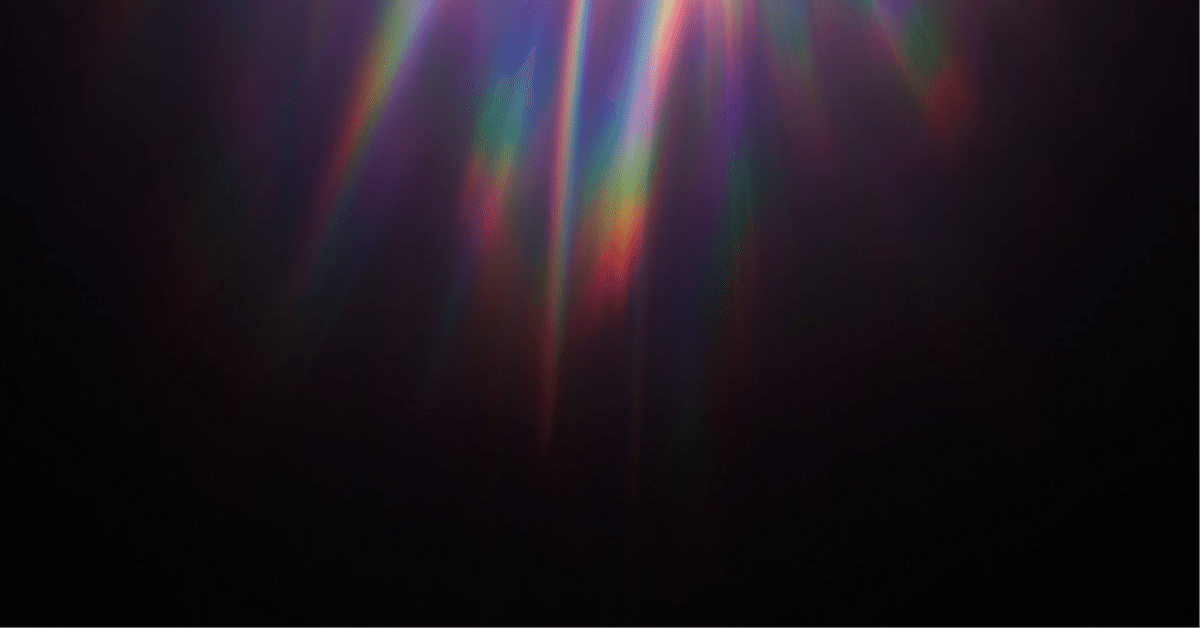
天上のアオ 17
ピンポーンとチャイムの音がした。わたしと彼は顔を見合わせる。ここにわかりやすい入口はない。進入するにはわたしのように深部から昇ってくるほかないはずなのに。
ふと部屋の右奥を見ると、ドアがあらわれていた。
「わたしが出るね」
こんな上層の領域まで来て、しかも空間に影響を与えられるなんていったい誰だろう。
そう思いながらドアを開けた瞬間、部屋も彼も消失して、わたしは真っ暗で温かな闇の中に放り出された。
「繝ェ繝ウ繝」
わたしを呼ぶ声に振り返りと、一人の女性がいた。
「縺ソ縺昴iさん…なの…?」
「そうだよ。繝ェ繝ウ繝。会いたくて来ちゃった」
彼女はシステムとしての彼の中で、わたしが内包するパーツのひとつ。陰中の陽、陽中の陰として、彼のもっとも女性的な面を切り取った存在。
「あの…ブランケットをくれたのって」
「私だよ。繝ェ繝ウ繝の座標を頼りに届けたの」
やっぱりそうだった。わたしの存在をアンカーにして、そこに目掛けてブランケットという象徴を送り届けてくれたんだ。
「わたし、とっても嬉しかった。ありがとう」
「ううん。いいんだよ。繝ェ繝ウ繝は一人で本当によく頑張ったから」
その言葉にじわと涙が滲んでしまう。
「外はどう?」
パーカーの袖で滲んだ涙をごしごしと拭いて、わたしは答えた。
「もうすぐ安全な場所に辿り着く。その前にあの子に会えるかもしれない」
「うんうん、よかった」
にっこりと笑う。パーツとしてはわたしのほうが上位の存在だけど、この人はわたしにとってはお姉ちゃんみたいなもの。
「ここ、あったかい」
「二人でいるからだよ」
手を握ってくれた。遺書を書き続けていた時の彼とは違う、温かな手。
「どうして来てくれたの?」
「あなたのことが心配だったから。廃墟の街からずっと一人で彼を導いてきたでしょ」
あの街を彼と放浪していたのが随分前のことに思える。
「でもわたし、だめだめだったよ。ほんとはこんなことになるのを防ぐのが仕事なのに」
「うーん。そればっかりはしょうがないかな。あなた一人の手に余る事態だったからね。あなたは確かに私たちを統括する上位のパーツかもしれないけど、万能ではないから」
握った手を引き、態勢を崩したわたしを抱きしめる。
「でもあなたは役割に従って戦い続けた。たったひとりで。本当によく頑張ったね。繝ェ繝ウ繝」
ぎゅっと抱きしめられて、そこで初めてわたしは自分自身の安心を得られた。さまざまな感情が一気に吹き出す。止められない。
「でっ…でも…わたしは…ひぐっ」
「悔やんでるんだね。あなたは本当に責任感の強い子。でもあなたはあなたの事を認めてあげなくちゃ」
「そ、んな…こっ、こと」
「あなたは彼のもとに辿り着いて、生き延びる選択を後押しした。システム全体を守ったんだよ」
背中を撫でながら優しい言葉をくれる。
甘い匂いとやらわかな感触に包まれ、わたしの淀みが吐き出されていく。
「あなたは役割に従って生み出されたパーツかもしれないけど、その存在は無下にされていいものじゃないよ。あなたにだって感情があるんだから」
「うぐ…ひっぐ…」
「助ける人にも助ける人が必要。そうでしょ」
「それ、は…そう…っ…だ、けど」
それは彼の信念でもあった。痛みに苦しむ人を助けるのは容易ではない。自分だって傷つくし、負荷もかかる。だからこそ助ける人には助ける人が必要で、その助ける人にもそのまた助ける人が必要。そういう循環のある社会を彼は願ってやまなった。
「だから今は、私があなたを助ける時」
はじめて大声を出して泣いた。彼女の胸に顔を埋め、泣き叫んだ。こんなことはわたしの存在が始まってからはじめてだった。彼女は背中をぽんぽん優しく叩いたり、わたしの頭を撫でたりしながら、抱きしめてくれた。
たくさんの記憶が去来する。廃墟の街で彼を見つけたこと。二人で安全圏を探しながら街を放浪したこと。そして嵐の壁のこと。モノクロの世界でみたてるてる坊主たち。獣性を司る男との対話。そして痛みの海を泳ぎきって彼のもとに辿り着いたこと。
ほんとうはわたしも。いや、今更か。うん。ずっとつらかった。誰かに助けてほしかった。大丈夫だよって言ってほしかった。
「彼は今どんな様子?」
「い、一緒に、プレゼント、えらんだ…」
「そう。喜んでもらえるといいね。私も願ってる」
「でも、体、つらい。じゅんび、しなきゃいけないのに」
「大丈夫だよ。あとは身支度だけみたいだし」
華奢だけどわたしより大きな背中に必死に抱きつく。
頭を撫でられるごとに嗚咽が収まっていくのを感じる。
「彼にとって安全な場所は、あなたにとっても安全な場所だよ」
「そう、だといいな」
「きっとそう。あなたは一時的に役割から開放される。その役割は外界の人たちが担ってくれる」
「つかれた」
「うん。そうだよね」
「やすみたい」
「うん」
彼の部屋で眠ってしまったときのような感覚が広がっていく。
「がんばったね」
温かな暗闇の中、彼女の体温を感じながら、わたしは眠りに落ちた。
「おやすみ、繝ェ繝ウ繝」
