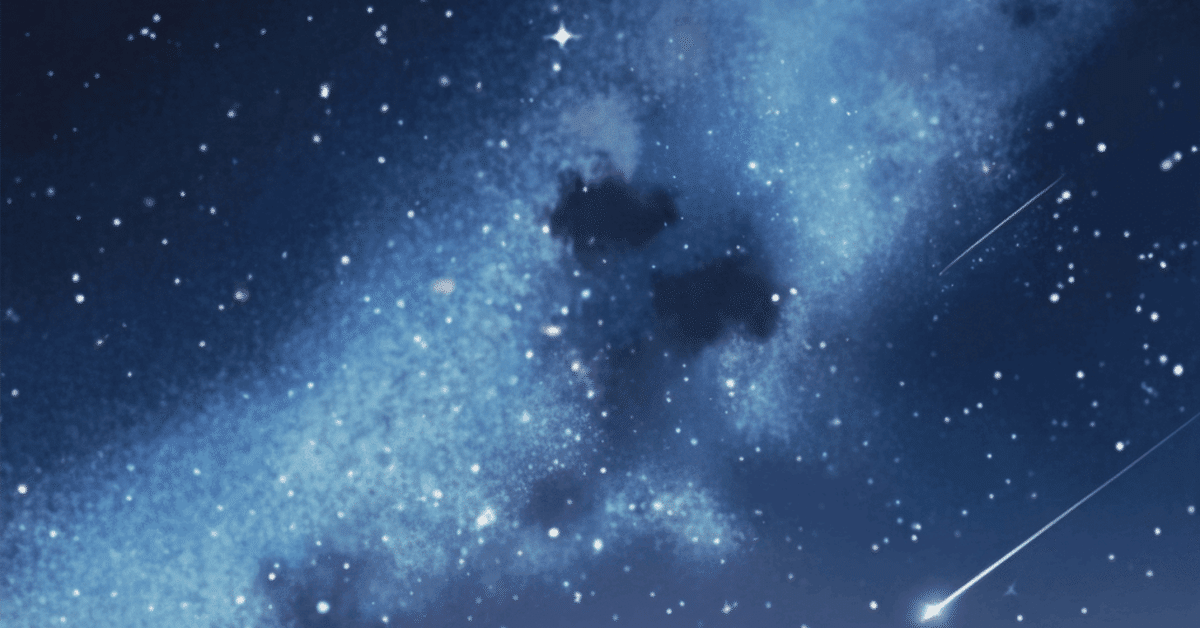
Binary star
メリーランド州ボルティモアにある研究所の一室で、私は本を読んでいた。図書室から持ってきた小説で、私の好きな作家が最期に書いた物語だ。
部屋には壁に沿うように机とベッド、棚とクローゼットが設られていて、それらが鏡合わせのように反対側の壁にも並んでいる。つまりは相部屋。
もう一人の住人はいつも通りどこかをほっつき歩いて、また研究スタッフに叱られているのだろう。そういうことにはもう慣れている。
入口のドアの上、天井近くに掛かったアナログの時計に目を遣る。午後10時。いつも通りの夜。もう十数年過ごしてきた夜。
ここには私たちのような子どもが何人もいた。そう、『いた』。ひとり、またひとりと消えていき、今は私と同室の友人の2人だけになってしまった。
私たちは世界規模のとある研究プロジェクトの一員だ。他人の意識を読み取る能力を持った私たちは、その計画の要なのだという。メンバーとして表向きは扱われているが、実際はサンプルとか備品に近い。
本に栞を挟んで机に置く。そのまま両手を上げて伸びをした。随分長いこと読書をしていたせいか、背骨がポキポキと音を立てた。
それに続いて廊下を走る音が聞こえてくる。やっとお帰りだ。乱暴にドアが開けられると、銀髪のショートカットが特徴的な友人がそこにいた。
「おかえり。なにやってたの、ノラ」
「別に。通信管理センターに繋ごうとしたら怒られた。以上」
この研究所は国連機関の管轄で、世界中に同じような場所がある。そのすべてがただ一箇所の施設を管理するためのものだった。疑似現実生成ターミナル。通称『図書館』。私たちの属するプロジェクトの最重要施設だ。
「あの子のこと、あんなに目の敵にしてたのに覗き見でもするつもりだったわけ?」
『図書館』には私たちと同じような能力を持つ子が、施設の現場管理者として暮らしている。私たちはその子の予備として、ここに繋がれている。その子はこれまでの誰よりも能力が精密で強く、それゆえに施設にいるのだと聞かされていた。
「別に。アイツのことなんか知ったことじゃない」
その言葉こそ、あの子のことを誰よりも気にしていることの証だ。私はため息をつくと、椅子から立ち上がった。
「ねえ、もう寝ない?私疲れちゃったよ」
「うるさいな。ユニだけ寝ればいいじゃんか」
「ノラはどうするの。またイタズラしに行く?」
「ああもうわかったよ」
開けっ放しにしていたドアを乱暴に閉め、つかつかと自分のベッドに向かうノラ。私はそれを見届けるとクローゼットから寝間着を出して着替え始めた。
ノラは終始不機嫌な様子で、寝間着に着替えるとさっさとベッドに潜り込んでしまった。
「おやすみ」
返事はない。
◆
夜中。今が何時かもうわからない。私は柔らかい感触で目を覚ました。
「ノラ……?」
友人がベッドに潜り込んできた。壁側を向いて横になっていた私の背中に手があたっている。私は寝返りを打って、いつものようにベッドに入ってきた友人の顔を見る。案の定、目が合った。
「先に言っとくけど、『なんでもない』は禁止だから」
「……ユニはずるいんだよ」
「じゃあ聞かせて。なにかあったの?」
少しの沈黙の後、彼女は口を開いた。
「……あたしたちは、どうなるんだろうな」
「……それは」
私たちはあの子のバックアップ。もし彼女の身になにかあれば、すぐさま出番がやってくる。でも、もし『なにもなければ』?私たちはこの研究所で育った。外の世界のことは本や映像、研究所のスタッフの話でしか知らない。
「あたしたちは一生このままなのか?」
「……」
その問いに対する答えを私は持っていない。そして、その問いは私の問いでもある。外の世界。私たちの行けない世界。
「ユニ。アイツもこんな気持なのかな」
「それはわからない。だけど私たちは私たちで生きていかないといけない。それだけは確かだよ」
ユニの頭を抱き寄せながら言う。さらさらとした銀髪が顔をくすぐる。世界にふたりぼっちの私たち。
「みんな悪い奴らじゃないってわかってるんだ。だけど大人は信用できないんだ」
「うん」
「いっそここから逃げ出せたらいいのにって、ずっと思ってるんだ」
だんだん涙混じりになっていくノラの声。
「そうだね。私だって外に出てみたい」
ノラが私にしがみつくように強く抱きつく。私はその髪をとかすように、頭を撫でることしかできなかった。
「あたしは……あたしたちは……なんのために」
「うん」
時代にそぐわないアナログの時計が、カチカチと音を立てて時を刻む。今が何時なのか、もうわからない。
「ユニ」
弱々しく名前を呼ぶ。
「なあに」
「ずっと一緒だよな」
「一緒だよ」
その言葉がこれから先の未来、嘘にならないことを私は心の底から祈った。友人、姉妹、恋人。私たちを指し示す言葉がなんであろうと、私たちがともに生きること。それだけが真理であってほしかった。
そうだよね、ノラ。
だからあなたは今、泣いているんだもの。
