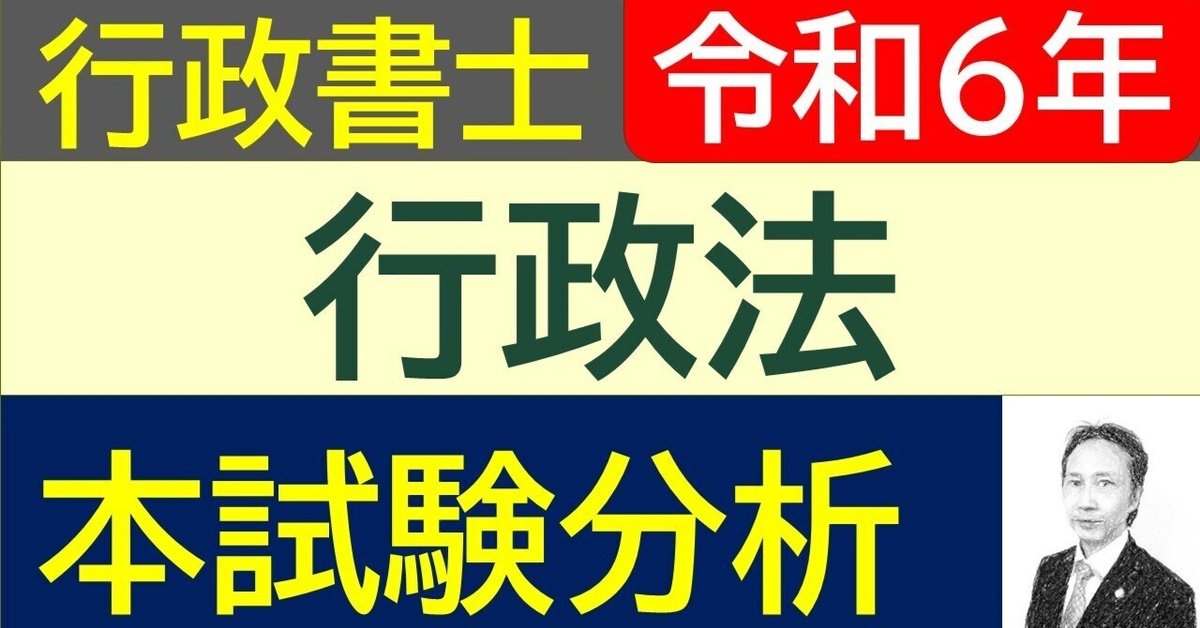
令和6年行政書士本試験分析と 今後の対策 行政法
1令和6行政書士試験分析(行政法)
YOUTUBE動画と同じ内容です。
【行政書士試験】2024本試験分析 行政法(択一編)
https://youtu.be/S5O8tK8wjU4
行政法の記述式の解説については、こちらの動画をご視聴ください。
【行政書士試験】2024年問44記述式解説
https://youtu.be/oe9ah3RUTOw
行政法の多肢選択式問42の解説についてはこちらの動画をご視聴ください。
【行政書士試験】2024年問42多肢選択式解説
https://youtu.be/WhGKSfDPoRw
令和6年行政法択一について以下で解説し、最後に今後の学習上の注意点を解説します。
2令和6年行政法択一式のテーマと正答率
問8 行政行為 正答率 56.7%(伊藤塾分析会)
問9 行政立法 正答率 52.6%
問10 一般原則 正答率 76.5%
問11 不利益処分 正答率60.3%
問12 行政指導 正答率 86.8%
問13 審査基準と処分基準 正答率64.5%
問14 審査請求 正答率85.7%
問15 適用除外等 正答率54.0%
問16 行審法と行訴法の比較 正答率71.1%
問17 訴えの利益 正答率90.9%
問18 抗告訴訟における判決 正答率72.8%
問19 民衆訴訟・機関訴訟 正答率33.8%
問20 国家賠償法判例 正答率80.1%
問21 国家賠償法1条 正答率89.2%
問22 地方公共団体の事務 正答率61.7%
問23 住民監査請求・住民訴訟 正答率67.2%
問24 条例・規則 正答率65.0%
問25 公立学校をめぐる裁判 正答率68.0%
問26 公文書管理法 正答率54.9%
3「正答率が低いワースト5」と「今年特徴的だった問11」
問題数が多いので、「正答率が低いワースト5」と「今年特徴的だった問11」について解説をし、最後に行政法の総括をします。
問8 行政行為 正答率56.7% 行政法の中で5番目に低い 妥当なものは肢5
肢1は処分を出した行政庁が処分を自ら職権取消できるため誤り。
肢2は最高裁平成22年6月3日の判決により、少なくとも固定資産税の賦課徴収に関する違法な課税処分によって国民が損害を被った場合に、当該課税処分の取消訴訟を経ずに、被った損害の填補を求めて国家賠償請求訴訟を提起できると判断しているので誤り(「行政処分の公定力と国家賠償訴訟ー主として金銭の徴収・給付を目的とする行政処分についてー」松本賢人)。
肢3は処分が無効であることを前提に民事訴訟(争点訴訟)を提起して争う余地があるため誤りの肢にしていると推測できます(中原「基本行政法」)。
肢4は最高裁平成21年12月17日(新宿たぬきの森事件)の判決では、先行行為の出訴期間経過後に後続処分の違法性を争おうとする場合に、違法性の承継を認めて、後続処分の前提とされた先行処分の違法性を主張できると判断しているので誤り(行政法判例50!、「行政法」櫻井・櫻井)。
肢5は行政行為は重大かつ明白な瑕疵がある場合に無効になるのが原則だが、例外的に瑕疵が重大であったことだけ認定して明白要件については言及することなく課税処分を無効とした判例があるため、例外的な判例も視野に入れて作られていると考えれば正しい肢となります。肢5はハイレベルな知識ですが、令和2年問9肢3(択一)で出題された知識なので、過去問学習が十分にできていれば、正解できる問題でした。
問9 行政立法 正答率 52.6% 妥当なものは肢2です。
肢1 行政機関が「命令等」を定める場合、意見公募手続きが必要となるところ、「命令等」に含まれる「審査基準、処分基準、行政指導指針」は行政規則に属するため、法規命令だけでなく行政規則も意見公募手続きの対象となる。行政規則も事実上の外部効果がある(間接的に国民に影響を与える)ため、法規命令(直接国民の権利義務にかかわるルール)だけでなく、行政規則(行政の内部基準として存在するルール・マニュアル)も意見公募手続の対象になっている(「行政法」橋本櫻井、「基本行政法」中原)。
肢2 過去問の平成23年9問肢1・5を学習していた方、あるいは、憲法の統治機構を捨てずに学習していた方は正しい肢と判断でき、問9の正解にたどりつけたと思います。問9の正解率が低いということは、憲法の統治機構の条文をあまり勉強していない方が少なくないということなのでしょう。
肢3 行政機関の処分が違法でも取り消すまでは有効というルール(公定力)
が働く場面は、違法な「行政行為(行政処分)」だ出た場面ですが、肢3は行政機関が制定した「命令」について問いかけており、「命令」には公定力は働かないと解釈されているため(「委任命令の違法性審査」正木宏長)、行政機関の制定した命令は法律の範囲を逸脱した違法なものとして無効となることから、誤りの肢です。
他方で、肢5は「行政行為(行政処分)」の領域の話です。行政庁に裁量を認める内容の処分基準(裁量基準)に従わない行政処分が出されても当然に違法になるわけではなく(マクリーン事件:中原「基本行政法」)、仮にその処分が違法と評価されたとしても、公定力が働き当然に無効にはなりませんから誤りの肢です。
肢4 通達の処分性を否定し、通達の取消訴訟は提起できないという有名な判例(最判昭43年12月24日)に照らし誤りです。
問15 行政不服審査法 適用除外等 正答率54.0% 妥当なものは肢4
順番を変えて肢5から入ります。
肢5 主婦連ジュース事件判決(最判昭53・3・14)は、「処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」に不服申立ての適格を認め、行審法の中には「自己の法律上の利益にかかわらない資格」で不服申立てを認める規定はないため、誤り。
肢1 金銭の納付を命じる不利益処分も行審法が適用されるため誤り。
肢2 審査請求の対象となる「不作為」とは、「法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと」と定義されている(行政不服審査法3条)ため、肢2のような申請を前提としない不利益処分は、審査請求の対象となる不作為には含まれない。
肢3 この仕組みは行政手続法にはあるが、行審法にはないため誤り。
メンバーシップ3:34~行手法解説
肢4 正しい肢として正解。メンバーシップ1:32~解説
問11 行政手続法の不利益処分 正答率60.3% 事例型 妥当なものは肢5
肢1 不許可処分とは異なり、免許(許可)取消処分は不利益処分なので誤り
肢2 司法警察職員が直接出した処分ではないため、適用除外にならず誤り
行政手続法3条5号 (適用除外)
刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員が
する処分及び行政指導
肢3地方公共団体がする処分で国法の処分と届出は行手法が適用され、誤り
肢4 審査基準は許可不許可の処分(申請に対する処分)を出す際の基準とし
て作成され、許可取消(不利益処分)の際の基準ではないので、誤り。
肢5 行手法13条2項3号により正しいため、正解
原則として
行政庁は、不利益処分をしようとする場合、不利益処分の名あて人に対し、意見陳述のための手続(許認可等を取り消す不利益処分の場合は聴聞手続き)をとらなければならない。
例外として聴聞等の手続きを取る必要がない場合(行手法13条2項3号)
法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
問19 民衆訴訟・機関訴訟 正答率33.8% 正しいものは肢3
本年度については、できなくても差がつかない問題です。
肢1 機関訴訟は個別の法律の定めがあってはじめて提起できるため×
42条 民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、
法律に定める者に限り、提起することができる。
肢2 民衆訴訟は「何人も」提起できるわけではないので✕
例えば、住民訴訟は、住民監査請求をした住民のみ提起可
肢3 機関訴訟で、取消訴訟を提起する場合もあるため、〇
(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)
43条1項 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるもの
については、第九条及び第十条第一項の規定を除き、取消訴訟
に関する規定を準用する。
肢4 議員の選挙の効力に関する訴訟は、民衆訴訟なので誤り。
肢5 民衆訴訟と機関訴訟も行政事件訴訟なので、民事訴訟の規定を排除していないので✕。行政事件訴訟法は訴訟手続きについて、独自の手続規定をわずかしか置いていないため、行政事件訴訟法に定めていない手続きについては、民事訴訟法の規定を用いるということ。
(この法律に定めがない事項)
7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、
民事訴訟の例による。
問26 公文書管理法 正答率54.9% 同法はかつて一般知識として出題。
受験生の多くは事前準備ができていない状況ですが、肢2が行き過ぎでしょうと感じられる内容だったため、正答率が50%を超えたのでしょうか。
誤っているものは肢2です。
肢1 公文書管理法2条4項の「行政文書」の定義規定のとおりで正しい。
肢2 公文書管理法では、「罰則」の定めがないため、誤り。
公務員が文書作成を忘れたら罰金払ってもらいますよというのであれば、
公務員になる人がいなくなるでしょうから、罰則は行き過ぎでしょう。
肢3 公文書管理法5条1項のとおりで正しい。
肢4 公文書管理法10条1項のとおりで正しい。平成28年問57肢3の知識
肢5 公文書管理法9条1項のとおりで正しい。平成28年問57肢2の知識
4 行政法の学習上注意すべきこと
❶公文書管理法の対策
公文書管理法は、かつて平成25年問55肢4・平成27年問54・平成28年問57・令和5年問26肢3で出題されおり、いずれも一般知識の分野で出題されていましたが、令和6年は行政法の分野で出題されました。来年以降の対策としては、過去に一般知識で出題されている過去問と公文書管理法の骨格部分を覚えるだけでよいでしょう。
❷過去問学習の重要性 H18以降の過去問知識で19分の12は解ける
【H18以降の過去問知識で解ける問題】
➡問8・9・10・12・13・14・15・16・17・18・21・24 19分の12
上記の問題で間違えている場合は、過去問学習がおろそかになっている
【H18以降の過去問知識だけでは解けない問題】
➡問11・19・20・22・23・25・26 19分の7
過去問で対応できない7問のうち4問程度は正解したいところなので、 知識の不足を補うため網羅性の高い行政法のテキストの学習も必要です。 問25・26は行政書士用の教材では事前準備がしにくい内容ですが、それでも常識感覚やバランス感覚で解けた方もいたため、いずれも正解率が50%を上回る結果となっています。
❸記述式はときどき試験委員の興味関心分野が反映される傾向
令和6年行政法記述式44問では、古い判例(東京12チャンネル事)を素材にしつつ判例の事例を大胆に変えた問題が出題され、意表を突く出題となりましたので、記述対策として事前準備をしていた受験生は少なかったと思います。現在の行政法の世界で特に注目されているわけでもない古い判例の東京12チャンネル事件を、なぜ記述式の元ネタにしたのか困惑している予備校関係者が多い様子ですが、野口貴公美試験委員が「行政法判例50!」の原告適格部分の執筆担当をしており、その中で東京12チャンネル事件をとり上げているため、作問時に野口先生の頭の中に浮かんできたのかもしれません。なかなか受験生が試験委員の関心分野をリサーチして学習するのは困難だと思いますので、令和7年受験も野口試験委員が退任されない場合は、令和7年夏以降に同委員の「行政法判例50!」執筆担当部分の判例について、いくつかピックアップして解説動画を上げる予定です。
❹多肢選択式(空欄補充問題)
素材となっている文章は行政法の判例や制度の全体像を解説した文章(出典不明)が多いので、判例や用語の単純な知識問題と考えがちですが、実は試験委員側は、多くの受験生が見たことがない文章(例えば、地裁レベルの判決・最高裁判例の補足意見・受験生が学習していないであろう判例等)を素材にして問題を作ることがあるため、事前に覚えてきた判例のキーワードを思い出せれば簡単に解けるような問題ではない場合が少なくないです。制度全体像・基本用語・判例の事例・争点等が何だったかを知っていることを前提にしつつ、あとは読解力と日本語力で解くことが求められるのが特徴です。つまり、長文読解の法律版であり、空欄前後の文章に調和するように日本語を正確に使い分けて穴埋めする力が試されています。多肢選択式は長文読解の法律版という意識で問題を解く訓練を事前にしておくことが必要です。令和6年度多肢選択式行政法問42は、別の記事及びYOUTUBE動画で解説しています。
いいなと思ったら応援しよう!

