
「プロボノならではのフラットな関係から見えた、社会課題×デザインのヒント」|10周年記念サイト 制作チームクロストーク
「子どもの貧困に、本質的解決を。」というミッションを掲げる認定NPO法人「Learning for All 」(以下、LFA)は設立10周年を迎えました。その設立10周年を記念し、2024年7月23日に公開され、様々な反響をいただいた「10周年記念特設サイト」。
今回はこの特設サイトの制作にプロボノ(※仕事で得たスキルや経験を活かす社会貢献活動、ラテン語の「Pro Bono Publico(公共善のために)」が語源)として携わっていただいた、インターブランドの東洋介さんと山崎大作さん、NEWTOWNの犬飼崇さんにお話を聞きました。通常のプロジェクトよりもフラットな関係で作り上げられたという本プロジェクトのプロセスには、「社会課題×クリエイティブ」のヒントがあったそう。ブランディングの考え方やデザインを通じてLFAの新たな一面を魅力的に表現してくださった御三方に、10周年プロジェクトの制作過程、葛藤や学びについてお話しいただきました。

東:インターブランドでクリエイティブ・ディレクターをしています、東です。インターブランドはロンドン発のブランディングエージェンシーで、現在はニューヨークに本社を構え、主に企業の理念体系の構築やロゴデザイン、ブランドを活性化させる体験構築などを通じて、企業の成長に貢献することを目指しています
私は2004年に多摩美術大学グラフィックデザイン学科を卒業し、20年近くのキャリアを歩んできました。就職活動では広告代理店を目指しましたが、倍率100倍の狭き門を突破できず、制作会社に就職。「自分はスターにはなれない」と挫折感を抱きながらも、反骨精神を持ってキャリアの中で「いつか見返してやる」と奮闘してきました。
制作会社でデザインの基礎を3年ほど学んだ後、中島祥文さんという巨匠の元でスパルタ指導を受け、技術や姿勢を磨きました。その後、中小規模の代理店で「ブランディング」という概念に可能性を感じ、国内のブランディングエージェンシーを経て現在に至ります。
現在は、ブランディングを軸に企業の経営層と直接対話し、成長をサポートする仕事をしています。泥臭い道のりでしたが、それが今の自分を支えていると思います。
山崎:インターブランドでデザイナーをしています、山崎です。私は一般大学を卒業後、デザインとは全く縁のない金融業界でキャリアをスタートしましたが、2007年にアップルに転職したのが転機となりました。当時、スティーブ・ジョブズが率いるアップルで、セールスをせずとも商品が売れる「ブランドの力」を目の当たりにし、デザインへの興味が芽生えました。
30歳を過ぎてからデザイン業界に飛び込み、個人事務所やベンチャー企業、またフリーランスとして活動。自身でブランドを立ち上げる経験もしましたが、課題を痛感。その後インターブランドに入社し、ブランディングの最前線で学びを深めて2年半が経過しました。ブランディングの奥深さを学び続けています。
犬飼:私は、東さん以上に泥臭いかもしれません(笑)。私も多摩美術大学出身ですが、就職活動時には広告代理店の仕事内容すら理解していませんでした。「迷っているなら一度ここで働いてみたら?」と声をかけてもらい、当時アルバイトをしていた出版社の雑誌編集部で働き始めたものの、卒業前に雑誌が休刊。その後、アパレルブランドの記念誌制作を通じて、私をデザインの道へと導いてくれた師匠と出会い、事務所に住み込みで働くように。ハードすぎて一度逃げ出してしまったこともありましたが、そこでエディトリアルデザインの基礎を学びました。
その後、活動の幅を広げようと広告も扱う事務所に転職し、そこからWebデザインに携わるようになり、現在は「NEWTOWN」という一人会社を立ち上げ、グラフィックとWebのデザインを手がけています。今後は新しいスタッフを迎え入れ、「第二期NEWTOWN」をスタートする準備を進めています。
はじまりはメールの問い合わせフォームから

── LFAとの出会いや、今回の10周年プロジェクトに参加することになったきっかけを教えてください。
東:インターブランドは「Better for Good」というプロジェクトを通じて、社会課題に挑むNPOやNGO、中小企業など、ブランド価値を十分に引き出せていない組織を支援しています。この取り組みは、金銭的なハードルやリソース不足に悩む組織に対し、直接的なサポートを提供することを目的としており、現在3年目から4年目に差し掛かるところです。
初年度は公募形式で参加組織を募りましたが、2年目からは私たちが自主的に動き、支援が必要な組織を探してアプローチする形に切り替えました。その中で、LFAさんにメールで問い合わせをしたのが始まりです。正直、こうしたメールに返信をいただけることは少ないのですが、幸いにも返信をいただけました。
犬飼:東さんからお声がけされたんですね。
東:最初は私からメールフォームを通じて問い合わせをし、LFAの岸本さんが連絡をくださり、話が動き始めました。怪しく見えないように活動の意図を丁寧にお伝えしましたが、それをしっかり読んでいただけたのだと思います。
── なぜLFAが候補にあがったんですか?
東:私自身が子を持つ親になったこともあり、子どもは未来を担う重要な存在であると考えて、「子ども」カテゴリーのNPOをリストアップする中で、LFAさんが目に留まりました。就学後の子どもや困難を抱える家庭に焦点を当てている点が、ユニークで意義深いと感じました。
ただ、つながった後、具体的に何をするかで悩むこともありました。当時LFAさんはリブランディングの検討を始められていて、通常のブランディング支援は必要ない状況でした。そのため、寄付のあり方を再発明するような取り組みを提案しましたが、タイミングが合わず、一度待つことになりました。
正直、その時期は「LFAさんと何か形にできたらよかったけれど、今回は難しいかもしれない」と感じて、少し落ち込むこともありました。その後、10周年プロジェクトで再び声をかけていただき、覚えてくださっていたことがとても嬉しかったです。
── プロジェクトがキックオフしたあとは、インターブランドさんと10周年企画のロゴやデザインの方向性を詰める形でスタートしましたね。ある程度デザインの方向性が見えた段階で、そのデザインをキャンペーンページに実装する役割で、LFAから犬飼さんにお声がけしました。(犬飼さんを知るきっかけになったのは、Xでも話題になった、デザイナーの採用ページ。)
犬飼:子どもに関するテーマは、自分に子どもができてから考えることも増えました。ただ、お話をいただいた時は案件が詰まっており、最初は「お受けできません」とお伝えしたんです。しかし「実装だけでも」と相談いただき、それならお手伝いできるとなりました。子どもに関するNPOでなければお断りしていたかもしれませんが、特別な意味を感じました。また、LFAさんの活動が、仕組み化や政策提言などの社会を変える動きも含んだもので、自分のイメージする「支援」とは異なる点も印象的でした。
両極を行き来しながらたどりついた、挑戦的なデザイン

東:まずLFAさんがプロジェクトの方向性を整理し、依頼をくれました。印象的だったのは、今回の周年企画が、単なるセレブレーションではなく「未来を見据えた実験」であるという点でした。届けたい対象は、職員やボランティア・インターン・OB・OGのみなさん、寄付者のみなさん、寄付企業・地域・連携企業・自治体の方々など、これまでLFAさんが関わった、ありとあらゆる方ということで多岐にわたっていました。
私たちはその意図を基にビジュアルアイデンティティを検討。山崎と澤田(インターブランドのデザイナー)が出した3案の中から山崎の案が選ばれ、タイポグラフィーなど具体的なデザインを詰めていきました。Webが主要タッチポイントだったため、キャンペーン全体の世界観を設定し、Webデザインと実装にも取り組みました。
犬飼さんに、デザインサンプルを提示しましたが、単にコンセプトワードだけを渡して丸投げするのではなく、細かなすり合わせを行いながら進めたのも特徴です。そのため、やりにくさや難しさは特に感じませんでした。
犬飼:むしろ理想的な進め方でしたね。デザインを受け取り、それをどう実装するかを考えました。特に難しいのは、デザイナーの意図を汲み取り再現することです。ウェブデザインに不慣れな場合、細かな「お作法」の違いがありますが、それを調整するのが私たちの役割です。
たとえば、横スクロール部分などはベストな形を模索し、こちらからも提案しました。今回採用したノーコードのWEB制作ツール「Studio」の強みである「素早く作る」ことを活かして、みなさんからクイックにフィードバックを得ながら作れたのが大きかったです。
山崎:おっしゃる通りで、具体的なアイデアをいただきながら試行錯誤し、まさに化学反応が起きたような感覚がありました。
東:プロジェクト中はメッセンジャーなどを使って細かくやり取りをしましたが、フラットかつフランクに意見を交わし合えたのも良かったです。この距離感が、スムーズなコラボレーションにつながった大きな要因だったと思います。
── デザインのプロセスはどのように進んだんですか?
山崎:LFAさんから依頼の際にいただいたクリエイティブのキーワード「祝祭感・人間味・真摯さ」のおかげで、大きなところは定まったなという印象でした。そこから澤田さんと東さんとでアイデアを出し、お互いで刺激し合いながら方向性を定めていきました。

チームで一番初めに会話した中でみんなの中で共通していたのが、イラストの重要性でした。しかし、イラストは一歩間違うと幼稚さにつながるので、注意が必要でした。NPO法人らしい落ち着きだけではなく、今回は少し「人間味」やプレイフルさ(遊び心)を付加していかないと成立しないと思い、それに合うイラストのトーンを探る中で参考にしたのが、アメリカの雑誌『THE NEW YORKER』。大人っぽさと遊び心の絶妙なバランスが目指すところに近い感じでした。
そして、「祝祭感」というところでは、澤田さんが「バルーン」の表現アイデアを持ってきて、このモチーフに何か先進性を足せると新しいものを生み出せるかもしれないと可能性を探り、そこから3D化したバルーンという表現に行き着きました。
LFAのロゴの「階段」のモチーフも使えればというところから、階段を上下だけではなく、色々な方向に広げたり、今回のサイトではコンテンツを上から下まで繋げるという役割も持たせました。
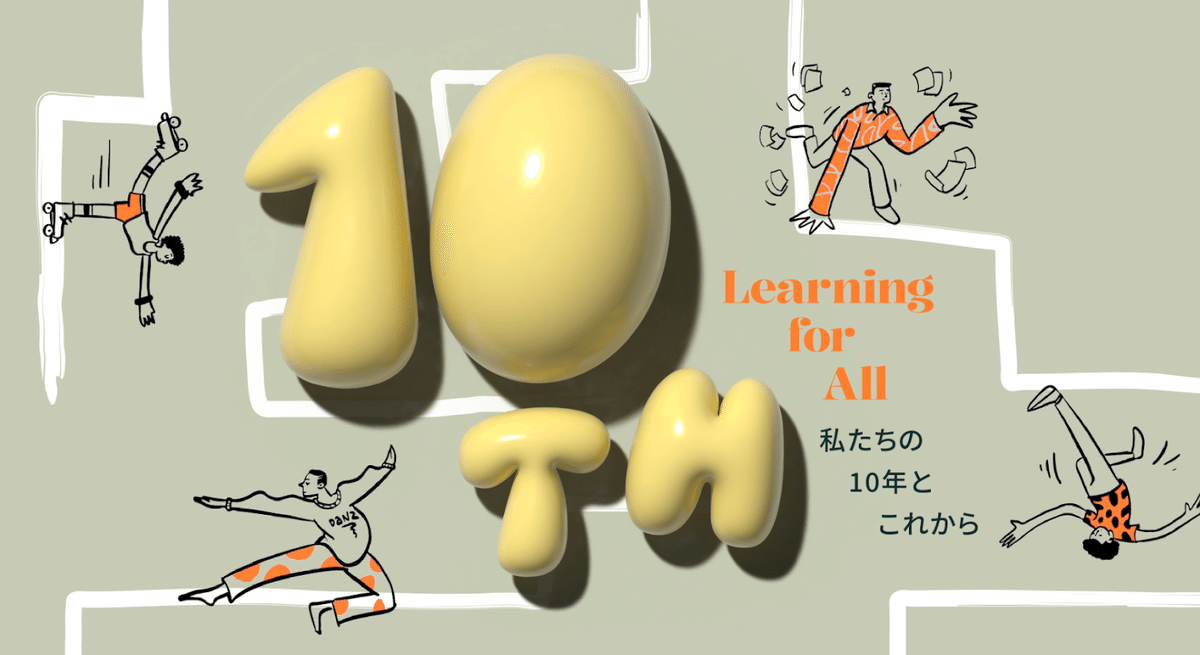
ロゴやデザインの方向性を定めるにあたっては、グッズ化したときにどう見えるかというものも最初から念頭に置いてました。グッズ化したらかわいいか、欲しくなるかという点も追求しましたね。
── カラフルなカラーリングやバルーンで作られたタイポグラフィ(文字)も印象的ですね。
山崎:あんまり日本にはない独特なカラーリングをしているので、どこまでやっていいのかというラインを定めるのに時間がかかりました。「祝祭感」と「真摯さ」の両極を行き来し、チームとも議論しながら保守的になりすぎないちょうどいいラインに落とし込めたことには満足しています。
カラーリングについては、LFAさんといくつかのパターン(LFAカラーのグリーン、パープルなど)をもとにディスカッションしながら絞り込んでいきました。最終的にはプロジェクトメンバーでの投票などを経て決定しましたね。
バルーンのタイポグラフィについても、東さんのディレクションがあってのことで、チームでやったからこそたどり着けたという印象です。また犬飼さんに入っていただいたおかげで、制約のある「Studio」を使いながらも絶妙な動きを実装できて良かったです。
寄付のボタンについても、圧を感じないように、あくまでも寄付をしたいと思ってくださった方に気持ちよく押してもらえるようなもの(ハート型のバルーン)になりましたね。
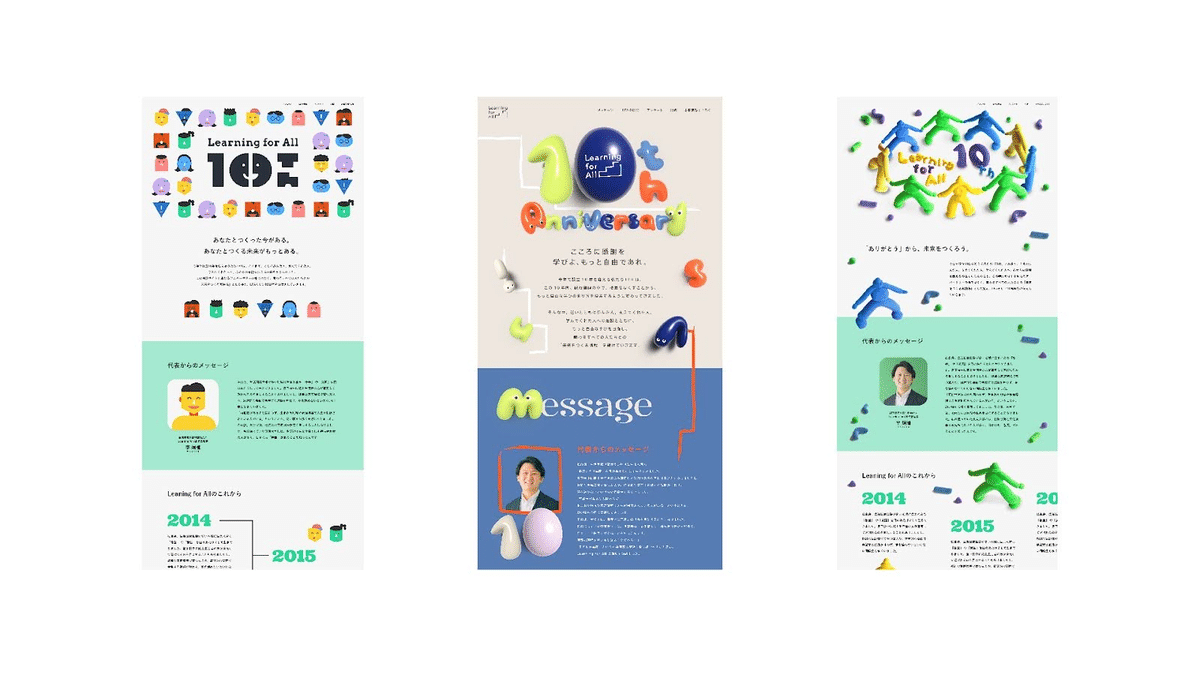
プロボノだから成り立つフラットな関係

── 制作において苦労した点はありましたか?
東:コンテンツの企画で少し時間がかかりましたね。デザインのトーンや実装の方向性は早い段階で固まりましたが、「何をどこまで公開するのか」というコンテンツ面の決定はギリギリまで調整が必要でした。LFAさんの内部でも、業務に加えて新たなプロジェクトを進める負担が大きかったのではないかと思います。
犬飼:そうですね。スケジュールを早めに切っていたので、進捗が見えない間はヒヤヒヤしました。
── NPOならではの課題として、通常業務もあるため人手が足りていなかったり、どこまでコンテンツ実行にコミットできるか判断しづらい、といった事情が影響していた部分はあったかと思います。
東:その事情も理解できます。あと、ミーティングでの雰囲気が良く、盛り上がって話せていた分、判断のラインを決めるのが難しいことがありました。LFAさんに判断を求めたいこともありつつ、LFAさん側が我々の意見を尊重してくれるのもあり。クリエイティブに関わるジャッジを誰が責任を持って決めるのか、という。
── 通常のクライアントワークと比べて、どのような違いがありましたか?
犬飼:私の場合、「仕事ではない」と思って取り組みました。これはお金をいただくクライアントワークではなく、ボランティアとして参加しているという意識が強かったです。だからこそ、フラットな姿勢で臨めることがやっぱり醍醐味でした。そのフラットな関係の中で「ここは違う」と意見を言うことも必要だと考え、今回はスケジュールや進め方も遠慮せずに提案しましたね。
東:通常のクライアントワークでは、時間や予算などしかるべき制約があることで、やるやらないの判断をしやすいこともありますが、今回のようなプロボノのプロジェクトではそうはいきません。社会課題に向き合うということで、「妥協せず理想を追求すべき」という考えが根底にあるので、どこまで自分の労力を割いて理想を追い求めるかは、関わるメンバーの意思に依る部分が大きい。
「全員がハッピーで関わり続けられるには」を念頭に、私が意思決定を担いながら、いい意味で妥協しない覚悟を持って進められたのが良かったですね。
犬飼:難しいですよね。会社としての関与範囲やLFAさんのやり方を考慮しつつ判断が必要でした。余談ですが、私は無償で案件を引き受けることがあります。「どうしてもお願いしたいけれどお金がない」と言われた場合、「払えないなら無償で」とする代わりに、お客様扱いはしないスタンスです。自分が「やりたい」と思える案件に限りますが、そうした関係でしか生まれない価値もあると感じています。今後もできる範囲で続けていきたいですね。
山崎:今回のプロジェクトでは「子どもの貧困」という社会課題への想いが支えになりました。タイポグラフィーやデザイン制作はハードワークでしたが、目の前の仕事の先にある「社会課題解決への貢献」を考えると自然と熱量が上がり、非常にハッピーに関われました。通常のクライアントワークでは得づらい資産になったと感じています。
東:インターブランド内部の事情になりますが、今回のようなプロボノのプロジェクトでは「潤沢に人をアサインする」という体制を敷くことはできません。リソースが決定的に足りないわけではないものの、各分野にスペシャリストを配置できないため、一人ひとりにジェネラリストとして幅広い役割を担ってもらう形になりました。企画やコーディング対応など本来は別担当が担う業務もデザイナーが対応することで守備範囲が広がり、メンバーのスキル向上につながったと感じています。結果として、成長とやりがいを得られるプロジェクトになったと思います。
いつも以上にケアし合うことで、うまくいく

── ボランティアやプロボノとして取り組むことに対するイメージと、実際にやってみた感覚の違いについて教えてください。
犬飼:ボランティアというと「奉仕」というイメージがありますが、私自身はデザイナーとして、仕事以外でもクリエイティブな活動を社会に還元するのは「やるべきこと」だと思っています。むしろ、NEWTOWNとしても取り組むべき課題であり、今回のプロジェクトはその良い機会でした。特別なことをしたという感覚はなく、自然な流れで取り組んだという印象です。
東:私たちもプロボノとしてこのプロジェクトを始めているので、「奉仕」というよりは、プロジェクトとして成り立たせることを意識していました。その意味でも、LFAさんとの間で期待値の調整は非常に大切でした。「この内容だと、想定していた業務範囲を超えてしまう」といった話を都度行い、お互いにフェアな形で進められたのではないかと思います。
山崎:インターブランドとしてプロボノの枠組みがあるのは非常にありがたいと感じています。私にとっては奉仕というよりも、自己成長や新しい可能性を探る場でもあるという捉え方でした。グーグルが行っているような「80%は利益を生むクライアントワーク、20%はR&Dや投資」という感覚に近いですね。
── プロボノやボランティアワークだからこそ、チームとして気をつけたほうがいい点は何でしょうか?
東:最初にプロジェクトの範囲を明確に定めることは非常に重要です。完全にドライに「ここまでしかやらない」と切り捨てるわけではありませんが、最低限の合意をもとに進めないと、最終的に双方にとって不健全な状態になることがあります。そのため、初めにしっかり話し合い、合意を得ることが大切です。
山崎:プレイヤーとして、特にデザイナーの立場では、自由度が高いゆえに悩む部分もありました。例えば、少し工夫するだけで「デザインが面白くなる」と思うと、つい追加の作業をしてしまうことがあります。通常のプロジェクトであれば追加費用が発生する部分ですが、「やってみたい」と思える範囲で動くことでチーム全体が喜ぶなら、やりたくなるのが正直なところです。この微妙な差し加減が、プロボノでは特に難しいですね。
── ボランティアやプロボノならではのチームのあり方については?
犬飼:東さんがおっしゃってたように、明確な分業体制が敷けるわけではなく、各自が幅広い範囲をカバーするので、普段のクライアントワーク以上にお互いを気遣い合う場面が多かったように感じます。
東:通常のクライアントワークでは、予算や契約が制約として守ってくれる部分もありますが、プロボノではそれがない分、相手(今回で言うLFA)と自分たちが、お互いにヘルシーに働けるよう、目配せをしながら進める必要があります。そのようにケアし合えるのは、やはり経験のあるメンバーがいるからこそだと思います。
デザインやクリエイティブが貢献できる、「社会課題の見える化」

──「社会課題×クリエイティブ・デザイン」の可能性や課題について、どのようにお感じですか?
山崎:今回、LFAさんからいただいた3つのキーワードが非常に重要で、特に「落ち着いた祝福感」を具体化するために試行錯誤しましたが、結果として既視感のない新しい表現ができたと思っています。
関連して、NPO法人の表現として「華美で派手に見えるデザイン」に見えないよう注意しました。絶妙なラインに落とし込めて、NPOとしての団体の立ち位置を損なうことなく、新たな一面を見せることができたのではないかと感じています。今回のケースをクリエイティブの力を活用した前進だと捉え、今後のさらなる発展に貢献していきたいです。
犬飼:おっしゃる通り、今回のようなプロジェクトでは「さじ加減」が非常に重要だと感じました。特に、魅力的に見えながらも「盛大にお金をかけている」ような印象を与えないようにする制約が難しいポイントでした。ただ、こうした制約の中でこそ、クリエイティブが力を発揮するのだと思います。
東:「社会課題」と「デザイン・クリエイティブ」のかけ合わせには、非常に大きな可能性があると感じています。特に海外では、デザインやクリエイティブが社会課題の解決に果たす役割や責任を強く自覚して取り組む例が多いです。一方、日本では一般的な社会課題へのリテラシーがそれほど高くない印象があります。社会問題が顕在化しづらい中で、デザインやクリエイティブがその課題を「見える化」し、その後の解決に向けたアクションを支える役割が大きいと思います。
まだまだ我々の仕事は山積みで、私たちクリエイターがもっと感度を高めていく必要があると感じています。これはデザインだけでなく、アートの分野でも同様です。アンテナを張り、意識を高めていくことで、社会課題解決に向けた取り組みをさらに広げていけるのではないでしょうか。
── インターブランドさんのプロボノ活動の意義についてはどうお考えですか?
犬飼:インターブランドさんのように、こうしたプロボノ活動を行うチームがあるのは素晴らしいことだと思います。課題に目を向けるきっかけが自然と提供されるのは、クリエイティブ業界で働く人たちにとって非常に有益ですし、こうした活動を通じて影響を受ける人も多いはずです。これは社内外において非常に意義のある取り組みだと思います。
東:社内における啓発も大切だと考えています。現状ではプロボノ活動が「非公認の部活動」のようになっている面もあるので、もっと積極的に社内外へ発信していく必要があります。例えば、今回のようなnoteでの発信は非常にありがたいですし、社内でのプレゼンテーションや外部メディアでの発信も強化していきたいですね。
実際、今回プロジェクトに参加しているデザイナーの澤田のように、プロボノ活動を知って入社を決めたメンバーもいます。こうした取り組みは、採用にもプラスになってくれます。
── 日本では「いいことは見えないところでやる」という美徳のようなも考え方もありますが、社会課題への取り組みを社内外に発信する重要性についてはどうお考えですか?
東:社会的意義のある活動をするだけでなく、そのことを発信することもまた重要な責務です。単にプロジェクトを成功させるだけでなく、その成果やプロセスを社内外に広めることで、より多くの人に知ってもらうことが大切だと思います。それが次のアクションや同様の活動につながるはずなので。
寄付やボランティアを、より日常的なものに

── 今回のプロジェクトを通じて学びや気づきがありましたか?
東:今回のプロジェクトで学んだのは、プロボノだからこそ遠慮せず、「こうすべき」と伝えることです。同様に、通常のクライアントワークでも、適切なタイミングで主張すべきだと気づきました。「お金をもらっているから遠慮する」というのは本質的ではありません。むしろ、フラットな関係で適切なスタンスで関わることが重要だと感じました。また、デザイナーたちが期待以上に頑張ってくれたことに感謝していますし、その自主性や能力の高さを実感しました。この経験を通常のプロジェクトにも活かしていきたいです。
山崎:プロジェクトにおいて制約や範囲を自分で決めすぎないことですね。また、自分の中で熱量を高められる対象を見つけることで、プロジェクトのより良い成果につなげられると感じました。今後もこの姿勢を大切にしていきたいです。
犬飼:僕の関わり方はローンチまでの数ヶ月と短期間だったので、なんとかやれたな、というのが正直な印象です。自分の会社なので、自分がやると決めてしまえばボランティアとして関われるものの、これを長期に渡って続けていくとなると、別のプロジェクトでの安定的な資金源と、安定的に関われるリソースの余白があって初めて成立する関わり方というか。うちのような小規模の会社では、持続的な関わり方も変わってきますね。無償だからほどほどのクオリティでいいというわけでもないし、お互いに気持ちよくやっていくためにはもっと考えないといけないことは多い気がします。今回は幸いにも上手くいきましたが、スケジュールはかなり綿密に引いて、それに沿って進行しないと、会社の収益源であるクライアントワークとの兼ね合いが難しくなります。ボランティアである分、スケジュールをクライアントワーク以上に余白を持っておくとか、稼動ボリュームも緩やかにしておくなど無理のないプロジェクトの設計が必要ですね。

── 今後、取り組んでみたいことはありますか?
東:LFAの10周年プロジェクトはまだイベントが控えています。昼間は子どもたちが楽しめる活動、夜は居酒屋形式の仕組みを取り入れるといったイベントのアイデアが話題になりました。実現に向けて協力してくれる酒造会社も見つかったので、もう一段話題性のある企画にしていきたいです。また、この10周年で終わりではなく、次年度以降も新しい取り組みを続けられたら良いなと思っています。
山崎:以前ミーティングの中で話に上がった「寄付していることを対外的に言いづらい」という日本の文化が非常に印象的でした。寄付やボランティアが日本ではまだハードルが高いという現状を変えるため、新しい寄付のあり方を模索することに興味を持っています。海外では、寄付やボランティアが文化として根付いていますが、日本でも市民権を得る形でこれらを浸透させることができれば、社会全体に大きな影響を与えられると思います。寄付やボランティアがより民主的に、より日常的なものになるような仕組みを作ることに挑戦してみたいですね。
犬飼:「デザインの寄付」という活動をしている同業者の方がいらっしゃるのですが、僕も年に1回は「デザインの寄付」をしていきたいなと思っています。依頼してくれるクライアント企業だけでなく、デザイナーが「社会にとって必要な存在」となっていくためには、このような活動は欠かせないですし、 デザイナーのこういう活動がもっと増えていくためのサンプルになれるといいですね。年1回やると、20年経てば、20団体をサポートできる。かなりのインパクトですよね。新しいスタッフも入ってきていますし、そういった人たちにもこういう活動をやってる姿は見せたいですよね。 僕だけじゃなくてやれるんならみんなやろうよって思うんです。 広げていかねば。
▼お知らせ:10周年記念グッズ発売開始



この10周年をみなさまとお祝いするにあたり、LFAのオリジナルグッズを制作しました。今回制作したオリジナルグッズは、これまで以上にLFAに愛着を持ってもらえたり、仲間としての一体感を感じてもらえたり、日常の中で子どもたちやLFAのことを思い出してもらう。またこのグッズを通して、「子どもの貧困問題」について考えたり、話題にしたり。そんな風に応援してもらえるきっかけになるといいな、という願いを込め、何度も話し合いながらこだわり抜き、つくりました。私たちの想いがたっぷり詰まったグッズをぜひご覧ください!(収益は子どもたちの未来を創るために必要な支援や取組に対して使われます)
(構成・文:鎌田宏史、写真:澤田智穂)
