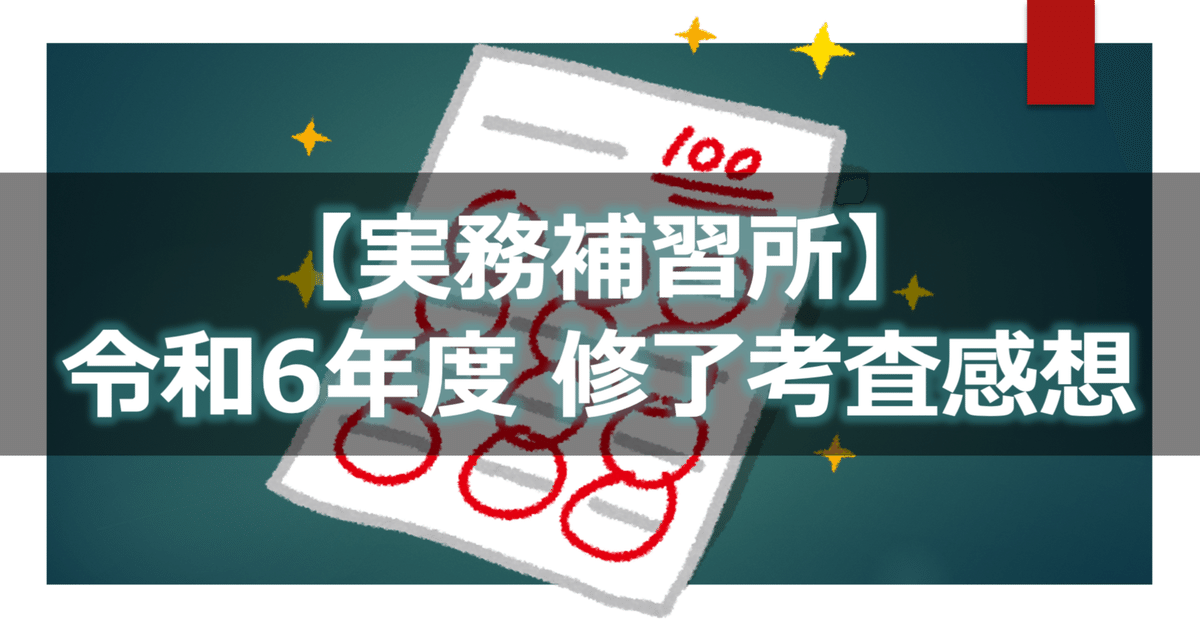
【実務補習所】令和6年度 修了考査感想
こんにちは!
最近更新できておらずすみません…
先日、修了考査を受けてきたのですが、ここ最近はその対策で手一杯だったのです…
ということで、せっかく頑張ったし、(順当にいけば)もう二度と経験できないことだし、記憶が新しいうちに感想でも書こうかなと思いました!
(これから修了考査受ける方にとっては参考になるかも??)
受験された方は、共感する点などあったらコメントでも頂けると嬉しいです〜〜!
会計実務
第一問
大問の前提情報ページには、企業集団の組織概要図がデカデカと載っていたので、「やっぱりまずは連結だよね〜」と考えながら解き進めたところ、個々の問題で問われている論点としては、企業集団をさほど意識する必要がない問題だけで構成され、全部解き終わった後に「で、最初の情報はどこかで使ったっけ?てかあれ使った?」と頭に???が浮かんでいました。
出来としては、ヘッジの仕訳問題は仕訳の形をド忘れしてしまったので全外しでしたが、他は計算・理論どちらも概ね良く出来たかなと思います。
第二問
分配可能額が出ましたね。2022年にあったニデックの分配可能額規制違反が話題になりましたが、トピックとして出題した感じでしょうか。もちろん外しました、ほとんどみんな解けてないと思います。笑
第一問に引き続き、計算・理論どちらも概ね良く出来たかなと思います。
総評
予備校テキストでは重要論点として挙げられる、税効果・リース・減損などは出ませんでしたね。「リースはもう変わる基準なんだから今あえて日本基準の処理は問わないっしょ」と密かに思ってたのですが、試験委員の先生方も同じように考えてくれていたのかもしれません。
出題論点に関連してもう一つ思ったのは、連結精算表や仕訳ベースで問う連結処理、会計方針の変更に伴う注記文案、関連当事者、セグメントなど、まさに監査法人J3くらいが担当するであろう"実務"に沿った出題だったなと思いました。実務とのリンクを感じた方も多いのでは無いでしょうか。これは分かっとけよ〜という試験委員の先生方の気持ちがヒシヒシと伝わりました。笑
わたしも過去に担当した経験があったのでその経験を生かせた部分がありました。普段、仕事頑張っててよかった〜〜!
個人的には良い試験問題だと思いました!
監査実務
第三問
会計上の見積り、固有リスク要因、イメージ文章、ITの利用から生じるリスクなんかが出題されました。いずれも重要論点からの出題で、解きやすいなと感じました。
第四問
監査の計画から完了段階まで広く問われました。事例問題は与えられた情報にヒントが散りばめられているので、じっくり読めば何かしら作文できたのではないかなと思います。
総評
しっかり対策された方にとっては、なかなか手応えを感じられるような問題だったのではないでしょうか。
監査も会計と同じく、監査法人J3ならこれくらいはわかっていてほしいという試験委員の先生方からのメッセージのようにも思います。
あと、監基報の丸暗記問題の比率が少なく解きやすかったです。文章を一語一句暗記することに何の意味もないと思っていたので、是非これからもこの傾向が続いてほしいですね。
監査も個人的には良い試験問題だと思いました!
税務実務
第五問
法人税別表四の総合問題トラップ「同額なら処分欄を○」が話題ですね。わたしは本番直前に令和5年の過去問を解いており、「○で出すパターンあるんだ〜」という認識があったため、無事指示に気付けたので○にできましたが、数値書いてしまった人は結構多いみたいですね。
CPAの税務実務の答練で○で出す回が一回もなかったので、もし令和5年と同じ形式だったら、指示見落とす人いるだろうなとは思っていましたが、悪い予感が的中してしまいました。CPAは○で出す答練回を作るべきだったと思いますよ…
現実の別表四は金額を記入するので、金額記入する方がリアルではあるのですが、「金額が間違ってても、区分を正しいものに出来たかどうかで部分点をあげられるようにしよう」という受験生のための指示だと思います、多分。指示に従わなかったのが、どういう取り扱いになるかは不明ですが、まあそこまで悪いようにはされないと思います。実務能力を測る試験ですから、白紙と同じ点数なわけないと思いますよ。
これから受験する方は、問題文はよく読むことを意識しましょう!
消費税については、総合問題がなくなりました。これは良い変化だと思いました。仕入税額控除の集計をひとつでも間違えたら半分落として、何もわからない受験生と同じ点数っていうのはあまりに不当だと思うので、こうなってよかったと思います。とはいえ個々の小問もなかなか難しくはありましたが…
最後の問題も癖ありましたね。固定資産税って書きましたが、固定資産税ってそもそも出題範囲でしたっけ…?笑
ちらっと聞いた話では、所得税の源泉所得税が正解なのではという話もあります。
まあ終わったしなんでもいっか〜〜
第六問
グループ通算の計算問題が出て、ちょっとびっくりでした。講義や答練では「まあ出来なくてもええよ〜」ってニュアンスでしたが、復習しておいてよかったです。
相続税は少々難しかったです。わたしは例の退職金の非課税枠の1,500万円は抑えていたのに、生前贈与加算対象の上場株式の相続税評価額を間違えて相続時の時価にしてしまい、課税価格以下全滅です。相続税総額が20百万円になった時は「綺麗な数字キタコレ」と思っていたのですが油断しました。バカですね。まあでも計算式書かせる形式なので、部分点はもらえるのではないかなと期待しています…
総評
一番大きく傾向が変わったのが税務実務ですね。別表一や消費税のクソゲー感のある出題形式がなくなったのは、良い変化だと思いますが、今後受験される方にとっては少し対策が立てづらくなったのかなと思います。しっかり時間をかけてヤマを張らずに勉強すること、他の税目との関連など含めて包括的な理解が求められているのかなと思いました。
経営実務
第七問
付加価値はどれ書けばよかったんですかね。賃借料、金融費用、租税公課、減価償却費の4つが候補で3つしか枠なかったので迷いましたが、後の問題との兼ね合いや費用の性質の違いなどから考えて、なんとなく減価償却費以外の3つを書いておきました。
その他、経営指標の計算は簡単でしたね。あれは記述問題の作文クオリティで決まるのかなと思います。それなりに良いこと書けたと思うのですが、どういう結果になるかは不明です…
第八問
経営のITは難しかったです。システム監査技術者の午後1の試験にちょっと似ているかな?と思いました。あちらと違ってこちらは字数制限が細かく定まっていないのが助かります。
仕掛品過大計上のシステム不備の事例問題は、指摘すべき事項が明らかで作文しやすかったので、まあまあ良い出来かなと思います。ここで稼ぎたいところです。
総評
まあまあ出来たんじゃないかなと思います。特筆することはないです!
職業倫理
第九問
公認会計士法で定められた一項二項業務・協会の役割、品質管理レビュー、審査会名称など、予備校ノーマークの論点が出ましたね。穴埋め・単語はほとんど落としました。腹たつ〜〜
記述問題と前半の倫理規則で点稼いで、なんとか耐えてくれ〜〜という気持ちです。
品質管理レビューと審査会名称は、確かいつかの考査で出たところだったので、考査チラ見しておけば…と悔やまれます。まあでもそこまで対策の手を広げていたら変態です。無理ですね。
第十問
一転して、こちらはストレートな出題でした。ただ、家族と近親者の定義は大外ししました。(それ、修了考査で出すほどのことなんですかね?)
まあでも良い点取れてると思います!
総評
前半はちょっと変わった出題でしたが、ちゃんと勉強していれば後半で稼げるので、みなさん足切りはないんじゃないかなと思います。
きっと来年から職業倫理のテキストは分厚くなりますね…
さいごに
色々ありましたが、手応え的にはなんとかなってると信じてます。割と自信ありです。
受験生のみなさんは4月の合格発表まではモヤモヤが続きますが、忘年会でたくさんお酒を飲んで、美味しいものを食べて、目一杯はしゃいで、全て忘れましょう。
以上、最後まで読んでくださりありがとうございました!
