
やみくもに過去問を解くだけじゃ得点は上がらない
■一番実力が付く教採対策法は過去問分析だけど…
ものすごく久々の更新となってしまいました。ごめんなさい。
突然ですが、皆さんは一番力がつく教採対策って何かご存知でしょうか。この答えは、古今東西、いにしえより「過去問」だと言われています。
でも、過去問は、めちゃくちゃたくさんあります。闇雲に手を付けていっても、志望自治体では出ないタイプの問題もあったりするので、時間ばかりが過ぎていってしまいます。
ですから、志望自治体の過去5年分くらいの出題分析をして、よく出る問題だけを解いていくのが、対策のコツです。
その際に、めちゃくちゃ役立つのが、この2つの組み合わせです。
①『月刊教員養成セミナー2月号』に載っている「全国出題頻度表(教職教養)」×②2024年度版『教職教養の過去問』(時事通信社)
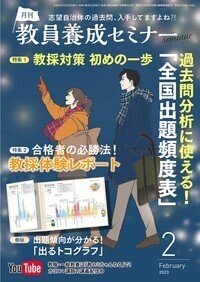
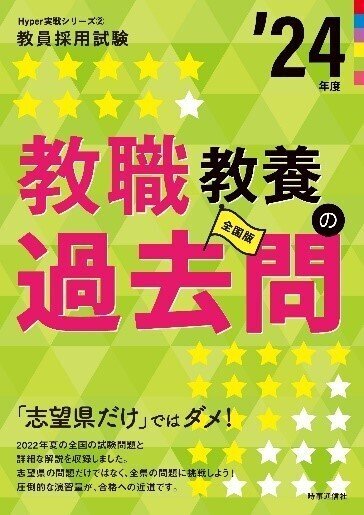
どのように使うのか、順を追ってご説明します。
■STEP1 「頻度表」から志望自治体の類題が出た自治体を特定
例えば、志望自治体が東京都の場合、「指導要録の作成」や「表簿の保存期間」に関する出題が多いことが分かるので、東京都以外の自治体の類題を演習したいところです。
頻度表のマスに「5」と示されている自治体では、令和5年度に該当事項の出題があったことを示しています。「指導要録の作成」については、宮城県、神戸市、香川県、佐賀県、熊本市、大分県で出題があったことが分かります。

■STEP2 「頻度表」に対応した2024年度版『教職教養の過去問』で類題演習
2024年度版『教職教養の過去問』には、令和5年度の全国の教職教養の試験問題が掲載されているので、マスに「5」がある自治体の問題を演習することができます。
例えば、東京都は、問題形式が正誤問題なので、同じ正誤問題形式の「宮城県・仙台市」が大いに参考になります。
【宮城県・仙台市の問題】

【東京都の問題】

■STEP3 『教職教養の過去問』の詳しい解答・解説でポイントを押さえていく
実は過去問は解くだけでなく、「解答・解説」を読んでいくことで、知識を確実に増やしていくことができます。『教職教養の過去問』は分厚い解答解説がついているので、これらを読んで、ポイントを整理していきましょう。
【宮城県・仙台市の解答・解説】

【東京都の解答・解説】

