
自作三味線【胴】
自作三味線の【胴】部分の作り方紹介になります。
三味線【全体】見取図はこちら↓
三味線【胴】図面はこちら↓
【材料】
・木材(檜材) 600×9×60 2ヶ
・シナベニヤ 600×300×4
・木工用ボンド
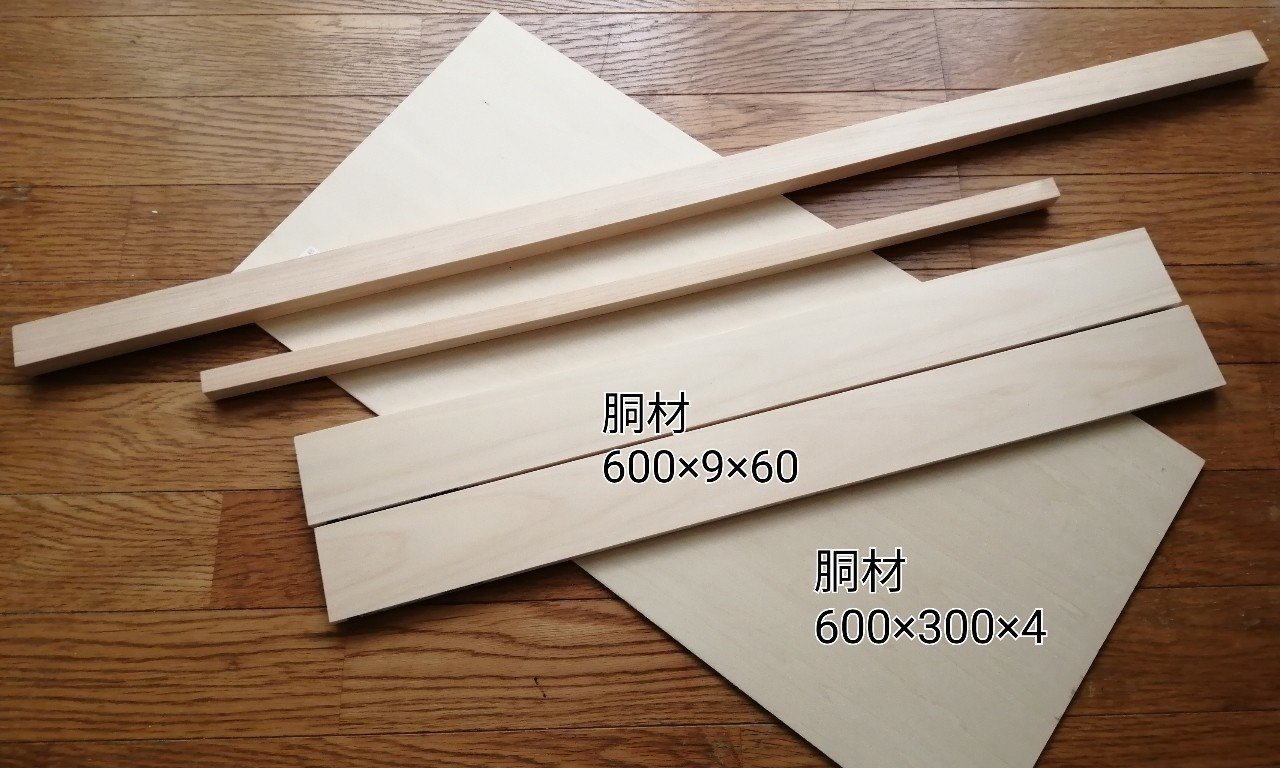
【工程】
1、メインカット(側面)
(サイズは図面を参考にしてください)
・木材(C)を202ミリにカット(2枚)
・木材(C)を156ミリにカット(2枚)

2、メインカット(上下面)
・202×174ミリにカット(2枚)

3、棹通し穴あけ
・156ミリカットした方の板に墨を入れる
(穴のサイズは30×9ミリ)
(位置は横が63-30-63ミリ、上から5ミリです)

(間違えて202ミリに書いてしまった写真)
・線の内側にドリルで穴をさらっていく
(この工程を行った方が圧倒的に楽です)

(写真は棹なので、参考までに)
・彫刻刀などで大まかに穴をさらってから、サイズに合わせ微調整して削っていく。

4、音抜け穴あけ
・上部になるベニアに音が抜ける穴をあけます。
今回は無意味にこだわり太陽の形にしましたが、丸でも四角でもなんでも大丈夫です。
(上記同様にドリルでさらい穴を開けます)


5、箱形成
・カットした板をボンドで張り合わせて箱をつくって行きます。
(今回は輪ゴムで絞めてますが、バイスがある方はその方が良いと思います)

(今回は上部のベニアだけ後回しにしました)
6、面取り
・全方向の角をやすります。
・四方の縦角に丸みをだします。
(板の厚みを抜かないように注意しましょう)

【胴の完成】

この説明は【胴】だけを作る工程になりますので、全体を作っていく流れは後日アップします。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
少しでも参考になれば幸いです。
総合的な制作の流れをまとめた【0知識からの三味線作り】はこちらから↓
