
教員採用試験の二次試験結果の受け止め方の一案(ハロー効果)
令和6年度の教員採用試験。
秋期募集はこれから試験ですが、その他は二次試験の結果も発表されていると思います。
結果発表までの時間は、とても長く感じられたことでしょう。
教員採用試験では、多くの自治体が二次試験に面接や模擬授業、場面指導などを取り入れています。
そのためか、二次試験で合格とならなかった場合、先生に向いていないのかも、と思ってしまう方もいらっしゃるようです。
今回は、自分の評価が低くみられたかもしれないと思ったときに思い出してみてほしい「ハロー効果」について、お話したいと思います。
ハロー効果とは
評価の際、別の側面が影響し、評価の方向が傾いてしまうことを「ハロー効果」といいます。
たとえば、
偏差値の高い大学出身だから高得点をとるだろう
陸上部だからマラソンは得意なはず
料理上手だからきっと食べることも好きだ
などです。また、
前回失敗したから、今回も失敗するだろう
汚れた服を着ているからだらしないと思う
笑顔が少ないから暗い性格のはず
というマイナスなイメージの場合もあります。
よいイメージをもつとさらによいイメージを
悪いイメージをもつとさらに悪いイメージを
このような捉え方をする現象の、実証的な研究をしたのがソーンダイクです。
ハロー効果の「ハロー」とは
太陽や月に薄い雲がかかると、その周りに光の輪が現れます。
この大気光学現象のひとつがhalo(ハロー)です。トップ画像にしたこれ↓ですね。

天使の絵などにも光の輪が描かれます。
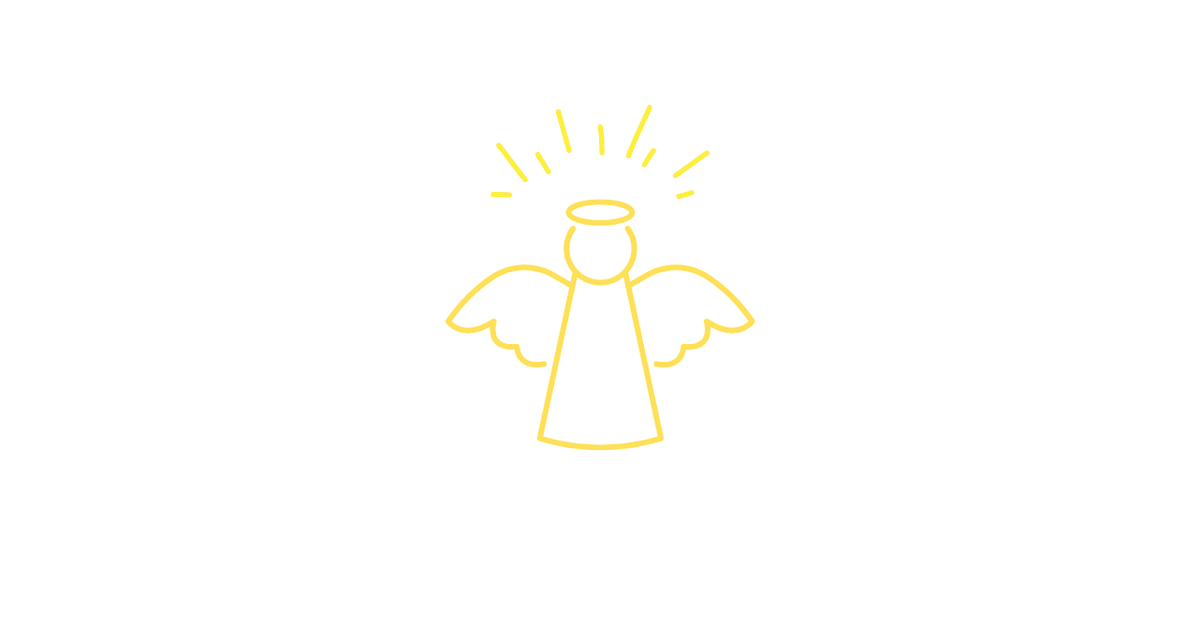
ハロー効果は英語表記「halo effect」から「ハロー」の意味を読みとると理解しやすいです。
ハロー効果は、よくも悪くも、光の輪が広がってしまう状況です。
面接官にハロー効果があったかも?
人が人をみているわけですから、面接官にハロー効果がなかったということは言い切れません。
ハロー効果があったかもしれない。
なぜなら、人はそれぞれ「自分のめがね」をかけているからです。
どんなに公平にといっても、それぞれ生きてきた過程が違うのですから、「めがね」は違っているのは当然だからです。
だからこそ、評価基準があり、それに沿って評価しているといえます。
ハロー効果を意識すること
面接対策で、服装や髪型、言葉づかいなどをそれぞれの職種にあったように整えるのも、このハロー効果を意識してのこと。
好印象を与えるようにというのは、教員採用試験でいえば、
言葉づかいがていねい→保護者対応も上手にできそうだ
笑顔が多い→子どもたちに好かれそうだ
そういったイメージをもってもらうということです。
この記事のまとめ
教員採用試験の二次試験で、合格とならなかったとしても、このハロー効果がよい方向に働かなかっただけかもしれません。
面接開始前に飲んだコーヒーを胸元にこぼしていたけれど気づかなかったのをみて、ハロー効果で低評価をした面接官の方がいたのかもしれません。
ほんの些細なことが、自分の気づかなかった小さなことが、面接官の何かに引っかかる。
それはありえないとも、面接官が悪いとも言い切れない。全ての人が違う「自分のめがね」を持っているのだから。
それが面接だと私は感じています。
教員採用試験に限ったことではありません。
私は年齢的にも、いろいろなことを経験してきたからかもしれませんが、物事は「流れにまかせること」で、よい方向に進むことがあると感じています。
なので、今回の教員採用試験が合格ではなかったとしても、教員に向いていないとは思わず、なりたい気持ちを大切にしてほしいと思っています。
教員の仕事については、いろいろ言われることもありますが、なってみなければわからないことは、きっとたくさんあると思います。
私は教員になってよかったと思っています。
きれいごとに聞こえるかもしれませんが、「教員になりたい」気持ちをこれからも応援したいです。
いいなと思ったら応援しよう!

