
映画を観たような、朗読劇~最終章
前半はこちら
高橋一生の肺に吸い込まれた空気が、彼の声帯を通り抜け、ピンと張りつめた会場を一瞬で溶かした。
空気の振動はさざ波となり、会場の数百のため息とともに私の内耳を揺らした。私は息をのみ、甘美なその振動に身を任せた。
朗読劇は始まっていた。
待田健一「どなたか知りませんが、ちょっとお聞きします。こういうのスパムメールというんですよね。こんなので騙される人いるんですか。」
甘さを押し殺した彼のナマ声が私を包む。
ああ、もうどうなってもいい。
耳から鼻血が吹き出しそうだ。
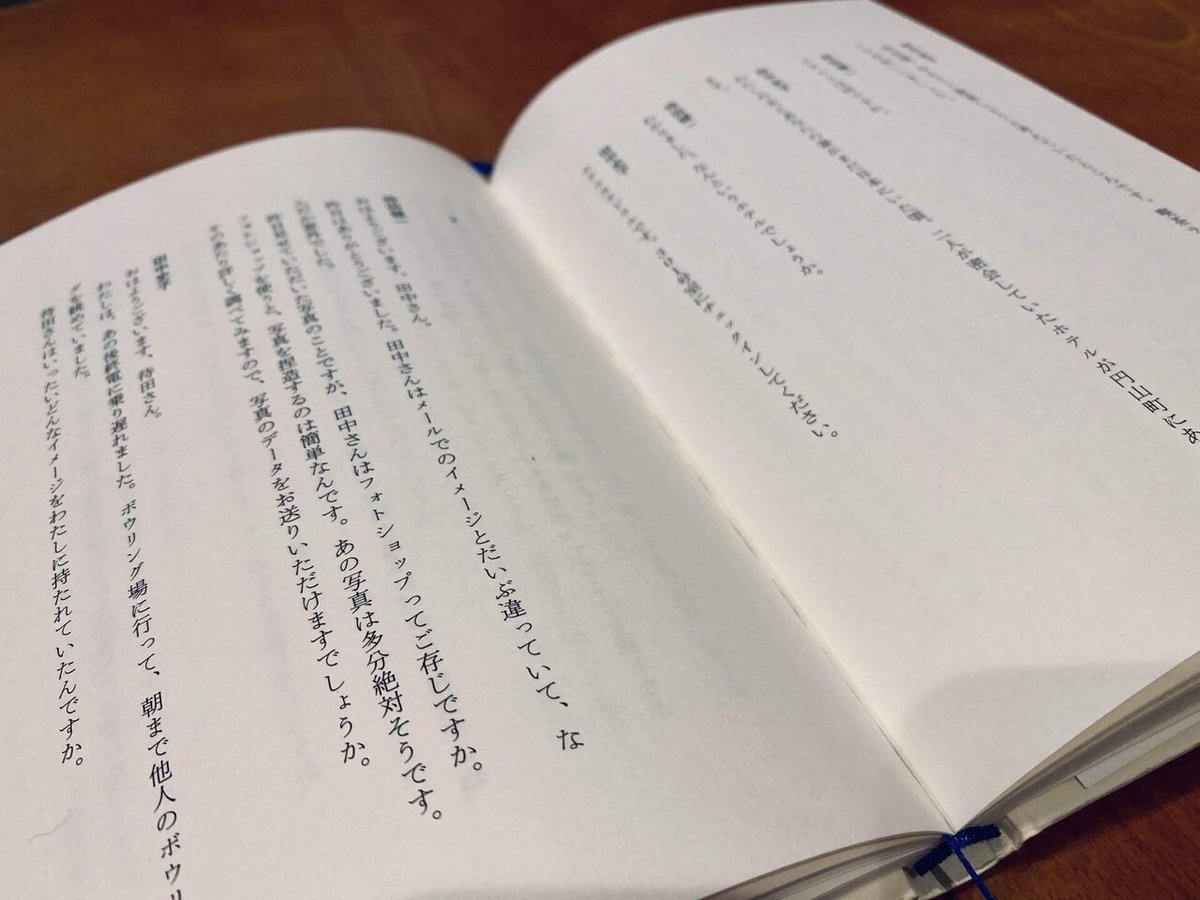
その物語は、妻を亡くして失意に暮れる高橋一生演じる待田健一が、一通のメールを受け取ることから始まった。
高橋一生の、いや待田健一の妻・幸菜は、地雷除去のボランティアをするとアフリカに向かい、その数カ月後に行方不明となっていた。ある日外務省から彼に連絡が入る。幸菜は、武装集団に襲われ少年兵の持つ自動小銃カラシニコフで撃たれ、死んだ、と伝えられていた。

メールの送り主・田中史子を演じる酒井若菜の淡々とした口調が、この先に潜む静かな不安を彩る。
田中史子は、メールでこんな不穏な発言をするのだ。
「待田さん、あなたの妻は生きています。アフリカの地でわたしの夫と一緒に暮らしています。」と。
初めは疑心暗鬼だったふたりも、やがて今や生死もしれない失踪した妻・夫が「密会していたホテル」で会うことになる。
そして、その日を境に、二人がやりとりするメールの敬称は、「様」から「さん」に変わるのだ。

舞台の上には、二客のソファ。ソファの横には小さなテーブルがあって、ペットボトルに入った水が置かれていた。その他そこに存在するのは二人の俳優だけだ。照明は、ソファに掛けたまま口元しか動かない俳優を、暗闇にぼんやりと映し出す。私は、彼らが吸う息の音を耳で追い続けた。
もはや、座席が後ろから5列目だということは、どうでもよかった。
彼と彼女の息遣い、セリフが終わらぬうちに被せてくる呼吸。私は、彼らの喉元から漏れ溢れ出る湿った吐息を、ひとつも漏らさず呑み込もうとした。

セリフが吐息に変わり、吐息は無言の間を生む。待田の畳みかけるように続く独白は、渋谷の不透明な街角を語る。スクランブル交差点の雑踏から逃れ、横道にそれたところにある「名曲喫茶ライオン」、そこから続く坂道を進んだ先のラブホテル街。そして進む先が見えない不安を、あの高橋一生の声が、焦りと不安を抱きしめたまま語り続けた。

私は、いつしか映画を観ているような錯覚に陥っていた。
高橋一生は、もはや待田健一でしかなくなった。それでも物語は、田中史子の不安と執拗な愛着をからめて進む。そして、彼らが独り抱え込んできた不安が、渋谷の雑踏にまみれ少しずつ二人の中で同化してゆく。彼らの声は、ゆっくりと柔らかくなり、気づかぬうちにねっとりとした甘さを加え、互いに絡み合い溶けあってゆく。

拍手が沸き上がった。
私は目をあげ、あわてて手を打った。
スポットライトが、静かにソファから立ち上が高橋一生を照らし出していた。
ああ、終わったのか。
私は頭の中でまだ繰り返される映像の切れ端と、舞台の上で照れたように微笑む彼をぼんやりと観ていた。
万雷の拍手は鳴りやまず、カーテンコールは4回を超えただろうか。
酒井若菜がぴょこんと小さく跳ね、彼の腕を取って目を合わせ可愛らしく笑って一礼した。
嫉妬が私の目を覚まさせた。
どのくらいの時間あの椅子に座っていたのだろう。
楽しみに恋焦がれていた舞台は、遠く目の前で腕を組み去ってゆく二人を前に、幕を下ろした。

the end.
