真夜中の疾走
「妹が危篤!」
その電話が妻に掛かってきて、私たちは孫のバスケの応援を中断して一旦、家に戻った。
妹が住んでいるのは東北の地方都市だ。こっちは北海道の真ん中。
直線距離ではそう遠くないが、交通の便が良くない。
飛行機は小型のジェット機(74席)が、日に2便。今からではキャンセル待ちだという。
鉄道路線は乗り継ぎの連続になる。新幹線は函館までしか来ていない。
自分の車で行くことにした。
高速道路を使っても函館のフェリー埠頭までは6時間くらいかかる。
夕方出発したが、途中休み休み行ったので埠頭に着いたのは真夜中を回っていた。車をフェリーに積み込んで一般客室に入る。

ざこ寝の部屋だったが乗客がまばらで、妻と二人でそれぞれ毛布を広げて仮眠することができた。
青森港までは3時間40分を波に揺られていく。
青森埠頭に着いたのはまだ夜明け前だ。すぐ高速道に乗る。
ゆっくりと静かに夜が明けていく静寂の中で、エンジンの振動だけがハンドルを通して身体に心地よく響いてくる。
(Photo by knk_since2019)
目的地に着いたのは朝8時前だった。
ここは妻の実家だ。危篤なのは妻の妹。
実家のあとを継いで妹は子供たちと暮らしていた。夫は昨年に急逝している。
危篤の電話をかけてきたのは長男だった。
その長男のお嫁さんはお腹が高く臨月を迎えている。
脳外科病院に駆けつけて、ICUに入っている妹に会った。
酸素マスクを充てられて、身体には点滴や心電計の管が絡まるように取り巻いている。危篤の電話がかかってきたとき、心臓が一時停止したという。
息を吹き返したが意識不明であった。
しかし、今は妹の意識が戻っていた。
妻の呼びかけに応えようとして口を動かすが、うまく聞き取れない。

妹は20年前に脳内出血を起こしている。以来、半身の麻痺が残ってリハビリを続けていた。近年になって腎臓を壊し、人工透析を週3回していた。
今回は癲癇と心臓の異常だったらしい。妹の身体は見た目にもぼろぼろだった。
次の日。
妹は妻の呼びかけに、はっきりと応え始めた。
「遠くからよく来たね。のどが渇いたわ。カルピスはないかしら?」
妻は安どした。ベッドを取り囲んでいた子供たちも安どしていた。
医者は「脳に異常はないので、この先は各課が揃っている総合病院に転院するのが良いでしょう。いま調整を図っているところです」
その午後に、妻とわたしは病院をあとにして北海道の自宅に向けて舵を切った。
妹のことは子供たちに任せることにした。
何日か滞在したい気持ちはあったが、わたしの抗がん剤投与日が迫っていた。

遅らせることはできる。しかし、それだけ癌をたたく機会を失うことになる。それでなくとも、副作用で下痢とだるさで辛くなり、血液の主要な数値が下がり過ぎて、毎週の投与が隔週に変更されたのだ。
わたしの身体も、言わば危篤状態である。
翌日の昼。
昼夜を飛ばして自宅に着いた。
さすがに疲れた。私の身体がよく持ってくれたと思う。出発するときはどこかで挫折するかもしれないと思っていた。
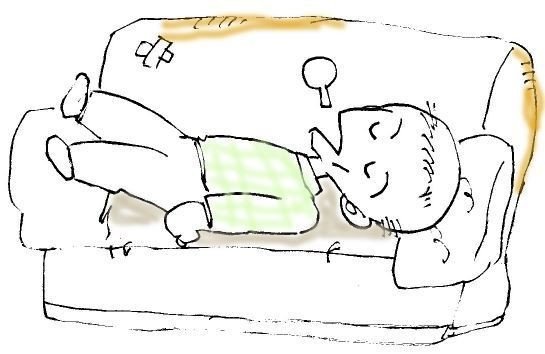
そのときはその時で仕方がないだろう、と考えてハンドルを握っていた。

