
一人の作家の、再生の原点――『ブッダその人へ』
「私は自分自身の避けられない死に際しても、できるだけ明晰でありたいと願う。死はどうやっても逃れられないのだから、逃れようとせず、悠揚として受け入れたい。ブッダのように生きて死にたいというのが古今の仏教徒の究極の理想だが、死を人生の法(ダルマ)として受容できる境地にせめて到達したい。それは充分に可能なのである。なぜなら、ブッダがすでに生きて死んでみせてくれたからである」
本書の書名が意味するところ、執筆にあたって著者が思い描いていたことは、この一文からおおむね察せられます。ブッダのように生き、ブッダのように死んでいく、そのような人生を歩むための方途を求めてインドへ向かったその旅の記録、それが本書です。
『ブッダ最後の旅─大パリニッバーナ経』(岩波文庫)をたよりに、ブッダその人が自身の死を見据えて歩いた道をたどり……。ただ、そう聞くと、よくある紀行文のたぐいだと思う人が多いかもしれません。立松和平といえば、国内外を問わず、そして海といわず川といわず、山といわず里といわず、しじゅう世界中を旅して歩いては綴り、綴ってはまた旅に出て思索を深め、そうして物語を紡いだ作家だったからです。ことに、しばしばテレビ番組で見せた旅先からのリポートの、あの朴訥とした口調を覚えている人ならば、のんびり、ほのぼのとしたインド旅行記を想うかもしれません。
けれども、そうではないのです。いや、正確にいえば、そうであったかもしれなかったのだけれど、そうではなくなった切実な理由がそこにはあるのです。

なぜ、そうではなくなったのかというと、出発予定日のおよそ2か月前に、取材旅行そのものが危ぶまれる出来事が起きたからです。立松和平さんはそのとき、取材の旅をとりやめる可能性を示しつつも、しばらく結論を待ってほしいと私に告げました。
事態は深刻でした。立松さんの著作をめぐるその出来事は容易に解決のつく問題とはとても思えず、テレビ番組の地方取材やコメンテーターとしても人気のあった作家に対して、またたくまのうちに世間からの強い逆風が吹きはじめました。
出発予定日の1か月前になっても、2週間前になっても、取材に向かうかどうか、行くことができるのかどうかが決まりません。世間の興味が少しずつ薄れて騒動が沈静化してきてはいても、さまざまな事情が立松さんの不在を許さなかったのだろうと思います。
ただ、いつゴーサインが出るかもしれず、私としては取材に向かう準備を怠るわけにはいきません。そのような状況で旅行代理店との打ち合わせも予定どおりの出発を前提にすすめるなか、残りはあと1週間、6日、5日……出発予定日はどんどん迫ってきます。

結論を先にいえば、出発予定の前日、しかも夜になって、立松さんから「明日はインドに行きます」という連絡が届きます。しかし、翌早朝、成田で合流した立松さんはじつに言葉少なで、以前の、快活で人を和ませる笑顔もそこにはなく、憔悴の色が全身からにじみ出ていました。
そもそもは、それより半年ほど前、タクシーの中で「立松さん、インドに行きませんか」「うん、行こう」というほどの、ごく短いやりとりにはじまった取材の旅です。ゴータマ・ブッダが歩いたインドの大地をめぐり、その人と教えに迫ろうという意図ではあっても、人生を深く見つめる旅にしようなどとは、私も著者である立松さんも思ってはいませんでした。それが、時のめぐりあわせで思わぬ方向に向かったのです。
当時のメモに、インドへ向かう機中で立松さんがつぶやくように口にした言葉が残っています。
「10年前の生活に戻ろうと思う」
ここには、いくつもの意味が重ねられていると思いますが、テレビタレントのような活躍によって得たもの、失ったもの、そして自分の身に起きたこと、起こしてしまったことの一切合切をきちんと受けとめ、新たな自分との出会いを期してインドに向かったことだけは間違いありません。

出発当日、私は「立松さんにとって、この旅は仏の慈悲そのものではないだろうか」と書き記しています。たしかにあの旅は、ブッダの慈悲に包まれたかのように終始、静謐なものでした。浮かれた気分などみじんも感じさせることなく、自己のあり方を深く見つめ直す作家の姿があるばかりでした。

移動の車中であれ、就寝前のベッドであれ、暇さえあれば持参した岩波文庫に目を落とし、ブッダの言葉を追い、自分の生き方、人の生と死、そして救いのありかを見きわめて自分のものにしようと、懸命に心を耕す。そうしてブッダの足跡をたどりながら、その教えが、その言葉が、立松さんの心を慰め、癒し、そしてまた内省をうながすのです。
一人の作家の、再生の原点──それが、この『ブッダその人へ』です。生きるうえでおかしたもろもろの罪と向きあい、ブッダその人と向きあう。そのことで、再生に向けての道すじをつかんでいく旅は、私たち一人ひとりの人生における抜き差しならないことがらとしても、また強く胸に迫ります。
インドという聖なる土地で、自身の死を受け入れたブッダの足跡を追うなかで、作家はどのように仏と対峙し、再生に向けた一歩を踏みだそうとしたのか。この一つの真実から、私たちは何を知り、生きる力を得ることになるでしょうか。

出発前、さまざまな心配事を理由にインド行をためらう立松さんの背中を押したのは、立松さんの奥さまでした。「未来のことを考えなさい」と励まし、「だからインドに行くべき」と強く後押ししてくれたのだそうです。
ブッダの慈悲は、いちばん身近なところで、あたかも観音菩薩が救いの手を差し伸べるかのように、力強く立松さんを包みこみ、はたらいていたということを思います。それはまた、私たちが気づきさえすれば、いつでも等しくはたらいている深い慈悲でもあると、私は信じています。
担当編集者 樹山隆司
********
『ブッダその人へ』 立松和平・著
〇ご購入はこちら
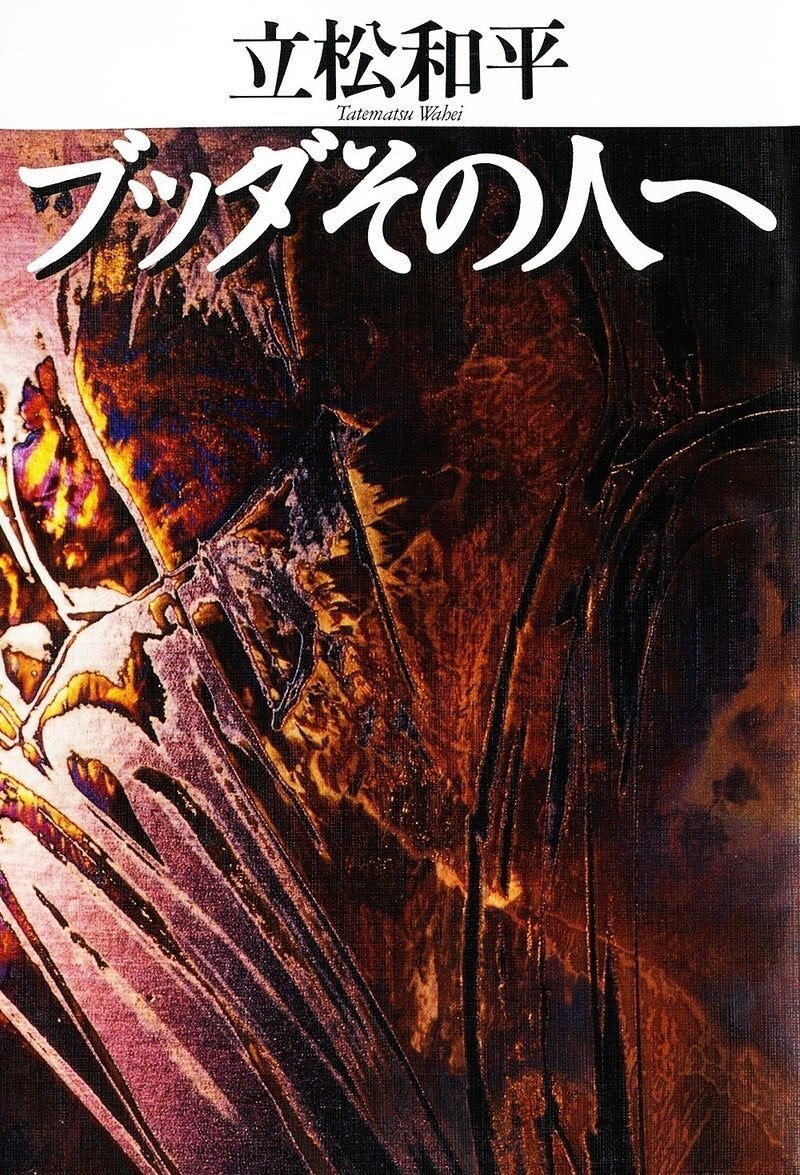
作品紹介
現代の「遊行者」を志願した苦悩の青春時代から20余年。今、運命の時を与えられた作家がとらえたブッダの生と死への歩み。インドの地に立ち、その普遍的な生き方を説く。現代人への救いの道標となる書。
立松和平
1947年、宇都宮市生まれ。
80年に『遠雷』で第2回野間文芸新人賞を受賞する。86年、アジア・アフリカ作家会議より「若い作家のためのロータス賞」(第2回)受賞。93年には『卵洗い』で坪田譲治文学賞を受賞する。最近の著作に『鳥の道』(新潮社)『黙示の華』(岩波書店)『ダカールへ』(文藝春秋)などがある。
【目次】
Ⅰ 犀の角のように
「ブッダのことば」に導かれ
救いの大地に再び
Ⅱ ゴータマからブッダへ
美しき森のなかで
大いなる決意
苦しみと惑いを超え
黄金の仏
法輪を転ずる
王舎城は楽しい
静かな日々
死を間近にして
Ⅲ 死を見据えて歩む
旅立ち
死はいまだ彼方に
悟らぬものゆえに
永遠のブッダ
友、チュンダよ
Ⅳ 完きニルヴァーナへ
やめよ、アーナンダよ
最期の説法
完きニルヴァーナヘ
参考文献
ISBN:9784333018239
出版社:佼成出版社
発売日:1996/11/10
