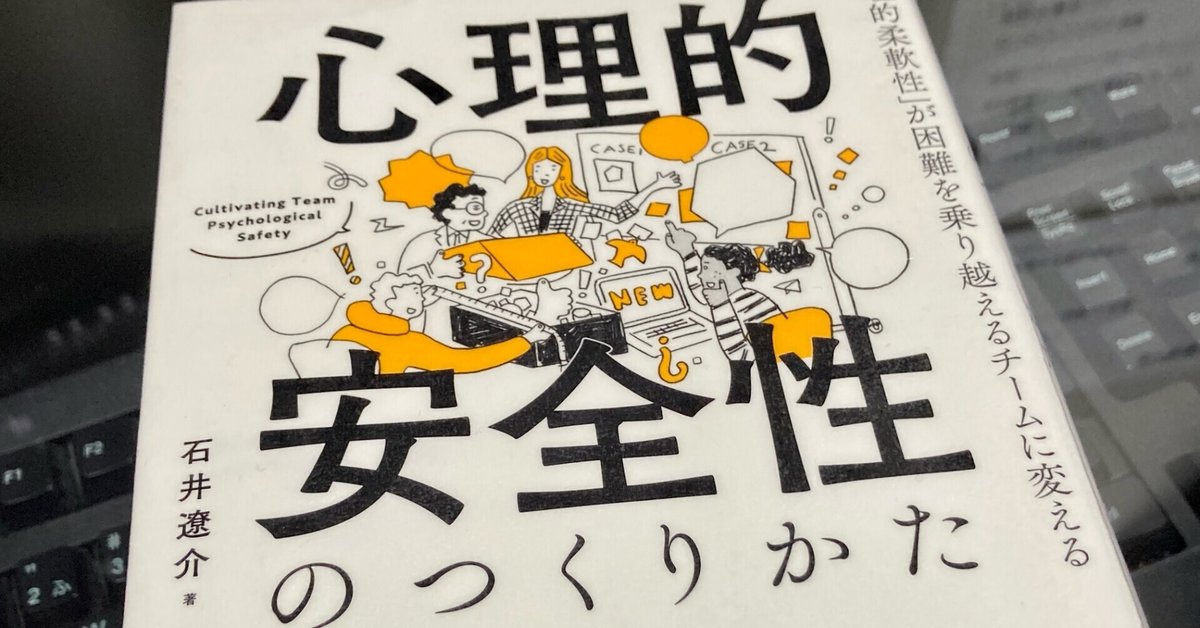
心理的安全性の確保はぬるま湯ではなくむしろ真逆 | 心理的安全性のつくりかた 石井 遼介 (著) | #塚本本棚
「何でも言ってね」は役に立たない。我流でチームに心理的安全性を構築しようとしている人には、良い教本になるかと。
・
今日は「心理的安全性のつくりかた( https://amzn.to/2ZwmIbp )」 石井 遼介 (著) #塚本本棚
・
【紹介文】
いま組織・チームにおいて大注目の心理的安全性とは「何か」から、職場・チームで高めるアプローチ方法をつかめます!
Googleのプロジェクトアリストテレスで、チームにとっての重要性が一気に認知された「心理的安全性」。本書ではその心理的安全性を理解し、心理的安全性の高い職場を再現できるよう、そのアプローチについて日本の心理的安全性を研究してきた著者が解説します。
・
・
【書評】
心理的安全性の構築は、それに向く組織と向かない組織があるなと感じます。
自走進化すべき組織や答えのない課題を解決する事業、それらはもれなくこちらで、心理的安全性を構築することが生産性の更なる飛躍につながると感じます。
一方で、正解のあるトップダウン型の組織には、必ずしもハマらないかもしれません。逆に大きなコストセンターになる可能性もあるなと感じます。
本書はチームへの心理的安全性構築のための入門書の立ち位置。なので実践した結果の考察などは薄く、まぁでもむしろ広く広まり実例が増えていくのはこれからなので、それはしょうがないのかもしれません。
本書を読めば心理的安全性の確保はぬるま湯ではなくむしろ真逆で、チームで全力を出しながら攻めるための、精神的補給ラインの確保をするようなものだというのが理解できると思います。
・
・
【本を読んで考えた・メモ】
・激しく変化し続ける時代には、組織とチームが挑戦し続けられる土壌が必要
・これまでのように正解があるなら、部下に挑戦がなくともトップダウンの方がミスなく早く、安く成長できた。だがこれからの時代は違う
・心理的安全性がある=メンバーが健全に意見を戦わせられる=生産的でよい仕事をすることに力を注げる (≠ぬるい職場←妥協が多い、≠結束した職場←異論が難しい)
・これらは思考力があり、ある程度は自己重要感がある人を採用しないと機能しないかも?
・指示待ち人材ばかりの組織だと難しそうだ。そして思考力がある人材は賃金も高い。であれば付加価値が高いビジネスモデルにしかこの方程式は成り立たない?
・心理的安全性を確保することで伸びる事業なのかという問いも大事。相性がありそう。もちろん、人生においては心理的安全性がある組織の方が成長可能性は高そう。
・心的安全性のあるチームであれば、リモートワーク下においてもオンラインでの対話・共同が続けられる可能性が高い。
・ケーススタディとして色んな業種で心理的安全性を確保してみて、どうだったかの実例が欲しかった。どうしても高度に洗練された人材と、答えがなく新しい分野に挑戦する企業にしかフィットしないように思える。
・自ら思考できない、何を提案すればいいのかわからない。わからないから適当に提案しても受け入れてくれる。と考えるような人を混ぜてはいけないんだろうなぁと推測する。
・心理的安全性のある職場は、ある意味自分が試される。同質性を許さないから。
・こんな効果があるはずなので、やってみよう!というのが本誌。まだまだ普及はこれからといったところで、今後も注視してフォローしていきたい。
・議論し見つけていく、壁打ちして作り上げていく、そんな事業には良いかもしれない。
・またカスタムメイドな商品を売っていたり、顧客ごとに対応が変わるようなビジネスにもフィットするような気がする。
・「何でも言ってね」は役に立たない。文脈に応じてより具体的な投げ方が大切。
・投げかけの言葉を知らないと、心理的安全性は構築できない。導入する人にも高度なスキルが必要となるし、その受けても最低限の思考力が必要とされるなと感じる。
