
情報セキュリティマネジメント(SG)試験 受験&合格日記
2019年4月21日に試験を受験するまでの日記とメモ。この記事に追記する形で書いていく。
2月上旬
執筆の仕事で、気力が続かない感じ、アイディアが枯渇しやすい感じが続くようになる。
「あぁ、インプット不足だなぁ」と感じたので、読みたい本ややりたいことについて考える。
その1つが「試験を受けること」だと思い、資格試験の年間受験スケジュール表を作る。
2月16日
IPAのサイトで、情報セキュリティマネジメント試験の受験申し込みをする。
2月17日
アメブロとFacebookで「受験します」宣言をする。
参考書を買いに行く。テキストや問題集との相性を確かめるため、私は必ず書店で本を見て選ぶ。
2月18日~22日
頭が沸騰しそうなほど仕事が押し寄せてきたので、資格の勉強など個人的な活動はほぼできず。
2月23日
セミナーのレジュメ作りをする。
インターネットで「勉強法」について検索し、気になった情報をひたすらノートに書き留めていく。
2月25日
夜に「ライターになるには?」セミナー。
「文章を書くための情報収集ってどうやるんですか?」というご質問があったので、23日に書き始めたノートをお見せする。

2月26日ごろから
新規案件の依頼が、またもや怒涛のようにやってきて、資格勉強など個人的な活動がしばらくできず。
「このままでは、いけない」との思いから、勉強がはかどりそうな画像をネットで集めて、手帳にたくさん貼りつける。潜在意識の活用。
3月2日
法事のため実家へ。2日までに原稿の構成案をクライアントに提出したので、仕事はいったん落ち着いていた。
3月3日
大阪北港ディンギークラブのキャットリグレース運営。
私のiPhone5の調子が、1か月ほど前から悪かったようで
「電話をしているのに、つながらないから、どうしたのかと心配していた」
というお声を多数いただき反省する。

3月6日
iPhone5の充電ができなくなり、修理店に相談した。スタッフの方からは
「パーツ交換で解決するかどうか不明。やってみてもいいが、かなり古い機種でもあるので、機種交換も検討されたほうが……」
との返事。機種交換を選ぶ。
気持ちを切り替えて、これまで収集してきた情報をもとに、レジュメとしてまとめる作業を行う。自分自身も受験生であり、役立つ情報を多々集めることができた。
3月7日
勉強法の情報収集中に、Youtubeで下記のチャンネルと出会う。大学受験の話題が中心だが、資格試験の勉強法として参考になる部分がある。
3月8日
仕事を始める前に、IPAの「過去問題」ページで、3回分の出題内容を流し読みした。次のことを感じた。
・よく出題される用語の意味を押さえなければならない
・IPAによる試験のリズム感を取り戻さなければならない
・難問、奇問が出題されている様子はない
リコレ(ソフマップの中古通販サイト)で購入したiPhone6が届く。3月6日の夜20時ごろ注文したもの。SIMカードの入れ替え等も無事に済む。
3月9日
午前中はセミナー。
本町駅近くのスターバックスでお昼ご飯。たくさんの人がテーブルを囲み、パソコンを使っていた。土曜日だけど、この季節は忙しいようだ。
SG試験の過去問題を見て気づいたこと。
・午前試験は問題文が「○○基準における……」「○○ガイドラインにおいて……」と始まる場合もあるが、○○基準や○○ガイドラインを正確におぼえていなくても解答できる問題が多い。
・午後試験は文章が長い。先に枝問を確認してから問題文を読むのは、受験時の基本だが、
枝問⇒問題文中の下線部や番号が書いてある部分の確認⇒問題文の把握
の順のほうが、より効率がよいと感じる
3月13日
原稿執筆の仕事が嵐のように来ていた。複数のエンドクライアントから来る仕事を、事務所の編集さんとともにリスケジュールしまくり、大変な日々だった。
3月14日
かかりつけの産婦人科へ。新しいお薬と治療計画の提案をいただく。
子宮内膜症による腹痛、腰痛そして脚までひびく痛みは、勉強を続ける上ですごいストレスになるので、合うお薬をつかってここまで楽に過ごせたことには感謝している。
ただ、薬には副作用があり、私の42歳という年齢を考えると、血栓症のリスクがより低いお薬に変えたほうがいいとのこと。体調の波を受け入れながら勉強もがんばっていこう。
3月16日
奈良セミナー会場へ向かいながら勉強。
難しい問題はあまり出ないようだが、私が情報処理技術者試験の勉強から離れていた期間が長いため、過去の知識だけでは不足という点を、改めて感じる。
3月19日
IT関連の試験では、
・アルファベットで表現される略語
・長いカタカナ語
がたくさん出てくる。
アルファベットをそのまま記憶しようとするとつらいときは、アルファベット1つ1つの意味を意識してみる。
長いカタカナ語に舌がもつれそうになるときは、あえて短い単語に区切っておぼえる。
これが記憶を定着させる私なりのコツ。
3月29日
本番まであと3週間と少し。この時期になると起こる現象がある。
電車に乗っているときやエアロバイクを漕いでいるときなど、勉強できるはずのときに、他のこと(スマホを見るなど)をしてしまうと、「してしまった」ことがストレスになるのだ。
気分をすっきりさせるためには、2,3ページでもいいのでテキストや過去問を進めるとよい。
以前の応用情報受験から時間がたっているため、覚えなおさなければいけないことがたくさんある。
今回は「7回読み」の手法で記憶を定着させることを試みている。
この方法は「テキストにしおりさえ挟んでおけば、いつでもどこでも学習を再開できる手軽さ」があることもありがたい。
4月5日
「受験票が届いてないけど、いつ発送だったかな?」と思い公式サイトで確認する。
いろんな試験を受けてきたけれど、こんな直前になって会場が変更されることも、受験票に変更前の会場が記載されていることも、受験票到着後に別途お知らせが来るらしいことも、初めての経験。
新しく設定された会場のほうが、私の家からは便利な場所なのでありがたく感じる。
4月9日

お知らせが速達、特定記録郵便で届いた。
お金かかっただろうなぁ。損害保険とか使えるのかなぁ。
4月22日
あっという間だった学習期間が終わり、受験日が来た。

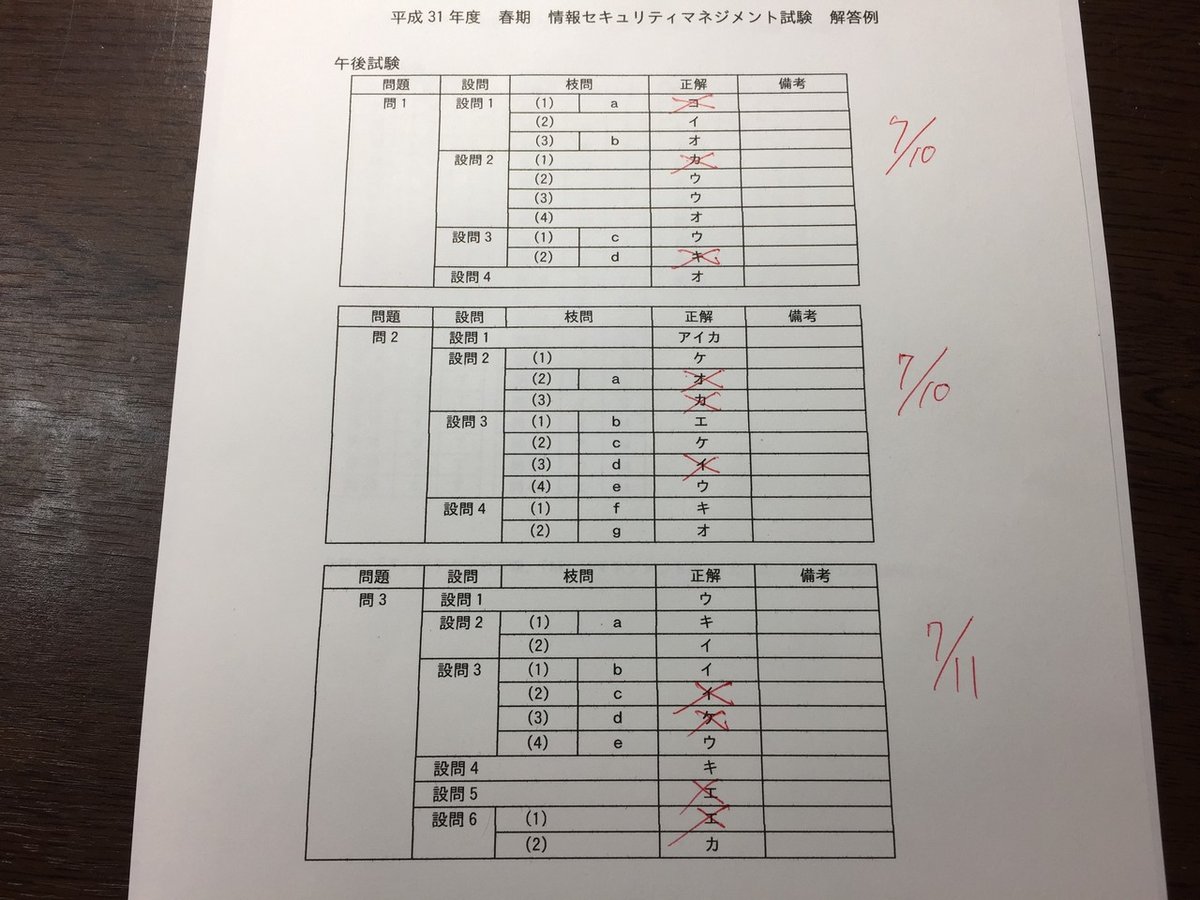
自己採点をしての感想。
知識の極端な偏りが見られる。
用語の意味やなんかの基準などの名称で数多く躓いている。
午前は初めの10問のうち6問を不正解しながら、あきらめずに解答を続けた自分に呆れる。。。
午後は、迷った末に選択肢を選ぶ⇒さらに迷ってもう一度選びなおす、とやったところで点数が伸びていない。正解だったのに書き直したパターンと、最初から不正解だったパターンがある。
そういう問題に時間をかけるのがよいのか、考えるべきだなぁ。。。
5月22日 結果発表
合格できたことが分かった。

テクノロジ系の得点率が低い。IPAの他の試験や、医療情報技師試験など他団体の試験も含めて、私はテクノロジ系の点数にかなりのばらつきがあり、試験ごとの当たり外れが大きい。
テクノロジ系の問題は、基礎的な知識や用語を知っていれば解答できる問いも多いのに、本番であれっというような間違いをしたり、時間をかけて選択肢を検討したのに、結果的に外したりする。
それは、暗記をするための時間や労力を、かけられていないからだと思う。5分でも時間を取ることができれば、記憶を定着させるための努力はできるのだから、本番であわてないよう、まじめにやろう。
……と試験直後に「だけ」反省して終わるパターンからも抜け出そう……
河野陽炎の保有資格
・海事代理士試験合格者(未登録)
・一級小型船舶操縦士
・応用情報技術者
・情報セキュリティマネジメント
・初級システムアドミニストレータ
・ITパスポート
・医療情報技師
・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種(ラインケアコース)
・普通救命講習修了
・労働安全衛生法による特別教育
(伐木等の業務、酸素欠乏・硫化水素危険作業)
・エックス線作業主任者
・発破技士
・特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
・.comMaster★
・工事担任者(デジタル第3種)
・危険物取扱者(乙種 全類)
・消防設備士(乙種 7類)
・第4級アマチュア無線技士
・日商簿記検定3級
・3級ファイナンシャルプランニング技能士
・不動産実務検定1級合格者
・一ツ星タマリエ
いいなと思ったら応援しよう!

