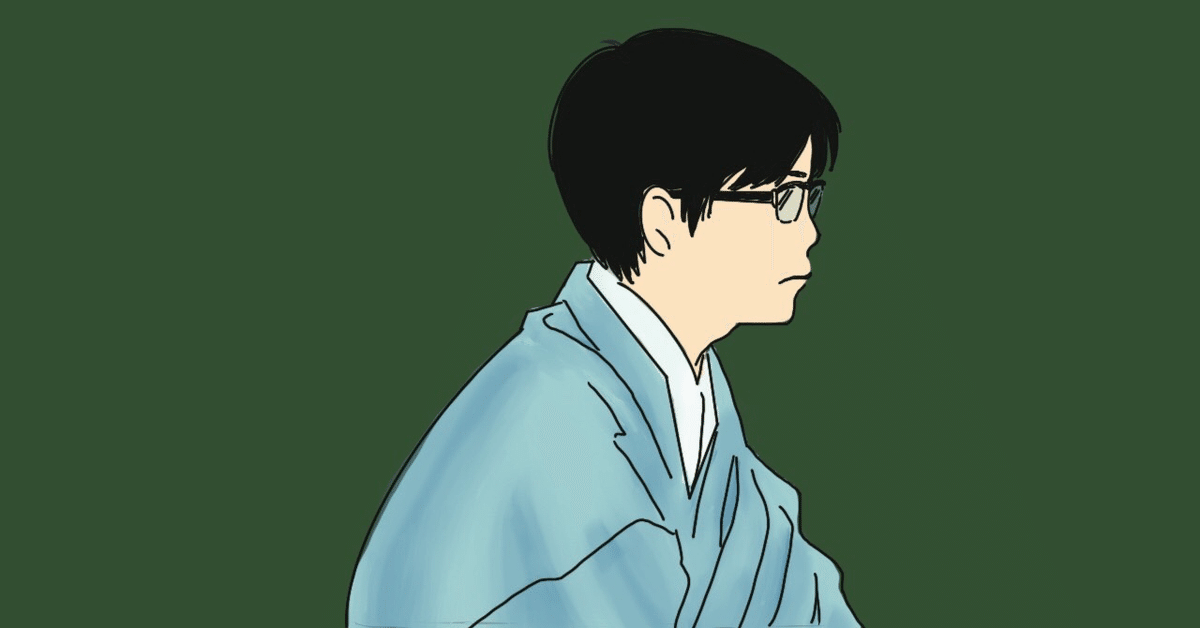
豊島/羽生さん?強いよね。 *日本語(の歴史)に關する話し
この記事は、researchmapの研究ブログに書いた記事を改變したものである。
(A)
(A) をリアル タイムで (NHK杯は錄畫だけど) 觀たことは、人生のファイン プレイのひとつである (どんだけショボい人生やねん ... )。この衝撃 (笑劇?)[*]が10年以上前のことゝは、俄かに信じられない。橋本崇載八段 (通稱ハッシー) は引退してしまふし。
[*] この辭書を使って、「衝撃」は「しょうげき」、「笑劇」は「せうげき」と入力してゐる爲、實は、筆者の中では駄洒落に成ってゐない。
將棋の話しはこの邊りで措いて、日本語の話しに移る。今囘の主題は「豐島」「羽生」と表記される名詞 (地名/名字)。
豐島
「豐島」表記は次のやうに讀まれる。
(B)
トヨシマ
テシマ
(B2) テシマは (B1) トヨシマから生じたものだらう。その過程は次のとほり。
(C)
1. tojo+sima > 2. toisima > 3. tesima
x > y: x から y への史的變化 j: 硬口蓋接近音 (ヤ行子音の音色)
音素表記を意味する /◌/ にも、音聲表記を意味する [◌] にも括られてゐない音形は抽象的音形。「tesimaの音價が [teɕimɐ] であることは、皆まで言はずとも分かりますよね?」といふ氣分の時に使ふ。
(C1–2) "jo > i" は、母音語幹動詞 (いはゆる一/二段動詞、カ/サ行變格活用動詞) の終止:命令形に見られる。次に例を擧げる。
(D)
上げろ: age-jo > agei
來い: ko-jo > koi
爲ろ: se-jo > sei
(D) の類例も次に追加しておく。
(E)
良い: jo-i > i:
月夜: tuki=no#jo > [t͡sudːoi][*] (鹿兒島縣上甑島瀨上)
音素體系が一般的ではない方言から例を擧げる場合は音聲表記 [◌] とする。
前掲 (C2–3) "oi > e" は、關東方言等における形容詞の終止/連體:平敍形に見られる。具體例は次のとほり。
(F)
凄い: sugo-i > sugeː
遲い: oso-i > oseː
良い: jo-i > (j)eː[*]
[*] (F3) はなぜか、"oi > e:" が多發する關東方言には認められず、"oi > e:" がまづ起こらない關西方言に生じてゐる。この齟齬は興味深い。
前掲 (C2–3) "oi > e" は、九州西南部方言の與格名詞[*]にも見られる。具體例は次のとほり。
(G)
此處に: koko=i --> koke(ː)
外に: soto=i --> sote(ː)
x --> y: 入力 x からの出力 y
[*] 格といふ槪念については次掲記事のこの節を參照されたい。
以上のことから、テシマはトヨシマに由來すると見て良からう。ひょっとすると、「手島(/嶋/嶌)」と表記されるテシマの中に豐島由來のテシマが紛れ込んでゐるかも知れない。或いは、「豐島」と表記されるテシマの一部が手島由來のテシマだったり。知らんけど。
日吉
「日吉」と表記されるヒヨシ : ヒエの關係も、トヨシマ : テシマとの關係に似てゐる。ヒヨシからヒエへの史的變化は次のやうに考へられる。
(H)
1. pi+josi > 2. pijoɕ > 3. pijoç( ?> pijoʝ) > 4. pijoi > 5. pi(j)e
史的變化 (H) は全くの空想ではなく、薩摩方言に起こってゐるものである (因みに、su も同じ變遷を遂げる)。
次に擧げるs語幹動詞 (いはゆるサ行五段動詞) テ形イ音便も、s の脫落に據るものではなく、史的變化 (H) に因るものと睨んでるのよ[*]。俺の目は騙されへんよ。俺の目騙せたら大したもんや。
(I)
出して: das-i-te > daste > daçte > daite > djaːte, deːte
落として: otos-i-te > otoste > otoçte > otoite > oteːte
蒸して: mus-i-te > muste > muçte > muite > m(w)iːte
[*] k/g語幹動詞テ形イ音便も、k/g の脫落に因るものではなく、次のやうなものだらう。
(1) ki, gi > (2) c͡ç, ɟ͡ʝ > (3) ç, ʝ > (4) i
(2) 有聲硬口蓋破擦音 [ɟ͡ʝ](のやうな音聲)は、東北方言の /k/ が /i/ に先行する場合の異音に存在する (e.g., /maki/ [mɐɟ͡ʝi] '薪')。
羽生
續いては「羽生」表記。次のとほり、これにはふたとほりの讀みが有る。
(J)
ハブ
ハニュー
兩者は同根であり、pani '埴' が産出される pu '生'[*]に由來する。
(K)
a. pani+pu > b. panpu > c. pambu > d. pabu
a. pani+pu > b. panip > c. paniu > d. panjuː
[*] シバフ '芝生' やアサヂフ '淺茅生' のフ。
(K1b–c) "np > mb" は次のやうに生じる。
(L)
歯茎閉鎖鼻音 n の調音部位が兩唇閉鎖清音 p のそれに順行同化して、兩唇閉鎖鼻音 m に。
兩唇閉鎖鼻音 m に續く兩唇閉鎖清音 p が濁音化して、兩唇閉鎖濁音 b に[*]。
[*] 閉鎖鼻音に續く清音が濁音化する例を次に擧げておく。
源氏: gwen-si > genzi
容體: joŋ-tai > joũdai > jo:dai
讀んで: jom-i-te > jomte > joũde > jonde, jo(:)de (中國地方西部、土佐、九州), jude (舊薩摩藩領)
史的變化の過程で、ハブ/ハニューを構成する pani '埴' が意識されなくなると共に、ハブ/ハニューのハが pa '羽' と(好意的に?)誤解されて、「羽生」と表記されるやうに至ったのだらう。これまた知らんけど。
いいなと思ったら応援しよう!

