
建築基準法改正!4号特例縮小と省エネ義務化
こんにちは、株式会社HARMONYの山本航聡(やまもとこうそう)です。
2025年4月1日から施行される建築基準法の改正について、その背景や主な改正内容、今後の展望を分かりやすく解説いたします。
背景
近年、地球温暖化対策や自然災害への備えとして、建築物の省エネルギー性能や安全性の向上が求められています。この流れを受けて、政府は建築物のエネルギー消費性能の向上と構造安全性の確保を目的に、建築基準法を改正する運びとなりました。
4号特例とは?

建築基準法では、小規模な建築物(4号建築物)に対し、建築確認申請や構造審査を簡略化する特例を設けています。この特例は、設計者や建築主の負担を軽減するためのものです。
対象となる建築物
木造建築物
2階建て以下
床面積500㎡以下
軒の高さ9m以下
建築物の高さ13m以下
階高3m以下
木造以外の建築物(鉄骨造、RC造など)
1階建て
床面積200㎡以下
特例内容
構造計算の省略
通常必要な構造計算(許容応力度計算など)が省略されます。ただし、簡易的な壁量計算や基礎の検討は必要です。
建築確認申請の簡略化
提出図書が緩和され、構造図や詳細図の提出が不要。平面図や断面図などの基本的な図面で申請可能です。
省エネ性能の審査対象外
現行法では、省エネルギー基準適合の審査義務がなく、設計者の裁量に任されています。
現行の課題
構造安全性の担保が不十分
審査が簡略化されているため、施工時に安全性が確保されないリスクがあります。
省エネ性能のばらつき
設計者の判断によって性能に差が出るため、住宅性能が統一されません。
違法建築のリスク
手続きの簡素化が、建築基準を満たしていない建物を生む可能性があります。
主な改正内容

1. 4号特例の縮小
木造2階建て建築物については、床面積に関わらず構造審査や省エネ審査が必要になります。この改正により、確認申請時の提出書類が増加し、設計者や建築主の負担が増すことが予想されます。
2. 省エネ基準の適合義務化
全ての新築建築物が、省エネルギー基準への適合を義務化されます。
住宅: 外皮性能基準および一次エネルギー消費量基準の適合。
非住宅建築物: 一次エネルギー消費量基準の適合。
3. 小規模木造建築物の構造関係規定の見直し
壁量基準の見直し
準耐力壁の取り扱い変更
筋かいの対象拡大
柱の小径基準の見直し
基礎の基準変更(鉄筋コンクリート基礎の必須化)
今後の課題と展望
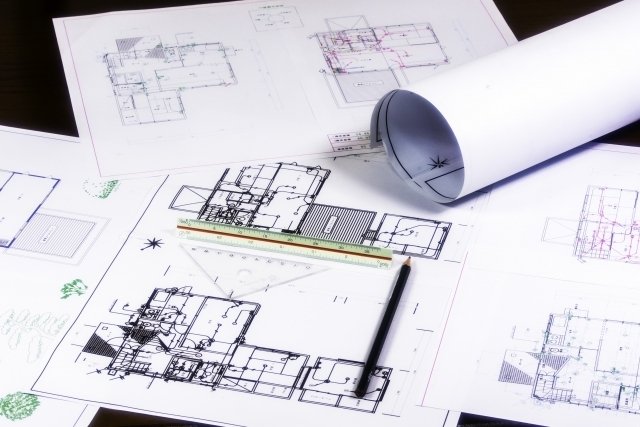
設計者・建築主の負担増加
構造計算や省エネ適合性判定の義務化により、設計段階でのコストや手間が増加します。これにより、小規模な工務店や設計事務所の経営が厳しくなる懸念があります。
工務店や地域業者への影響
大手メーカーとの格差拡大
技術者や設計体制が整わない地元工務店は、競争力を失うリスクがあります。
価格競争の激化
設計や構造計算のコストが顧客に転嫁されることで、価格競争がさらに激しくなる可能性があります。
顧客負担の増加
建築コストが上昇し、特にローコスト住宅を求める顧客にとっては負担が増します。手続きの複雑化も計画の妨げになる可能性があります。
まとめ
2025年4月からの建築基準法改正は、建築物の安全性や省エネ性能の向上を目指す重要なステップです。しかし、設計者や建築主、さらには顧客にとって負担が増す側面もあります。この変化をチャンスと捉え、業界全体で協力しながら、効率的で持続可能な住宅づくりを目指すことが必要です。
「課題を乗り越えた先には、より安全で快適な住環境が広がっている。」
この記事が家づくりをする方の参考に少しでもなれば幸いです。
株式会社HARMONY 山本航聡(やまもとこうそう)
