
【読書考】「物価を考える」を読んで.
0.「今日の記事のポイント」

☆「物価を考える:著:渡辺努:2024年:日本経済新聞出版と、デフレの謎とインフレの謎の本だよ」
☆「異端の国ニッポンだって?と、30年デフレの犯人は誰だ!」
☆「ノルムと自粛の解消は難しいと、ホントに悪いのは経団連と連合なの?」
☆「コロちゃんと経済書の読書習慣」

1.「物価を考える:著:渡辺努:2024年:日本経済新聞出版」
コロちゃんは、この「物価を考える」という本の著者の、「渡辺努東大教授」の本を読むのは初めてではありません。
以前に「世界インフレの謎※」という本を読んで、「コロナ禍におけるインフレ」について、素人のコロちゃんにもわかりやすく解説していると思っていたのです。
(※世界インフレの謎:著・渡辺努:2022年:講談社現代新書)
さらにこの「渡辺教授」は、政府の「経済財政諮問会議」の資料の中で時々その名前を拝見していましたので、コロちゃんはその都度に「こんなところにも出ているよ」と思っていたのです。
経済評論家の中では「渡辺教授」の名は「渡辺チャート」や「物価の神様」で有名でしたので、コロちゃんはこの「物価を考える」という本が出版されたと知ると、急いでリクエスト(※)しましたよ。
(※もちろん図書館へのリクエストです)

2.「デフレの謎とインフレの謎の本だよ」
本書は、表紙の中に「副題」として「デフレの謎、インフレの謎」と書かれていますね。
確か「デフレ」って物価が下がる状態で、「インフレ」って物価が上がる状態ですよね。
そのあれこれを本書では書いているのですが、読んでみると要するに「失われた30年は誰が悪かったのか?」という内容なのですよ。
最初に前提としてコロちゃんの「読後感」で思ったことを書いておきますが、どうやら「経済学」っていうのは「完成した学問」ではないということなんですよね。
だから「失われた30年の原因と理由」も、未だに「経済学者」の本でも「百家争鳴」とまではいかなくとも、次々と新しい「知見・意見」が出てきているのですよ。
さて、この「渡辺教授」の本では、コロちゃんも初めて知る「失われた30年の戦犯」が出てきていました。
それが果たして正しい見解なのかは、今後の他の「経済学者」が後を続くかどうかだとコロちゃんは思いましたよ。

3.「異端の国ニッポンだって?」
本書では、最初に「異端の国ニッポン」と書き出しています。
「インフレ」ってよく聞きますけれど「物価が上昇すること」ですよね。そして「デフレ」がその逆で「物価が下落すること」ですね。
これが「数年間続く事」は、どこの国でもあることで珍しい事ではないそうですが、「渡辺教授」によると、これが30年間も続くことは、歴史的にも他国にも前例がないそうなんですよ。
「デフレ」の経済指標には「物価、賃金、金利」があるとしています。この3つが「日本」では、ここ「30年間上がらない状態」が続いているというのです。
それで「異端の国ニッポン」となるわけですね。
コロちゃんは、ちょっとその「30年間も物価と賃金と金利が上がらない」という状況をビジュアルで見てみたいと思って以下のグラフを探してきましたよ。

〇「30年間上がらない物価・賃金・金利だよ」
最初は「物価」を見てみましょう。30年間上がっていないかどうかを確認してみますね。以下ですよ。
下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出しますね。
「独立行政法人 労働政策研究・研修機構 消費者物価指数」より

出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構 早わかり グラフでみる長期労働統計より(2月4日利用)
上記のグラフは「独立行政法人:労働政策研究・研修機構」が発表した1990~2023年の「消費者物価指数」の推移です。
上記はグラフの中の1990年~2013年の部分の「拡大図」ですが、確かに1995年から2020年頃まで100を下回って横這いに推移しています。
そして最後の2022年から、グラフが急に跳ね上がっていますね。これが最近の「物価上昇」ですね。
このグラフは「2020年を100」としたものですから、確かにここ30年間で「物価が上がっていない」ことは間違いがありません。
「渡辺教授」は、「本書」で1995年あたりから上がらなくなったと書いていますね。
次は「賃金」を見てみましょう。以下ですよ。
下記のグラフをご覧ください。内容は下に書き出します。
「独立行政法人 労働政策研究・研修機構 主要企業春季賃上げ率」より

出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構 早わかり グラフでみる長期労働統計より(2月4日利用)
上記のグラフは、「独立行政法人:労働政策研究・研修機構」が発表した1956~2023年の「主要企業春季賃上げ率の推移」です。
グラフを見ると、確かに1995年以降の「賃上げ率」が低空飛行をしています。
コロちゃんがバックデータで確認したところ、1995~2001年までは2%台で、2002~20013年は1%台で、2014~2022年は2%台ですが2021年は1%台と、賃金はほとんど上がっていませんね。
この「賃金」も、確かに30年間の間ほとんど上がらない時代が続いていましたね。
最後は「金利」です。下記のグラフをご覧ください。
「内閣府 長期金利の推移」より

l出典:内閣府:長期金利の推移より:2月4日利用
上記のグラフは、「内閣府」が発表した2000~2024年の「長期金利の推移」です。一番下の赤線グラフが「長期金利」ですね。
ご覧のように左から右へ、金利は上がるどころか低空飛行で一部はマイナスに落ち込んでいます。
確かに「金利」もここ30年間あがっていませんね。
これらの「物価・賃金・金利」が、数年間は上がらないことは珍しくないそうですが、ともに「30年間上がらないことは異常なことだ」と「渡辺教授」は、本書で書いているのですよ。
コロちゃんは、素人のおじいちゃんですから、30年間ずっと変わらない状況が「平常状態」と思っていましたが、そうではないというのです。

4.「30年間のデフレの犯人は誰だ!」
上記で「物価・賃金・金利」が上がらないことが「普通の状態ではない」ということになると、その「原因は何か?」が次の疑問点になりますね。
しかし、コロちゃんが知る限りでは「現在の経済学者」がその原因をハッキリと解明した方はいないと思っています。
何しろ、みんな言うことが違っているのですよ。
以前は「中国から安い製品が入って来るのが原因だ」と言っておられた方もいますし、「企業が内部留保を貯め過ぎているのが悪い」とか、「非正規雇用が増えすぎた」という方もいます。
ああ「投資が少なくなった」とか「人的資本の劣化だ」と言う方もおられましたね。
どうやら「経済学の世界」では、まだこの「失われた30年」の全容の解明は出来ていないというのがコロちゃんの見方です。
まあ、だから素人のコロちゃんが興味深々で「経済学の本」を読んでいるのですけれどね。
そのコロちゃんの「読書志向」はどうでも良いのですよ。
\(-\)(/-)/ ソレハコッチニオイトイテ…
話しを戻して「失われた30年の犯人は誰だ?」を、「渡辺教授」は以下のように書いていますよ。
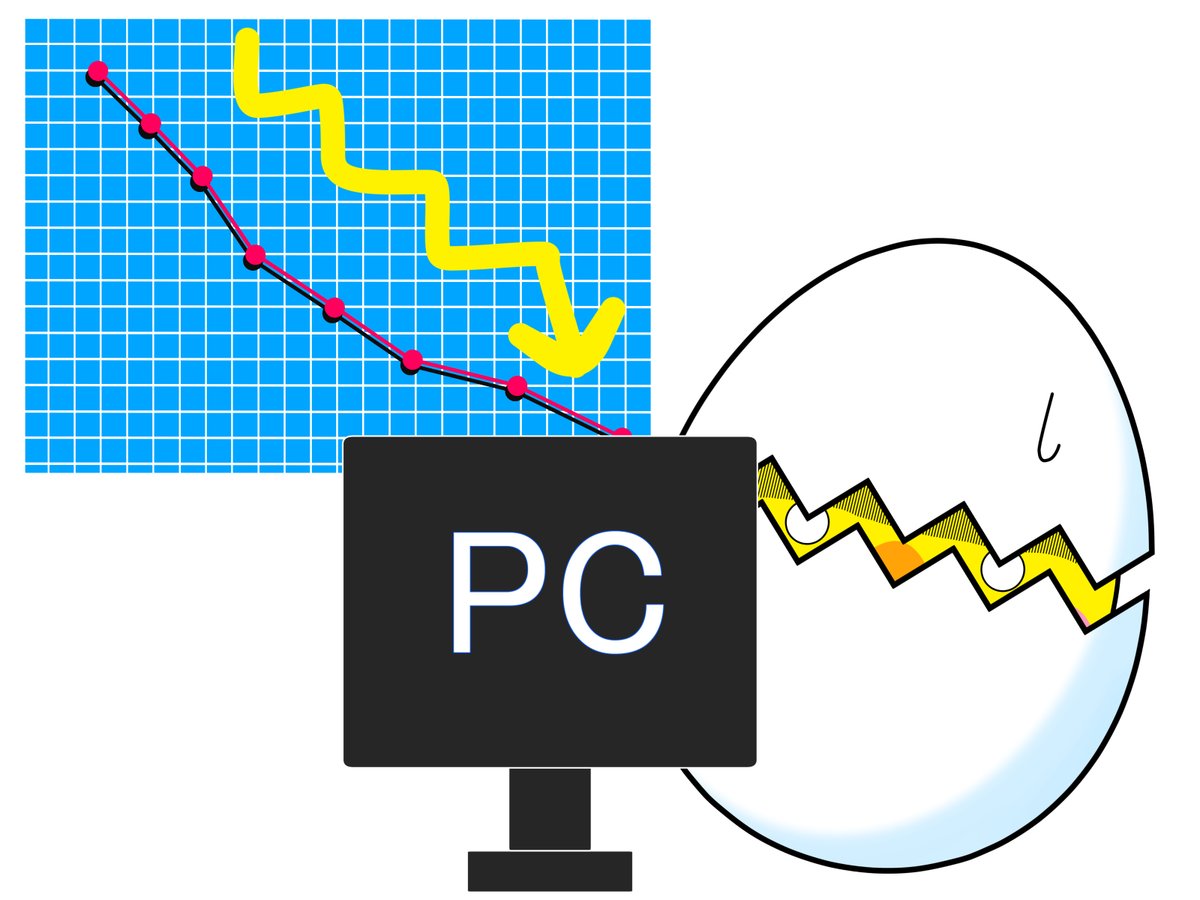
➀「物価・賃金スパイラル理論とは?」
ここで「渡辺教授」は「物価・賃金スパイラル理論」を紹介しています。
この理論では「賃上げをめぐる企業と労働組合のにらみ合い」を、以下のように解説しています。
➀「労組の考え」
・「企業が4月に賃金を決めるとすると、労組にとっては次の賃上げの機会は来年4月になる。だから、今後物価が上がると実質賃金は下がってしまうから、今の春闘でその分も要求しておこう」
②「企業の考え」
・「企業が10月に製品の価格を改定するとして、企業にとってはこの先賃金が上がるのであれば、今のうちに製品の価格を上げておこう」
上記は「健全な状態」の「企業と労組」の関係です。
その場合は、上記のようにお互いが相手の出方を読み合って「賃金上げ」⇒「価格上げ」⇒「賃金上げ」と「スパイラル的」に進んでいくというのですよ。
これは、どっかで聞いたことありますよね。そうです「岸田前総理」が言い出して、今「石破総理」が継承している「経済の好循環:物価と賃金の好循環の理論」です。
しかし現在は、上記の「好循環のスパイラル」が成り立っていません。それは「逆回転」しているからですね。以下だというのですよ。
❶「労組の考え」
・「企業が4月に賃金を決めるとすると、労組にとっては次の賃上げの機会は来年4月になる。だけど今後も物価は上がらないだろうから実質賃金は下がらない。だったら春闘の賃上げも低くて良い」
❷「企業の考え」
・「企業は10月に製品の価格を上げないでおこう、企業にとってはこの先賃金が上がらないならば、別に製品の価格を上げることはない」
うーむ、なんかわかったような、わからないような?
(。・_・?)ハテ?
こちらが「悪循環のスパイラル」ですね。お互いが、相手の出方を読み合って「賃上げなし」⇒「価格そのまま」⇒「賃上げなし」と「スパイラル的」に進むというのですよ。
こう考えると「労組と企業」のどっちかが、「スパイラルの好循環」から「スパイラルの悪循環」の転換の引き金を引いたから始まったということになりますよね。
だけど、こんな「単純な理屈」で「失われた30年」が続いたのかなー?
( ̄へ ̄|||) ウーム
だって、これがホントなら、悪いのは「経団連」か「連合」しかいないジャン!
(っ`Д´)っダメジャン

➁「高いニッポンへの恐怖と対処法」
本書では「物価と賃金が上がらなくなったのは1990年代後半」としていますから、2000年代初頭から始まった「春闘ベアゼロ」は、「引き金」というよりは「ダメ押し」だったのかも知れませんね。
本書では、その「引きがね」を「高いニッポン」への対抗処置で起きたものとしています。
今では、世界各国に比べて「安いニッポン」と言われていますから、なかなか実感が持てないと思いますね。
コロちゃんは、1990年代の後半から2000年代にかけて、「中国の賃金」が「日本の賃金の10分の1以下だ」と騒がれていたことを憶えていますよ。
当時の日本は、世界的にも「高い賃金」だったのです。現在の「安いニッポン」から見ると、とても信じられないかも知れませんね。
しかし、その恐怖は「経済団体共通」のものでしたね。
コロちゃんは、1995年に「日経連(後に経団連と統合)」が発表した「新時代の日本的経営」というレポートを思いだしましたよ。
この内容は、今後の「日本の経営形態」を以下のように分けなければならないというものでした。
①「長期蓄積能力活用型グループ」
②「高度専門能力活用型グループ」
③「雇用柔軟型グループ」
上記の「①長期蓄積能力活用型グループ」と「②高度専門能力活用型グループ」は「正規雇用」ですね。そして「③雇用柔軟型グループ」が「非正規雇用」ですね。
この1995年の「日経連(後に経団連と統合)」のレポートが、現在の4割にも増えた「非正規雇用」のスタートラインだったのですよ。
これらは全て当時の「高いニッポン」への、経済界の対処法だったのでしょう。・・・やっぱり「戦犯は経団連」かな?
(。・_・?)ハテ?

③「経団連のベアゼロ回答と、連合の雇用を守れ」
「本書」では、著者と経済学者の「早川英男氏」とのレストランでの会話を紹介しています。この「早川英男氏」は、やはり「経済学者」の方ですね。
コロちゃんは、この方の「金融政策の誤解※」という本を読んだことがあり、切れ味の良い考察と文章に感嘆したことがありますよ。
(※金融政策の誤解:2016年:著・早川英男:慶応義塾大学出版会)
それ以来、この方の「雑誌での論考」は必ずジックリ読むことにしていますよ。
この「早川英男氏と渡辺教授」との会話の中で、1990年代の末に経営者たちが「賃金が高い日本では、このままでは到底中国と戦えない。賃金を抑えるべきだ」と提案したというのです。
それで「早川氏」は、「1997年頃に労使の密約があったと考えている」というのですよ。
この「密約」は、当然「賃金を上げない代わりに雇用は守る」というものでしょう。もちろん「真偽」は分かりませんよ。だけど結果を見るとホントかも?
上記のグラフで見た「春闘賃上げ率」は、2002年~2013年まで「1%台」という「定昇(2%)」以下に抑えられています。
だったら「失われた30年の戦犯」は、「経団連と連合」ということになるのでしょうけど、ホントかな?
( ̄へ ̄|||) ウーム
うーんと、1997年の「経団連会長」は、「豊田章一郎氏(1994~1998)」ってトヨタの現会長(豊田章男)の父親じゃん!
(゚Д゚)アッラー
その後は「今井敬氏(新日鉄会長:1998~2002)」、そして「奥田会長」はその後か。やっぱり2002年の「奥田会長(当時トヨタの会長でもあった:2002~2006)」が怪しいですね。
|゚д゚)アヤシイ
なにしろ、「雇用維持」のため「ベア見送り、定期昇給の凍結にも踏み込む」姿勢を表明しましたし、当時1兆円の利益を計上していたトヨタが、奥田会長の一喝で「ベアゼロ」となっていますからね。
当時はこれを「トヨタショック」と呼んで、たちまち世の中に拡がっています。
そしてこの時の「連合会長」は、「鷲尾悦也氏(1997~2001年)」か「笹森清氏2001~2005)」のどちらかか両方ですね。どっちも、コロちゃんは知らない方ですね。
だけどホントかなー?
ʅ(。◔‸◔。)ʃ…ハテ?
確かに今から振り返ると「30年間も賃金が上がってない」ことは間違いがない事実ですけれど、こんな「密約」なんて「連合」にしてみれば組合員への裏切り行為でしょう。
それに「企業」は「正社員の雇用は守った」けれど、その代わりに「退職した正社員」の代わりに「非正規雇用」を雇いだしたんですよね。
これって「密約破り※」じゃないの? 「密約※」には「正社員の退職後の補充も正社員とする」とか書いてなかったのかなー?
(。・_・?)ハテ?
(※ホントに密約があったかどうかはわかりません)
しかし、「賃上げ」をしないことで、企業が「商品の値段を上げない」ことに繋がり、その結果「物価が上がらない」で、その連鎖が「失われた30年」になったという理論は初めて聞きましたよ。
果たして、この見解が正しいのかどうかは、今後他の「経済学者」が検討してくれるでしょうね。

5.「ノルムと自粛の解消は難しい」
もちろん本書を書いたのは「東大教授の渡辺努氏」ですから、上記のような素人にもわかりやすいような内容ばかりではありません。
とにかく沢山の考察や、過去の「経済理論」が紹介されているのですが、それらはコロちゃんにはかみ砕いて説明することも出来ません。
だけど、もう1つだけご紹介しますね。
「渡辺教授」は、「慢性デフレの始まりも終わりも、人々の予想が起点と考えている」とおっしゃられています。
「経済学」が難しい理由のひとつがこれですね。人々の予想次第で、未来が変わってしまうということですよ。
これは「将来の物価と賃金が今後もずっと変わらない」と多くの人々が考えていると、それが実現してしまうというものですね。
これを「日銀」では「ノルム(社会規範)」と言っていましたね。
コロちゃんは、これを読んだ時に「人のせいにするな!」とイラっとしたのですよ。だって、そんなことは事前に考慮して「政策」を進めるのがプロでしょうに。
しかし、現在の「経済学」では、「人々の予想」は立派な「経済理論」に組み込まれているようですね。
例えば「多くの方が物価は将来上がる」と予想すれば、実現してしまうというようにですね。
本書では、「インフレ予想はこれまでの人生経験に左右されるという仮説」が紹介されていますね。
これは、何となくわかるような気もします。今の若い方は「30年も物価が上がらない社会」を生きてきましたから、急激なインフレなどはなかなか想像つかないのではないでしょうか。
また「ノルム(社会規範)」も紹介されていますよ。
これは「エスカレーターの片側に立つルール」や「マスク着用ルール」などがあげられています。
ここで「渡辺教授」は、「コロナ禍の自粛ノルム」と「慢性デフレ下の自粛ノルム(上がらない物価と賃金)」が酷似していると言うのですよ。
そして、その経過を諸外国の例と検討する中で、日本ではいったん定着したノルムの解消は難しいと結論づけています。
どうやら「黒田日銀」の失敗は、社会のノルムを変えることが出来なかったことにもあると考えているのでしょう。
どうやら「日本と言う国」は、よその国よりも「ノルムが変わりにくい」が、一旦「定着する」と、今度はまた「戻りにくい国」のようですね。
だけどコロちゃんは、「経済政策」や「金融政策」の失敗を「ノルム」や「人々の心の中の意識」のせいにすることには拒否感をもつのですよ。
だってそこには、「為政者」が命令をすれば「人々は従うものだ」と言う「上から目線の権威主義的な考え」がチラつきますからね。
「偉い方」が、「政策は正しかったが、従わなかった民が悪い」ということと、「政策は正しかったが、しつこいノルムがあって失敗した」と言う言い方は、紙一重だと思うのですよ。
コロちゃんは、これを読んでそんな思いを感じましたよ。

6.「ホントに悪いのは経団連と連合なの?」
コロちゃんは、本書を読んで「デフレが4~5年ならばともかく、30年も続くのは異常だ」と言うことは分かりましたよ。
だけど、その「賃上げと値上げの自粛」が「長期デフレの原因」とする「本書」の内容は、コロちゃんには思わず「んー?」と考えましたよ。
(*゚・゚)ン〜?
だって「30年に及ぶデフレ」は「マクロ経済上の問題」だと、コロちゃんの拙い経済知識では考えていましたけれど、「賃上げや値上げ」は「ミクロ経済で扱う問題」だと思ったのですよ。
いわゆる「金融政策は日銀の担当」で、「財政政策は財務省の担当」ですよね。同じ「経済問題」でも、別れているのですよ。
「短期の経済現象であるミクロ経済」は、「長期の経済現象のマクロ経済」には影響は及ぼさないはずなのではないかなと思ったのですよ。
コロちゃんは、素人のおじいちゃんですから、詳しい内容はわかりませんが、「経団連と連合の春闘賃上げ」が10年以上「ゼロ回答」だったのは、確かに酷いと思いますよ。
だって、それが「高いニッポン」から「安いニッポン」に落ち込む原因になったのは明らかですからね。
だけど、それが「日本経済が30年以上デフレ経済に落ち込む主因だった」と考えるのは、ちょっとちょっと・・・?、と躊躇してしまいますね。
いずれにしろ、本書では既に「いつまでも安いニッポンではまずいし困る」との認識が「社会に拡がっているから、今後は変わるだろうとポジティブに纏めていますね。
あと「渡辺教授」は、上記の「経団連と連合」に「長期デフレの原因」を押し付けている以外には、「日銀」にも「アベノミクス」にも否定的な見解は一切書いていません。
コロちゃんは、人が悪いですから「渡辺教授」は「世渡り・・ゲフンゲフン・・心が優しい方」なのかもしれないと感じましたよ。
(* ̄∀ ̄)ゞエヘヘ

7.「コロちゃんと蔵書の話」
コロちゃんの趣味は「読書」ですが、今「蔵書」というのはほとんどありません。2階の押し入れに40~50冊ぐらいは残っていますでしょうか。
かつては400~500冊はあったのですが、10年前に「大腸がん」と判明した時に、そのほとんどを「断捨離」してしまいました。
近隣の「ブックオフ」に持ち込んで売り払ってしまったのです。
その後は読む本は「図書館」から借りるものとして「読書習慣」を続けていましたので「蔵書数」は一向に増えません。
この前読んだ本で、作家の「佐藤優氏」の蔵書は4万冊あり、その中でもいつも読む本を800冊だけ身近の本棚に収納していると書いてありましたね。
やはり「知の巨人」ともなると「蔵書4万冊」ですよ。どうやってこんな数の本を読めるのでしょうか。コロちゃんだったら、絶対に読み切れませんよ。
だけど、昔「知の巨人」と言われた「立花隆氏」は「蔵書数10万冊」と言われていましたね。いやー、上には上がいるものですね。
(゚0゚)スッゴッイ!
こうなると、ほとんど「読書中毒」のようなもので、普通の人が息をしたり食事をするように「本を読んでいる」と言えるのでしょう。
コロちゃんは、とてもとても、このような方たちには及びもつきませんが、それでも「知の巨人」の爪の垢ぐらいの数の本を読みたいと思っていますよ。
今日は、「渡辺努教授」の著書の「物価を考える」を読んで、その内容を気の趣くままにご紹介しながら、コロちゃんの感想を書き連ねてみました。
どっちかと言うと、「本の紹介」よりもコロちゃんの感想と意見の方が目立ったかも知れませんね。
だけど、これでちょっとでも「本書」に興味をもった方は、是非下記のリンクからお読みください。興味深い良い本だとコロちゃんは思いましたよ。
コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。
このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)
おしまい。
