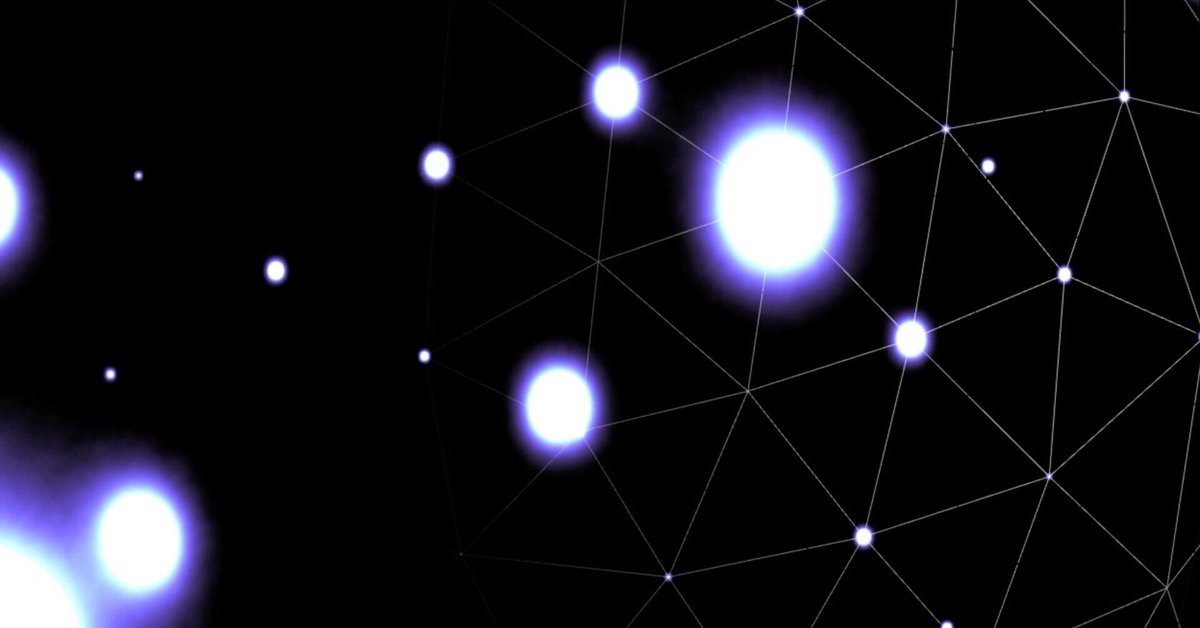
ぺらぺら
やればやるほど薄っぺらくなる気がしたら、一度やめた方が良い。
何かに熱中することは手軽な精神療法だ、現実からの逃避だ、精神の解放だ、強迫観念だ、承認欲求だ、それは、そう。
でもそうだ、自分に合うドアを探しているというか、猫とかハムスターとかが狭い場所にすっぽり収まってるみたいな、そういうものを探してるのかもしれない。
別に孤高を気取ってる訳じゃなくて、本当にただ見つからない。
自分にだけドアが見つからなくて、仕方なく適当に入ると、どこかのトイレの窓だったりして異常者だと思われる、みたいなことを何度も繰り返してきたと思う。
もちろんトイレの窓から入ろうとする人が普通じゃないってことは自分にも分かる。でも誰もドアと窓の違いを教えてくれないし、結局のところ自分にしっくりくるドアは自分で作るしかなくて、僕の好きな人たちはみんなそうやってきたんだ、ということに最近やっと気がついた。
今コーヒーカップに手が当たって、パソコンにちょっとかかっちゃって、ああ、惰性でコーヒーを飲んでるとこういうことになる、でも惰性で生きるのはちゃんと大切なことだ。
僕がいちいち立ち止まってる間に桜はもう咲いてる。
そうだよ、こんなにぶれた人間でもちゃんと返したいという気持ちはあって、僕のような人間に触れざるを得なかった人に対して、なんか、そういう存在がいてくれることに対して、何かお返しをしたくて、漫才師の人がなんでやねん、っていうツッコミをするみたいに、誰もいない舞台の上で腕を突き出してる。もっと早く返せば触れられたのに、どうしてもできない馬鹿だから、ひとりで。
馬鹿と言えば、今でも君と似た人を見かけると心臓が止まりそうになってて、この前は会社の本棚の前で急に心臓がどきどきして、なんでだろうって思ってたら君の使ってたアイコンと似た配色の本があった。
もう人ですらなくて、君の名前と似た綴りが目に入っただけでも、あっ、ってなる。
多分脳がバグを起こしてるから、もしこのまま認知症になっちゃったら、一生君の幻覚に囲まれて過ごせるのかな、って、馬鹿なことを考えた。
でも幻覚の君と上手く話せる自信がないからやっぱ無理だ。
書くときに手を合わせている感覚はあると思う。
書くことで、苦しんで死にゆく自分やあなたを供養している、みたいな。
人間の芸術活動は死んだ人の供養(鎮魂)から始まったという説が僕は好きで、芝居とか映画には、苦しんでいた魂が慰められる「たましづめ」と呼ばれる場面が大体入ってる。踊りや音楽もそう。
それはいわゆる癒しのための必要手順みたいなもので、苦しみを再生してもう一度立ち向かうことで、萎れてしまった花に水を注ぐような感じだと思う。
もちろん失敗することもあるし、成功したところで寂しさは消えないから、結構つらい。
というか、新しい苦しみとたましづめの儀式を延々と繰り返している訳だから、基本的に平穏というのは僕やあなたの中にはないのかもしれない。
もし君が幽霊みたいにこの世界をうっすら眺めている存在になって、時間がものすごくあったら、暇つぶしに僕のうたを読んでくれる可能性だってあるでしょ、ないかな、ないならないでも良い、でもあるかもしれないって信じられるうちは書ける。
君じゃなくて、君の友だちや、これから生まれてくるであろう子どもや、孫でも良いし、もっと言えば全然関係のない、君と同じ映画が好きな人とか、似た髪型の人でも良くて、とにかく何か一つ、かつて君を構成していた面影の一部が、それを感じてくれたら良いと思う。
鮮明すぎる記憶は文章がうまくまとまらない。
だから頭の中で一回全部モノクロにして、やすりで擦って、ざらざらにして、それでも残った情報を掬い取って、昔のレイヤーに重ねて、音と映像に焼き直してる。
僕にもうちょっと音楽のセンスがあれば良いんだけど、下手の横好きで終わりそうです。
目の前にいる君に対して、地球の反対側から会いに行くような不器用さで申し訳ないと思う。
272.同じことばでも君と僕ではまるで違う重さとなりぬ ぺらぺらの星
